「記事をたくさん公開しているのに、なかなか検索順位が上がらない」「一度は上位表示されたのに、最近順位が下がってきた」このような悩みを抱えているWebサイト運営者の方は多いのではないでしょうか。
実は、新規記事の作成だけに力を入れるよりも、既存記事のリライトに取り組む方が効率的にSEO効果を上げられることをご存知ですか。
調査データによると、リライトによって効果が出た記事は全体の75%、そのうち50%は200%以上のセッション増加を実現しています。
一方で、リライトを実施しなかった記事の69.8%は、公開から約6か月後にはセッション数が横ばいまたは減少傾向にあることが明らかになっています。
この記事では、SEOリライトの基本的な考え方から具体的な実践手順まで、検索順位向上に直結するノウハウを詳しく解説します。
記事を最後まで読んでいただければ、どの記事をリライトすべきか、どのような手順で進めればよいか、そして効果的な改善ポイントは何かが明確になるでしょう。
検索エンジンからの流入を安定的に増やし、ビジネス成果に繋げたい方は、ぜひ参考にしてください。

Index
SEOリライトの基礎知識
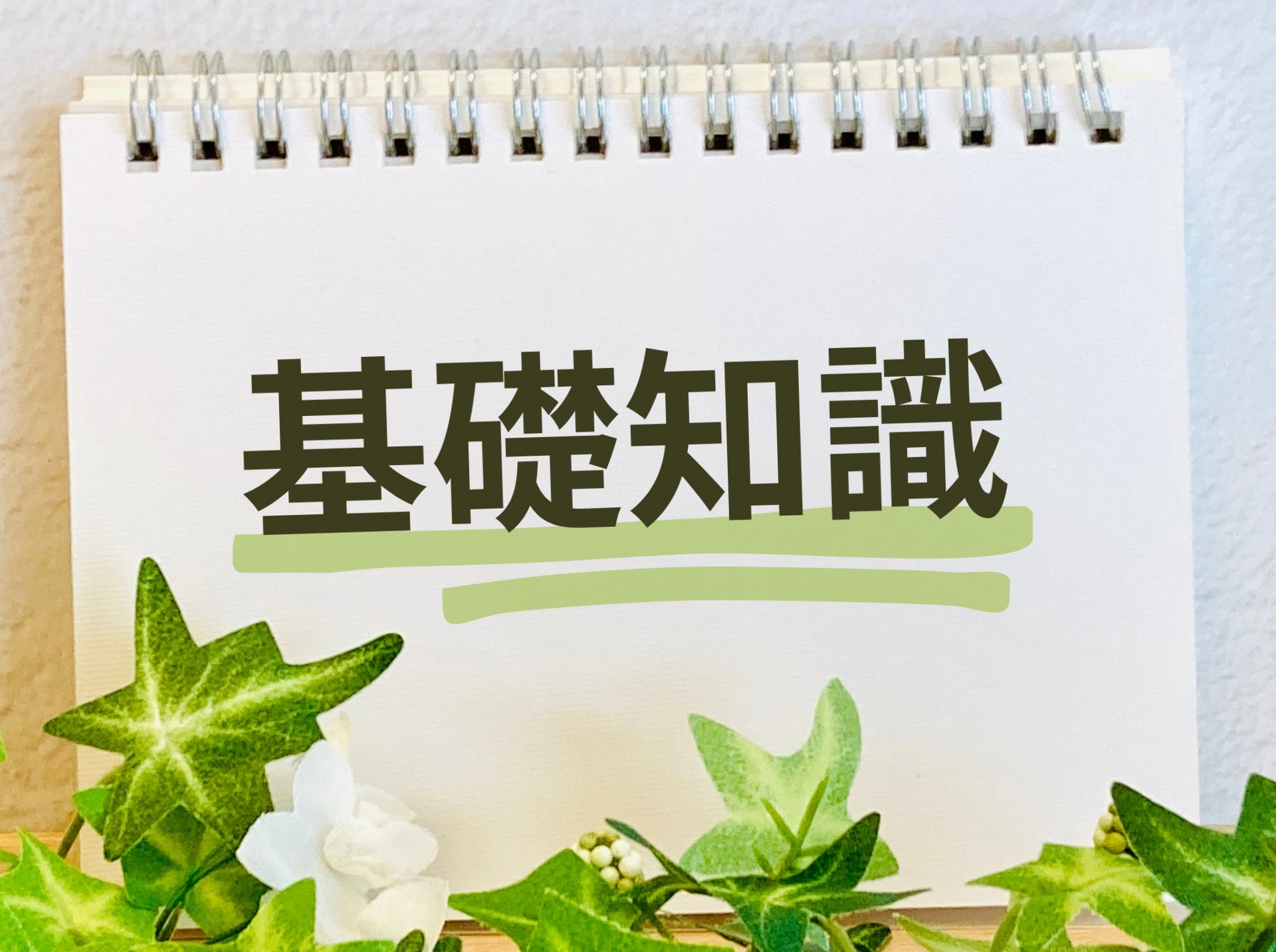
リライトとは何か
リライト(Rewrite)とは、既に公開されている記事やコンテンツを書き直し、改善する作業のことを指します。
単純に文章の表現を変えたり、誤字脱字を修正したりするだけではなく、検索エンジンとユーザーの両方にとってより価値の高いコンテンツに生まれ変わらせることが本来の目的です。
SEOにおけるリライトは、以下のような要素を総合的に見直す作業になります。
| 改善対象 | 具体的な作業内容 |
| タイトルタグ | 対策キーワードの適切な配置、クリック率向上のための訴求力強化 |
| 見出し構成 | ユーザーの検索意図に沿った論理的な構成への変更 |
| 本文内容 | 不足している情報の追加、古い情報の更新、独自性の強化 |
| 内部リンク | 関連記事への適切な誘導、サイト全体の回遊性向上 |
| メタデータ | ディスクリプションの最適化、構造化データの追加 |
従来のWeb制作では「一度公開したらそのまま」という考え方が主流でしたが、現在のSEOでは継続的な改善とメンテナンスが不可欠です。
特に競合が激しいキーワードでは、一度上位表示されても、より良いコンテンツが登場すれば順位が下がってしまうため、定期的なリライトが求められます。
また、リライトは新規記事作成と比べて、既に一定の評価を得ているページの改善であるため、比較的短期間で効果が現れやすいという特徴があります。
SEOにおけるリライトの重要性
現在のSEO環境において、リライトは新規記事作成と同等かそれ以上に重要な施策となっています。
その理由として、まず検索エンジンのアルゴリズムが常に進化し続けていることが挙げられます。
Googleは年に数回のコアアルゴリズムアップデートを実施しており、評価基準の変化に合わせてコンテンツも進化させる必要があります。
また、ユーザーの検索行動や求める情報の質も時代とともに変化しているため、過去に作成したコンテンツでは現在のニーズを満たせない場合があります。
数値的な根拠として、以下のようなデータが報告されています。
| 指標 | リライト実施 | 未実施 |
| 効果が出た記事の割合 | 75% | – |
| 200%以上のセッション増加 | 50% | – |
| 6か月後のセッション維持・増加 | – | 30.2% |
さらに、リライトは新規記事作成よりも工数が少なく、ROIが高い施策でもあります。
すでに検索エンジンにインデックスされているページを改善するため、ゼロからドメインパワーを蓄積する必要がなく、改善効果が比較的早く現れる傾向があります。
競合分析のデータも蓄積されているため、どのような改善を行えば効果的か判断しやすいのも大きなメリットです。
新規記事作成との違い
リライトと新規記事作成には、アプローチ方法や期待できる効果に明確な違いがあります。
まず、情報収集の段階から違いが生まれます。
新規記事では競合分析や検索意図の推測から始める必要がありますが、リライトでは既存記事の実際のパフォーマンスデータを基に改善点を特定できます。
Googleサーチコンソールのデータを見れば、どのキーワードで何位に表示され、どれくらいクリックされているかが正確に把握できるため、より精度の高い改善策を立てられます。
効果が現れるまでの期間にも差があります。
| 比較項目 | 新規記事作成 | リライト |
| 効果が現れる期間 | 3〜6か月 | 1〜3か月 |
| 必要な工数 | 100% | 50〜70% |
| 成功確率 | 不確実 | 既存データに基づき高い |
| ドメイン評価 | ゼロからスタート | 既存評価を活用 |
さらに、リライトはサイト全体のドメインパワー向上にも寄与します。
低品質なコンテンツを改善することで、サイト全体の平均品質が向上し、他のページの検索順位にもプラスの影響を与える可能性があります。
一方、新規記事作成では、記事数の増加によってサイトの専門性を高められる効果がありますが、即効性という観点ではリライトに軍配が上がるといえるでしょう。
リライトが必要な理由

検索順位向上の必要性
現在のデジタルマーケティング環境において、検索順位の向上は企業の生存戦略に直結する重要な課題となっています。
検索順位とクリック率の関係を示すデータによると、1位表示された場合のクリック率は32.35%(デスクトップ)、26.70%(モバイル)となっています。
一方、10位以下になるとクリック率は急激に下降し、2ページ目以降ではほとんどクリックされないのが現実です。
この数値差が、ビジネスに与える影響は計り知れません。
例えば、月間検索ボリューム10,000のキーワードで10位から1位に上昇した場合、月間のアクセス数は約3,000以上増加する計算になります。
| 検索順位 | デスクトップCTR | モバイルCTR | 月間流入数(検索ボリューム10,000) |
| 1位 | 32.35% | 26.70% | 3,235〜2,670 |
| 5位 | 4.15% | 3.15% | 415〜315 |
| 10位 | 1.32% | 1.84% | 132〜184 |
さらに、上位表示されることで得られるのはアクセス数の増加だけではありません。
検索結果の上位に表示されることで、ユーザーからの信頼度や企業のブランド価値も向上します。
多くのユーザーは、検索結果の上位に表示されるサイトを「より信頼できる」「より専門的」と認識する傾向があるためです。
また、SEO経由の流入は、広告と異なり継続的なコストが発生しないという大きなメリットがあります。
一度上位表示を獲得できれば、そのポジションを維持する限り安定した集客が可能になります。
アルゴリズム変更への対応
Googleをはじめとする検索エンジンは、ユーザーにより良い検索体験を提供するため、常にアルゴリズムを改善しています。
特に年に数回実施されるコアアルゴリズムアップデートでは、大幅な順位変動が発生することがあります。
近年の主なアップデートでは、以下のような変化が見られました。
| アップデート時期 | 主な変更内容 | 影響を受けやすいサイト |
| 2024年8月 | ユーザー価値重視の強化 | SEOテクニック重視のサイト |
| 2023年10月 | E-E-A-T評価の厳格化 | 専門性の低いコンテンツ |
| 2023年3月 | AI生成コンテンツの評価変更 | 独自性の乏しいコンテンツ |
これらのアップデートに対応するためには、既存コンテンツの定期的な見直しと改善が不可欠です。
例えば、E-E-A-T(Experience、Expertise、Authoritativeness、Trust)の重要性が高まった際には、執筆者情報の追加や専門的な根拠の補強が必要になります。
また、AI生成コンテンツの台頭により、オリジナリティや独自の視点がより重視されるようになっています。
従来は網羅性があれば評価されていたコンテンツでも、他サイトと似たような内容では上位表示が困難になっているのが現状です。
アルゴリズム変更への対応では、単発の対策ではなく継続的なモニタリングと改善のサイクルを構築することが重要です。
競合サイトの変化
デジタル市場では、競合他社も常にSEO対策を強化しており、相対的な順位競争が激化しています。
一度上位表示を獲得しても、競合がより優れたコンテンツを公開すれば、自社の順位は下がってしまいます。
特に、以下のような変化に注意が必要です。
| 競合の動向 | 自社への影響 | 必要な対策 |
| より詳細なコンテンツの公開 | 検索順位の低下 | 情報量の拡充、専門性の強化 |
| 新しい切り口での記事作成 | ユーザーの流出 | 独自性の追加、差別化ポイントの明確化 |
| 技術的SEOの改善 | ページ評価の相対的低下 | サイト速度改善、構造化データ対応 |
競合分析を継続的に行うことで、市場での自社ポジションを正確に把握できます。
上位表示されている競合サイトがどのような情報を提供しているか、どんな構成になっているか、どのような独自性があるかを分析し、自社コンテンツの改善点を見つけることが重要です。
また、競合が対応していない新しいニーズや情報があれば、それを先取りしてコンテンツに反映することで競争優位を築ける可能性があります。
例えば、法改正や業界の新しいトレンドに真っ先に対応することで、一時的にでも検索上位を獲得できるチャンスが生まれます。
このような競合環境の中で生き残るためには、定期的なリライトによって常にコンテンツの鮮度と競争力を維持することが不可欠です。
リライト対象記事の選び方

検索順位11-30位の記事
検索順位11-30位に位置する記事は、最も効果的なリライト対象として注目すべきです。
この順位帯の記事は、検索エンジンから一定の評価を受けているものの、検索結果の1ページ目に到達していないため、大きな改善余地があります。
特に重要なのは、8-12位の境界線付近にある記事です。
この位置にある記事は、わずかな改善で1ページ目入りを果たし、大幅なアクセス増加が期待できます。
検索順位別のクリック率データを見ると、その効果の大きさが明確になります。
| 検索順位 | 平均CTR | 月間流入数(検索ボリューム1,000の場合) |
| 8位 | 2.31% | 23 |
| 10位 | 1.32% | 13 |
| 15位 | 0.89% | 9 |
| 20位 | 0.65% | 7 |
11-30位の記事を選定する際は、以下の条件を満たすものを優先します。
対策キーワードの検索ボリュームが月間1,000以上あること、公開から3か月以上経過していること、すでに複数のキーワードで検索結果に表示されていることが重要な判断基準となります。
また、Googleサーチコンソールのデータで表示回数は多いがクリック数が少ない記事も、リライトによって大きな効果が期待できます。
このような記事は、検索ユーザーの目には触れているものの、タイトルやスニペットが魅力的でないために選ばれていない可能性が高いためです。
リライト対象として選定した記事は、競合上位サイトとの差分を詳細に分析し、不足している情報や改善すべき構成要素を明確にしてから作業に取りかかりましょう。
アクセス数が減少した記事
過去に安定したアクセスを獲得していたにも関わらず、最近になって流入数が減少している記事は、緊急度の高いリライト対象です。
アクセス数の減少は、複数の要因が考えられますが、主なものとして以下が挙げられます。
競合サイトの台頭、検索エンジンのアルゴリズム変更、情報の陳腐化、ユーザーニーズの変化などです。
Googleアナリティクスで過去6か月から1年間のトラフィック推移を確認し、明確な減少トレンドが見られる記事を特定しましょう。
| 減少パターン | 主な原因 | 対策の方向性 |
| 急激な減少 | アルゴリズム変更、競合の台頭 | 競合分析、技術的SEO改善 |
| 緩やかな減少 | 情報の陳腐化、ニーズ変化 | 情報更新、構成見直し |
| 季節的な減少 | トレンドの変化 | 新しい切り口での情報追加 |
アクセス減少の原因を特定するためには、Googleサーチコンソールのデータと併せて分析することが重要です。
表示回数とクリック数の両方が減っている場合は検索順位の下落、表示回数は維持されているがクリック数が減っている場合はタイトルやスニペットの問題が考えられます。
また、特定のキーワードでのみアクセスが減少している場合は、そのキーワードに関連する競合分析を重点的に行う必要があります。
一方で、複数のキーワードで全体的にアクセスが減少している場合は、記事全体の品質向上や構成の見直しが必要になるでしょう。
アクセス減少への対応は時間との勝負でもあります。
減少トレンドを放置すると、さらなる順位下落を招く可能性があるため、原因を特定次第、速やかにリライト作業に着手することが重要です。
古い情報を含む記事
情報の鮮度は、現代のSEOにおいて極めて重要な評価要素となっています。
古い情報をそのまま掲載している記事は、ユーザーにとって有害となる可能性があり、検索エンジンからの評価も下がりやすくなります。
特に、YMYL(Your Money or Your Life)領域に関する記事では、最新性と正確性が厳格に評価されるため、定期的な情報更新が不可欠です。
公開から1年以上経過
公開から1年以上経過した記事は、情報の陳腐化リスクが高いため、優先的にリライト対象として検討すべきです。
特に以下のような分野の記事は、情報の変化が激しいため注意が必要です。
| 分野 | 主な変化要素 | 更新頻度の目安 |
| IT・テクノロジー | ソフトウェアのバージョンアップ、新サービス | 3〜6か月 |
| 法律・制度 | 法改正、制度変更 | 6か月〜1年 |
| 金融・投資 | 金利変動、税制変更 | 3〜6か月 |
| 医療・健康 | 新しい研究結果、ガイドライン変更 | 6か月〜1年 |
1年以上経過した記事をリライトする際は、単純な情報更新だけでなく、全体的な構成や切り口の見直しも検討しましょう。
過去1年間で業界に新しいトレンドや話題が生まれている場合、それらを反映することで記事の価値を大幅に向上させることができます。
また、公開当時は想定していなかった新しい検索ニーズが生まれている可能性もあります。
関連キーワードの検索ボリューム変化を調査し、現在のユーザーニーズに合わせた情報追加を行うことが重要です。
法改正等で情報が変更
法改正や制度変更により情報が変更されている記事は、最優先でリライトすべき対象です。
古い法的情報を掲載し続けることは、ユーザーに誤った判断をさせる可能性があり、サイトの信頼性に大きな悪影響を与えます。
近年、特に注意が必要な分野として以下が挙げられます。
| 分野 | 主な変更内容 | 影響度 |
| 個人情報保護 | GDPR、改正個人情報保護法 | 高 |
| 働き方改革 | 労働基準法の改正 | 高 |
| 税制 | 消費税率変更、所得税改正 | 高 |
| デジタル関連法規 | プロバイダ責任制限法改正 | 中 |
法改正に関する情報更新では、改正前と改正後の違いを明確に示すことが重要です。
単に新しい情報に差し替えるだけでなく、「何が変わったのか」「いつから適用されるのか」「ユーザーにどんな影響があるのか」を分かりやすく説明しましょう。
また、信頼できる一次情報源からの引用を必ず行い、情報の正確性を担保することが必要です。
官公庁のWebサイトや公式発表資料などを適切に引用し、ユーザーが詳細を確認できるよう配慮しましょう。
法改正に関する記事は、検索ユーザーの関心も高く、適切に更新されていれば大きなアクセス増加が期待できる分野でもあります。
競合分析の方法

上位サイトの構成調査
競合上位サイトの構成分析は、効果的なリライト戦略を立てる上で最も重要な工程です。
対策キーワードで実際に検索を行い、上位10位以内に表示されるサイトの記事構成を詳細に調査しましょう。
分析すべき要素は多岐にわたりますが、特に重要なのは以下の項目です。
タイトルの文字数と訴求ポイント、見出し構成とキーワード配置、記事全体のボリューム、使用されている画像や図表、内部リンクの設置状況などです。
| 分析項目 | 確認ポイント | 自社記事への影響 |
| タイトル構成 | キーワード配置、訴求表現、文字数 | クリック率改善の参考 |
| 見出し構造 | h2、h3の階層、論理的な流れ | ユーザビリティ向上 |
| コンテンツ量 | 文字数、情報の網羅性 | 情報量の充実度判断 |
| 独自性 | オリジナルデータ、体験談 | 差別化要素の発見 |
上位サイトの構成調査では、単純に真似をするのではなく、なぜその構成が評価されているのかを理解することが重要です。
例えば、上位サイトが特定の見出し順序を採用している場合、それがユーザーの情報収集プロセスに沿っているからかもしれません。
また、複数の上位サイトに共通する要素は、そのキーワードで求められる必須情報である可能性が高いため、自社記事にも反映を検討しましょう。
一方で、上位サイトには含まれていない独自の情報や視点を見つけることができれば、それが競合との差別化ポイントになり得ます。
業界の専門知識、実務経験、独自調査データなど、自社だけが提供できる価値を特定し、積極的に記事に盛り込むことで、競合を上回る評価を得られる可能性が高まります。
コンテンツ内容の比較
上位サイトとのコンテンツ内容比較では、情報の質と量の両面から詳細な分析を行う必要があります。
単純な文字数の比較だけでなく、どのような情報が含まれているか、どの程度詳細に解説されているか、どのような根拠やデータが示されているかを総合的に評価しましょう。
分析の際は、以下のような観点で比較を行います。
| 比較観点 | 評価基準 | 改善アクション |
| 情報の網羅性 | 必要な情報が全て含まれているか | 不足情報の追加 |
| 情報の深度 | どの程度詳細に説明されているか | 解説の充実 |
| 根拠の明示 | データや事例が適切に示されているか | 根拠の追加・更新 |
| 独自性 | 他にはない情報や視点があるか | オリジナル要素の強化 |
特に重要なのは、上位サイトが共通して取り上げている情報です。
これらは、そのキーワードで検索するユーザーが必ず知りたがっている情報である可能性が高いため、自社記事にも必須の要素として含める必要があります。
逆に、上位サイトでも触れられていない情報があれば、それを詳細に解説することで検索結果での優位性を築けるかもしれません。
コンテンツ比較の際は、最新性も重要な評価軸となります。
上位サイトの情報が古い場合、より新しい情報や最新のトレンドを反映することで、一気に順位を上げられる可能性があります。
また、ユーザーの理解しやすさも比較対象として重要です。
専門用語の解説、図表の使用、具体例の提示など、どのサイトがよりユーザーフレンドリーな構成になっているかを分析し、自社記事の改善に活かしましょう。
検索意図の再確認
検索意図の正確な把握は、リライト成功の鍵を握る最重要要素です。
同じキーワードでも、時代とともにユーザーの検索意図は変化する可能性があるため、定期的な再確認が必要です。
検索意図は、一般的に以下の4つのタイプに分類されます。
| 検索意図タイプ | 特徴 | 具体例 |
| Know(情報収集) | 何かについて知りたい | 「SEOとは」「リライト方法」 |
| Go(特定サイト) | 特定のサイトやページに行きたい | 「Google アナリティクス ログイン」 |
| Do(行動) | 何かを実行したい | 「SEO対策 やり方」「記事 書き方」 |
| Buy(購入) | 商品やサービスを購入したい | 「SEOツール おすすめ」「格安 SEO対策」 |
検索意図を再確認する方法として、実際の検索結果画面の詳細な分析が最も効果的です。
上位表示されているページのタイプ(情報提供型、商品紹介型、ツール型など)を見ることで、Googleがそのキーワードに対してどのような意図を想定しているかが分かります。
また、関連キーワードや再検索キーワードの変化も重要な手がかりになります。
Googleの検索結果下部に表示される「他のキーワード」や、サジェスト機能で表示されるキーワードを定期的にチェックし、新しいニーズの兆候を察知しましょう。
さらに、ユーザーの検索行動データも検索意図理解に役立ちます。
Googleサーチコンソールで、実際にどのようなクエリで自社記事が表示されているかを確認し、想定していた検索意図と実際のユーザー行動にズレがないかを検証することが重要です。
検索意図が変化している場合は、記事の構成や内容を大幅に見直す必要があります。
例えば、従来は情報収集型だったキーワードが、商品比較型に変化している場合、商品の比較情報や選び方の解説を充実させる必要があるでしょう。
効果的なリライト手順
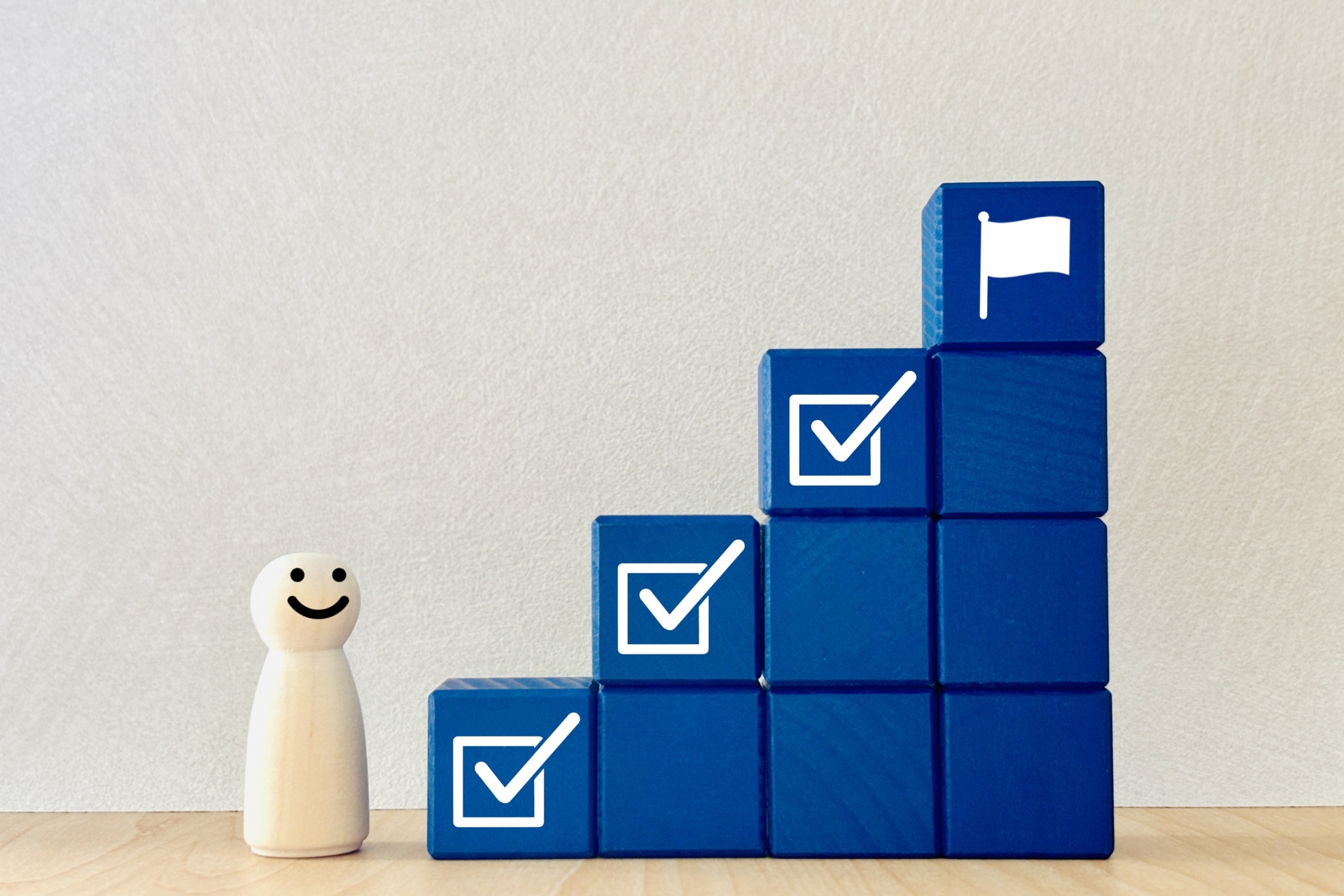
現状分析とゴール設定
効果的なリライトを実現するためには、現状の正確な把握と明確なゴール設定が不可欠です。
まず、対象記事の現在のパフォーマンスを数値で把握しましょう。
GoogleサーチコンソールとGoogleアナリティクスを活用し、検索順位、表示回数、クリック数、平均CTR、セッション数、滞在時間、直帰率などのデータを収集します。
これらのデータから、記事の強みと弱みを明確に特定することが重要です。
| 分析項目 | 現状把握のポイント | 改善の方向性 |
| 検索順位 | 主要キーワードでの順位推移 | 順位向上の可能性と難易度 |
| CTR | 順位に対するクリック率の適切性 | タイトル・スニペット改善の必要性 |
| 滞在時間 | ユーザーの記事満足度 | コンテンツ品質向上の必要性 |
| 直帰率 | 記事の魅力度と関連性 | 構成や内部リンクの改善必要性 |
ゴール設定では、具体的で測定可能な数値目標を設定しましょう。
「検索順位を上げる」という曖昧な目標ではなく、「3か月以内に対策キーワードで5位以内に入る」「月間セッション数を50%増加させる」といった明確な指標を定めることが重要です。
また、競合分析の結果と現状のギャップも明確にしておきましょう。
上位サイトと比較して不足している要素、改善すべきポイントを具体的にリストアップし、優先順位を付けて改善計画を立てます。
さらに、リライトに投入できるリソース(時間、人員、予算)の制約も考慮し、現実的に達成可能なゴールを設定することが成功の秘訣です。
無理な目標設定は、中途半端な改善に終わる可能性が高いため、着実に成果を上げられる範囲で計画を立てましょう。
キーワード調査
リライト時のキーワード調査は、新規記事作成時以上に綿密に行う必要があります。
既存記事が実際にどのキーワードで検索されているか、どのキーワードで順位が付いているかを正確に把握し、それらの情報を基により効果的なキーワード戦略を構築します。
まず、Googleサーチコンソールの「検索結果」データから、現在流入につながっているキーワードを全て抽出しましょう。
| キーワード分析項目 | 調査内容 | 活用方法 |
| 主要流入キーワード | 最もアクセスを集めているキーワード | メインキーワードとして強化 |
| 順位向上可能キーワード | 11-30位に位置するキーワード | リライトで重点的に対策 |
| 関連キーワード | 検索意図が近いキーワード群 | 情報の網羅性向上に活用 |
| 新規獲得可能キーワード | 未対策だが関連性の高いキーワード | 新たな流入源として追加 |
関連キーワードの調査では、複数のツールを組み合わせて使用することをお勧めします。
Googleキーワードプランナー、ラッコキーワード、Answer The Publicなどのツールを活用し、対策キーワードに関連する検索語句を幅広く収集しましょう。
特に重要なのは、「再検索キーワード」の分析です。
Google検索結果の最下部に表示される「他のキーワード」は、ユーザーが最初の検索で満足できずに再検索したキーワードを示しており、コンテンツに不足している情報のヒントになります。
また、共起語の分析も効果的です。
上位表示されているページで頻出する単語を調査し、自社記事で不足している語句があれば自然な形で追加することで、検索エンジンの評価向上が期待できます。
キーワード調査の結果は、優先度を付けて整理し、リライト作業の指針として活用しましょう。
見出し構成の見直し
見出し構成は、ユーザーの読みやすさと検索エンジンの理解しやすさの両方に大きく影響する重要な要素です。
リライト時には、現在の見出し構成が最適かどうかを根本から見直し、必要に応じて大幅な変更を行うことも重要です。
まず、ユーザーの情報収集プロセスを考慮した論理的な構成になっているかを確認しましょう。
タイトルタグの最適化
タイトルタグは、検索結果でのクリック率に最も大きな影響を与える要素です。
効果的なタイトル作成では、以下の要素を適切にバランスさせる必要があります。
| 最適化要素 | 重要なポイント | 具体例 |
| キーワード配置 | 主要キーワードを前方に配置 | 「SEOリライト」を文頭に |
| 文字数 | 32文字以内(スマホ表示を考慮) | タイトルの省略を避ける |
| 訴求力 | 数字や具体的なベネフィットを含める | 「5つのコツ」「30%向上」 |
| 独自性 | 競合との差別化ポイントを示す | 「初心者でも」「実践的な」 |
タイトル最適化では、現在のCTRデータを基に改善効果を測定することが重要です。
Googleサーチコンソールで、順位に対するCTRが平均値を下回っている場合は、タイトルの改善により大幅な流入増加が期待できます。
また、感情に訴えかける表現を適度に取り入れることで、ユーザーの関心を引きやすくなります。
「失敗しない」「確実に」「驚くほど」といった表現は、適切に使用すればクリック率向上に効果的です。
ただし、誇大表現や煽り文句は避け、記事内容と一致した正確な表現を心がけることが重要です。
検索エンジンとユーザーの両方から信頼を失う可能性があるためです。
h2・h3タグの改善
見出しタグ(h2、h3)の最適化は、記事の構造化と検索エンジンの理解促進に直結します。
見出しには、適切にキーワードを配置しつつ、ユーザーにとって分かりやすい表現を使用することが重要です。
見出し改善のポイントを以下にまとめます。
| 改善観点 | 具体的な方法 | 効果 |
| キーワード配置 | 主要・関連キーワードを自然に含める | 検索エンジンの評価向上 |
| 階層構造 | 論理的な情報の流れを作る | ユーザビリティ向上 |
| 文字数 | 簡潔で内容が分かりやすい長さ | 読みやすさの向上 |
| 一貫性 | 表現スタイルを統一する | プロフェッショナルな印象 |
見出しの順序も重要な最適化要素です。
一般的に、ユーザーが知りたい情報の順番で見出しを配置することで、記事の満足度と滞在時間が向上します。
例えば、「基本概念 → 具体的方法 → 注意点 → まとめ」という流れは、多くのテーマで効果的です。
また、見出しだけを読んでも記事の全体像が把握できるような構成を心がけましょう。
多くのユーザーは、まず見出しを流し読みして、興味のある部分を詳しく読む傾向があるためです。
見出し改善の際は、競合上位サイトの見出し構成も参考にしつつ、自社ならではの独自性を加えることで、より魅力的な記事構成を実現できます。
コンテンツの加筆修正
不足情報の追加
競合分析で明らかになった情報不足を補うことは、リライトの最重要タスクです。
上位サイトが共通して取り上げている情報で、自社記事に含まれていない要素は必ず追加しましょう。
ただし、単純に情報を羅列するのではなく、自社独自の視点や経験を加えて差別化を図ることが重要です。
情報追加の優先順位を以下のように設定することをお勧めします。
| 追加情報の種類 | 優先度 | 具体例 |
| 基本的な説明 | 高 | 用語の定義、基本概念 |
| 実践的な手順 | 高 | ステップバイステップの方法論 |
| 具体的な事例 | 中 | 成功事例、失敗例、数値データ |
| 最新の情報 | 中 | 業界トレンド、新しい手法 |
| 補足的な情報 | 低 | 関連知識、豆知識 |
独自性の高い情報を追加することで、競合との明確な差別化が可能になります。
自社の実験結果、顧客事例、業界での経験談、独自調査データなどは、他社では提供できない価値の高い情報です。
例えば、株式会社エッコのようなSEO専門企業であれば、実際のクライアント支援で得られた知見や、独自の分析結果を記事に盛り込むことで、競合を大きく上回る価値を提供できるでしょう。
また、ユーザーが実際に抱えている疑問や課題に対する解答も重要な追加要素です。
FAQ形式での情報追加や、よくある失敗例とその対策などは、ユーザーの満足度向上に大きく貢献します。
古い情報の更新
情報の鮮度維持は、現代SEOにおける必須条件です。
古い情報をそのまま放置することは、ユーザーに害を与える可能性があり、検索エンジンからの評価も下がります。
まず、記事全体を通して日付や数値データ、統計情報をチェックし、最新のものに更新しましょう。
| 更新対象 | チェック内容 | 更新頻度 |
| 統計データ | 最新の調査結果、市場データ | 6か月〜1年 |
| 法規制情報 | 法改正、制度変更 | 即座 |
| ツール情報 | 機能追加、価格変更 | 3か月〜6か月 |
| 業界トレンド | 新しい手法、考え方の変化 | 3か月〜6か月 |
リンク先の確認も重要な更新作業です。
外部リンクが切れていたり、リンク先の情報が変更されている場合は、適切な代替リンクを探すか、リンクを削除して自社内の情報で補完しましょう。
また、画像やスクリーンショットも定期的な更新が必要です。
特にツールの使い方を説明している記事では、インターフェースの変更により古いスクリーンショットが役に立たなくなっている可能性があります。
情報更新の際は、変更点を明確に示すことも重要です。
「2024年の最新情報に更新」「法改正に伴い情報を更新」などの注記を追加することで、ユーザーに情報の新しさをアピールできます。
さらに、更新日の記載も忘れずに行いましょう。
記事の更新日が明記されていることで、ユーザーは情報の新しさを判断でき、検索エンジンも最新性を評価しやすくなります。
リライトのコツと注意点

削除よりも加筆を重視
リライトの基本方針として、既存コンテンツの削除は最小限に留め、加筆による改善を優先することが重要です。
これは、既存の記事がすでに一定のSEO評価を獲得している可能性があり、安易な削除によってその評価を失うリスクがあるためです。
特に、検索順位11-30位に位置している記事は、検索エンジンから一定の評価を受けている証拠です。
そのような記事のコンテンツを大幅に削除してしまうと、現在獲得している評価まで失ってしまう可能性があります。
加筆を重視する具体的なアプローチを以下に示します。
| 改善方法 | 適用場面 | 期待効果 |
| 情報の追加 | 競合より情報量が少ない場合 | 網羅性向上、検索順位上昇 |
| 詳細化 | 説明が浅い部分 | ユーザー満足度向上 |
| 最新情報の追加 | 情報が古くなっている部分 | 鮮度向上、信頼性確保 |
| 独自情報の追加 | 差別化が必要な場合 | 独自性向上、競合優位性 |
ただし、明らかに間違った情報や、検索意図から大きく外れた内容については削除が必要です。
また、同じ内容が重複している場合や、記事のテーマと関連性の低い情報も削除を検討すべきでしょう。
削除を行う際は、削除する理由を明確にし、その部分を改善された内容で置き換えることが重要です。
単純に削除するだけでは記事のボリュームが減ってしまい、相対的な競争力が低下する可能性があります。
また、内部リンクの調整も加筆重視のアプローチで重要な要素です。
新しく追加したコンテンツに関連する他の記事があれば、適切に内部リンクを設置し、サイト全体の価値向上を図りましょう。
ユーザビリティの向上
ユーザビリティの向上は、検索エンジン評価の向上に直結する重要な改善要素です。
どれほど有益な情報を提供していても、ユーザーにとって読みにくい記事では、滞在時間の短縮や直帰率の上昇を招き、SEO評価が下がってしまいます。
ユーザビリティ向上のための具体的な改善ポイントを以下にまとめます。
| 改善要素 | 具体的な対策 | 効果 |
| 文章の読みやすさ | 段落分け、適切な改行、漢字比率の調整 | 読了率向上 |
| 視覚的な工夫 | 太字、色付け、表、箇条書きの活用 | 理解度向上 |
| 画像・図表 | 説明を補助する視覚的要素の追加 | 分かりやすさ向上 |
| ナビゲーション | 目次、内部リンク、関連記事の設置 | ユーザー体験向上 |
文章の構造も重要な改善対象です。
長すぎる段落は分割し、一文が長くなりすぎないよう調整しましょう。
また、結論を先に述べる構成(PREP法:Point、Reason、Example、Point)を意識することで、ユーザーが素早く必要な情報を見つけられるようになります。
表や箇条書きの効果的な活用も、ユーザビリティ向上に大きく貢献します。
複雑な情報や比較データは、文章よりも表形式で提示する方が理解しやすくなります。
手順を説明する際は、番号付きリストを使用することで、ユーザーが迷わずに作業を進められるでしょう。
さらに、スマートフォンでの読みやすさも重要な考慮点です。
現在はモバイルファーストインデックスが採用されているため、スマートフォンでの表示を優先して最適化する必要があります。
文字サイズ、行間、画像サイズなどをモバイル環境に適したものに調整しましょう。
E-E-A-Tの強化
E-E-A-T(Experience、Expertise、Authoritativeness、Trust)の強化は、現代SEOにおける最重要課題の一つです。
特にYMYL(Your Money or Your Life)領域では、E-E-A-Tの評価が検索順位に大きな影響を与えるため、リライト時には必ず強化を図る必要があります。
各要素の強化方法を具体的に説明します。
| E-E-A-T要素 | 強化方法 | 具体例 |
| Experience(経験) | 実体験や実例の追加 | 実際の取組結果、事例紹介 |
| Expertise(専門性) | 専門知識の深掘り | 詳細な解説、専門用語の説明 |
| Authoritativeness(権威性) | 執筆者情報の明示 | プロフィール、実績、資格 |
| Trust(信頼性) | 情報源の明示 | 引用元、参考文献、データソース |
Experience(経験)の強化では、実際に手法を試した結果や、具体的な数値データを盛り込むことが効果的です。
「理論的にはこうなる」ではなく、「実際に試したところ、このような結果が得られた」という実体験ベースの情報は、ユーザーにとって非常に価値が高くなります。
Expertise(専門性)の向上では、業界の専門知識を活かした深い解説を心がけましょう。
表面的な情報だけでなく、「なぜそうなるのか」「どのような仕組みで機能するのか」といった背景知識まで含めることで、専門性をアピールできます。
Authoritativeness(権威性)の確立には、執筆者や監修者の情報を明確に示すことが重要です。
記事の最後に執筆者プロフィールを追加し、その分野での経験や実績を具体的に記載しましょう。
Trust(信頼性)の担保では、情報の出典を明確にし、信頼できるソースからの引用を行うことが必要です。
官公庁のデータ、学術論文、業界団体の調査結果などを適切に引用し、情報の正確性を示しましょう。
内部リンクの最適化
内部リンクの戦略的な設置は、サイト全体のSEO価値を高める重要な施策です。
リライト時には、新しく追加したコンテンツに関連する他の記事への適切なリンクを設置し、ユーザーの回遊性向上とクローラビリティの改善を図りましょう。
効果的な内部リンク設置の原則を以下に示します。
| 設置原則 | 具体的な方法 | 効果 |
| 関連性の高いページへのリンク | トピックが関連する記事への誘導 | ユーザー満足度向上 |
| 自然な文脈でのリンク設置 | 読み流れを妨げない位置への配置 | ユーザビリティ維持 |
| アンカーテキストの最適化 | リンク先の内容が分かる表現 | クローラビリティ向上 |
| 適切なリンク数 | 1記事あたり3-5個程度 | バランスの取れた誘導 |
関連記事への誘導では、ユーザーの情報収集プロセスを考慮したリンク設置が重要です。
例えば、SEOリライトの記事では、「SEO基礎知識」「キーワード選定方法」「コンテンツマーケティング戦略」などの関連記事にリンクすることで、ユーザーのより深い学習をサポートできます。
アンカーテキストは、リンク先の内容を正確に表現する自然な文章にしましょう。
「詳しくはこちら」「クリック」といった曖昧な表現ではなく、「SEOキーワード選定の具体的手順」のように、リンク先で得られる情報を明確に示すことが重要です。
また、サイト構造を意識したリンク設置も効果的です。
上位カテゴリーの記事から下位記事へのリンク、関連するシリーズ記事間でのリンクなど、サイト全体の情報構造を強化する配置を心がけましょう。
外部リンクとのバランスも考慮が必要です。
内部リンクばかりでは自己完結的になってしまうため、信頼できる外部ソースへのリンクも適度に含めることで、情報の客観性と信頼性を高められます。
効果測定と継続改善

リライト後の順位変動監視
リライト効果を正確に把握するためには、継続的な順位変動監視が不可欠です。
リライト実施後は、最低でも3か月間は毎週順位をチェックし、改善効果を定量的に測定しましょう。
順位変動の監視では、以下の項目を重点的に追跡します。
| 監視項目 | 測定頻度 | 確認ポイント |
| 主要キーワード順位 | 毎日 | 対策キーワードでの順位推移 |
| 関連キーワード順位 | 週1回 | 新規獲得キーワードの有無 |
| 検索ボリューム | 月1回 | キーワードトレンドの変化 |
| 競合順位 | 週1回 | 競合サイトとの相対位置 |
リライト効果が現れるタイミングは、一般的に1-4週間程度ですが、大規模な変更の場合はより長期間を要することがあります。
順位変動には複数の要因が影響するため、他の変動要因との切り分けが重要です。
Googleのアルゴリズムアップデート、競合サイトの動向、季節的な検索トレンドの変化なども順位に影響するため、これらの外部要因も併せて分析する必要があります。
順位上昇が見られた場合は、どの改善要素が効果的だったかを分析し、他の記事のリライトにも応用しましょう。
逆に、順位下降や横ばいの場合は、追加の改善策を検討する必要があります。
順位監視には、GRC、Ahrefs、SEMrushなどの専門ツールの活用をお勧めします。
これらのツールを使用することで、効率的で正確な順位追跡が可能になり、改善効果の測定精度が向上します。
アクセス数・コンバージョンの確認
順位向上の最終目的は、アクセス数の増加とビジネス成果の向上です。
検索順位の改善が実際の流入増加に繋がっているか、さらにはコンバージョンに貢献しているかを定期的に確認しましょう。
Googleアナリティクスを活用し、以下の指標を継続的に監視します。
| 測定指標 | 確認内容 | 改善の判断基準 |
| オーガニック流入数 | 自然検索からの訪問者数 | リライト前比20%以上の増加 |
| 滞在時間 | ページでの平均滞在時間 | リライト前比10%以上の向上 |
| 直帰率 | 1ページのみで離脱する率 | リライト前比10%以上の改善 |
| コンバージョン率 | 問い合わせや購入などの達成率 | リライト前比5%以上の向上 |
流入の質的変化も重要な評価要素です。
単純にアクセス数が増えただけでなく、より質の高いユーザーが流入しているかを確認しましょう。
例えば、「SEOリライト」で流入したユーザーが、その後「SEOコンサルティング」に関する記事も閲覧し、最終的に問い合わせに至るような導線が機能しているかを分析します。
コンバージョンへの貢献度測定では、アトリビューション分析が有効です。
リライトした記事が直接的なコンバージョンに繋がらなくても、ユーザーの最初の接点として機能し、後にコンバージョンに貢献している可能性があります。
株式会社エッコのようなBtoB企業では、リード獲得までの接触回数や検討期間も考慮して効果測定を行うことが重要です。
SEO記事での情報収集から、サービス詳細ページの閲覧、資料ダウンロード、問い合わせまでの一連の流れを追跡し、リライトが全体的なマーケティングファネルに与える影響を評価しましょう。
PDCAサイクルの実践
継続的な改善を実現するためには、体系的なPDCAサイクルの実践が不可欠です。
リライトは一度実施すれば終わりではなく、定期的な見直しと改善を繰り返すことで、長期的な成果を維持・向上させることができます。
Plan(計画)フェーズでは、具体的で測定可能な改善目標を設定することが重要です。
「検索順位を上げる」という曖昧な目標ではなく、「3か月以内に対策キーワードで10位以内に入り、月間流入数を50%増加させる」といった明確な数値目標を立てましょう。
また、改善施策の優先順位付けも重要です。
リソースは限られているため、最も効果が期待できる施策から順番に実施し、段階的に改善を進めることが成功の鍵となります。
Do(実行)フェーズでは、計画した施策を確実に実行することが求められます。
リライト作業のチェックリストを作成し、作業漏れやミスを防ぐ仕組みを構築しましょう。
また、実行過程で気づいた改善点は記録し、次回の計画立案に活かすことが重要です。
Check(評価)フェーズでは、設定した指標に基づいて客観的な効果測定を行います。
感覚的な評価ではなく、データに基づいた正確な分析を心がけ、成功要因と失敗要因を明確に特定することが次の改善に繋がります。
Act(改善)フェーズでは、評価結果を基に次回の施策を立案します。
成功した施策は他の記事にも横展開し、失敗した施策は原因を分析して改善策を検討しましょう。
このようなPDCAサイクルを継続することで、組織全体のSEOスキルが向上し、より効率的で効果的なリライトが可能になります。
まとめ

本記事では、SEOリライトで検索順位を向上させるための体系的な手順とコツについて詳しく解説してきました。
リライトは新規記事作成よりも効率的で、75%の記事で効果が確認されている実証済みの施策です。
特に検索順位11-30位の記事や、アクセス数が減少している記事は、適切なリライトにより大幅な改善が期待できます。
成功するリライトの要点を振り返ると、まず現状分析と明確なゴール設定から始まり、競合分析に基づく戦略的な改善を実施することが重要です。
削除よりも加筆を重視し、E-E-A-Tの強化とユーザビリティの向上を図りながら、継続的な効果測定とPDCAサイクルの実践により長期的な成果を維持できます。
特に重要なのは、単発の作業として捉えるのではなく、継続的な改善プロセスとして位置づけることです。
検索エンジンのアルゴリズムは常に進化し、競合他社も改善を続けているため、一度の改善で満足せず、定期的な見直しと最適化を続けることが成功の鍵となります。
効果的なSEOリライトの実践には、専門的な知識と豊富な経験が必要です。
自社での実施が困難な場合や、より専門的なサポートが必要な場合は、SEOの専門家に相談することをお勧めします。
株式会社エッコでは、データに基づいた戦略的なSEOリライト支援を提供しており、多くの企業様の検索順位向上とビジネス成果の最大化をサポートしています。
継続的なSEO成果を実現し、競合他社に差をつけたい企業様は、ぜひ専門家のサポートを活用しながら、体系的なリライト施策に取り組んでいただければと思います。
あなたのWebサイトが検索エンジンで上位表示を獲得し、ビジネス目標の達成に大きく貢献することを心から願っています。



