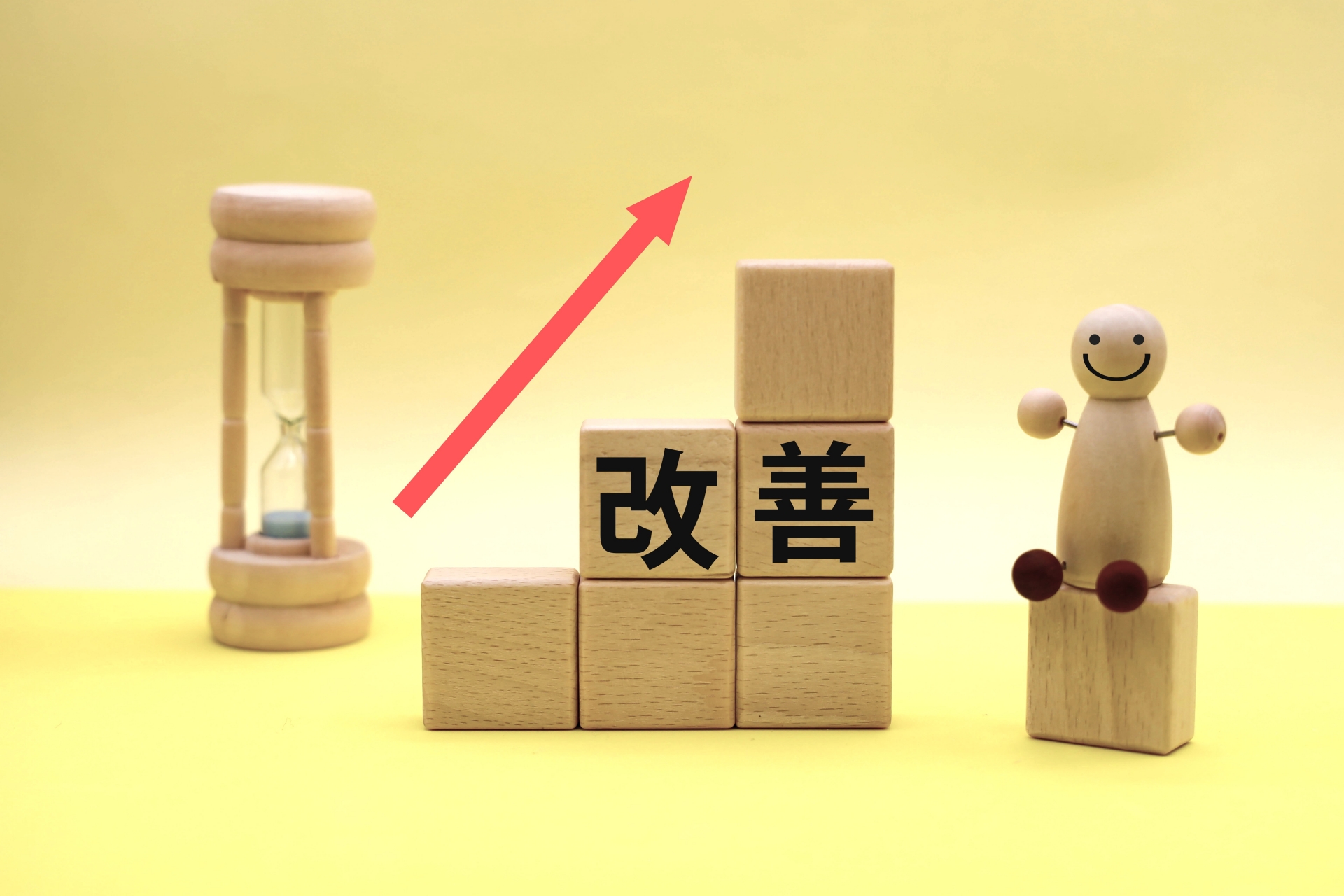「Webサイトをそろそろリニューアルしたいけれど、何から始めればいいのかわからない」
このような悩みを抱えている企業のWeb担当者は少なくありません。
サイトリニューアルは、単にデザインを新しくするだけの作業ではありません。
企業の成長戦略を支える重要なプロジェクトであり、進め方を間違えると時間と費用を無駄にするだけでなく、検索順位の下落やコンバージョン率の低下を招くリスクもあります。
実際に、目的を明確にしないままリニューアルを進めた結果、アクセス数が半減してしまったという失敗事例も数多く存在します。
本記事では、サイトリニューアルの基本的な考え方から具体的な手順、成功のポイント、よくある失敗例まで、実務で役立つ情報を網羅的に解説していきます。
これからリニューアルを検討している方はもちろん、すでにプロジェクトが進行中の方にも参考になる内容をお届けします。
最後まで読んでいただければ、失敗しないサイトリニューアルの全体像をつかむことができるでしょう。
Index
サイトリニューアルとは?目的と必要性
サイトリニューアルの定義
サイトリニューアルとは、既存のWebサイトに対して大規模な変更を加え、新しいサイトへと生まれ変わらせる取り組みのことです。
具体的には、デザインの刷新やサイト構造の見直し、システム基盤の変更、コンテンツの再構築などを総合的におこないます。
一般的なサイト更新が既存の枠組みのなかでの改修であるのに対し、リニューアルはサイト全体を根本から見直す点が大きな違いといえるでしょう。
企業がサイトリニューアルをおこなう目的は、業種や事業フェーズによってさまざまです。
- 集客力の強化(アクセス数やお問い合わせ数の増加)
- ブランドイメージの刷新(企業の新しい方向性を反映)
- ユーザビリティの向上(使いやすさの改善による離脱率低下)
- コンバージョン率の改善(売上や成約数のアップ)
- 運用効率の向上(更新作業の簡素化やコスト削減)
重要なのは、リニューアル自体を目的にしないことです。
「なぜリニューアルが必要なのか」「リニューアルによって何を達成したいのか」を明確にすることが、成功への第一歩となります。
名古屋でWebコンサルティングを手がける株式会社エッコでは、こうした目的設定の段階から企業をサポートしています。
リニューアルが必要とされる背景
近年、サイトリニューアルの重要性はますます高まっています。
その背景には、Webを取り巻く環境の急速な変化があります。
ある調査によると、企業の約39%が2〜3年に1回、約33%が毎年サイトリニューアルを実施しているというデータがあります。
かつては5年以上同じサイトを運用する企業も珍しくありませんでしたが、現在では3〜4年程度でのリニューアルが一般的になりつつあるのです。
| リニューアルが求められる背景 | 具体的な変化 |
| ユーザー行動の変化 | スマートフォン利用の増加、情報収集方法の多様化 |
| 検索エンジンの進化 | モバイルファーストインデックス、コアウェブバイタル重視 |
| デザイントレンドの変化 | フラットデザイン、ミニマルデザインの普及 |
| セキュリティ要件の厳格化 | SSL対応必須化、脆弱性対策の重要性向上 |
| 競合環境の激化 | 競合他社のサイト品質向上、差別化の必要性 |
特にBtoC企業では、ユーザーの目が肥えているため、古いデザインや使いにくいサイトは即座に離脱される傾向があります。
BtoB企業においても、取引先の信頼を得るために、時代に合ったサイト運営が求められるようになりました。
こうした環境変化に対応するため、定期的なサイトリニューアルは企業にとって避けて通れない課題となっています。
単なる更新との違い
サイトリニューアルと通常のサイト更新は、似ているようで本質的に異なります。
この違いを理解しておくことは、適切な施策を選択するうえで非常に重要です。
通常のサイト更新とは、既存のサイト構造やデザインの枠組みを維持したまま、部分的な改修をおこなうことを指します。
たとえば、新しいお知らせを追加する、商品情報を更新する、一部のページのテキストを修正するといった作業が該当します。
- サイト更新:既存の枠組み内での部分的な改修
- サイトリニューアル:サイト全体の抜本的な見直しと再構築
- サイト改善:データに基づく継続的な最適化活動
- リプレイス:デザインを維持したままCMSやシステムを入れ替える作業
一方、サイトリニューアルでは、サイトの目的や戦略から見直すことが前提となります。
情報設計を一からおこない、デザインコンセプトを策定し、必要に応じてシステム基盤も刷新します。
工数も費用も通常の更新作業とは桁違いになることが多いため、事前の計画と準備が欠かせません。
どちらの施策が適切かは、現状の課題や達成したい目標によって異なります。
「なんとなくサイトが古くなったから」という理由だけでリニューアルを決めると、必要以上のコストをかけてしまう可能性もあるでしょう。
まずは自社の課題を整理し、リニューアルが本当に最適な解決策なのかを見極めることが大切です。
サイトリニューアルを検討すべきタイミング
デザインやシステムの老朽化
サイトリニューアルを検討する最も一般的なきっかけが、デザインやシステムの老朽化です。
Webデザインにはトレンドがあり、一般的に2〜3年周期で変化するといわれています。
5年以上前に制作したサイトは、現在のユーザーから見ると「古臭い」と感じられる可能性が高いでしょう。
デザインの古さは、単なる見た目の問題にとどまりません。
ユーザーに「この会社は本当に今も営業しているのだろうか」という不信感を与え、ビジネス機会の損失につながるリスクがあります。
| 老朽化のサイン | 具体的な症状 |
| デザイン面 | フラッシュを使用している、影や立体感のある古いデザイン |
| システム面 | サポートが終了したCMSやプラグインを使用している |
| 表示面 | スマートフォンで正常に表示されない、表示速度が遅い |
| 機能面 | 必要な機能が追加できない、更新作業に時間がかかる |
| セキュリティ面 | SSL非対応、セキュリティパッチが当てられない |
システム面では、古いCMSを使い続けることでセキュリティリスクが高まるという問題もあります。
サポートが終了したシステムは脆弱性が放置されやすく、サイバー攻撃の標的になりやすいのです。
競合他社のサイトと見比べて明らかに見劣りする場合は、リニューアルを本格的に検討する時期といえるでしょう。
コンバージョン率の低下
アクセス数は維持できているのに、お問い合わせや資料請求の数が減少しているという状況は、リニューアルを検討すべき重要なシグナルです。
コンバージョン率の低下には、さまざまな原因が考えられます。
ユーザーが求める情報に辿り着けない導線設計の問題、競合と比較して魅力が伝わらないコンテンツの問題、入力フォームの使いにくさなど、原因は多岐にわたります。
- お問い合わせフォームまでの導線が複雑になっている
- ユーザーが求める情報と提供している情報にズレがある
- 競合サイトと比較して訴求力が弱くなっている
- サイトの読み込み速度が遅く離脱されている
- スマートフォンでの操作性が悪い
これらの問題が複合的に絡み合っている場合、部分的な改修では根本的な解決が難しいこともあります。
サイト全体の構造を見直し、ユーザーの行動導線を再設計するリニューアルが効果的な選択肢となるでしょう。
Googleアナリティクスなどのツールで現状を分析し、どこで離脱が発生しているのかを把握することが、判断の第一歩です。
企業戦略やブランディングの変更
企業の経営戦略が変化したタイミングも、サイトリニューアルの好機です。
新規事業の立ち上げ、主力サービスの転換、ターゲット顧客の変更、M&Aによる企業統合など、事業環境が大きく変わる場面では、Webサイトもそれに合わせて変革する必要があります。
特にリブランディングをおこなう場合は、コーポレートカラーやロゴ、キービジュアルなどの変更に伴い、サイト全体のデザインを刷新することが一般的です。
| 戦略変更のパターン | サイトリニューアルの方向性 |
| 新規事業の立ち上げ | 新サービス専用のサイト構築または既存サイトへの統合 |
| ターゲット変更 | ペルソナの再設定とそれに合わせたコンテンツ・デザイン刷新 |
| リブランディング | 新しいブランドイメージを反映したビジュアルへの変更 |
| 企業統合 | 複数サイトの統合と情報の整理・再構築 |
| 海外展開 | 多言語対応とグローバル向けコンテンツの追加 |
古い情報が残ったままのサイトは、ユーザーに混乱を与える原因になります。
「以前のサービスしか載っていない」「会社の雰囲気と合っていない」と感じさせてしまうと、せっかくの事業変革も効果が半減してしまうでしょう。
企業戦略の転換期こそ、サイトリニューアルを検討するベストなタイミングです。
モバイル対応やアクセシビリティの課題
2018年にGoogleが導入したモバイルファーストインデックスにより、スマートフォン対応は必須となりました。
モバイルファーストインデックスとは、検索エンジンがWebサイトを評価する際に、スマートフォン版のページを基準にする仕組みです。
パソコン版しか用意していないサイトや、スマートフォンで見づらいサイトは、検索順位で不利になる可能性が高まっています。
- レスポンシブデザインに対応していない
- スマートフォンで文字が小さすぎて読めない
- タップしにくいボタンやリンクが多い
- 横スクロールが必要なページがある
- 画像が最適化されておらず表示が遅い
総務省の調査によると、個人のインターネット利用機器はスマートフォンが68.5%に達し、パソコンの48.1%を上回っています。
つまり、多くのユーザーはスマートフォンでサイトを閲覧しているのです。
アクセシビリティの観点からも、すべてのユーザーが快適に利用できるサイト設計が求められるようになっています。
視覚や聴覚に障がいのある方、高齢者など、多様なユーザーへの配慮は企業の社会的責任としても注目されています。
セキュリティやCMS機能の更新ニーズ
Webサイトを安全に運用するためには、セキュリティ対策が欠かせません。
2018年以降、SSL化(https対応)されていないサイトは、ブラウザで「保護されていません」と警告が表示されるようになりました。
この警告を見たユーザーは不安を感じ、サイトから離脱してしまう可能性が高くなります。
| セキュリティ・CMS関連の課題 | リスクと影響 |
| SSL非対応 | ブラウザでの警告表示、検索順位への悪影響 |
| 古いCMSの使用 | セキュリティホールの放置、サイバー攻撃のリスク |
| サポート終了プラグイン | 脆弱性の修正がおこなわれない |
| 更新しにくいシステム | 運用コストの増大、情報発信の遅延 |
| バックアップ機能の欠如 | データ消失時の復旧困難 |
また、CMS(コンテンツ管理システム)の機能が時代遅れになっているケースも少なくありません。
最新のCMSでは、SEO対策に必要な設定が自動化されていたり、サイトマップの送信が簡単におこなえたりと、運用効率が大幅に向上しています。
更新作業に毎回外部の制作会社を頼らなければならない状況は、スピーディーな情報発信の妨げになります。
社内で簡単に更新できる環境を整えることも、サイトリニューアルの重要な目的の一つといえるでしょう。
サイトリニューアルの手順【6ステップ】
ステップ1:目的とKPI設定
サイトリニューアルで最も重要なのが、プロジェクトの目的を明確に定めることです。
「デザインが古くなったから」「競合がリニューアルしたから」という漠然とした理由では、成功するリニューアルは実現できません。
まず、自社が抱える経営課題を整理し、その課題解決にWebサイトがどう貢献できるのかを考えましょう。
目的が定まったら、次にKGI(重要目標達成指標)とKPI(重要業績評価指標)を設定します。
| 指標の種類 | 内容 | 具体例 |
| KGI | 最終的に達成したい目標 | 売上20%アップ、問い合わせ数月50件 |
| KPI | KGI達成のための中間指標 | セッション数、CVR、直帰率、ページ滞在時間 |
たとえば「売上を増やしたい」という目的であれば、「月間の問い合わせ数を現状の30件から50件に増やす」というKGIを設定します。
そのうえで、「サイトへのアクセス数を1.5倍にする」「コンバージョン率を2%から3%に改善する」といったKPIを定めていきます。
数値で測定できる目標を設定することで、リニューアル後の効果検証が可能になります。
目標設定に不安がある場合は、Webコンサルティング会社に相談するのも一つの方法です。
名古屋を拠点とする株式会社エッコでは、こうした目標設計の段階からサポートを提供しています。
ステップ2:現状分析と課題の洗い出し
目的とKPIが定まったら、次は現状のサイトを徹底的に分析します。
現状を正しく把握しなければ、適切な改善策を打つことはできません。
分析には、数値データに基づく定量分析と、ユーザーの声を拾う定性分析の両方が必要です。
- 定量分析:アクセス解析ツールを使った数値の把握
- 定性分析:ユーザーテストやヒアリングによる課題発見
- 競合分析:競合サイトとの比較による強み・弱みの把握
- 技術分析:サイトの表示速度やSEO状況のチェック
この段階で手を抜くと、見当違いな施策にリソースを費やしてしまうリスクがあります。
時間をかけてでも、現状を正確に把握することが成功への近道です。
アクセス解析による定量分析
定量分析では、Googleアナリティクスなどの解析ツールを活用します。
現在のサイトがどのような状態にあるのか、数値データから客観的に把握することが目的です。
確認すべき主な指標は多岐にわたります。
| 分析項目 | 確認ポイント |
| セッション数 | サイト全体への訪問数の推移 |
| ページビュー数 | 各ページがどれだけ閲覧されているか |
| 直帰率 | 1ページだけ見て離脱するユーザーの割合 |
| 平均滞在時間 | ユーザーがサイトに滞在している時間 |
| コンバージョン率 | お問い合わせや購入に至る割合 |
| 流入経路 | 検索、SNS、広告など、どこからユーザーが来ているか |
| デバイス比率 | PC、スマートフォン、タブレットの利用割合 |
特に注目すべきは、どのページで離脱が発生しているかという点です。
離脱率が高いページには、何らかの問題が潜んでいる可能性があります。
表示速度が遅い、コンテンツが期待と異なる、次のアクションがわかりにくいなど、原因を特定することでリニューアルの方向性が見えてきます。
また、Google Search Consoleを使えば、どのキーワードで検索されているか、どのページが検索結果に表示されているかを確認できます。
SEOの観点からも現状を把握しておくことが重要です。
ユーザーテストやヒアリングによる定性分析
数値データだけでは見えない課題を発見するために、定性分析も欠かせません。
定性分析とは、ユーザーの声や行動を観察することで、数字には表れない課題や改善点を見つける手法です。
代表的な方法としては、ユーザーテストがあります。
- 実際のユーザーにサイトを操作してもらい、行動を観察する
- 操作中の感想や疑問点を声に出してもらう(シンクアラウド法)
- 社内メンバーに「初めてサイトを訪れたユーザー」として操作してもらう
- 営業担当者に顧客からよく聞かれる質問をヒアリングする
- お問い合わせフォームからの質問内容を分析する
ユーザーテストを実施すると、「このボタンが目立たなくて気づかなかった」「どこをクリックすればいいかわからなかった」といった具体的な課題が浮き彫りになります。
社内メンバーへのヒアリングも有効です。
営業担当者は「お客様からこういう質問をよく受ける」という情報を持っていることが多く、サイトに掲載すべきコンテンツのヒントになります。
定量分析と定性分析を組み合わせることで、より精度の高い課題発見が可能になります。
ステップ3:戦略立案と要件定義
現状分析で課題が明確になったら、次はリニューアルの戦略を立案します。
どのような方向性でサイトを改善するのか、具体的な施策を決めていく段階です。
この段階でまとめる内容は、後の制作工程の土台となります。
| 要件定義に含める項目 | 内容 |
| リニューアルの目的と目標 | 何を達成するためのリニューアルか |
| ターゲットユーザー | 誰に向けたサイトにするのか |
| サイト構造 | どのようなページ構成にするのか |
| 必要な機能 | お問い合わせフォーム、検索機能、会員機能など |
| 使用するCMS | WordPress、Movable Typeなど |
| デザインの方向性 | 参考サイトやイメージカラーなど |
| スケジュール | いつまでに公開するのか |
| 予算 | どの程度の費用をかけられるのか |
要件定義書としてまとめておくことで、制作会社への依頼もスムーズになります。
曖昧な状態で制作に入ると、後から「思っていたのと違う」というトラブルが発生しやすくなります。
ターゲットユーザーの再設定
サイトリニューアルにあたっては、ターゲットユーザーを改めて明確にする必要があります。
既存サイトを制作した当時と現在では、事業環境や顧客層が変化している可能性があるためです。
ペルソナ(理想的な顧客像)を設定し、そのユーザーがどのような情報を求めているのかを具体的に描き出しましょう。
- 年齢、性別、職業、役職
- 抱えている課題や悩み
- サイトを訪れる目的
- どのような情報を求めているか
- どのようなデバイスで閲覧するか
- 購入や問い合わせに至るまでの心理プロセス
BtoBサイトの場合、サイトを閲覧する担当者と最終的な意思決定者が異なることも多いです。
複数の決裁者がいることを想定したコンテンツ設計が求められます。
客観的なデータや導入事例など、社内稟議を通しやすい情報を充実させることが効果的です。
サイト構造とコンテンツ設計
ターゲットが明確になったら、サイト全体の構造を設計します。
サイトマップを作成し、どのようなページを用意するか、ページ同士をどう繋げるかを決めていきます。
理想的なサイト構造は、トップページから3クリック以内ですべてのページにアクセスできる状態です。
| サイト構造設計のポイント | 内容 |
| 階層の深さ | 深くなりすぎないよう3階層程度に抑える |
| ナビゲーション | ユーザーが迷わない分かりやすいメニュー構成 |
| 導線設計 | お問い合わせや購入につながる自然な流れ |
| コンテンツの優先順位 | 重要な情報ほどアクセスしやすい位置に配置 |
| 内部リンク | 関連するページ同士を適切にリンク |
コンテンツ設計では、ユーザーの検討段階に応じた情報提供を意識しましょう。
認知段階のユーザーには課題解決型のコラムや導入事例、比較検討段階のユーザーには詳細な機能説明や料金表、導入フローなどが有効です。
既存コンテンツの棚卸しもおこない、残すもの、統合するもの、削除するものを整理しておきます。
ステップ4:デザイン・開発の実施
要件定義が固まったら、実際のデザイン・開発作業に入ります。
この段階は専門的なスキルが必要なため、多くの企業では制作会社に依頼することになります。
デザイン工程では、まずワイヤーフレーム(ページのレイアウト設計図)を作成し、その後デザインカンプ(完成イメージ)を制作します。
- ワイヤーフレーム作成:各ページのレイアウトと要素配置を決定
- デザインカンプ作成:実際の色やフォント、画像を反映したビジュアル
- デザイン確定:依頼者の確認を経て最終決定
- コーディング:HTML、CSS、JavaScriptでデザインを実装
- CMS構築:WordPressなどのシステムにコンテンツを組み込み
- 機能実装:お問い合わせフォームや検索機能などの開発
デザイン確定後に大幅な変更を依頼すると、追加費用や納期遅延の原因になります。
ワイヤーフレームやデザインカンプの段階で、関係者全員がしっかり確認することが重要です。
株式会社エッコのようなWeb制作会社では、クライアントとの綿密なコミュニケーションを通じて、イメージのズレを防ぐ取り組みをおこなっています。
ステップ5:テストと品質確保
開発が完了したら、公開前の最終チェックをおこないます。
このテスト工程を疎かにすると、公開後に不具合が発覚し、ユーザーに悪い印象を与えてしまう恐れがあります。
テスト項目は多岐にわたりますが、最低限以下の確認は必須です。
| テスト項目 | 確認内容 |
| デザイン再現テスト | デザインカンプ通りに実装されているか |
| ブラウザテスト | Chrome、Safari、Edge、Firefoxでの表示確認 |
| レスポンシブテスト | スマートフォン、タブレットでの表示確認 |
| リンクチェック | すべてのリンクが正しく機能しているか |
| フォームテスト | お問い合わせフォームが正常に動作するか |
| 表示速度テスト | ページの読み込み速度は適切か |
| SEOチェック | タイトルタグやメタディスクリプションの設定確認 |
特にリンク切れや誤字脱字は見落としやすいポイントです。
制作会社側でチェックをおこなうのはもちろん、依頼者側でも実際にサイトを操作して確認することをおすすめします。
可能であれば、社外のモニターに使ってもらい、フィードバックを得るのも効果的です。
ステップ6:公開と効果測定
テストを経て問題がなければ、いよいよサイトを公開します。
ただし、公開して終わりではありません。
むしろ、リニューアルの成否が問われるのは公開後です。
- 公開直後にリダイレクトが正常に機能しているか確認
- Googleアナリティクスやサーチコンソールの計測設定を確認
- SNSやメルマガ、プレスリリースでリニューアルを告知
- 公開後1週間は毎日サイトの状態をチェック
- 1ヶ月後を目安に効果測定を実施
公開後1ヶ月程度経過したら、KPIの達成状況を確認しましょう。
アクセス数、コンバージョン率、直帰率などの指標が改善しているか、データを分析します。
思うような結果が出ていない場合は、原因を特定して改善施策を打つ必要があります。
リニューアルは一度やって終わりではなく、継続的な改善が前提であることを忘れないでください。
リニューアル成功のための重要ポイント
明確な目標設定と関係者の合意形成
サイトリニューアルを成功させるためには、プロジェクト開始前の準備が重要です。
特に、目標設定と関係者の合意形成は、プロジェクトの成否を左右する要素といえます。
目標が曖昧なまま進めると、途中で方向性がブレたり、関係者間で認識のズレが生じたりする原因になります。
| 合意形成すべき項目 | 内容 |
| リニューアルの目的 | なぜリニューアルが必要なのか |
| 達成すべき目標 | 具体的な数値目標(KGI・KPI) |
| プロジェクト体制 | 誰が責任者で、誰が意思決定するのか |
| スケジュール | いつまでに公開するのか、各工程の期限 |
| 予算 | 初期費用と運用費用の上限 |
| 優先順位 | 予算や時間に制約がある場合に何を優先するか |
特に注意が必要なのは、意思決定権を持つ人を明確にすることです。
担当者レベルで進めていたものの、最終段階で経営層から「やっぱりこうしてほしい」と言われて大幅な手戻りが発生するケースは珍しくありません。
プロジェクト開始時点で、経営層や関連部署を巻き込んで合意を得ておくことが重要です。
ユーザー視点に立った設計
リニューアルの設計において、最も重視すべきはユーザーの視点です。
企業側が伝えたいことと、ユーザーが知りたいことは必ずしも一致しません。
自社の都合だけでサイトを作ると、ユーザーにとって使いにくいサイトになってしまいます。
- ユーザーはどんな課題を解決したくてサイトを訪れるのか
- どのような情報があれば安心して問い合わせできるか
- 初めて訪れた人でも迷わず目的のページに辿り着けるか
- スマートフォンでも快適に閲覧・操作できるか
- 読みやすい文章量、適切な画像サイズになっているか
BtoBサイトの場合、複数の決裁者が関わることを意識した設計が求められます。
現場担当者が情報収集し、上司に報告し、経営層が最終判断するというプロセスを考慮して、それぞれに必要な情報を提供できるコンテンツ構成にしましょう。
ユーザーテストやカスタマージャーニーマップの活用も、ユーザー視点を取り入れるうえで効果的な手法です。
SEO対策を考慮した移行計画
サイトリニューアルでは、SEO対策を十分に考慮した移行計画が不可欠です。
適切な対策を講じないと、検索順位が大幅に下落し、オーガニック流入が激減するリスクがあります。
特に、URLの変更やコンテンツの削除・統合をおこなう場合は、慎重な対応が求められます。
| SEO観点での注意点 | 対策 |
| URL変更 | 301リダイレクトを必ず設定 |
| コンテンツ削除 | 流入のあるページは慎重に判断 |
| 内部リンク構造 | 重要なリンクが失われないよう注意 |
| メタ情報 | タイトルタグ、ディスクリプションの再設定 |
| サイトマップ | XMLサイトマップの更新と送信 |
リニューアル前にどのページがどれだけのアクセスを集めているか、現状のSEOパフォーマンスを把握しておくことが重要です。
評価の高いページを安易に削除したり、URLを変更したりすると、積み上げてきた検索順位を失ってしまいます。
URLの変更とリダイレクト設定
サイトリニューアルでURLが変更になる場合、301リダイレクトの設定は必須です。
301リダイレクトとは、古いURLにアクセスしたユーザーを新しいURLに自動転送する仕組みで、「恒久的な移転」を意味します。
この設定をおこなわないと、旧URLにリンクしていた外部サイトからの評価が引き継がれず、検索順位が大幅に下落する可能性があります。
- 旧URLと新URLの対応表を作成する
- すべての旧URLに対して301リダイレクトを設定する
- 公開後にリダイレクトが正常に機能しているか確認する
- リダイレクトチェーンが発生していないか確認する
- Googleサーチコンソールでインデックス状況を監視する
よくあるミスとして、トップページへの一括リダイレクトがあります。
すべての旧ページをトップページに転送してしまうと、ユーザーは目的の情報に辿り着けず、検索エンジンからの評価も下がります。
旧ページと内容が対応する新ページへ、個別にリダイレクト設定をおこなうことが重要です。
既存コンテンツの評価と活用
リニューアルにあたっては、既存コンテンツの棚卸しをおこないましょう。
すべてのコンテンツを新しく作り直す必要はありません。
すでに検索流入を獲得しているページや、ユーザーに支持されているコンテンツは、適切に活用すべき資産です。
| コンテンツの評価基準 | 判断の目安 |
| 残すべきコンテンツ | 検索流入が多い、被リンクがある、コンバージョンに貢献 |
| 更新すべきコンテンツ | 情報が古い、デザインが合わない、改善の余地がある |
| 統合すべきコンテンツ | 類似した内容が複数ある、ページ数が多すぎる |
| 削除すべきコンテンツ | アクセスがほぼない、情報が完全に古く価値がない |
コンテンツを削除する場合は、そのページへの流入やリンクがないかを必ず確認してください。
わずかでも検索流入がある場合は、削除ではなく関連ページへのリダイレクトを検討しましょう。
既存コンテンツを活かすことで、SEOの評価を維持しながらリニューアルを進めることができます。
段階的なリリースとリスク管理
大規模なサイトリニューアルでは、段階的なリリースを検討することも有効です。
一度にすべてを公開するのではなく、主要ページから順次公開していく方法です。
この方法のメリットは、問題が発生した場合の影響を最小限に抑えられる点にあります。
- まずトップページと主要な下層ページを公開
- 問題がないことを確認してから残りのページを公開
- ECサイトの場合は商品数を限定してテスト公開
- アクセスの少ない時間帯を狙って本番公開
- 万が一に備えて旧サイトのバックアップを保持
特にECサイトやWebサービスなど、サイトが直接売上に影響する場合は、リスク管理を徹底する必要があります。
公開後に致命的な不具合が見つかった場合に備えて、旧サイトにすぐ戻せる体制を整えておくことも重要です。
段階的なリリースは時間がかかりますが、リスクを抑えながら確実にリニューアルを進めることができます。
サイトリニューアルの費用と期間の目安
規模別の費用相場
サイトリニューアルにかかる費用は、サイトの規模や目的によって大きく異なります。
一般的な費用相場を把握しておくことで、適切な予算計画を立てることができます。
以下は、コーポレートサイトをリニューアルする場合の目安です。
| リニューアルの内容 | 費用相場 | 主な作業内容 |
| デザインのみ刷新 | 50〜100万円 | 既存構造を維持しつつビジュアルを変更 |
| 標準的なリニューアル | 100〜300万円 | サイト設計の見直し、コンテンツ再構築 |
| 大規模リニューアル | 300〜500万円 | 戦略設計から制作、SEO対策まで包括的に実施 |
| フルスクラッチ開発 | 500万円以上 | 独自システム開発を含む大規模プロジェクト |
費用を左右する主な要因は、ページ数、機能の複雑さ、制作会社の規模です。
大手制作会社に依頼すると人件費が高くなる傾向がありますが、その分クオリティや安心感を得られる面もあります。
- ページ数が多いほど費用は高くなる
- お問い合わせフォーム以外の機能(会員機能、EC機能など)があると追加費用が発生
- オリジナルデザインとテンプレート利用で費用が変わる
- ライティングや写真撮影を依頼すると追加費用が必要
- 運用サポートを含める場合は月額費用が発生
見積もりは複数社から取得し、内容を比較検討することをおすすめします。
安さだけで選ぶと、品質が低かったり、後から追加費用が発生したりするリスクがあります。
プロジェクト期間の設定
サイトリニューアルに要する期間は、規模や内容によって異なりますが、最低でも2〜3ヶ月は見込んでおく必要があります。
シンプルなサイトであっても、企画・設計から公開までには一定の時間がかかります。
10ページ以上の中規模サイトや、複雑な機能を含む場合は、半年程度を想定しておくと安心です。
| フェーズ | 期間目安 | 主な作業内容 |
| 企画・要件定義 | 2〜4週間 | 目的設定、現状分析、競合調査、要件整理 |
| 設計 | 2〜4週間 | サイトマップ作成、ワイヤーフレーム作成 |
| デザイン | 2〜4週間 | デザインカンプ作成、修正対応 |
| 開発・実装 | 4〜8週間 | コーディング、CMS構築、機能実装 |
| テスト | 1〜2週間 | 各種テスト、修正対応 |
| 公開準備・公開 | 1週間 | リダイレクト設定、公開作業、告知 |
スケジュールに余裕がないと、品質が低下したり、後から追加費用が発生したりするリスクが高まります。
特にコンテンツの準備(原稿や写真の用意)は、依頼者側の作業として時間がかかることが多いため、早めに着手しましょう。
公開希望日が決まっている場合は、逆算して余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。
予算を抑えるための工夫
限られた予算のなかでサイトリニューアルを実現するために、コストを抑える工夫も可能です。
ただし、安易なコストカットは品質低下につながるため、優先順位を明確にして判断することが重要です。
- テンプレートデザインを活用する(完全オリジナルより費用を抑えられる)
- 原稿や写真を自社で用意する(ライティングや撮影費用を削減)
- 機能を必要最小限に絞る(将来的に追加できる設計にしておく)
- ページ数を厳選する(本当に必要なページのみ制作)
- 地方の制作会社に依頼する(大都市圏より人件費が抑えられる場合がある)
最も避けるべきは、目的達成に必要な部分のコストを削ることです。
たとえば、集客を目的としているのにSEO対策を省いたり、お問い合わせを増やしたいのに導線設計を疎かにしたりするのは本末転倒です。
「ここだけは外せない」という部分を明確にし、それ以外の部分でコストを調整するのが賢明な方法といえます。
名古屋のWebコンサルティング会社である株式会社エッコでは、予算に応じた最適なプランの提案もおこなっています。
リニューアルでよくある失敗例と対策
目的が不明確なまま進めてしまう
サイトリニューアルで最も多い失敗が、目的を明確にしないまま進めてしまうケースです。
「なんとなくサイトが古くなったから」「競合他社がリニューアルしたから」という曖昧な理由でプロジェクトを開始すると、成功する可能性は低くなります。
目的が不明確だと、関係者間で方向性の認識がズレ、途中で「やっぱりこうしたい」という要望が頻出します。
| 失敗パターン | 具体的な症状 |
| 目的の欠如 | 「なぜリニューアルするのか」を説明できない |
| 目標の未設定 | 成功・失敗を判断する基準がない |
| 関係者間のズレ | 担当者と経営層で期待する成果が異なる |
| スコープの肥大化 | 途中であれもこれもと要望が増える |
対策としては、プロジェクト開始前に目的とKPIを明文化することが有効です。
「月間の問い合わせ数を30件から50件に増やす」「直帰率を60%から45%に改善する」など、具体的な数値目標を設定しましょう。
目標が明確であれば、途中で方向性がブレそうになったときの判断基準にもなります。
デザインだけを重視して機能性が犠牲になる
「おしゃれなサイトにしたい」という思いが先行し、デザインばかりに注力してしまう失敗も少なくありません。
見た目は美しくなったものの、使いにくくなってしまっては本末転倒です。
特にBtoBサイトでは、必要な情報にすぐ辿り着けることがユーザーにとって最も重要です。
- ナビゲーションがわかりにくく、目的のページに辿り着けない
- 文字サイズが小さすぎて読みにくい
- アニメーションが多すぎてページの読み込みが遅い
- スマートフォンでの操作性が考慮されていない
- お問い合わせフォームが見つけにくい位置にある
対策としては、デザインはあくまでも目的達成の手段と位置づけることが大切です。
デザインの好みで判断するのではなく、「このデザインでユーザーは必要な情報を得られるか」「コンバージョンにつながる設計になっているか」という観点で評価しましょう。
ユーザーテストを実施し、実際のユーザーの反応を確認することも効果的です。
SEO対策を怠りアクセスが激減する
サイトリニューアルで特に注意すべきなのが、SEO対策の不備によるアクセス激減です。
適切な移行対策を講じないと、検索順位が大幅に下落し、オーガニック流入が半減以上になることもあります。
一度下がった検索順位を回復させるには、数ヶ月から1年以上かかる場合もあるため、慎重な対応が求められます。
| SEOの失敗パターン | 結果 |
| リダイレクト未設定 | 旧ページの評価が引き継がれず順位下落 |
| 重要コンテンツの削除 | 流入を獲得していたページを失う |
| 内部リンク構造の崩壊 | サイト内の評価が分散・低下 |
| タイトルタグの変更 | 検索キーワードとの関連性が低下 |
| 表示速度の悪化 | ユーザー体験悪化による評価低下 |
対策としては、リニューアル前にSEOの現状を把握しておくことが重要です。
どのページがどのキーワードで流入を獲得しているか、被リンクはどこについているかを確認し、それらを損なわない移行計画を立てましょう。
SEOに自信がない場合は、専門知識を持つ制作会社やコンサルティング会社に相談することをおすすめします。
公開後の運用体制を考慮していない
サイトリニューアルは公開して終わりではなく、その後の運用が成果を左右します。
しかし、運用体制を十分に検討しないままリニューアルを進めてしまう企業は少なくありません。
特に、CMSの使い方が難しくて更新できない、担当者が異動して引き継ぎができないといった問題が発生しがちです。
- CMSの操作が複雑で、社内で更新できる人がいない
- コンテンツを更新するたびに制作会社への依頼が必要
- 担当者の退職や異動で、サイト運用のノウハウが失われる
- 効果測定の仕組みがなく、改善ポイントがわからない
- 更新が滞り、情報が古いままになってしまう
対策としては、運用を見据えたCMS選定と体制構築が重要です。
誰が更新作業をおこなうのか、どの程度の頻度で更新するのか、効果測定は誰がどのようにおこなうのかを事前に決めておきましょう。
CMSは高機能なものよりも、自社の担当者が使いこなせるものを選ぶことが大切です。
リニューアル後の運用と継続的改善
効果測定と分析の実施
サイトリニューアルの成果を正しく評価するためには、定期的な効果測定が欠かせません。
公開後1ヶ月を目安に、設定したKPIの達成状況を確認しましょう。
改善が見られない項目があれば、原因を分析して対策を講じる必要があります。
| 測定項目 | 確認ポイント |
| セッション数 | リニューアル前と比較して増減はあるか |
| 直帰率 | 改善されているか、悪化しているページはないか |
| コンバージョン率 | 目標に対してどの程度達成できているか |
| 検索順位 | 重要キーワードの順位に変動はないか |
| ページ表示速度 | Core Web Vitalsのスコアは良好か |
| 流入経路 | オーガニック、広告、SNSなどの比率はどうか |
効果測定の結果、期待通りの成果が出ていない場合も珍しくありません。
その場合は、「なぜ成果が出ていないのか」を深掘りし、改善施策を実行することが重要です。
リニューアルは一度やって終わりではなく、継続的な改善活動の起点と捉えてください。
ユーザーフィードバックの収集
数値データだけでなく、ユーザーの生の声を収集することも大切です。
アクセス解析では見えない課題や改善のヒントが、ユーザーフィードバックから得られることがあります。
リニューアル後に「使いにくくなった」という声が上がっていないか、積極的に情報を集めましょう。
- お問い合わせフォームからの質問内容を分析する
- 営業担当者に顧客からの反応をヒアリングする
- サイト上にアンケート機能を設置する
- SNSでの言及やレビューをチェックする
- 社内メンバーに使用感を聞く
特に既存顧客からのフィードバックは重要です。
以前のサイトに慣れていたユーザーは、変化に対して敏感に反応します。
「前のほうが使いやすかった」という声が多い場合は、導線設計やナビゲーションの見直しが必要かもしれません。
定期的なコンテンツ更新と改善
サイトの価値を維持・向上させるためには、コンテンツの定期的な更新が不可欠です。
リニューアル直後は注目を集めても、その後更新が途絶えてしまうと、ユーザーは「この会社は活動しているのだろうか」と不安を感じます。
検索エンジンも、更新が活発なサイトを評価する傾向があります。
| 更新・改善の種類 | 内容 |
| お知らせ更新 | 新サービス、イベント、メディア掲載などの情報発信 |
| コラム・ブログ | SEO対策を兼ねた情報提供コンテンツの追加 |
| 事例追加 | 新しい導入事例や実績の掲載 |
| 既存ページの改善 | データに基づく文言修正やレイアウト調整 |
| 機能追加 | ユーザーのニーズに応じた新機能の実装 |
更新頻度の目安は、最低でも月に1回以上何らかの更新をおこなうことが望ましいです。
更新のためのリソースが社内で確保できない場合は、運用代行サービスを活用することも検討してみてください。
株式会社エッコでは、サイト制作だけでなく、公開後の運用サポートまで一貫して対応しています。
継続的な改善を繰り返すことで、サイトは着実に成果を生み出す資産へと成長していきます。
まとめ

サイトリニューアルは、企業のWeb戦略において非常に重要なプロジェクトです。
本記事では、サイトリニューアルの基本から具体的な手順、成功のポイント、よくある失敗例まで、幅広く解説してきました。
成功するサイトリニューアルのポイントを改めて整理すると、以下のようになります。
- 目的とKPIを明確に設定し、関係者間で合意を得る
- 定量分析と定性分析の両面から現状を正しく把握する
- ユーザー視点に立った設計を心がける
- SEO対策を考慮した移行計画を立てる
- 公開後の運用体制まで見据えて準備する
- 継続的な効果測定と改善をおこなう
リニューアルは一度やって終わりではありません。
公開後の運用と改善こそが、本当の成果につながるということを忘れないでください。
「何から始めればいいかわからない」「自社だけで進めるのは不安」という方は、専門家に相談することをおすすめします。
名古屋を拠点とするWebコンサルティング会社、株式会社エッコでは、サイトリニューアルの企画段階から運用まで、一貫したサポートを提供しています。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
本記事が、皆様のサイトリニューアルを成功に導く一助となれば幸いです。