Google広告を運用するうえで、成果を大きく左右するのが「入札戦略」の選び方です。
適切な入札戦略を設定すれば、限られた予算でも効率よくコンバージョンを獲得できます。
一方で、自社の目的に合わない戦略を選んでしまうと、広告費がむだに消化されるだけでなく、期待した成果を得られないケースも少なくありません。
「クリック数の最大化」「目標コンバージョン単価」「目標ROAS」など、Google広告にはさまざまな入札戦略が用意されています。
しかし、選択肢が多いがゆえに「どれを選べばよいかわからない」「自動入札に任せて大丈夫なのか不安」といった悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。
本記事では、Google広告の入札戦略について基礎から実践的な運用ノウハウまでを網羅的に解説します。
入札戦略の種類と特徴はもちろん、目的別の選び方や設定方法、運用時の注意点、よくある失敗パターンまで詳しくお伝えします。
これからGoogle広告をはじめる方も、すでに運用中で戦略の見直しを検討している方も、ぜひ最後までお読みください。
Index
Google広告の入札戦略とは

Google広告における入札戦略とは、広告オークションでどのように入札価格を決定するかを設定するしくみです。
ユーザーが検索をおこなうたびに、複数の広告主が広告枠を競い合うオークションが発生します。
このオークションで広告が表示されるかどうか、そしてどの位置に表示されるかを左右する重要な要素が入札価格なのです。
入札戦略を正しく設定することで、予算を効率的に活用しながら、目標とする成果を最大化できます。
逆に、目的に合わない戦略を選んでしまうと、広告費を投じても思うような結果が得られません。
Google広告の成果を高めるためには、まず入札戦略の基本をしっかりと理解することが大切です。
- 入札戦略は広告オークションの入札価格を決めるしくみ
- 適切な戦略選択で予算効率と成果を最大化できる
- 目的に合わない戦略は広告費のむだにつながる
- 成果向上の第一歩は入札戦略の基本理解から
入札戦略の基本概念
入札戦略の基本概念を理解するには、まずGoogle広告のオークション形式について知っておく必要があります。
Google広告では、ユーザーが検索キーワードを入力するたびに広告オークションが発生します。
このオークションにおいて、広告主は「1クリックあたりいくらまで支払うか」という入札価格を提示します。
入札戦略とは、この入札価格をどのような方法で設定・調整するかを定めたルールのことです。
たとえば「できるだけ多くのクリックを集めたい」という目的であれば、クリック数を最大化する戦略を選びます。
「1件あたり5,000円以内でコンバージョンを獲得したい」という目的であれば、目標コンバージョン単価を設定する戦略が適しています。
このように、入札戦略は広告運用の目的をGoogleに伝えるための指示書といえるでしょう。
Googleのシステムは設定された入札戦略にもとづいて、オークションごとに最適な入札価格を自動で算出します。
近年は機械学習の進化により、ユーザーの属性や行動履歴、デバイス、時間帯など、さまざまなシグナルを考慮した高精度な入札が可能になりました。
| 項目 | 内容 |
| 入札戦略の役割 | オークションでの入札価格の決定方法を設定する |
| 設定の目的 | 広告運用の目標をGoogleに伝える |
| 最適化の対象 | クリック数、コンバージョン数、費用対効果など |
| 調整方法 | 手動または自動(機械学習)で入札価格を調整 |
広告ランクとの関係性
入札戦略を理解するうえで欠かせないのが、広告ランクという概念です。
広告ランクとは、広告オークションにおいて掲載順位や表示の可否を決める指標のことをいいます。
多くの方が「入札価格を高くすれば広告が上位に表示される」と考えがちですが、実際はそれほど単純ではありません。
広告ランクは、入札価格だけでなく広告の品質も加味して算出されます。
具体的には、推定クリック率、広告の関連性、ランディングページの利便性などが品質の評価基準となります。
つまり、入札価格が高くても広告の品質が低ければ、上位表示は実現しにくいということです。
反対に、品質が高ければ比較的低い入札価格でも上位に表示されるチャンスがあります。
入札戦略を選ぶ際には、単に入札価格を上げることだけを考えるのではなく、広告文やランディングページの品質向上も並行して取り組むことが重要です。
入札戦略と広告品質の両輪で、はじめて効果的な広告運用が実現できるのです。
| 要素 | 広告ランクへの影響 |
| 入札価格 | 高いほど広告ランクが上がりやすい |
| 推定クリック率 | クリックされやすい広告は高評価 |
| 広告の関連性 | 検索キーワードとの関連度が重要 |
| ランディングページ | ユーザビリティや読み込み速度が評価対象 |
| 広告表示オプション | 設定することで広告ランク向上に寄与 |
手動入札と自動入札の違い
Google広告の入札方法は、大きく「手動入札」と「自動入札」の2種類に分かれます。
手動入札は、広告主が自分で入札価格を設定する方式です。
キーワードごと、広告グループごとに細かく入札価格をコントロールできるため、運用者の意図を反映しやすいメリットがあります。
ただし、すべての調整を人の手でおこなう必要があるため、運用工数がかかります。
また、リアルタイムでの最適化には限界があり、機会損失が生じやすい面もあります。
一方、自動入札はGoogleの機械学習を活用して、オークションごとに最適な入札価格を自動で算出する方式です。
ユーザーの検索意図やデバイス、地域、時間帯など、多様なシグナルをもとにリアルタイムで入札を最適化します。
運用者の手間を大幅に削減できるだけでなく、人の手では実現できない精度の高い入札が可能になります。
近年のGoogle広告では、自動入札の活用が標準的な運用方法となっています。
ただし、自動入札が機能するためには一定のデータ量が必要であり、コンバージョン実績が少ない初期段階では手動入札を選択するケースもあります。
| 比較項目 | 手動入札 | 自動入札 |
| 入札価格の決定 | 広告主が手動で設定 | Googleが自動で算出 |
| 運用工数 | 高い(細かな調整が必要) | 低い(自動化により省力化) |
| 最適化精度 | 運用者のスキルに依存 | 機械学習による高精度 |
| データ要件 | 特になし | 一定のコンバージョンデータが必要 |
| おすすめの場面 | 初期段階やデータ不足時 | 十分なデータがある場合 |
入札戦略の種類と特徴

Google広告では、広告運用の目的に応じて複数の入札戦略が用意されています。
それぞれの入札戦略には異なる特徴があり、何を重視して最適化するかによって選ぶべき戦略が変わってきます。
大きく分類すると、クリック重視、コンバージョン重視、インプレッション重視の3つのカテゴリに分けられます。
ここからは、各入札戦略の特徴と活用シーンを詳しく解説していきます。
自社の広告運用目標と照らし合わせながら、最適な入札戦略を見つけてください。
入札戦略の選び方に迷った場合は、Google広告の運用実績が豊富な株式会社エッコにご相談いただくことも可能です。
| カテゴリ | 主な入札戦略 | 重視する指標 |
| クリック重視 | クリック数の最大化、目標CPC | クリック数、クリック単価 |
| コンバージョン重視 | CV数の最大化、目標CPA、目標ROAS | コンバージョン数、CPA、ROAS |
| インプレッション重視 | 目標インプレッションシェア | 表示回数、表示位置 |
クリック重視の入札戦略
クリック重視の入札戦略は、ウェブサイトへのアクセス数を増やすことを主な目的としています。
広告がクリックされるとユーザーは広告主のサイトに遷移するため、サイト流入を増やしたい場合に有効な選択肢となります。
コンバージョン獲得よりもまずはトラフィックを集めたい、認知を広げたいというフェーズで活用されることが多いです。
また、運用初期でコンバージョンデータがまだ十分に蓄積されていない場合にも、クリック重視の戦略からスタートするケースがあります。
データを集めながら、徐々にコンバージョン重視の戦略へ移行するという段階的なアプローチが可能です。
- サイト流入の増加を最優先する場合に最適
- 認知拡大フェーズでの活用に効果的
- 運用初期のデータ収集にも有効
- コンバージョン重視戦略への移行準備として活用できる
クリック数の最大化
「クリック数の最大化」は、設定した予算内でできるだけ多くのクリックを獲得することを目指す自動入札戦略です。
Googleのシステムが自動的に入札価格を調整し、予算を効率的に使いながら最大限のクリックを集めます。
この戦略の最大のメリットは、運用の手間を抑えながらトラフィックを増やせる点にあります。
キーワードごとの細かな入札調整が不要なため、広告運用にかける時間を他の施策に充てられます。
とくに運用初期のデータ収集フェーズで効果を発揮します。
まずはクリック数の最大化でアクセスを集め、どのキーワードやターゲティングが効果的かを把握します。
その後、蓄積したデータをもとにコンバージョン重視の戦略へ切り替える流れが一般的です。
ただし、この戦略はクリック数の獲得に特化しているため、コンバージョンにつながるかどうかは考慮されません。
クリックは集まっても成果につながらないケースもあるため、目的に応じた使い分けが重要になります。
| 項目 | 内容 |
| 最適化対象 | クリック数の最大化 |
| 入札方式 | 自動入札 |
| メリット | 運用工数が少なく、効率的にトラフィック獲得が可能 |
| デメリット | コンバージョン効率は考慮されない |
| おすすめの場面 | 運用初期、データ収集フェーズ、認知拡大目的 |
目標クリック単価(CPC)
目標クリック単価は、希望するクリック単価を設定して、その単価内でクリックを最大限獲得する入札戦略です。
「1クリックあたり100円以内に抑えたい」といった具体的なコスト目標がある場合に活用できます。
クリック数の最大化と似ていますが、より細かなコストコントロールが可能な点が特徴です。
予算管理を重視しながらも、一定のクリック数を確保したい場合に適しています。
ただし、設定した目標単価が市場の相場と大きく乖離していると、十分なクリックを獲得できない可能性があります。
現実的な目標値を設定することが、この戦略を成功させるポイントです。
競合状況やキーワードの競争率を考慮しながら、適切な目標クリック単価を見極めましょう。
なお、この入札戦略は主にデマンドジェネレーションキャンペーンで利用可能であり、すべてのキャンペーンタイプで選択できるわけではありません。
- 具体的なクリック単価の目標がある場合に最適
- 予算管理を重視しながらクリックを獲得できる
- 目標値は市場相場を考慮して現実的に設定する
- デマンドジェネレーションキャンペーンで主に利用可能
コンバージョン重視の入札戦略
コンバージョン重視の入札戦略は、商品購入や問い合わせなどの成果獲得を最優先とする戦略です。
多くの企業がGoogle広告を運用する目的は、最終的にコンバージョンを獲得することでしょう。
この戦略群では、Googleの機械学習がコンバージョンしやすいユーザーを予測し、効率的に成果を最大化します。
「スマート自動入札」とも呼ばれ、過去のコンバージョンデータをはじめとするさまざまなシグナルを活用した高度な最適化が可能です。
ただし、機械学習が効果を発揮するには一定量のコンバージョンデータが必要になります。
Googleの推奨では、過去30日間で30件以上のコンバージョンがあることが望ましいとされています。
データが不足している状態でコンバージョン重視の戦略を選択すると、最適化がうまく機能しない場合があります。
| 入札戦略 | 特徴 | 推奨条件 |
| コンバージョン数の最大化 | 予算内でCV数を最大化 | 月30件以上のCV実績 |
| 目標コンバージョン単価 | 目標CPA内でCV数を最大化 | 月30件以上のCV実績 |
| コンバージョン値の最大化 | 予算内でCV値を最大化 | 月30件以上のCV実績 |
| 目標広告費用対効果 | 目標ROAS内でCV値を最大化 | 月50件以上のCV実績 |
コンバージョン数の最大化
「コンバージョン数の最大化」は、設定した予算内でできるだけ多くのコンバージョンを獲得することを目指す自動入札戦略です。
Googleのシステムがコンバージョンの見込みが高いユーザーやタイミングを予測し、最適な入札価格を自動で設定します。
この戦略は、コンバージョン単価(CPA)よりもコンバージョンの件数を重視する場合に適しています。
「とにかく多くの問い合わせを獲得したい」「リード数を最大化したい」といった目標がある場合に効果を発揮します。
予算を最大限に活用してコンバージョンを獲得するため、日予算をしっかり消化する傾向にあります。
そのため、予算の消化ペースが早くなる可能性がある点には注意が必要です。
また、コンバージョン数を優先するあまり、CPAが想定よりも高くなるケースもあります。
コストを厳密に管理したい場合は、次に紹介する目標コンバージョン単価の設定を検討しましょう。
| 項目 | 内容 |
| 最適化対象 | コンバージョン数の最大化 |
| メリット | 予算内で最大限のコンバージョンを獲得できる |
| デメリット | CPAが高騰する可能性がある |
| 適した場面 | コンバージョン件数を最優先する場合 |
| 注意点 | 予算消化が早くなりやすい |
目標コンバージョン単価(CPA)
「目標コンバージョン単価」は、1件あたりの獲得コストを目標値に近づけながらコンバージョン数を最大化する入札戦略です。
「1件あたり5,000円以内でコンバージョンを獲得したい」といった具体的なコスト目標がある場合に最適です。
Googleのシステムは設定した目標CPAを達成できるよう、オークションごとに入札価格を自動調整します。
この戦略の最大の強みは、コスト効率を維持しながら成果を追求できる点にあります。
コンバージョン数の最大化ではCPAが高騰するリスクがありましたが、目標CPAを設定することでそのリスクを軽減できます。
ただし、目標値を現実的な水準に設定することが重要です。
過去の実績と大きくかけ離れた目標CPAを設定すると、広告配信が制限されてしまう可能性があります。
たとえば、過去30日間の平均CPAが8,000円であるにもかかわらず、目標CPAを2,000円に設定するのは適切ではありません。
過去の実績を参考に、実現可能な目標値を段階的に設定していくことがポイントです。
- 具体的なCPA目標がある場合に最適な戦略
- コスト効率を維持しながらコンバージョン獲得を目指せる
- 目標値は過去の実績をもとに現実的に設定する
- 極端な目標設定は配信制限につながる恐れあり
コンバージョン値の最大化
「コンバージョン値の最大化」は、コンバージョンの件数ではなく金銭的価値を最大化することを目指す入札戦略です。
ECサイトのように商品ごとに価格が異なる場合、単純なコンバージョン件数よりも売上金額を重視したいケースがあります。
この戦略では、コンバージョンに割り当てられた価値(売上金額など)をもとに、全体の価値が最大になるよう入札が最適化されます。
たとえば、1,000円の商品を3件売るよりも、5,000円の商品を1件売るほうが価値が高いと判断される場合があります。
売上や利益の最大化を目標とするビジネスに適した入札戦略といえるでしょう。
この戦略を利用するには、コンバージョンごとの価値をあらかじめ設定しておく必要があります。
ECサイトであれば、購入金額をコンバージョン値として動的に計測する設定が必要になります。
設定がやや複雑になりますが、売上重視の広告運用を目指すなら検討すべき戦略です。
| 項目 | 内容 |
| 最適化対象 | コンバージョン値(売上金額など)の最大化 |
| メリット | 売上や利益を最大化する運用が可能 |
| デメリット | コンバージョン件数が減少する可能性がある |
| 必要な設定 | コンバージョン値の計測設定 |
| 適したビジネス | ECサイト、高単価商材など |
目標広告費用対効果(ROAS)
「目標広告費用対効果(目標ROAS)」は、広告費に対する売上の比率を目標値に維持しながらコンバージョン値を最大化する入札戦略です。
ROASとは「Return On Advertising Spend」の略で、広告費1円あたりどれだけの売上を得られたかを示す指標です。
たとえば、目標ROASを500%に設定すると、広告費の5倍の売上を目指して入札が最適化されます。
この戦略は、投資対効果を重視した広告運用を実現したい場合に最適です。
とくにECサイトや複数の商品を扱うビジネスで、費用対効果を維持しながら売上を伸ばしたい場合に活用されます。
ただし、コンバージョン値の最大化と同様に、コンバージョン値の計測設定が必要です。
また、Googleの推奨では過去30日間で50件以上のコンバージョンがあることが望ましいとされています。
十分なデータがない状態では最適化が機能しにくいため、利用条件を確認してから導入しましょう。
- 広告費に対する売上比率(ROAS)を目標に設定
- 投資対効果を重視した運用に最適
- ECサイトや複数商品を扱うビジネスにおすすめ
- 過去30日間で50件以上のCV実績が推奨条件
インプレッション重視の入札戦略
インプレッション重視の入札戦略は、広告の表示回数や表示位置を最優先する戦略です。
クリックやコンバージョンよりも、まずは広告を多くのユーザーに見てもらうことを目的としています。
ブランド認知の向上や、特定のキーワードで競合よりも目立つ位置に広告を表示したい場合に活用されます。
自社名や商品名などの指名検索キーワードで確実に広告を表示させたい場合にも有効です。
ただし、表示を優先するあまりクリック単価が高騰したり、コンバージョン効率が悪化したりするリスクもあります。
目的とコストのバランスを考慮しながら活用することが重要です。
| 戦略名 | 最適化対象 | 主な活用シーン |
| 目標インプレッションシェア | 検索結果での表示割合 | ブランドキーワード、認知拡大 |
| 視認範囲のインプレッション単価 | 視認されたインプレッション | ディスプレイ広告のブランディング |
目標インプレッションシェア
「目標インプレッションシェア」は、検索結果の特定の位置に広告が表示される割合を目標として設定する入札戦略です。
「ページ最上部」「上部」「任意の場所」のいずれかを選択し、目標とするインプレッションシェアを指定します。
たとえば、「ページ最上部のインプレッションシェアを80%」と設定すると、検索結果の最上部に80%の割合で表示されるよう入札が調整されます。
この戦略は、ブランドキーワードで確実に上位表示したい場合に効果的です。
自社名や商品名で検索されたときに競合の広告が上位に表示されていると、ユーザーが競合に流れてしまう可能性があります。
目標インプレッションシェアを活用すれば、指名検索での機会損失を防げます。
また、コンバージョン率が高いキーワードで取りこぼしを防ぎたい場合にも有効です。
ただし、上位表示を優先するためクリック単価が高騰しやすい点には注意が必要です。
予算に余裕がある場合や、上位表示の価値が高い場合に活用するとよいでしょう。
| 設定項目 | 選択肢 |
| 広告の掲載場所 | ページ最上部、上部、任意の場所 |
| 目標インプレッションシェア | 1%〜100%で設定可能 |
| 上限クリック単価 | 任意で設定可能(推奨は設定なし) |
視認範囲のインプレッション単価
「視認範囲のインプレッション単価制(vCPM)」は、ユーザーが実際に視認したと判断されるインプレッションに対して課金される入札戦略です。
ディスプレイ広告や動画広告で利用可能な戦略で、ブランディングや認知向上を目的とした配信に適しています。
視認範囲とみなされる基準は、広告面積の50%以上が画面に表示され、ディスプレイ広告では1秒以上、動画広告では2秒以上継続して表示された場合です。
つまり、単に広告が配信されただけでなく、ユーザーの目に入った可能性が高いインプレッションに対して費用が発生します。
通常のインプレッション単価制と比較すると、より質の高い表示に対して予算を使えるメリットがあります。
「広告を見てもらえたかどうか」を重視するブランディング目的の配信に最適です。
ただし、クリックやコンバージョンは最適化の対象外となるため、成果重視の運用には向いていません。
- ディスプレイ広告・動画広告で利用可能
- 視認された可能性が高いインプレッションに課金
- ブランディングや認知向上が目的の場合に最適
- クリック・コンバージョン獲得には不向き
その他の入札戦略
Google広告には、ここまで紹介した戦略以外にもいくつかの入札オプションがあります。
自動入札と手動入札の中間的な位置づけの戦略や、完全に手動でコントロールする戦略などです。
それぞれに特徴があり、特定の状況で活用されることがあります。
ただし、近年のGoogle広告では自動入札の活用が推奨されており、これらの戦略を選択する機会は減少傾向にあります。
とくに拡張クリック単価(eCPC)については、仕様変更により利用できるキャンペーンタイプが限られています。
| 戦略名 | 特徴 | 現在の状況 |
| 拡張クリック単価(eCPC) | 手動入札をベースにCVを最適化 | 検索・ディスプレイでは利用不可に |
| 個別クリック単価 | 完全手動で入札価格を設定 | データ不足時に限定的に利用 |
拡張クリック単価(eCPC)
「拡張クリック単価(eCPC)」は、手動で設定した入札価格をベースに、コンバージョンの見込みに応じて自動調整する入札戦略です。
コンバージョンの獲得が見込める場合は入札価格を引き上げ、見込みが低い場合は引き下げます。
手動入札の細かなコントロールと、自動入札の最適化機能を組み合わせたハイブリッド型の戦略といえます。
以前は多くの広告主に活用されていた戦略ですが、仕様変更により利用範囲が制限されています。
現在、検索キャンペーンとディスプレイキャンペーンでは拡張クリック単価を選択できなくなりました。
ショッピングキャンペーンなど一部のキャンペーンタイプでは引き続き利用可能ですが、今後の動向には注意が必要です。
新規で広告運用をはじめる場合は、eCPCではなくスマート自動入札の活用を検討することをおすすめします。
| 項目 | 内容 |
| 入札方式 | 手動入札+自動調整 |
| 最適化対象 | コンバージョン獲得 |
| 現在の利用状況 | 検索・ディスプレイでは利用不可 |
| 代替戦略 | コンバージョン数の最大化、目標CPA |
個別クリック単価
「個別クリック単価制」は、広告主がキーワードや広告グループごとにクリック単価を手動で設定する入札戦略です。
Google広告の最も基本的な入札方式であり、細かなコントロールが可能な点が特徴です。
特定のキーワードで確実に上位表示したい場合や、自動入札では対応しにくい特殊な運用ケースで活用されます。
ただし、すべての調整を手動でおこなう必要があるため運用工数がかかります。
また、オークションごとの最適化はできないため、自動入札と比較すると成果効率で劣る場合があります。
現在のGoogle広告運用では、十分なコンバージョンデータがない初期段階や、特殊な要件がある場合に限定的に利用されています。
データが蓄積できたら、自動入札への移行を検討するのが一般的な運用の流れです。
Google広告の入札戦略選びで迷った際は、株式会社エッコの無料相談をご活用ください。
- 最も基本的な入札方式
- キーワード・広告グループ単位で細かく設定可能
- 運用工数がかかるため、継続的な調整が必要
- データが蓄積できたら自動入札への移行を推奨
目的別の入札戦略の選び方

入札戦略は、広告運用の目的に応じて選択することが重要です。
「どの戦略を選べばよいかわからない」という場合は、まず自社の広告運用目標を明確にしましょう。
認知拡大、サイト流入増加、コンバージョン獲得、ROI改善など、目的によって最適な戦略は異なります。
ここからは、代表的な4つの目的別に、おすすめの入札戦略を解説していきます。
自社の状況と照らし合わせながら、最適な選択肢を見つけてください。
| 広告の目的 | おすすめの入札戦略 | 重視する指標 |
| 認知拡大 | 目標インプレッションシェア、vCPM | 表示回数、表示位置 |
| サイト流入増加 | クリック数の最大化 | クリック数、CPC |
| コンバージョン獲得 | CV数の最大化、目標CPA | コンバージョン数、CPA |
| ROI改善 | 目標ROAS、CV値の最大化 | ROAS、売上金額 |
認知拡大が目的の場合
ブランドや商品の認知度を高めることが目的であれば、インプレッション重視の入札戦略が適しています。
新商品のローンチ時やブランディングキャンペーンでは、まずは多くのユーザーに広告を見てもらうことが重要になります。
検索広告であれば「目標インプレッションシェア」を選択し、検索結果の上部に高い割合で広告を表示させます。
ディスプレイ広告や動画広告であれば「視認範囲のインプレッション単価制」が効果的です。
とくにブランドキーワード(自社名や商品名)では、競合に広告枠を奪われないよう高いインプレッションシェアを確保することが重要です。
指名検索での機会損失を防ぎ、確実に自社のメッセージを届けられます。
ただし、認知拡大を目的とした運用では、クリック単価が高騰しやすい傾向があります。
予算との兼ね合いを考慮しながら、目標とするインプレッションシェアを設定しましょう。
- 新商品ローンチやブランディングに最適
- 検索広告では目標インプレッションシェアを選択
- ディスプレイ・動画ではvCPMが効果的
- ブランドキーワードでの取りこぼし防止に有効
サイト流入増加が目的の場合
ウェブサイトへのアクセス数を増やすことが目的であれば、「クリック数の最大化」が最適な選択肢です。
Googleが自動的に入札を調整し、設定した予算内で最大限のクリックを獲得できます。
キーワードごとの細かな入札調整が不要なため、運用工数を抑えながらトラフィックを増やせるメリットがあります。
サイト流入の増加は、さまざまなビジネス目標の基盤となります。
アクセス数が増えれば、コンバージョンの機会も自然と増加します。
また、どのキーワードやターゲティングが効果的かを把握するためのデータ収集にも役立ちます。
運用初期でコンバージョンデータがまだ十分でない場合は、まずクリック数の最大化でデータを蓄積しましょう。
その後、蓄積したデータをもとにコンバージョン重視の戦略へ移行する流れが効果的です。
| フェーズ | 推奨戦略 | 目的 |
| 初期 | クリック数の最大化 | データ収集とトラフィック獲得 |
| 中期 | コンバージョン数の最大化 | 成果獲得の最大化 |
| 成熟期 | 目標CPA・目標ROAS | 効率的な成果獲得 |
コンバージョン獲得が目的の場合
商品購入や問い合わせなどのコンバージョンを獲得することが目的であれば、スマート自動入札の活用が推奨されます。
件数を最優先するなら「コンバージョン数の最大化」、コスト効率も重視するなら「目標コンバージョン単価」を選択します。
コンバージョン数の最大化は、予算を使い切って最大限のコンバージョンを獲得する戦略です。
「とにかくリード数を増やしたい」「問い合わせ件数を最大化したい」という場合に適しています。
一方、目標コンバージョン単価はCPAを一定範囲に収めながらコンバージョンを増やす戦略です。
「1件あたり1万円以内で獲得したい」といった具体的なコスト目標がある場合に効果を発揮します。
どちらの戦略を選ぶかは、コスト効率と件数のどちらを優先するかによって決まります。
なお、スマート自動入札が効果を発揮するには、過去30日間で30件以上のコンバージョン実績があることが望ましいです。
データが不足している場合は、まずクリック数の最大化などでデータを蓄積してから移行しましょう。
- 件数優先なら「コンバージョン数の最大化」を選択
- コスト効率重視なら「目標コンバージョン単価」を選択
- 月30件以上のCV実績があることが推奨条件
- データ不足時はクリック重視戦略から段階的に移行
ROI改善が目的の場合
広告投資に対するリターンを最大化することが目的であれば、「目標広告費用対効果(目標ROAS)」の活用が効果的です。
ROASとは、広告費に対する売上の比率を表す指標です。
目標ROASを設定することで、その目標値を維持しながらコンバージョン値(売上金額)の最大化を目指せます。
この戦略は、複数の価格帯の商品を扱うECサイトなどで特に効果を発揮します。
単純なコンバージョン件数ではなく、売上金額ベースで最適化されるため、高単価商品の販売促進にも適しています。
たとえば、目標ROASを400%に設定すれば、広告費1万円あたり4万円の売上を目指す運用となります。
ただし、目標ROASを高く設定しすぎると配信量が制限され、かえって売上が減少するリスクがあります。
過去の実績を参考に、実現可能な範囲で目標値を設定することが成功のポイントです。
| 目標ROAS | 意味 | 適した場面 |
| 200% | 広告費の2倍の売上 | 利益率が高い商材 |
| 400% | 広告費の4倍の売上 | 一般的なECサイト |
| 800% | 広告費の8倍の売上 | 低利益率・大量販売型 |
入札戦略の設定方法

入札戦略の選び方がわかったら、次は実際の設定方法を確認しましょう。
Google広告の管理画面から、キャンペーン単位で入札戦略を設定・変更できます。
新規キャンペーンの作成時に設定する方法と、既存キャンペーンの設定を変更する方法があります。
また、複数のキャンペーンにまとめて同じ入札戦略を適用できる「ポートフォリオ入札戦略」という機能もあります。
ここでは、それぞれの設定手順を具体的に解説します。
実際の操作画面を見ながら、正しく設定をおこないましょう。
- 入札戦略はキャンペーン単位で設定可能
- 新規キャンペーン作成時に初期設定をおこなう
- 既存キャンペーンの戦略変更も管理画面から可能
- 複数キャンペーンの一括管理にはポートフォリオ入札戦略を活用
新規キャンペーンでの設定手順
新規キャンペーンを作成する際、入札戦略は「予算と入札単価」の画面で設定します。
キャンペーン作成の流れに沿って、目標設定からキャンペーンタイプの選択を経て入札戦略の設定画面に進みます。
デフォルトでは、選択したキャンペーン目標に応じた入札戦略が自動で推奨されます。
たとえば「販売促進」を目標に選ぶと、コンバージョン重視の戦略が推奨されるしくみです。
推奨された戦略をそのまま使用しても構いませんし、「入札戦略を直接選択」をクリックして別の戦略を選ぶこともできます。
目標コンバージョン単価や目標ROASを設定する場合は、具体的な数値を入力します。
過去の実績データを参考に、現実的な目標値を設定することが重要です。
設定が完了したら、他のキャンペーン設定と合わせて内容を確認し、キャンペーンを公開します。
| 手順 | 操作内容 |
| 1 | Google広告にログインし「新しいキャンペーン」をクリック |
| 2 | キャンペーン目標とタイプを選択 |
| 3 | 「予算と入札単価」画面で入札戦略を確認・変更 |
| 4 | 目標値(CPA、ROASなど)を設定 |
| 5 | 他の設定を完了してキャンペーンを公開 |
既存キャンペーンの入札戦略変更方法
すでに運用中のキャンペーンでも、入札戦略を後から変更できます。
管理画面の左側メニューから「キャンペーン」を選択し、変更したいキャンペーンの設定画面に移動します。
「設定」タブを開き、「単価設定」のセクションを見つけて「入札戦略を変更」をクリックします。
プルダウンメニューから新しい入札戦略を選択し、必要に応じて目標値を入力します。
変更内容を確認したら「保存」をクリックして反映させます。
ただし、入札戦略の変更はアカウントの配信成果に大きな影響を与えるため、慎重におこなう必要があります。
とくに、スマート自動入札を利用している場合は、戦略を変更すると学習がリセットされます。
頻繁な変更は避け、十分なデータを蓄積してから判断することをおすすめします。
入札戦略の変更タイミングや最適な設定値に迷う場合は、株式会社エッコへご相談ください。
- 管理画面のキャンペーン設定から変更可能
- 「単価設定」→「入札戦略を変更」で操作
- 変更後は学習期間が発生することを考慮
- 頻繁な変更は成果悪化の原因になりうる
ポートフォリオ入札戦略の活用
「ポートフォリオ入札戦略」は、複数のキャンペーンにまとめて同じ入札戦略を適用できる機能です。
通常、入札戦略はキャンペーンごとに個別設定しますが、ポートフォリオ入札戦略を使えば一括管理が可能になります。
たとえば、商品カテゴリごとに分けた複数のキャンペーンを、同じ目標CPAで運用したい場合に便利です。
一つのポートフォリオ入札戦略を変更すれば、適用されたすべてのキャンペーンに反映されるため、管理効率が向上します。
設定方法は、管理画面の「ツールと設定」から「入札戦略」を選択し、新しいポートフォリオ入札戦略を作成します。
入札戦略の種類と目標値を設定し、適用するキャンペーンを選択すれば完了です。
アカウント全体で一貫した入札方針を維持したい場合や、複数キャンペーンの成果を合算して最適化したい場合に有効です。
| メリット | 内容 |
| 管理効率の向上 | 複数キャンペーンの入札戦略を一括管理できる |
| 一貫性の確保 | アカウント全体で統一された入札方針を維持 |
| 成果の合算最適化 | キャンペーンをまたいだ学習が可能 |
| 変更の効率化 | 一か所の変更で全キャンペーンに反映 |
入札戦略運用時の注意点

入札戦略を正しく設定しても、運用方法を誤ると期待した成果は得られません。
とくに自動入札を活用する場合は、いくつかの重要な注意点を理解しておく必要があります。
学習期間の存在、データ蓄積の重要性、頻繁な変更のリスク、予算設定との関係性などは、運用成果に直結するポイントです。
ここからは、入札戦略を運用するうえで押さえておくべき注意点を詳しく解説します。
これらのポイントを理解しておけば、自動入札の効果を最大限に引き出せるでしょう。
- 学習期間中はパフォーマンスが安定しない
- 十分なコンバージョンデータが最適化の鍵
- 頻繁な設定変更は学習をリセットしてしまう
- 予算設定が入札戦略の効果に影響する
学習期間について理解する
自動入札を設定すると、**最初の1〜2週間は「学習期間」**と呼ばれるパフォーマンスが安定しない時期が発生します。
学習期間中、Googleのシステムはアカウントの配信データを収集・分析し、最適な入札調整方法を学習しています。
この期間はCPAやCPCが大きく変動したり、予想外の成果が出たりすることがあります。
「設定を間違えたのでは?」と不安になるかもしれませんが、学習期間中の変動は正常な挙動です。
慌てて入札戦略を変更したり、目標値を大幅に調整したりすると、学習がリセットされてしまいます。
学習期間が終わるまでは、できるだけ設定を変更せずに待つことが重要です。
管理画面の「入札戦略のステータス」で、現在学習中かどうかを確認できます。
「学習中」と表示されている場合は、学習完了まで2〜4週間程度かかることを想定しておきましょう。
| ステータス | 意味 | 対応 |
| 学習中 | 機械学習が最適化を進行中 | 設定変更を控えて待機 |
| 有効 | 学習完了、正常に稼働中 | 成果を確認しながら運用 |
| 制限付き | 何らかの制限で最適化が不十分 | 原因を確認して対処 |
| 学習(データ不足) | データが足りず学習が進まない | データ蓄積を優先 |
データ蓄積の重要性
自動入札が効果を発揮するためには、十分なコンバージョンデータの蓄積が不可欠です。
機械学習は過去のデータをもとに、どのようなユーザーがコンバージョンしやすいかを学習します。
データが少ない状態では学習の精度が低く、最適な入札がおこなわれない可能性があります。
Googleの推奨では、過去30日間で30件以上のコンバージョンがあることが望ましいとされています。
目標ROAS(目標広告費用対効果)を利用する場合は、50件以上のコンバージョン実績が推奨されます。
これらの条件を満たせない場合は、まずクリック数の最大化などでデータを蓄積することを優先しましょう。
また、コンバージョンデータが少ない業種では「マイクロコンバージョン」の活用も検討できます。
マイクロコンバージョンとは、最終目標(購入、問い合わせなど)の手前にある中間的な行動(フォーム到達、商品詳細閲覧など)を計測する方法です。
これにより、機械学習に必要なデータ量を確保しやすくなります。
- 月30件以上のCV実績がスマート自動入札の推奨条件
- 目標ROASは月50件以上のCVが推奨
- データ不足時はクリック重視戦略から開始
- マイクロコンバージョンでデータ量を補う方法も有効
頻繁な変更を避ける理由
自動入札を運用するうえで、頻繁な設定変更は大きなマイナス要因となります。
入札戦略や目標値を変更するたびに、機械学習は新しい設定にもとづいて再学習を始めます。
つまり、変更のたびに学習期間がリセットされ、パフォーマンスの安定までに時間がかかるのです。
「思ったより成果が出ない」と感じて数日おきに戦略を変更していると、いつまでも学習が完了せず、成果が安定しません。
一般的には、入札戦略の設定後は2〜4週間は変更を控えることが推奨されています。
この期間を過ぎてもパフォーマンスが改善しない場合に、はじめて設定の見直しを検討しましょう。
また、目標値(目標CPAや目標ROASなど)を変更する際も、急激な変更は避けるべきです。
一度に大幅な変更をおこなうと、最適化が追いつかずパフォーマンスが不安定になります。
±20%程度の範囲で段階的に調整していくことが、安定した運用のポイントです。
| 変更頻度 | 影響 | 推奨対応 |
| 数日おき | 学習が進まず成果不安定 | 避けるべき |
| 2〜4週間おき | 適切な検証期間を確保 | 推奨 |
| 目標値の急激な変更 | 最適化が追いつかない | ±20%以内で段階的に |
予算設定との関係性
入札戦略の効果は、予算設定と密接に関係しています。
予算が不足していると、自動入札が最適な配信をおこなえない場合があります。
たとえば、目標コンバージョン単価を1万円に設定していても、日予算が5,000円しかなければ、1日に1件もコンバージョンを獲得できる機会がありません。
Googleの推奨では、目標CPAの10倍以上の日予算を設定することが望ましいとされています。
これにより、システムが十分な配信をおこない、学習に必要なデータを収集できます。
また、「コンバージョン数の最大化」などの戦略は、日予算を最大限に使い切る傾向があります。
予算消化のペースが想定よりも早くなる可能性があるため、予算管理には注意が必要です。
一方で、予算を過度に制限すると、機械学習が十分に機能せず、最適化の精度が低下します。
成果を最大化するには、入札戦略と予算のバランスを考慮した設定が重要です。
- 日予算は目標CPAの10倍以上が推奨
- 予算不足は自動入札の効果を制限する
- CV数の最大化は予算消化が早くなりやすい
- 予算と入札戦略のバランス調整が成果の鍵
運用フェーズ別の推奨入札戦略

Google広告の入札戦略は、運用のフェーズに応じて使い分けることが効果的です。
広告配信を開始したばかりの初期段階と、データが蓄積した後の段階では、最適な戦略が異なります。
また、運用が成熟期に入ったら、さらに効率を追求した戦略への移行を検討します。
ここでは、配信開始初期、データ蓄積後、成熟期の3つのフェーズ別に、おすすめの入札戦略を解説します。
段階的に戦略を切り替えていくことで、広告運用の成果を最大化できます。
| フェーズ | 主な目的 | おすすめ戦略 |
| 配信開始初期 | データ収集、アカウント構築 | クリック数の最大化 |
| データ蓄積後 | コンバージョン獲得の最大化 | CV数の最大化、目標CPA |
| 成熟期 | 効率化、ROI最大化 | 目標ROAS、目標CPA |
配信開始初期の戦略
広告配信を開始したばかりの初期段階では、まずデータを収集することが最優先です。
自動入札(スマート自動入札)が効果を発揮するには、一定量のコンバージョンデータが必要になります。
しかし、配信初期はデータがまだ蓄積されていないため、いきなりコンバージョン重視の戦略を選んでも最適化が機能しにくいです。
そこで、初期段階では「クリック数の最大化」を選択してトラフィックを集めることをおすすめします。
クリック数を増やすことで、どのキーワードやターゲティングが効果的かを把握できます。
また、サイトへのアクセスが増えればコンバージョンの機会も生まれ、データ蓄積が進みます。
配信開始から2〜4週間程度を目安に、30件以上のコンバージョンが獲得できたら次のフェーズへの移行を検討しましょう。
なお、予算やビジネスモデルによっては、最初からコンバージョン重視の戦略でスタートすることも可能です。
自社の状況に合わせて柔軟に判断することが重要です。
- 初期段階はデータ収集を最優先に考える
- クリック数の最大化でトラフィックを集める
- どのキーワード・ターゲティングが有効かを把握
- 30件以上のCVを獲得したら次フェーズへ移行
データ蓄積後の最適化戦略
コンバージョンデータが一定量(月30件以上が目安)蓄積できたら、コンバージョン重視の戦略への移行を検討します。
このフェーズでは、「コンバージョン数の最大化」または「目標コンバージョン単価」の活用が効果的です。
コンバージョン件数をとにかく増やしたい場合は「コンバージョン数の最大化」を選択します。
予算を最大限に活用して、できるだけ多くのコンバージョンを獲得することを目指します。
一方、コスト効率も重視したい場合は「目標コンバージョン単価」を設定します。
「1件あたり5,000円以内」といった具体的なCPA目標を維持しながらコンバージョン数を増やせます。
目標CPAを設定する際は、過去の実績データを参考にしましょう。
実績と大きくかけ離れた目標値を設定すると、広告配信が制限されてしまう可能性があります。
まずは過去のCPA実績に近い値で設定し、成果を見ながら段階的に調整していくのが効果的です。
| 戦略 | 適した状況 | 注意点 |
| コンバージョン数の最大化 | 件数を最優先したい | CPAが高騰する可能性 |
| 目標コンバージョン単価 | コスト効率も重視 | 現実的な目標値設定が必要 |
成熟期の効率化戦略
運用が成熟期に入り、安定したコンバージョンが獲得できるようになったら、さらなる効率化を目指します。
このフェーズでは、単なるコンバージョン件数ではなく、投資対効果(ROI)の最大化に注力します。
ECサイトなど売上金額を重視するビジネスであれば、「目標広告費用対効果(目標ROAS)」への移行を検討しましょう。
目標ROASを設定することで、広告費に対する売上比率を維持しながら、売上の最大化を目指せます。
また、コンバージョン単価(CPA)を重視する場合は、目標CPAを段階的に引き下げていくことで効率化を図れます。
ただし、目標値を急激に変更するとパフォーマンスが不安定になるため、±20%程度の範囲で段階的に調整することが重要です。
成熟期の運用では、入札戦略だけでなく、広告文やランディングページの改善も並行しておこないましょう。
入札戦略で効率化を図りつつ、クリエイティブの質を高めることで、さらなる成果向上が期待できます。
- 成熟期は投資対効果(ROI)の最大化にフォーカス
- ECサイトでは目標ROASへの移行が効果的
- 目標値は±20%以内で段階的に調整する
- 広告文やLPの改善と並行して取り組む
入札戦略の効果測定とモニタリング

入札戦略を設定したら、定期的に効果を測定してモニタリングすることが重要です。
自動入札だからといって完全に放置するのではなく、パフォーマンスを確認しながら必要に応じて調整をおこないます。
Google広告の管理画面では、入札戦略のステータスや各種パフォーマンス指標を確認できます。
どの指標を見るべきか、どのタイミングで改善をおこなうべきかを理解しておくことが、効果的な運用につながります。
ここでは、入札戦略の効果測定とモニタリングのポイントを解説します。
- 入札戦略のステータスを定期的にチェック
- KPIに応じたパフォーマンス指標を確認
- 改善タイミングの判断基準を明確にする
- データにもとづいた意思決定をおこなう
ステータスの確認方法
入札戦略が正常に機能しているかどうかは、**「入札戦略のステータス」**で確認できます。
Google広告の管理画面で、キャンペーンの入札戦略欄にカーソルを合わせると、現在のステータスが表示されます。
ステータスには「有効」「学習中」「制限付き」「無効」などの種類があり、それぞれ意味が異なります。
「有効」と表示されていれば、入札戦略は正常に稼働しています。
「学習中」は機械学習が進行中であり、2〜4週間程度で完了する見込みです。
「制限付き」や「無効」の場合は、何らかの問題が発生しているため対処が必要です。
「制限付き」の場合は、予算不足、入札単価の上限設定、品質スコアの低さなどが原因として考えられます。
ステータス欄に表示される詳細情報を確認し、原因に応じた対策をおこないましょう。
| ステータス | 意味 | 推奨対応 |
| 有効 | 正常に稼働中 | 継続してモニタリング |
| 学習中 | 機械学習が進行中 | 設定変更を控えて待機 |
| 制限付き | 何らかの制限あり | 原因を確認して対処 |
| 無効 | 入札戦略が機能していない | 設定を見直す |
パフォーマンス指標の見方
入札戦略の効果を測定するには、選択した戦略に応じた適切な指標を確認する必要があります。
クリック重視の戦略であれば、クリック数、クリック率(CTR)、クリック単価(CPC)が主要な確認指標となります。
コンバージョン重視の戦略であれば、コンバージョン数、コンバージョン率(CVR)、コンバージョン単価(CPA)を確認します。
目標ROASを設定している場合は、コンバージョン値とROASの推移をモニタリングします。
これらの指標は、Google広告の管理画面やレポート機能で確認できます。
カスタム列を追加すれば、自社のKPIに合わせた指標を一覧で表示することも可能です。
また、指標を確認する際は単日のデータだけでなく、週単位や月単位の推移を見ることが重要です。
一時的な変動に惑わされず、トレンドを把握したうえで判断をおこないましょう。
| 入札戦略 | 主要な確認指標 |
| クリック数の最大化 | クリック数、CTR、CPC |
| コンバージョン数の最大化 | CV数、CVR、CPA |
| 目標コンバージョン単価 | CPA、CV数、予算消化率 |
| 目標ROAS | ROAS、コンバージョン値、売上 |
| 目標インプレッションシェア | インプレッションシェア、掲載位置 |
改善のタイミングと判断基準
入札戦略の改善をおこなうタイミングは、学習期間終了後のパフォーマンスをもとに判断します。
学習期間中(設定後2〜4週間)は、たとえ成果が不安定でも設定変更を控えるのが原則です。
学習期間が終了し、ステータスが「有効」になった後も成果が目標を下回る場合に、改善を検討します。
具体的には、目標CPAを達成できていない、CV数が想定より大幅に少ないなどの状況が改善の判断基準となります。
改善策としては、目標値の見直し、ターゲティングの調整、広告文やLPの改善などが考えられます。
入札戦略自体を変更する場合は、十分なデータと明確な理由にもとづいて判断しましょう。
感覚的な判断で頻繁に戦略を変更すると、かえって成果が不安定になります。
株式会社エッコでは、Google広告の効果測定から改善提案まで一貫したサポートを提供しています。
- 学習期間(2〜4週間)終了後に成果を評価
- 目標達成状況をもとに改善要否を判断
- 改善は目標値調整、ターゲティング、クリエイティブの見直しから
- 入札戦略変更は十分なデータと根拠をもって判断
よくある失敗パターンと対策
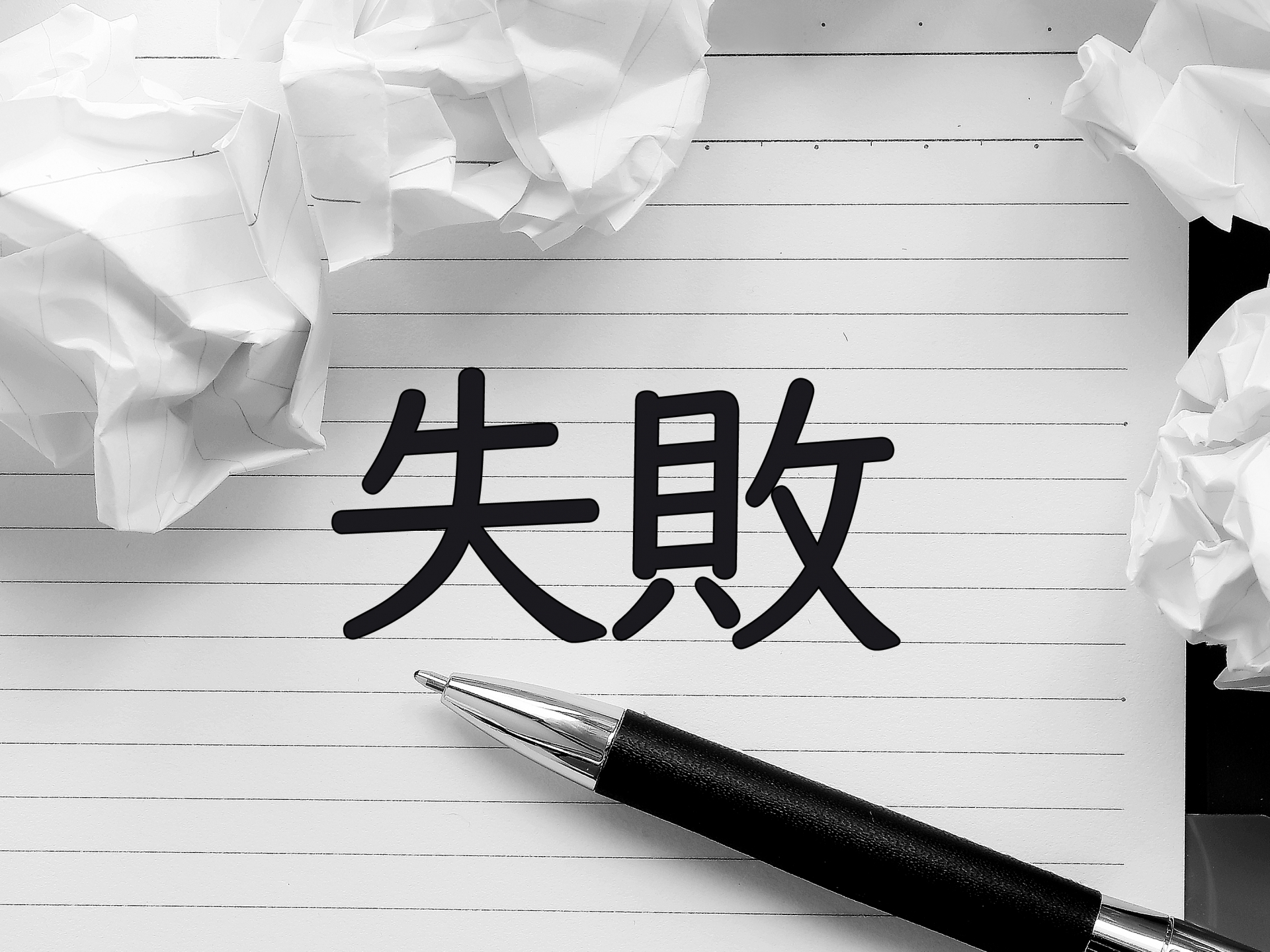
Google広告の入札戦略では、よくある失敗パターンがいくつか存在します。
これらの失敗を避けることで、入札戦略の効果を最大限に引き出すことができます。
ここでは、代表的な3つの失敗パターンと、その対策を解説します。
これから入札戦略を設定する方も、すでに運用中で成果が伸び悩んでいる方も、ぜひ参考にしてください。
失敗パターンを事前に理解しておけば、スムーズな広告運用が実現できます。
| 失敗パターン | 原因 | 対策 |
| 配信開始直後の自動入札設定 | データ不足で最適化が機能しない | クリック重視戦略からスタート |
| 不適切な目標値設定 | 実績とかけ離れた目標を設定 | 過去実績をもとに現実的な値を設定 |
| データ不足時の戦略変更 | 学習完了前に変更してリセット | 2〜4週間は設定を維持 |
配信開始直後の自動入札設定
初心者がやりがちな失敗の一つが、配信開始直後にコンバージョン重視の自動入札を設定してしまうことです。
「目標コンバージョン単価」や「コンバージョン数の最大化」は高い成果が期待できる戦略ですが、十分なデータがなければ機能しません。
機械学習は過去のコンバージョンデータをもとに最適化をおこなうため、データがない状態では学習が進みません。
結果として、広告配信が制限されたり、CPAが高騰したりするケースがあります。
対策としては、まずクリック数の最大化でデータを蓄積してからコンバージョン重視の戦略に移行することです。
30件以上のコンバージョンを獲得してから、スマート自動入札への切り替えを検討しましょう。
または、フォーム到達や商品詳細閲覧などのマイクロコンバージョンを設定してデータ量を補う方法もあります。
- データ不足でいきなりCV重視戦略を設定するのは危険
- 学習が進まず配信制限やCPA高騰の原因に
- まずはクリック数の最大化でデータを蓄積
- マイクロコンバージョンでデータ量を補う方法も有効
不適切な目標値設定
もう一つのよくある失敗が、実績とかけ離れた目標値を設定してしまうことです。
たとえば、過去のCPAが8,000円なのに、目標CPAを2,000円に設定するケースがこれにあたります。
このような非現実的な目標を設定すると、Googleのシステムは条件を満たす配信機会を見つけられません。
結果として、広告がほとんど配信されず、コンバージョンもまったく獲得できない状況に陥ります。
目標ROASについても同様です。
過去のROASが200%なのに、いきなり1,000%を目標にしても達成は困難です。
対策としては、過去の実績データを参考に、実現可能な範囲で目標値を設定することが重要です。
まずは過去実績に近い値からスタートし、成果を見ながら段階的に目標を引き上げていきましょう。
| 設定例 | 問題点 | 推奨対応 |
| 過去CPA8,000円→目標2,000円 | 乖離が大きすぎる | 過去実績の±10〜20%から開始 |
| 過去ROAS200%→目標1,000% | 達成不可能な目標 | 200%→250%→300%と段階的に引き上げ |
データ不足時の戦略変更
入札戦略の成果が出ないからといって、学習期間中に戦略を変更してしまうのも失敗パターンの一つです。
自動入札は設定後すぐに効果を発揮するわけではなく、1〜2週間程度の学習期間が必要です。
この期間はCPAが乱高下することもありますが、それは機械学習が最適化を探っている正常な挙動です。
「うまくいっていない」と感じて数日で戦略を変更すると、学習がリセットされてしまいます。
変更のたびに学習がリセットされるため、いつまでたっても最適化が完了しません。
対策としては、設定後2〜4週間は変更を控えて学習完了を待つことです。
学習期間中はパフォーマンスの変動を許容し、ステータスが「有効」になってから成果を評価しましょう。
入札戦略の運用に不安がある場合は、株式会社エッコにご相談ください。
豊富な運用実績にもとづいた適切なアドバイスを提供いたします。
- 学習期間中の変更は学習リセットの原因に
- 2〜4週間は設定を変更せずに待機する
- 学習完了後のデータをもとに成果を評価
- パフォーマンスの一時的な変動は正常な挙動
まとめ
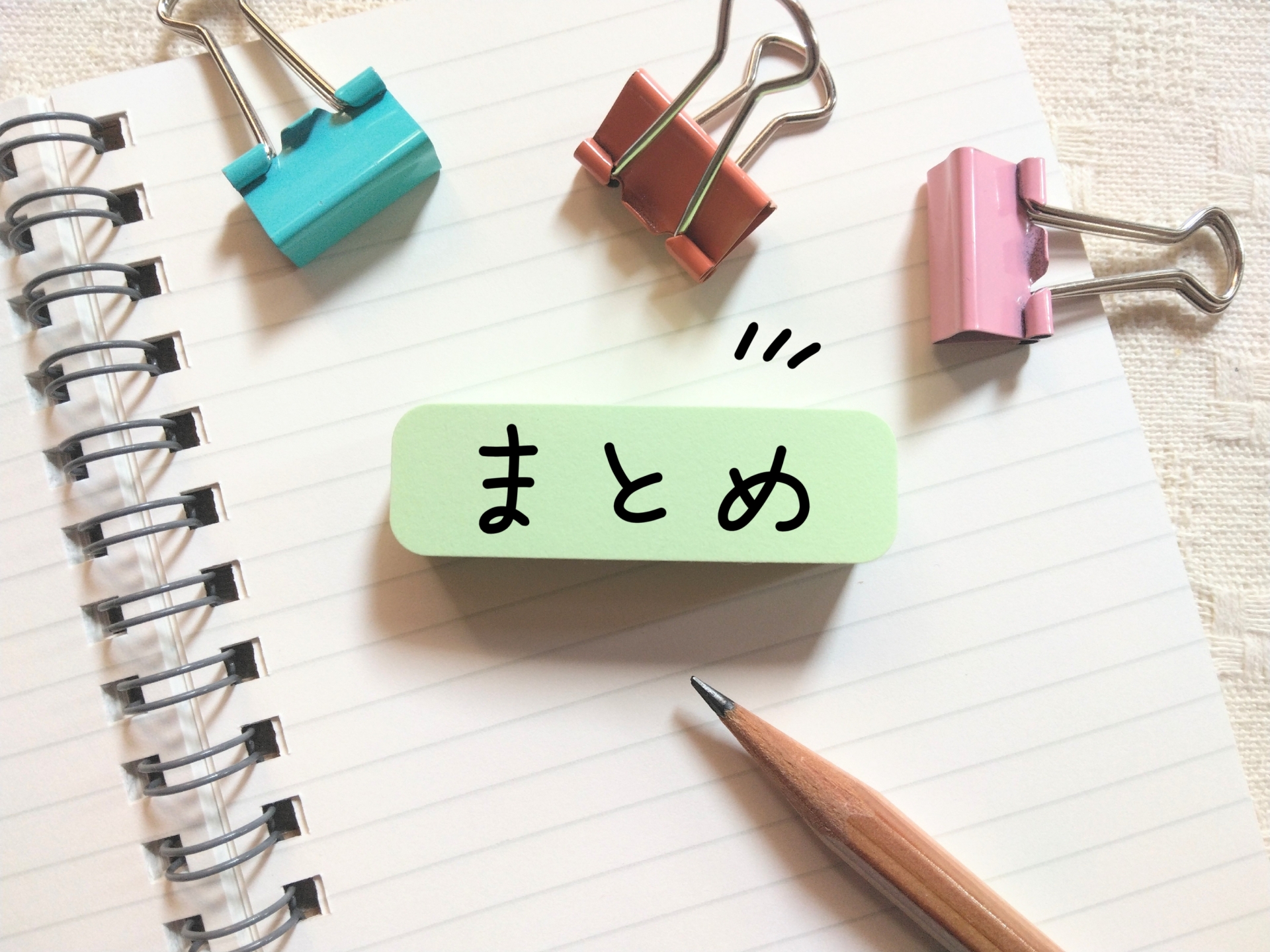
本記事では、Google広告の入札戦略について基礎から実践的な運用ノウハウまで解説しました。
入札戦略は、広告オークションでの入札価格を決定するしくみであり、広告成果を大きく左右する重要な設定項目です。
クリック重視、コンバージョン重視、インプレッション重視など、目的に応じてさまざまな戦略が用意されています。
最適な入札戦略を選ぶためには、まず自社の広告運用目標を明確にすることが大切です。
そのうえで、データの蓄積状況や予算に応じた戦略を選択し、運用フェーズに合わせて段階的に最適化を進めていきましょう。
自動入札を活用する際は、学習期間の存在、十分なデータ蓄積の重要性、頻繁な変更を避けることなど、いくつかの注意点を理解しておく必要があります。
これらのポイントを押さえることで、入札戦略の効果を最大限に引き出せます。
入札戦略の選び方や運用方法に迷った場合は、名古屋のWebコンサル会社、株式会社エッコにご相談ください。
豊富なGoogle広告運用実績にもとづき、お客様のビジネス目標達成に向けた最適な入札戦略をご提案いたします。
- 入札戦略は広告成果を左右する重要な設定項目
- 目的に応じてクリック重視、CV重視、インプレッション重視を選択
- 運用フェーズに合わせて段階的に戦略を最適化
- 学習期間の理解とデータ蓄積が自動入札成功の鍵
- 入札戦略のお悩みは株式会社エッコにご相談ください



