Webサイトを運営しているけれど、「検索結果で思うように表示されない」「どんなキーワードで訪問されているかわからない」と悩んでいませんか?
そんな課題を解決してくれるのが、Googleが無料で提供しているGoogleサーチコンソールです。
このツールを活用すれば、検索エンジンがあなたのサイトをどう評価しているのか、どのページが検索結果に表示されているのかを詳しく把握できます。
特に初心者の方にとっては、難しそうに感じるかもしれませんが、基本的な使い方さえ覚えれば、誰でもサイト改善に役立てることができます。
本記事では、Googleサーチコンソールの基本概念から初期設定、具体的な活用方法までを初心者の方にもわかりやすく解説します。
名古屋のWebコンサルティング会社・株式会社エッコでも、多くのクライアント様にサーチコンソールの活用をサポートしており、実際に検索流入が大幅に改善した事例も数多くあります。
この記事を読み終える頃には、あなたもサーチコンソールを使いこなして、サイトのアクセス数を増やすための第一歩を踏み出せるはずです。
それでは、さっそく見ていきましょう。
Index
Googleサーチコンソールとは

Googleサーチコンソールは、Webサイト運営において欠かせないツールの1つです。
ここでは、その基本的な概念から、似たようなツールとの違い、そして導入するメリットまでを詳しく解説します。
サーチコンソールの基本概念
**Googleサーチコンソール(Google Search Console)**とは、Googleが無料で提供している、Webサイトの検索パフォーマンスを分析・管理するためのツールです。
以前は「Googleウェブマスターツール」という名称でしたが、2015年5月に現在の名称に変更されました。
愛称として「サチコ」とも呼ばれており、多くのWebサイト運営者やSEO担当者に親しまれています。
このツールの最大の特徴は、Google検索結果での自社サイトの状況を詳細に把握できるという点にあります。
具体的には、以下のような情報を確認できます。
| 確認できる主な情報 | 内容 |
| 検索キーワード | ユーザーがどんな言葉で検索してサイトに辿り着いたか |
| 表示回数 | 検索結果に自社サイトが表示された回数 |
| クリック数 | 検索結果から実際にクリックされた回数 |
| 平均掲載順位 | 各キーワードでの平均的な検索順位 |
| インデックス状況 | Googleに登録されているページの状態 |
| サイトの問題点 | エラーや改善が必要な箇所の通知 |
さらに注目すべきは、サーチコンソールがGoogle検索に特化しているという点です。
YahooやBingなど他の検索エンジンのデータは含まれませんが、日本の検索エンジンシェアはGoogleとYahoo(検索エンジンはGoogleと同じ)で約95%を占めるため、実質的には十分なカバー率といえます。
サーチコンソールは、サイト所有者とGoogleをつなぐコミュニケーションツールとしての役割も果たしています。
Googleがあなたのサイトをどう認識しているのか、どんな問題があるのかを教えてくれるため、適切な対策を打つことができるのです。
Googleアナリティクスとの違い
Webサイト分析ツールとして、Googleサーチコンソールとよく比較されるのが**Googleアナリティクス(GA4)**です。
どちらもGoogleが提供する無料ツールですが、分析できる範囲とタイミングが大きく異なります。
最も重要な違いは、「サイトに来る前」と「サイトに来た後」という視点の違いです。
サーチコンソールは「サイトに来る前」のデータを扱います。
ユーザーがGoogle検索で何を入力したのか、検索結果で何位に表示されたのか、そしてクリックして訪問したのかという情報を確認できます。
一方、Googleアナリティクスは「サイトに来た後」のデータを分析します。
訪問者がサイト内でどのページを閲覧したのか、どれくらい滞在したのか、どこから離脱したのかといったユーザー行動を追跡します。
| 比較項目 | Googleサーチコンソール | Googleアナリティクス |
| 主な分析範囲 | サイト訪問前の検索行動 | サイト訪問後のユーザー行動 |
| 確認できる検索キーワード | 具体的なキーワードすべて | 限定的(連携すれば一部確認可能) |
| 検索順位 | 確認できる | 確認できない |
| ページビュー数 | 確認できない | 確認できる |
| 滞在時間 | 確認できない | 確認できる |
| コンバージョン測定 | 確認できない | 確認できる |
| インデックス状況 | 確認できる | 確認できない |
この違いを理解すると、両方のツールを併用することの重要性が見えてきます。
サーチコンソールで「どんなキーワードでサイトに来ているか」を把握し、Googleアナリティクスで「訪問後にどんな行動をしているか」を分析する。
この2つの視点を組み合わせることで、より効果的なサイト改善が可能になります。
名古屋の株式会社エッコでは、クライアント様のサイト分析において、両ツールのデータを統合的に活用することで、検索流入からコンバージョンまでの導線を最適化するサポートを行っています。
サーチコンソールを使うメリット
Googleサーチコンソールを導入することで得られるメリットは数多くありますが、特に重要なポイントを紹介します。
1つ目のメリットは、検索パフォーマンスを数値で正確に把握できるという点です。
「なんとなくアクセスが増えた気がする」という感覚的な判断ではなく、具体的な数値データに基づいてサイトの状況を評価できます。
どのページが何回表示されて、何回クリックされたのか、平均で何位に表示されているのかを明確に知ることができるため、改善施策の効果測定も正確に行えます。
2つ目のメリットは、サイトの技術的な問題を早期発見できることです。
- Googleにインデックスされていないページの存在
- モバイル表示での不具合
- ページ速度の問題
- セキュリティ上の脅威
- 手動ペナルティの通知
これらの問題は、放置すると検索順位の大幅な下落につながる可能性があります。
サーチコンソールを導入していれば、問題が発生した時点でメール通知を受け取れるため、迅速な対応が可能になります。
3つ目のメリットは、ユーザーの検索意図を深く理解できる点です。
実際にどんなキーワードで検索されているかを知ることで、ユーザーが何を求めているのか、どんな悩みを持っているのかが見えてきます。
想定していなかったキーワードでの流入があれば、それは新しいコンテンツのアイデアにもなります。
| サーチコンソールの主なメリット | 具体的な効果 |
| 無料で利用できる | コストをかけずにプロレベルの分析が可能 |
| リアルタイムで問題を検知 | サイトのトラブルに即座に対応できる |
| SEO改善の方向性が明確になる | どのページを優先的に改善すべきかわかる |
| Googleの評価基準を理解できる | 検索エンジンの視点でサイトを見直せる |
| コンテンツ制作のヒントが得られる | ユーザーニーズに合った記事を作成できる |
これらのメリットを最大限に活かすためには、ツールを導入するだけでなく、定期的にデータを確認し、分析する習慣をつけることが重要です。
株式会社エッコでは、サーチコンソールの導入から日々の運用サポートまで、クライアント様のWebマーケティングを総合的に支援しています。
Googleサーチコンソールの初期設定
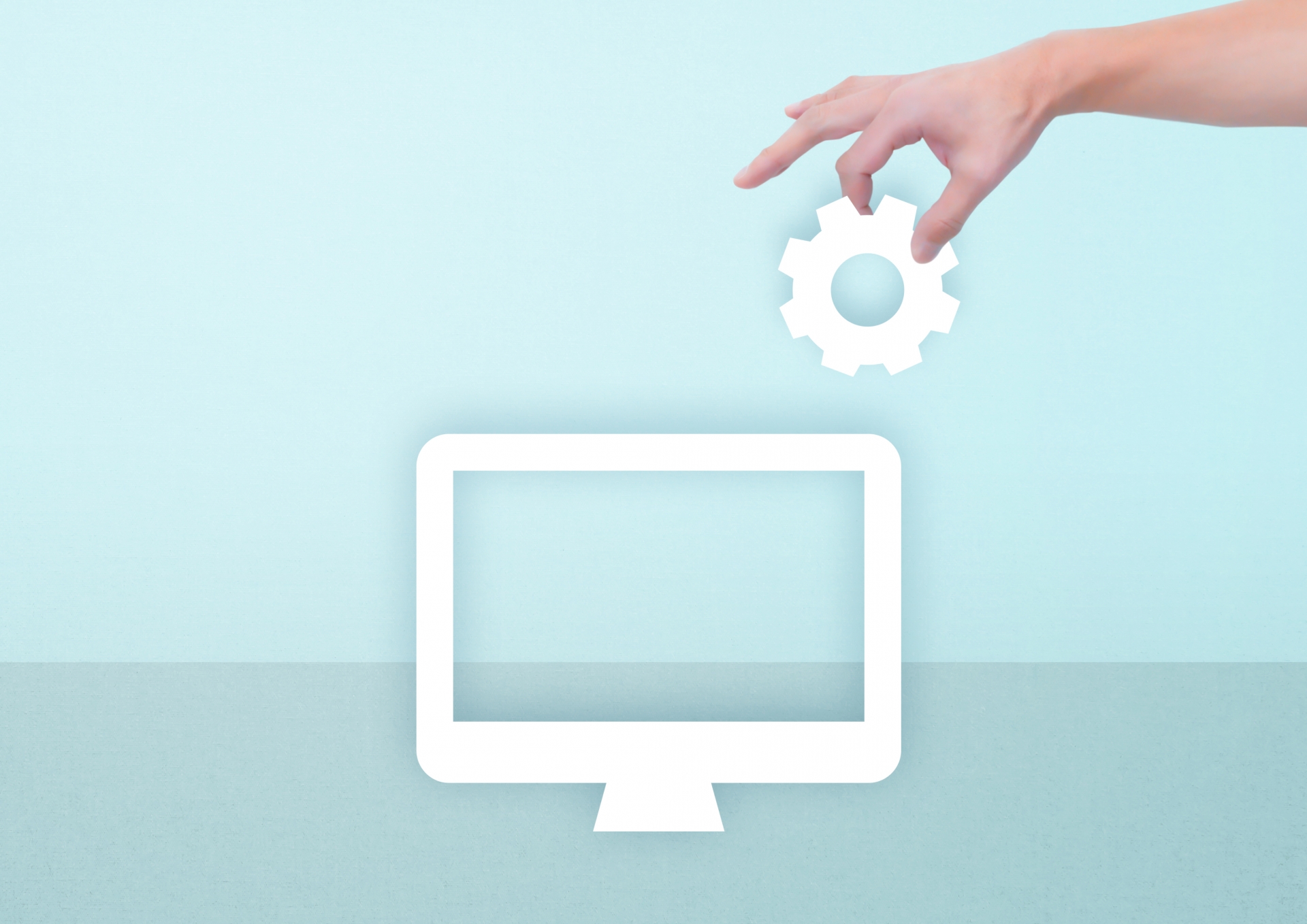
サーチコンソールのメリットを理解したところで、次は実際に導入するための初期設定を進めていきましょう。
初めての方でも迷わないよう、手順を詳しく解説します。
アカウント作成の手順
サーチコンソールを利用するための第一歩は、アカウント作成です。
ここでは、アカウント準備からプロパティの追加まで、順を追って説明します。
Googleアカウントの準備
サーチコンソールを利用するには、Googleアカウントが必要です。
既にGmailやGoogleドライブを使っている方は、そのアカウントをそのまま利用できます。
まだGoogleアカウントを持っていない方は、以下の手順で作成しましょう。
- Googleアカウント作成ページにアクセスする
- 名前とメールアドレスを入力する
- パスワードを設定する
- 電話番号を登録して本人確認を行う
- 利用規約に同意して登録を完了する
アカウント作成が完了したら、Google Search Consoleの公式サイトにアクセスします。
「今すぐ開始」ボタンをクリックすると、先ほど作成したGoogleアカウントでログインする画面が表示されます。
ここで注意したいのが、サイト管理に使用するアカウント選びです。
個人用のGmailアドレスではなく、会社の担当者間で共有できるアカウントを使用することをおすすめします。
そうすることで、担当者が変わってもスムーズにサイト管理を引き継ぐことができます。
プロパティの追加方法
Googleアカウントでログインすると、プロパティタイプの選択画面が表示されます。
プロパティとは、サーチコンソールで管理するWebサイトのことを指します。
ここで選択できるのは「ドメイン」と「URLプレフィックス」の2種類です。
「ドメイン」プロパティを選択すると、以下のようなURLをまとめて管理できます。
- http://example.com
- https://example.com
- http://www.example.com
- https://www.example.com
- https://sub.example.com(サブドメイン)
つまり、プロトコル(httpとhttps)やwwwの有無、サブドメインの違いを気にせず、ドメイン全体のデータを一元管理できるのです。
一方、「URLプレフィックス」プロパティは、入力した特定のURL配下のみを管理します。
初心者の方には、設定が比較的簡単な「URLプレフィックス」がおすすめです。
| プロパティタイプ | 推奨される状況 |
| ドメイン | 複数のサブドメインを運用している、httpとhttpsを併用している場合 |
| URLプレフィックス | 単一のサイトを管理する、Googleアナリティクスと連携したい場合 |
どちらを選ぶか迷った場合は、まず「URLプレフィックス」から始めて、必要に応じて後から「ドメイン」プロパティを追加することもできます。
選択したら、管理したいサイトのURLを入力し、「続行」ボタンをクリックします。
所有権の確認方法
プロパティを追加しただけでは、まだサーチコンソールは使えません。
そのサイトが本当にあなたのものであることをGoogleに証明する必要があります。
これを「所有権の確認」と呼びます。
所有権の確認方法はいくつかありますが、ここでは代表的な3つの方法を紹介します。
HTMLファイルによる確認
最も一般的な確認方法が、HTMLファイルをサイトにアップロードする方法です。
この方法は、FTP接続などでサーバーにファイルをアップロードできる環境があれば、誰でも実行できます。
手順は以下の通りです。
- サーチコンソールの所有権確認画面で「HTMLファイル」を選択する
- 表示された確認用HTMLファイルをダウンロードする
- FTPソフトを使って、サイトのルートディレクトリにファイルをアップロードする
- ブラウザで「https://yoursite.com/ファイル名.html」にアクセスして表示を確認する
- サーチコンソール画面に戻り「確認」ボタンをクリックする
確認が成功すると、「所有権を確認しました」というメッセージが表示されます。
注意点として、確認後もこのHTMLファイルは削除してはいけません。
ファイルを削除すると、所有権が失われてしまいます。
もしFTPの操作に不安がある場合や、サーバーへのアクセス権限がない場合は、次に紹介する別の方法を試してみてください。
HTMLタグによる確認
2つ目の方法は、サイトのHTMLコードに専用のメタタグを追加する方法です。
この方法は、WordPressなどのCMS管理画面から直接コードを編集できる場合に便利です。
- 所有権確認画面で「HTMLタグ」を選択する
- 表示されたメタタグをコピーする
- サイトのトップページのHTMLソースを開く
- <head>セクション内の、</head>タグの直前にメタタグを貼り付ける
- 変更を保存してページを公開する
- サーチコンソール画面に戻り「確認」ボタンをクリックする
メタタグは、ページには表示されませんが、ソースコード上には記述されている状態になります。
WordPressを使用している場合は、テーマの編集画面から「header.php」ファイルを開いて追加するか、SEO系のプラグインを使って設定することもできます。
この方法も、確認後にメタタグを削除すると所有権が失われるので注意してください。
Googleアナリティクスとの連携
3つ目の方法は、既にGoogleアナリティクスを導入しているサイトで使える方法です。
同じGoogleアカウントでアナリティクスとサーチコンソールを使用している場合、最も簡単に所有権を確認できます。
- 所有権確認画面で「Googleアナリティクス」を選択する
- 該当するアナリティクスプロパティを選択する
- 「確認」ボタンをクリックする
この方法なら、ファイルのアップロードもコードの編集も不要です。
ただし、この方法が使えるのは、アナリティクスで「編集」権限以上を持っている場合に限られます。
また、アナリティクスのトラッキングコードが正しくサイトに設置されている必要があります。
| 確認方法 | 難易度 | メリット | デメリット |
| HTMLファイル | 中 | 確実性が高い | FTP操作が必要 |
| HTMLタグ | 中 | ファイルアップロード不要 | HTMLコード編集が必要 |
| Googleアナリティクス | 低 | 最も簡単 | アナリティクス導入済みが前提 |
名古屋の株式会社エッコでは、クライアント様のサイト環境に応じて最適な確認方法をご提案し、初期設定のサポートを行っています。
サイトマップの送信
所有権の確認が完了したら、次はサイトマップの送信を行います。
サイトマップとは、サイト内のページ構造をGoogleに伝えるためのファイルです。
XML形式で作成され、「sitemap.xml」という名前で保存されることが一般的です。
サイトマップを送信することで、以下のようなメリットがあります。
- Googleのクローラーがサイト全体を効率的に巡回できる
- 新しいページを素早くインデックスしてもらえる
- 更新したページの変更を早く認識してもらえる
- サイト構造が複雑でも、すべてのページを見つけてもらえる
送信の手順は非常にシンプルです。
- サーチコンソールの左メニューから「サイトマップ」を選択する
- 「新しいサイトマップの追加」欄にサイトマップのURLを入力する(例:sitemap.xml)
- 「送信」ボタンをクリックする
- ステータスが「成功しました」と表示されることを確認する
WordPressを使用している場合は、「Yoast SEO」や「XML Sitemaps」などのプラグインを使えば、自動的にサイトマップを生成できます。
サイトマップの送信は、大規模なサイトや新規サイト、頻繁に更新するサイトで特に重要です。
小規模なサイトでも送信しておくことで、より確実にGoogleに認識してもらえます。
ただし、サイトマップを送信したからといって、すぐにすべてのページがインデックスされるわけではありません。
Googleが適切と判断したタイミングでクロールとインデックスが行われます。
サーチコンソールでできること6つ

初期設定が完了したら、いよいよサーチコンソールの機能を使ってみましょう。
ここでは、サイト運営に欠かせない6つの主要機能について詳しく解説します。
検索パフォーマンスの分析
サーチコンソールの中でも最も頻繁に使う機能が、この検索パフォーマンスです。
左側のメニューから「検索パフォーマンス」→「検索結果」を選択すると、サイトの検索パフォーマンスに関する詳細なデータを確認できます。
この機能を使いこなすことで、SEO改善の具体的な方向性が見えてきます。
クリック数・表示回数の確認
検索パフォーマンス画面の上部には、4つの重要な指標が表示されています。
デフォルトでは「合計クリック数」と「合計表示回数」にチェックが入っていますが、「平均CTR」と「平均掲載順位」にもチェックを入れることで、より詳細な分析が可能になります。
合計クリック数は、検索結果からあなたのサイトが実際にクリックされた回数を示します。
これは、サイトへの実際の訪問数(正確には検索経由の訪問数)を表す重要な指標です。
合計表示回数は、検索結果にあなたのサイトが表示された回数です。
表示されただけでクリックされていないケースも含まれるため、クリック数よりも大きな数値になります。
画面下部には、クエリ(検索キーワード)ごとの詳細データが一覧表示されます。
- どのキーワードで検索されているか
- それぞれのキーワードで何回表示されたか
- 何回クリックされたか
- クリック率は何パーセントか
- 平均で何位に表示されているか
これらの情報から、「表示回数は多いのにクリック数が少ないキーワード」や「意外なキーワードで検索されている」といった発見があるはずです。
検索順位の推移チェック
「平均掲載順位」の項目では、各キーワードでの検索順位の平均値を確認できます。
ただし、これはあくまで平均値なので、例えば1日の中でも順位が変動している場合があります。
検索順位の推移をチェックする際は、期間を比較する機能が非常に便利です。
- 画面上部の日付をクリックする
- 「比較」タブを選択する
- 比較したい期間を設定する
例えば、「過去28日間」と「その前の28日間」を比較することで、順位が上がったキーワードと下がったキーワードを一目で確認できます。
順位が上昇したキーワードは、そのまま維持できるようコンテンツを強化し、順位が下落したキーワードは原因を分析して改善策を考えます。
クリック率(CTR)の分析
**クリック率(CTR:Click Through Rate)**は、表示回数に対してどれだけクリックされたかを示す割合です。
計算式は以下の通りです。
CTR(%)= クリック数 ÷ 表示回数 × 100
| 検索順位 | 平均的なCTR |
| 1位 | 約28〜35% |
| 2位 | 約15〜20% |
| 3位 | 約10〜15% |
| 4〜5位 | 約7〜10% |
| 6〜10位 | 約3〜7% |
| 11位以下 | 約2%以下 |
上記は一般的な目安ですが、業界やキーワードによって大きく異なります。
重要なのは、自社サイトの平均CTRと比較して、特に低いキーワードを見つけることです。
例えば、5位に表示されているのにCTRが2%しかない場合、タイトルやディスクリプション(説明文)が魅力的でない可能性があります。
このような場合は、タイトルを改善することでクリック数を増やせる可能性が高いのです。
インデックス状況の管理
インデックスとは、Googleがあなたのサイトのページをデータベースに登録することを指します。
インデックスされていないページは、検索結果に表示されません。
左メニューの「ページ」をクリックすると、サイト全体のインデックス状況を確認できます。
画面には以下のような情報が表示されます。
| ステータス | 意味 | 対応 |
| インデックス済み | Googleに正常に登録されている | 特に対応不要 |
| クロール済み – インデックス未登録 | クロールされたが登録されなかった | ページ品質の見直しが必要 |
| 検出 – インデックス未登録 | 見つかったがクロールされていない | 内部リンクの強化を検討 |
| noindexタグにより除外 | 意図的に登録を拒否している | 意図的なら問題なし |
| ページにリダイレクトがあります | 別のページにリダイレクトされている | 意図的なら問題なし |
特に注意が必要なのは、重要なページが「インデックス未登録」になっている場合です。
詳細をクリックすると、該当するURLの一覧が表示されるので、それぞれの原因を特定して対処します。
インデックス状況は、サイトの検索パフォーマンスに直結する重要な要素です。
新しいページを公開したら、必ずインデックスされているかを確認する習慣をつけましょう。
サイトの問題点の発見と修正
サーチコンソールは、サイトに問題が発生したときに通知してくれる機能があります。
「エクスペリエンス」メニューの中にある項目や、画面右上のベルアイコンから確認できます。
主な問題の種類は以下の通りです。
- モバイルユーザビリティの問題(文字が小さい、タップ要素が近すぎるなど)
- ウェブに関する主な指標の問題(ページ速度が遅い、レイアウトが不安定など)
- 構造化データのエラー(リッチリザルト表示のためのコードに不備がある)
- セキュリティの問題(マルウェア感染、ハッキングの疑いなど)
- 手動による対策(Googleのガイドライン違反によるペナルティ)
これらの問題を放置すると、検索順位の下落や、最悪の場合は検索結果から削除される可能性もあります。
問題が通知されたら、できるだけ早く対応することが重要です。
各問題には詳細な説明と、Googleが推奨する修正方法へのリンクが表示されるので、それに従って修正を進めます。
修正が完了したら、サーチコンソール上で「修正を検証」をクリックすることで、Googleに再確認してもらえます。
被リンク状況の確認
被リンクとは、他のサイトからあなたのサイトへ向けられたリンクのことです。
SEOにおいて、質の高い被リンクは非常に重要な評価要素の1つとされています。
左メニューの「リンク」をクリックすると、以下の情報を確認できます。
- 外部リンク(他サイトからのリンク)
- 上位のリンクされているページ(どのページが最も被リンクを集めているか)
- 上位のリンク元サイト(どのサイトから多くリンクされているか)
- 上位のリンク元テキスト(どんな文言でリンクされているか)
- 内部リンク(自サイト内のリンク構造)
特に注目すべきは、どんなサイトからリンクされているかという点です。
権威性の高いメディアや、関連性の高い業界サイトからのリンクは、SEO評価にプラスに働きます。
一方で、スパムサイトや質の低いサイトからの不自然なリンクは、逆にマイナス評価につながる可能性があります。
もし不自然な被リンクを大量に発見した場合は、「リンクの否認ツール」を使ってGoogleに無視するよう依頼することもできます。
| チェックポイント | 確認内容 |
| 被リンクの総数 | 増減の傾向をチェック |
| リンク元ドメイン数 | 多様なサイトからリンクされているか |
| リンクされているページ | 特定のページに集中していないか |
| アンカーテキスト | 不自然なキーワードの繰り返しがないか |
定期的に被リンク状況をチェックすることで、SEO評価の変動要因を把握できます。
モバイルユーザビリティの確認
現在、Google検索の大部分はスマートフォンから行われているため、モバイル対応は必須です。
Googleも「モバイルファーストインデックス」という方針を採用しており、主にモバイル版のサイトを評価基準にしています。
「エクスペリエンス」メニューから「モバイルユーザビリティ」を選択すると、スマートフォンでの表示に問題がないかを確認できます。
よくある問題としては、以下のようなものがあります。
- テキストが小さすぎて読めない
- クリック可能な要素同士が近すぎる
- コンテンツの幅が画面サイズより大きい
- 互換性のないプラグインを使用している
これらの問題がある場合、該当するURLと具体的な修正方法が表示されます。
WordPressなどのCMSを使っている場合は、レスポンシブ対応のテーマを選ぶことで、多くの問題を解決できます。
修正後は、Googleの「モバイルフレンドリーテスト」ツールを使って、改善されたかを確認しましょう。
モバイルでの使いやすさは、ユーザー体験に直結するだけでなく、検索順位にも影響する重要な要素です。
URL検査機能の活用
URL検査機能は、個別のページの状態を詳しくチェックできる便利なツールです。
画面上部の検索窓に、調べたいページのURLを入力すると、以下のような情報が表示されます。
- Googleインデックスに登録されているか
- 最後にクロールされた日時
- クロール時に発見された問題
- ページの読み込み状況
- モバイル版の表示状態
この機能が特に役立つのは、新しいページを公開した直後や、既存ページを大幅に更新した後です。
検査結果画面で「インデックス登録をリクエスト」をクリックすると、Googleのクローラーに優先的に訪問してもらうよう依頼できます。
ただし、リクエストしたからといって即座にインデックスされるわけではありません。
また、1日に何度もリクエストしても効果は変わらないので、1回リクエストしたら数日待つのが適切です。
「公開URLをテスト」機能を使えば、現時点での最新のページ状態をGoogleがどう認識するかをシミュレーションできます。
この機能を使うことで、ページ公開前に問題を発見し、修正してから公開するという流れも可能になります。
名古屋の株式会社エッコでは、新規コンテンツ公開時のインデックス確認から、既存ページの最適化まで、サーチコンソールを活用した包括的なサポートを提供しています。
効果的な活用方法
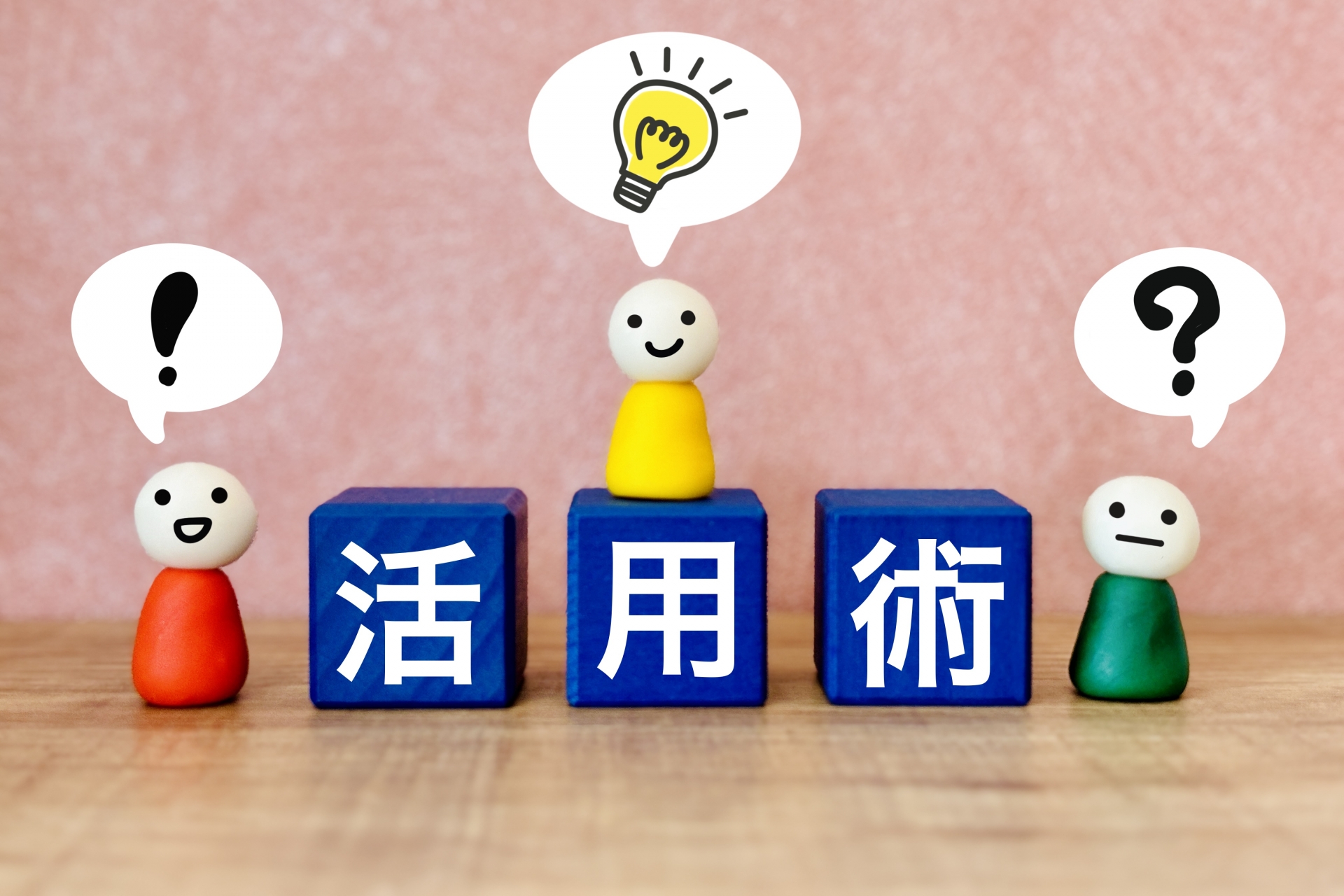
サーチコンソールの機能を理解したところで、次は実際のサイト改善にどう活かすかを見ていきましょう。
ここでは、すぐに実践できる具体的な活用方法を紹介します。
SEO改善に役立つデータの見方
サーチコンソールのデータは膨大ですが、どこに注目すべきかを知ることで、効率的にSEO改善ができます。
まず重要なのは、「検索パフォーマンス」でクエリ(検索キーワード)とページの関係を分析することです。
左メニューから「検索パフォーマンス」→「検索結果」を開き、「クエリ」タブで気になるキーワードをクリックします。
そして「ページ」タブに切り替えると、そのキーワードでどのページが表示されているかがわかります。
| 分析すべきポイント | 見るべきデータ | 改善アクション |
| 順位は高いのにCTRが低い | 平均掲載順位とCTR | タイトルタグを魅力的に書き直す |
| 表示回数は多いのに順位が低い | 表示回数と掲載順位 | コンテンツの質を向上させる |
| 意図しないキーワードで流入 | 流入キーワード一覧 | ページ内容を見直す、または新記事作成 |
| 想定キーワードで表示されない | フィルター機能で検索 | 内部リンクの見直し、キーワード最適化 |
次に、期間比較機能を使った分析も効果的です。
画面上部の日付範囲で「過去3ヶ月」などを選択し、「比較」タブで前期間と比較します。
これにより、順位が上がったキーワード、下がったキーワードを一覧で確認できます。
順位が下がったキーワードについては、競合サイトが新しい記事を公開していないか、自社のコンテンツが古くなっていないかをチェックしましょう。
また、「ページ」タブから個別のページを選択し、そのページが獲得しているキーワードを確認することも重要です。
1つのページで複数の関連キーワードを獲得できていれば、そのコンテンツは評価されている証拠です。
一方、狙ったキーワードで全く流入がない場合は、コンテンツの方向性が間違っている可能性があります。
リライト記事の選定方法
限られた時間の中で最大の効果を得るには、どの記事をリライトするかの優先順位づけが重要です。
サーチコンソールを使えば、改善すべき記事を効率的に見つけられます。
最も効果的なのは、11位〜20位に表示されているキーワードを見つける方法です。
この順位帯のページは、少し改善すれば検索結果の1ページ目(1〜10位)に入る可能性が高いからです。
手順は以下の通りです。
- 「検索パフォーマンス」→「検索結果」を開く
- 画面上部の「+新規」をクリック
- 「掲載順位」を選択し、「次より大きい」で「10」、「次より小さい」で「21」と入力
- 「適用」をクリック
これで11〜20位のキーワードだけが表示されます。
さらに「表示回数」でソート(並び替え)することで、検索需要の多いキーワードから優先的に取り組めます。
次に、該当するキーワードをクリックして「ページ」タブを見ると、どのページがそのキーワードで表示されているかがわかります。
そのページを開いて、以下の観点でリライトします。
- キーワードを意識しながらも、自然な形で本文中に含める
- 見出し構成を整理し、読みやすくする
- 情報を最新のものにアップデートする
- 関連する画像や図表を追加する
- 内部リンクを適切に設置する
リライト後は、再度URL検査機能を使ってインデックス登録をリクエストし、数週間後に順位の変化を確認します。
もう1つ効果的なのは、CTRが低いページを改善する方法です。
- 「平均CTR」と「平均掲載順位」にチェックを入れる
- 「+新規」から「掲載順位」を選択し、「次より小さい」で「6」と入力(5位以内を抽出)
- CTRでソートし、平均より低いページを探す
5位以内に表示されているのにCTRが低い場合、タイトルやメタディスクリプションを見直すだけで、大幅にクリック数を増やせる可能性があります。
GA4との連携で得られる相乗効果
サーチコンソールとGA4(Googleアナリティクス4)を連携させると、サイトへの流入前と流入後のデータを統合的に分析できます。
連携の手順は以下の通りです。
- GA4の管理画面を開く
- 左下の「管理」をクリック
- 「Search Consoleのリンク」を選択
- 「リンク」ボタンをクリック
- サーチコンソールのプロパティを選択して確認
- 対応するウェブストリームを選択
- 「送信」をクリックして完了
連携が完了すると、GA4のレポート画面で「Search Console」という項目が表示されるようになります。
ここでは、以下のような分析が可能になります。
| 分析内容 | わかること | 活用方法 |
| 流入キーワードごとのコンバージョン率 | どのキーワード経由が最も成果につながるか | 高CVキーワードのコンテンツを強化 |
| 流入後の回遊状況 | 検索経由の訪問者がどう行動しているか | 離脱率の高いページを改善 |
| キーワード別の滞在時間 | どのキーワードがエンゲージメント高いか | 滞在時間の長いテーマでコンテンツ拡充 |
| デバイス別のパフォーマンス | PC・モバイルでの行動の違い | デバイスに応じた最適化 |
例えば、サーチコンソールで「クリック数は多いのにコンバージョンが少ない」キーワードを見つけたら、GA4で流入後の行動を分析します。
すぐに離脱しているのか、他のページを見ているのか、どこで離脱しているのかを確認し、ユーザーの期待と実際のコンテンツのギャップを埋めていきます。
また、GA4の「エンゲージメント」指標と組み合わせることで、単なる流入数だけでなく、質の高いトラフィックを生み出しているキーワードを特定できます。
名古屋の株式会社エッコでは、サーチコンソールとGA4の両方を活用した総合的なWebマーケティング戦略の立案・実行をサポートしています。
定期的なチェック項目
サーチコンソールは、定期的に確認する習慣をつけることで最大の効果を発揮します。
ここでは、チェック頻度別におすすめの項目を紹介します。
毎日チェックする項目
- メッセージ(ベルアイコン):重大なエラーやペナルティの通知がないか
週1回チェックする項目
- 検索パフォーマンスの推移:前週と比較してクリック数や表示回数が大きく変動していないか
- インデックスカバレッジ:新たなエラーが発生していないか
- 新規公開ページのインデックス状況:公開したページが正しく登録されているか
月1回チェックする項目
- 検索パフォーマンスの詳細分析:どのキーワード・ページが成長しているか
- 被リンク状況:新しいリンク獲得があるか、不自然なリンクが増えていないか
- モバイルユーザビリティ:新たな問題が発生していないか
- ウェブに関する主な指標:ページ速度などのユーザー体験指標
四半期に1回チェックする項目
- 全体的なSEO戦略の見直し:サーチコンソールのデータをもとに、次の施策を計画
- 過去との長期比較:年間を通じた季節変動やトレンドの把握
- 競合サイトとの比較分析:自社の立ち位置を確認
これらのチェックを習慣化するために、スプレッドシートやタスク管理ツールに記録していくことをおすすめします。
チェックの際に気づいた点をメモしておけば、後で振り返ったときに改善のヒントになります。
よくあるトラブルと対処法

サーチコンソールを使っていると、様々な問題に直面することがあります。
ここでは、初心者が陥りがちなトラブルと、その解決方法を紹介します。
インデックス登録されない場合
「新しいページを公開したのに、いつまで経っても検索結果に表示されない」という悩みは非常に多く見られます。
インデックス登録されない主な原因は以下の通りです。
原因1:noindexタグが設定されている
ページのHTMLに「noindex」というタグが入っていると、Googleは意図的にそのページをインデックスしません。
WordPressの場合、SEOプラグインの設定で誤ってnoindexにチェックが入っている可能性があります。
ページのソースコードを確認するか、URL検査機能で「カバレッジ」を見ると、noindexが原因かどうかがわかります。
原因2:robots.txtでクロールがブロックされている
サイトのルートディレクトリにある「robots.txt」というファイルで、クローラーのアクセスが制限されている場合があります。
サーチコンソールの「robots.txtテスター」機能を使って、該当のURLがブロックされていないか確認しましょう。
原因3:ページの品質が低いと判断されている
- コンテンツの文字数が極端に少ない
- 他サイトからのコピーコンテンツ
- ユーザーにとって価値のない内容
- キーワードを不自然に詰め込んでいる
このような場合、Googleは「インデックスする価値がない」と判断することがあります。
対処法は、コンテンツの質を根本から見直すことです。
| トラブル内容 | 確認方法 | 対処法 |
| noindexタグの誤設定 | URL検査→カバレッジ | noindexタグを削除 |
| robots.txtのブロック | robots.txtテスター | robots.txtを修正 |
| 内部リンクがない | サイト構造の確認 | 関連ページから内部リンクを設置 |
| ページ品質の問題 | コンテンツの見直し | 情報を充実させ、独自性を高める |
インデックス登録をリクエストしても、すぐには登録されない場合があります。
通常、数日から数週間かかることもあるので、焦らず待つことも大切です。
クロールエラーへの対応
クロールエラーとは、Googleのクローラーがページにアクセスしようとした際に発生する問題のことです。
「ページ」メニューで「エラー」と表示されているページがあれば、詳細を確認して対処する必要があります。
よくあるクロールエラーと対処法を紹介します。
404エラー(ページが見つからない)
ページが削除されている、URLが間違っているなどの理由で発生します。
対処法は以下の通りです。
- ページが不要なら、301リダイレクトで別の関連ページに転送する
- ページを誤って削除した場合は、復元する
- URL構造を変更した場合は、リダイレクト設定を行う
サーバーエラー(500番台のエラー)
サイトのサーバーに問題がある場合に発生します。
サーバーの容量不足、プラグインの競合、PHPのバージョン問題などが原因として考えられます。
レンタルサーバーの管理画面やエラーログを確認し、必要に応じてサーバー会社に問い合わせましょう。
リダイレクトエラー
リダイレクトが多段階になっている、リダイレクトループが発生しているなどの場合に起こります。
リダイレクトは、できるだけ1回で最終的なURLに転送されるよう設定します。
クロールエラーを放置すると、サイト全体の評価が下がる可能性があるため、定期的にチェックして対応しましょう。
ペナルティ通知を受けた時の対処
Googleからペナルティを受けると、検索順位が大幅に下落したり、最悪の場合は検索結果から削除されたりします。
ペナルティには「手動ペナルティ」と「アルゴリズムペナルティ」の2種類がありますが、サーチコンソールで通知されるのは手動ペナルティです。
「セキュリティと手動による対策」メニューで「手動による対策」を確認し、問題が表示されている場合は以下の手順で対処します。
- 問題の内容を詳しく読む(どのページが、どんな理由でペナルティを受けたか)
- 該当ページの問題箇所を修正する
- 修正が完了したら「再審査リクエスト」を送信する
- Googleの審査を待つ(数日〜数週間かかる場合がある)
よくあるペナルティの原因は以下の通りです。
- 質の低い外部リンクを大量に購入している
- コンテンツをコピーしている
- 隠しテキストや隠しリンクを使用している
- キーワードを不自然に詰め込んでいる
- ユーザーを誤解させるような表示をしている
ペナルティを受けた場合、単に問題箇所を削除するだけでなく、なぜその問題が発生したのか、今後どう防ぐのかを再審査リクエストで説明することが重要です。
真摯に対応すれば、ペナルティは解除される可能性が高いので、諦めずに適切に対処しましょう。
株式会社エッコでは、ペナルティを受けたサイトの原因調査から、具体的な改善策の実施、再審査リクエストのサポートまで、包括的な支援を提供しています。
まとめ

Googleサーチコンソールは、Webサイトの検索パフォーマンスを向上させるために欠かせない無料ツールです。
本記事では、初心者の方に向けて、サーチコンソールの基本概念から初期設定、具体的な活用方法まで詳しく解説してきました。
サーチコンソールを使いこなすことで得られる主なメリットをあらためて整理すると、以下の通りです。
- どんなキーワードで検索されているかを正確に把握できる
- サイトの技術的な問題を早期に発見し、迅速に対処できる
- ユーザーの検索意図を理解し、コンテンツ改善の方向性が明確になる
- インデックス状況を管理し、新しいページを確実に検索結果に表示させられる
- 被リンク状況を確認し、SEO評価の変動要因を把握できる
重要なのは、ツールを導入するだけでなく、定期的にデータを確認し、分析し、改善につなげるサイクルを回すことです。
最初は難しく感じるかもしれませんが、毎週少しずつでもサーチコンソールを開いて眺めるだけでも、徐々にデータの見方がわかってくるはずです。
特に以下の3つの機能は、初心者の方でもすぐに活用できます。
- 検索パフォーマンスで流入キーワードを確認する
- URL検査で新規ページのインデックス状況をチェックする
- メッセージ機能で重大なエラーを見逃さない
サーチコンソールのデータを活用すれば、「なんとなく」ではなく、データに基づいた戦略的なSEO施策を実施できるようになります。
その結果、検索順位の向上、検索流入の増加、そして最終的にはビジネス成果の向上につながっていくのです。
名古屋を拠点とする株式会社エッコでは、Googleサーチコンソールの導入支援から、日々のデータ分析、具体的な改善施策の立案・実行まで、Webマーケティング全般をサポートしています。
「サーチコンソールを導入したけれど、どう活用すればいいかわからない」「データは見ているけれど、具体的な改善策が思いつかない」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
地域密着型のサポート体制で、あなたのWebサイトの成長をしっかりとお手伝いいたします。
さあ、今日からあなたもGoogleサーチコンソールを使って、サイトの検索パフォーマンスを飛躍的に向上させましょう。
最初の一歩は、サーチコンソールにログインして、あなたのサイトがどんなキーワードで検索されているかを確認することから始まります。



