「SEO対策には何文字くらい必要なんだろう?」
Webサイトの運営担当者なら、一度は悩んだことがあるのではないでしょうか。
インターネット上には「最低1,000文字は必要」「3,000文字以上書けば上位表示される」といった情報があふれています。
しかし、本当に文字数を増やすだけでSEO効果が高まるのでしょうか?
実は、Googleは文字数そのものを評価基準としていません。
それにもかかわらず、検索結果の上位に表示される記事の多くが長文である理由には、明確な背景があります。
この記事では、SEOと文字数の本当の関係性について、データと実例をもとに徹底解説します。
「何文字書けばいいのか」という表面的な疑問から一歩踏み込んで、検索エンジンに評価される質の高いコンテンツの作り方まで、実践的なノウハウをお伝えします。
名古屋でWebコンサルティングを手がける株式会社エッコでも、多くのお客様から文字数に関するご相談をいただきます。
この記事を読めば、文字数にとらわれることなく、ユーザーに価値を提供するコンテンツ制作の本質が理解できるはずです。
それでは、SEOと文字数の真実を一緒に見ていきましょう。
Index
SEOと文字数の関係性の真実

SEO対策において、文字数がどのような役割を果たすのかを正しく理解することは、効果的なコンテンツ制作の第一歩です。
ここでは、多くの人が誤解している「文字数神話」の真相を、Googleの公式見解と実際のデータをもとに明らかにしていきます。
Googleは文字数を直接評価していない
Googleは文字数の多さそのものを検索順位の評価基準としていません。
これは、Googleのジョン・ミューラー氏が2016年7月8日に公式に発言した内容です。
彼は「Googleには、ページの文字数を数えて『100文字未満は悪い、100〜500文字は良い』といった判断をするアルゴリズムは存在しない」と明言しています。
| Googleの評価基準 | 詳細 |
| 文字数 | 直接的な評価要素ではない |
| コンテンツの質 | ユーザーの検索意図を満たしているか |
| 情報の網羅性 | 必要な情報が過不足なく含まれているか |
| ユーザー体験 | 読みやすさ、理解しやすさ |
つまり、1,000文字書けば上位表示される、3,000文字あればSEOに強いといった固定的な基準は存在しないのです。
Googleが重視しているのは、ユーザーにとって価値のある情報が提供されているかどうかという点です。
検索エンジンは、文字数の多寡ではなく、ページ全体を総合的に評価して順位を決定しています。
これは、Googleのビジネスモデルとも深く関係しています。
Googleは検索エンジンに表示される広告から収益を得ているため、ユーザーが満足する検索結果を提供し続けることが最優先事項なのです。
もし文字数が多いだけの低品質なコンテンツばかりが上位表示されれば、ユーザーはGoogleを使わなくなり、広告収入も減少してしまいます。
だからこそ、Googleは文字数よりもコンテンツの質を評価する仕組みを進化させ続けているのです。
上位表示サイトの文字数に傾向がある理由
文字数が直接的な評価基準でないにもかかわらず、実際に検索上位に表示されるサイトの多くは文字数が多い傾向にあります。
これには明確な理由があります。
アメリカの著名なSEO調査機関Backlinkoが約100万件の検索結果を分析した結果、検索1ページ目に表示されるコンテンツの平均文字数は英語で1,890単語でした。
これを日本語に換算すると、約4,000〜5,000文字に相当します。
この傾向が生まれる理由は、ユーザーの検索意図を満たすために必要な情報を網羅的に提供した結果、自然と文字数が増えているからです。
たとえば「SEO対策」というキーワードで検索するユーザーは、SEOの定義だけでなく、具体的な施策方法、効果測定の方法、注意点など、幅広い情報を求めています。
これらすべてに丁寧に答えようとすれば、必然的に一定の文字数が必要になります。
つまり、文字数が多いから上位表示されているのではなく、質の高い網羅的な情報を提供した結果として文字数が多くなり、それがGoogleに評価されているのです。
これは因果関係の逆転を理解することが重要なポイントです。
株式会社エッコでは、クライアント様のSEO対策をサポートする際、文字数ではなく「ユーザーが本当に知りたい情報は何か」という視点から逆算してコンテンツ設計を行っています。
検索ニーズと文字数の相関関係
検索キーワードによって、ユーザーが求める情報量は大きく異なります。
そのため、最適な文字数もキーワードの種類によって変動するのです。
たとえば「東京 天気」と検索するユーザーは、今日の天気が晴れか雨かという端的な情報だけを求めています。
この場合、数百文字で簡潔に答えるコンテンツの方が、ユーザーにとって価値が高いでしょう。
一方、「SEO対策 初心者 始め方」と検索するユーザーは、SEOの基礎知識から具体的な実践方法、ツールの使い方、注意点まで、包括的な情報を求めています。
これに答えるには、5,000文字以上の詳細な解説が必要になるケースが多いのです。
| 検索意図のタイプ | 必要な情報量 | 文字数の目安 |
| 即答型(天気、営業時間など) | 端的な事実のみ | 500〜1,000文字 |
| 情報収集型(〜とは、〜方法など) | 網羅的な解説 | 3,000〜5,000文字以上 |
| 比較検討型(〜比較、〜おすすめなど) | 複数の選択肢と評価基準 | 4,000〜8,000文字 |
このように、検索ニーズが複雑であるほど、それに答えるための文字数も増えるという相関関係があります。
重要なのは、文字数を目標にするのではなく、ユーザーの検索意図を深く理解し、それに応える情報を過不足なく提供することです。
そうすることで、結果として適切な文字数のコンテンツが自然に生まれるのです。
キーワード別の最適な文字数の考え方

SEO対策において、「このキーワードなら何文字書けばいいのか」という疑問は多くの方が抱えています。
ここでは、キーワードのタイプ別に文字数の傾向を分析し、実践的な調査方法までご紹介します。
情報収集型キーワードの文字数傾向
情報収集型キーワードとは、ユーザーが何かを学びたい、知りたいという意図で検索する言葉です。
「〜とは」「〜方法」「〜やり方」といった形式が典型的です。
このタイプのキーワードでは、4,000〜7,000文字程度のボリュームが必要になるケースが多い傾向にあります。
なぜなら、情報収集型キーワードで検索するユーザーは、基礎知識から応用まで、包括的な情報を求めているからです。
たとえば「コンテンツマーケティング とは」と検索するユーザーは、定義だけでなく、具体的な手法、メリット・デメリット、成功事例、始め方など、多角的な情報を必要としています。
| 情報収集型キーワードの特徴 | 求められる情報 |
| 基礎知識が必要 | 用語の定義、背景、歴史 |
| 実践方法を知りたい | 具体的な手順、ツール、テクニック |
| 成功のコツを知りたい | 事例、注意点、よくある失敗 |
| 関連情報も欲しい | 関連用語、次のステップ、参考資料 |
これらすべてに丁寧に答えようとすると、自然と文字数は増えていきます。
ただし、文字数を稼ぐために冗長な表現や不要な情報を盛り込むのは逆効果です。
読者が本当に知りたい情報を、わかりやすく、過不足なく提供することを心がけましょう。
情報収集型キーワードでは、見出し構成を工夫して、初心者から中級者まで段階的に理解できる構造にすることが重要です。
株式会社エッコでは、クライアント様のターゲット層に応じて、情報の深さと広さのバランスを最適化したコンテンツ設計をご提案しています。
商品比較型キーワードの文字数傾向
商品比較型キーワードは、複数の選択肢の中から最適なものを選びたいというニーズを持つユーザーが使用します。
「〜比較」「〜おすすめ」「〜ランキング」といった形式が代表的です。
このタイプでは、5,000〜10,000文字を超える長文コンテンツが上位表示される傾向があります。
比較型キーワードの場合、複数の商品やサービスについて、それぞれの特徴、メリット・デメリット、価格、適した用途などを詳しく説明する必要があります。
たとえば、3つの商品を比較する記事なら、各商品について1,000文字程度の解説が必要でしょう。
さらに、選び方のポイント、比較表、よくある質問などを加えると、文字数は自然と増えていきます。
| 商品比較型コンテンツに必要な要素 | 内容 |
| 選定基準の明示 | どのような観点で比較しているか |
| 各選択肢の詳細説明 | 特徴、価格、メリット・デメリット |
| 比較表 | 一目で違いがわかる視覚的な情報 |
| おすすめの使い分け | どんな人にどれが向いているか |
ただし、比較型コンテンツで重要なのは文字数ではなく、公平で信頼できる情報を提供することです。
実際に使用した経験や、客観的なデータに基づいた評価が求められます。
また、2024年以降のGoogleアルゴリズムでは、E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)がより重視されるようになっています。
単に他のサイトの情報をまとめただけの記事ではなく、独自の視点や実体験に基づいた情報を盛り込むことが、上位表示への近道です。
競合サイトの文字数を調査する方法
最適な文字数を判断するための実践的な方法は、実際に競合サイトを調査することです。
狙っているキーワードで上位表示されているサイトの文字数を調べることで、そのキーワードで求められる情報量の目安がわかります。
ただし、この調査で得られる文字数はあくまで参考値であり、それをそのまま目標にするのではなく、「なぜその文字数が必要なのか」という視点で分析することが重要です。
無料の文字数カウントツールの活用
競合サイトの文字数を調べるには、無料の文字数カウントツールが便利です。
代表的なツールとして、以下のようなものがあります。
**「ラッコツールズ 文字数カウント」**は、URLを入力するだけでWebページの文字数を自動でカウントしてくれます。
使い方は非常にシンプルで、調査したいページのURLをコピーして貼り付けるだけです。
**「文字数カウント」**は、テキストを直接コピー&ペーストして文字数を確認できるツールです。
競合サイトの本文をコピーして貼り付ければ、瞬時に文字数が表示されます。
| ツール名 | 特徴 | 使い方 |
| ラッコツールズ | URL入力で自動カウント | URLを貼り付けるだけ |
| 文字数カウント | テキスト直接入力 | 本文をコピー&ペースト |
| Googleドキュメント | 編集しながら確認 | ツール→文字カウント |
これらのツールを使えば、数分で複数の競合サイトの文字数を調べることができます。
ただし、文字数だけでなく、どのような情報が含まれているか、どのような構成になっているかも同時に分析することが大切です。
株式会社エッコでは、競合分析の際に文字数だけでなく、見出し構成、使用されているキーワード、独自性のある情報なども総合的に調査しています。
上位10サイトの平均文字数の調べ方
より精度の高い分析をするには、上位10サイトの文字数を調べて平均値を算出する方法が効果的です。
この方法により、そのキーワードで求められる標準的な情報量が見えてきます。
具体的な手順は以下の通りです。
まず、狙っているキーワードで実際に検索し、検索結果の1位から10位までのサイトをリストアップします。
次に、各サイトの文字数を前述の文字数カウントツールを使って調査します。
そして、10サイトの文字数を合計し、10で割って平均値を算出します。
| 順位 | サイトURL | 文字数 |
| 1位 | 例:サイトA | 6,500文字 |
| 2位 | 例:サイトB | 5,200文字 |
| 3位 | 例:サイトC | 7,800文字 |
| 平均 | – | 約6,000文字 |
ただし、この平均値は絶対的な目標ではなく、あくまで参考値として扱うべきです。
重要なのは、上位サイトがどのような情報を、どのような順序で提供しているかという「内容」の部分です。
文字数が多いサイトは、どのような情報を追加しているのか。
逆に文字数が少なくても上位表示されているサイトは、どのような工夫をしているのか。
こうした視点で分析することで、本当に必要な情報が見えてきます。
競合分析は、模倣するためではなく、自社のコンテンツに何が足りないか、何を独自に提供できるかを見極めるために行うものです。
この視点を忘れずに、効果的なコンテンツ制作に活かしていきましょう。
文字数よりも重要なSEOの本質
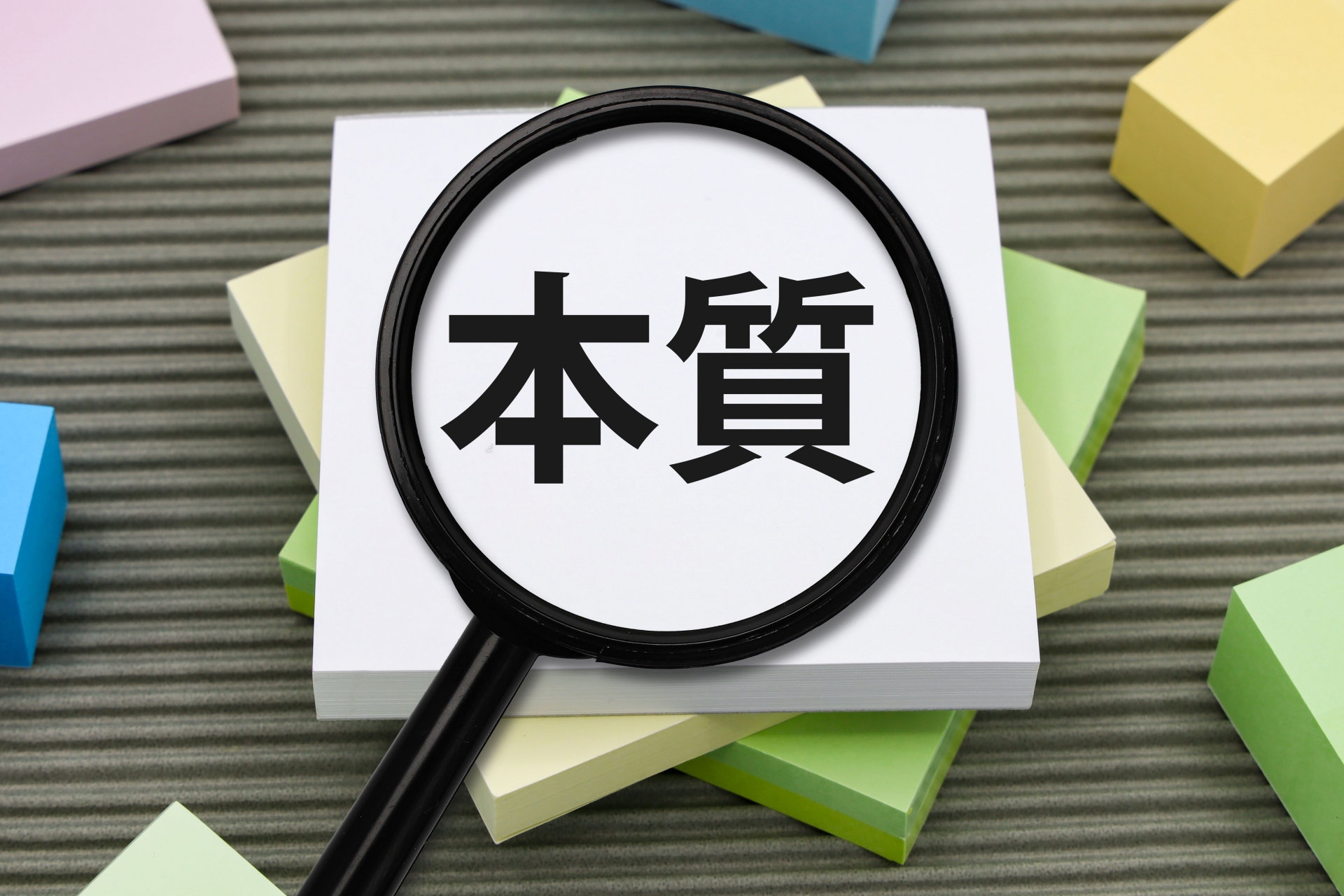
文字数は目に見える指標として気になるものですが、SEO対策において本当に重要なのは「コンテンツの質」です。
ここでは、Googleが評価する本質的な要素について、具体的に解説していきます。
検索意図を満たす情報の網羅性
検索意図(サーチインテント)とは、ユーザーが検索キーワードを入力した背景にある目的やニーズのことです。
SEOで成果を上げるには、この検索意図を正確に理解し、ユーザーが求める情報を過不足なく提供することが不可欠です。
たとえば「WordPress 始め方」と検索するユーザーの検索意図を考えてみましょう。
表面的には「WordPressの始め方を知りたい」というニーズですが、さらに深掘りすると、サーバーの選び方、ドメインの取得方法、初期設定の手順、おすすめのテーマやプラグインなど、一連の情報をまとめて知りたいという潜在的なニーズがあります。
| 検索意図の階層 | 具体的なニーズ | 必要な情報 |
| 表面的な意図 | 始め方を知りたい | 基本的な手順 |
| 潜在的な意図 | 失敗せずに始めたい | 注意点、よくある失敗 |
| 最終的な目的 | ブログで成果を出したい | 運用のコツ、成功事例 |
このように、検索意図には層があり、深い層まで満たすコンテンツほど高く評価される傾向にあります。
情報の網羅性を高めるためには、以下のポイントを意識しましょう。
まず、検索結果の上位サイトがどのような情報を提供しているかを分析します。
次に、関連キーワードやサジェストキーワード(検索窓に表示される予測変換)を調査します。
そして、Yahoo!知恵袋やSNSなどで、実際のユーザーがどのような疑問を持っているかを確認します。
ただし、網羅性を追求するあまり、不要な情報まで詰め込んでしまうのは逆効果です。
ユーザーにとって本当に必要な情報を選別し、わかりやすく整理して提供することが重要です。
株式会社エッコでは、クライアント様の業界やターゲット層を深く理解した上で、最適な情報設計をご提案しています。
ユーザー体験を考慮したコンテンツ設計
どれだけ情報が充実していても、読みにくい、理解しにくいコンテンツではユーザーは離脱してしまいます。
Googleは、ユーザーがコンテンツに満足しているかどうかを、滞在時間や直帰率などの指標から判断しています。
そのため、ユーザー体験(UX)を意識したコンテンツ設計が、SEO対策において非常に重要になっています。
読みやすいコンテンツには、いくつかの共通点があります。
適切な見出し構成によって、情報が階層的に整理されています。
段落は短めに分けられ、1つの段落で1つのテーマを扱っています。
重要なポイントは太字で強調され、一目でわかるようになっています。
箇条書きや表を効果的に使い、情報を視覚的に整理しています。
特に近年は、スマートフォンからのアクセスが増えているため、モバイルでの読みやすさも重視されています。
長文の記事でも、スマートフォンで読んだときにストレスを感じないよう、適切な改行や見出しの配置が必要です。
また、ページの読み込み速度もユーザー体験に直結します。
画像サイズが大きすぎる、不要なプラグインが多いなどの理由でページの表示が遅いと、ユーザーは待ちきれずに離脱してしまいます。
コンテンツの質を高めることと、ユーザー体験を向上させることは、どちらも欠かせない要素です。
両方をバランスよく追求することで、Googleからもユーザーからも評価されるコンテンツを作ることができます。
E-E-A-Tを意識した専門性の高い記事
E-E-A-Tとは、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の頭文字を取った言葉です。
Googleは、この4つの要素を満たすコンテンツを高く評価するという方針を明確にしています。
特に、健康、金融、法律など、人々の生活に大きな影響を与える分野(YMYL:Your Money or Your Life)では、E-E-A-Tが厳しく評価されます。
それぞれの要素について、具体的に見ていきましょう。
**Experience(経験)**は、2022年に新たに追加された評価基準です。
実際に製品を使った、サービスを利用した、現場で働いたといった実体験に基づく情報が重視されます。
**Expertise(専門性)**は、そのテーマに関する深い知識や技術を持っているかという点です。
専門的な資格、実務経験、研究実績などが評価されます。
**Authoritativeness(権威性)**は、その分野において認知されている存在かどうかです。
他のサイトからの言及、メディア掲載、業界での評判などが影響します。
**Trustworthiness(信頼性)**は、情報の正確性や透明性です。
情報源の明示、運営者情報の開示、SSL化(https)などが重要です。
| E-E-A-Tの要素 | 評価を高める方法 |
| Experience(経験) | 実体験に基づく具体的な情報、事例の提供 |
| Expertise(専門性) | 専門的な知識の提示、資格や実績の明示 |
| Authoritativeness(権威性) | 外部サイトからの言及、メディア掲載 |
| Trustworthiness(信頼性) | 情報源の明示、運営者情報の開示 |
E-E-A-Tを高めるために、記事の中で以下のような要素を盛り込むことが効果的です。
著者プロフィールを明示し、その分野での経験や実績を示す。
信頼できる情報源(公的機関、学術論文、業界団体など)を引用し、出典を明記する。
実際の体験談や独自の調査データを含める。
他サイトのコピーではない、オリジナルの視点や分析を提供する。
株式会社エッコでは、クライアント様の専門性や独自の強みを最大限に活かしたコンテンツ制作を支援しています。
名古屋を拠点に、地域密着型のWebマーケティング支援を行っており、クライアント様ごとの業界特性や競合状況を踏まえた戦略をご提案しています。
E-E-A-Tを意識したコンテンツ作りは、短期的な施策ではなく、長期的な資産形成につながります。
信頼性の高い情報を継続的に発信することで、Googleからの評価はもちろん、ユーザーからの信頼も獲得できるのです。
質の高いコンテンツを作る5つのステップ

ここまでの内容を踏まえて、実際に質の高いコンテンツを作るための具体的なステップをご紹介します。
このプロセスに従えば、文字数に頼らない、本質的なSEO効果の高いコンテンツを作成できます。
対策キーワードのユーザーニーズ分析
コンテンツ制作の第一歩は、対策キーワードを検索するユーザーが何を求めているのかを深く理解することです。
この段階を疎かにすると、どれだけ文章を書いても的外れなコンテンツになってしまいます。
ユーザーニーズの分析には、いくつかの効果的な方法があります。
まず、実際にそのキーワードで検索し、上位10サイトの内容を詳しく読み込みます。
どのような情報が提供されているか、どのような構成になっているか、どのような視点で書かれているかを分析します。
次に、検索窓に表示されるサジェストキーワード(予測変換)を確認します。
「SEO対策」と入力すると、「SEO対策 初心者」「SEO対策 費用」「SEO対策 やり方」などが表示されます。
これらは実際に多くの人が検索している関連ニーズを表しています。
Yahoo!知恵袋やQuoraなどのQ&Aサイトで、そのキーワードに関する質問を検索することも有効です。
実際のユーザーがどのような悩みを抱えているか、どのような言葉で質問しているかを知ることができます。
また、TwitterやFacebookなどのSNSで、そのテーマについてどのような会話がされているかを調べることも参考になります。
ユーザーニーズを多角的に分析することで、表面的な情報だけでなく、潜在的なニーズまで把握できます。
この段階で時間をかけてじっくり分析することが、質の高いコンテンツを作る基盤となります。
顕在ニーズと潜在ニーズの両方に対応
ユーザーニーズには、顕在ニーズと潜在ニーズの2つの層があります。
両方に適切に対応することで、ユーザー満足度が大きく向上します。
顕在ニーズとは、ユーザー自身が自覚している、表面的な情報ニーズです。
「WordPressの使い方を知りたい」「SEO対策の方法を知りたい」といった、検索キーワードに直接表れるニーズです。
一方、潜在ニーズとは、ユーザー自身は明確に意識していないものの、根底にある本質的なニーズです。
「WordPressの使い方」を検索する人の潜在ニーズは、「効率的にWebサイトを運営したい」「集客力のあるサイトを作りたい」かもしれません。
| ニーズの種類 | 特徴 | 対応方法 |
| 顕在ニーズ | ユーザーが自覚している | 記事の前半で直接的に回答 |
| 潜在ニーズ | 本質的な目的や悩み | 記事の後半で深掘りして解説 |
効果的なコンテンツ構成は、まず顕在ニーズに端的に答え、その後で潜在ニーズに応えるという流れです。
たとえば「SEO 文字数」というキーワードの場合、前半では「Googleは文字数を直接評価していない」という顕在ニーズに答えます。
そして後半では、「では、どうすれば上位表示できるのか」「質の高いコンテンツをどう作るか」という潜在ニーズに応えます。
この構成により、すぐに答えを知りたいユーザーも、深く学びたいユーザーも満足させることができます。
株式会社エッコでは、クライアント様のターゲット層の行動心理を分析し、顕在ニーズと潜在ニーズの両方に効果的にアプローチするコンテンツ戦略を設計しています。
見出し構成の最適化
見出し構成は、コンテンツの骨格となる重要な要素です。
適切な見出し構成により、情報が整理され、ユーザーにとって理解しやすく、検索エンジンにとっても評価しやすいコンテンツになります。
見出しには階層があり、HTML的にはh1タグ(最も大きな見出し)からh6タグ(最も小さな見出し)まであります。
一般的に、h1はページタイトル、h2は大見出し、h3は中見出し、h4は小見出しとして使用します。
見出し構成を作る際のポイントは以下の通りです。
まず、ユーザーニーズ分析で洗い出した情報を、論理的な順序で並べます。
基本的には、概要→詳細、原因→解決策、基礎→応用という流れが理解しやすくなります。
次に、各見出しに対策キーワードや関連キーワードを自然に含めます。
ただし、キーワードを無理に詰め込むのではなく、読者にとってわかりやすい表現を優先します。
そして、1つの見出しの下の本文が長くなりすぎないよう、適度に見出しで分割します。
目安として、h2見出しの下は500〜1,000文字程度、h3見出しの下は300〜500文字程度が読みやすいでしょう。
見出しだけを読んでも内容の概要が理解できるような構成を心がけます。
これにより、ユーザーは自分が知りたい情報がどこにあるかを素早く見つけられます。
見出し構成は、記事を書き始める前に必ず作成することをおすすめします。
先に構成を固めることで、論理的で一貫性のあるコンテンツを効率的に作成できます。
関連キーワードと共起語の自然な配置
関連キーワードと共起語を適切に配置することで、コンテンツのテーマ性が強化され、検索エンジンに内容が正確に伝わりやすくなります。
関連キーワードとは、メインキーワードと関連性の高い言葉です。
たとえば「SEO対策」の関連キーワードには、「検索エンジン最適化」「Google」「検索順位」「上位表示」などがあります。
共起語とは、メインキーワードと一緒に使われることが多い言葉です。
「SEO対策」の共起語には、「コンテンツ」「キーワード」「内部対策」「外部対策」「アクセス」などがあります。
ただし、これらのキーワードを機械的に詰め込むのは逆効果です。
自然な文章の流れの中で、必要な場面で適切に使用することが重要です。
| キーワード配置の原則 | 具体的な方法 | |—|—|—| | 自然な使用 | 無理にキーワードを入れず、文脈に合わせる | | 適度な頻度 | メインキーワードは全体の1〜2%程度 | | バリエーション | 同じ表現の繰り返しを避け、言い換えも使う | | 重要箇所への配置 | タイトル、見出し、導入文、まとめに含める |
たとえば、「SEO対策」というキーワードを使う場合、毎回「SEO対策」と書くのではなく、「検索エンジン最適化」「SEO施策」「検索順位の改善」など、バリエーションを持たせることで、より自然で読みやすい文章になります。
また、関連キーワードや共起語を調べるツールもいくつかあります。
Googleの検索窓に表示されるサジェストキーワードや、ページ下部の「関連する検索キーワード」は無料で活用できる有用な情報源です。
重要なのは、キーワードのために文章を書くのではなく、読者のために文章を書き、その結果として必要なキーワードが自然に含まれる状態を目指すことです。
この視点を忘れなければ、SEO効果とユーザー体験の両方を満たすコンテンツが作れます。
読みやすさとモバイル対応
どれだけ良い情報を提供していても、読みにくいコンテンツではユーザーは最後まで読んでくれません。
特に近年は、スマートフォンからの閲覧が全体の60〜70%を占めているため、モバイルでの読みやすさは必須条件となっています。
読みやすいコンテンツには、いくつかの共通する特徴があります。
まず、適度な改行と段落分けがされています。
1文ごとに改行し、2〜3文で1段落とすることで、視覚的に読みやすくなります。
次に、重要なポイントは太字で強調されています。
ただし、強調しすぎると逆に読みにくくなるため、1つの見出し内で2〜3箇所程度が適切です。
| 読みやすさを高める要素 | モバイル対応のポイント |
| 適度な改行 | スマホ画面で3〜4行で段落を分ける |
| 太字の使用 | 重要ポイントを視覚的に強調 |
| 箇条書き・表 | 情報を整理して提示 |
| 画像・図解 | 文字だけでなく視覚情報も |
| フォントサイズ | 16px以上が推奨 |
箇条書きや表を効果的に使うことも重要です。
複数の項目を列挙する場合、文章で書くよりも箇条書きにした方が、情報が整理され、理解しやすくなります。
画像や図解を適度に挿入することで、文字だけのコンテンツよりも視覚的に理解しやすくなります。
特に、手順を説明する場合や、比較表を示す場合などは、画像の方が効果的です。
モバイル対応では、横幅に注意が必要です。
表や画像が横に長すぎると、スマートフォンでは横スクロールが必要になり、ユーザー体験を損ないます。
また、ページの読み込み速度も重要です。
画像サイズを最適化し、不要なスクリプトを削減することで、ページの表示速度を改善できます。
読みやすさは、コンテンツの質と同じくらい重要な要素です。
株式会社エッコでは、デザインとSEOの両面から、ユーザーにとって最適なコンテンツ制作をサポートしています。
タイトルとメタディスクリプションの文字数
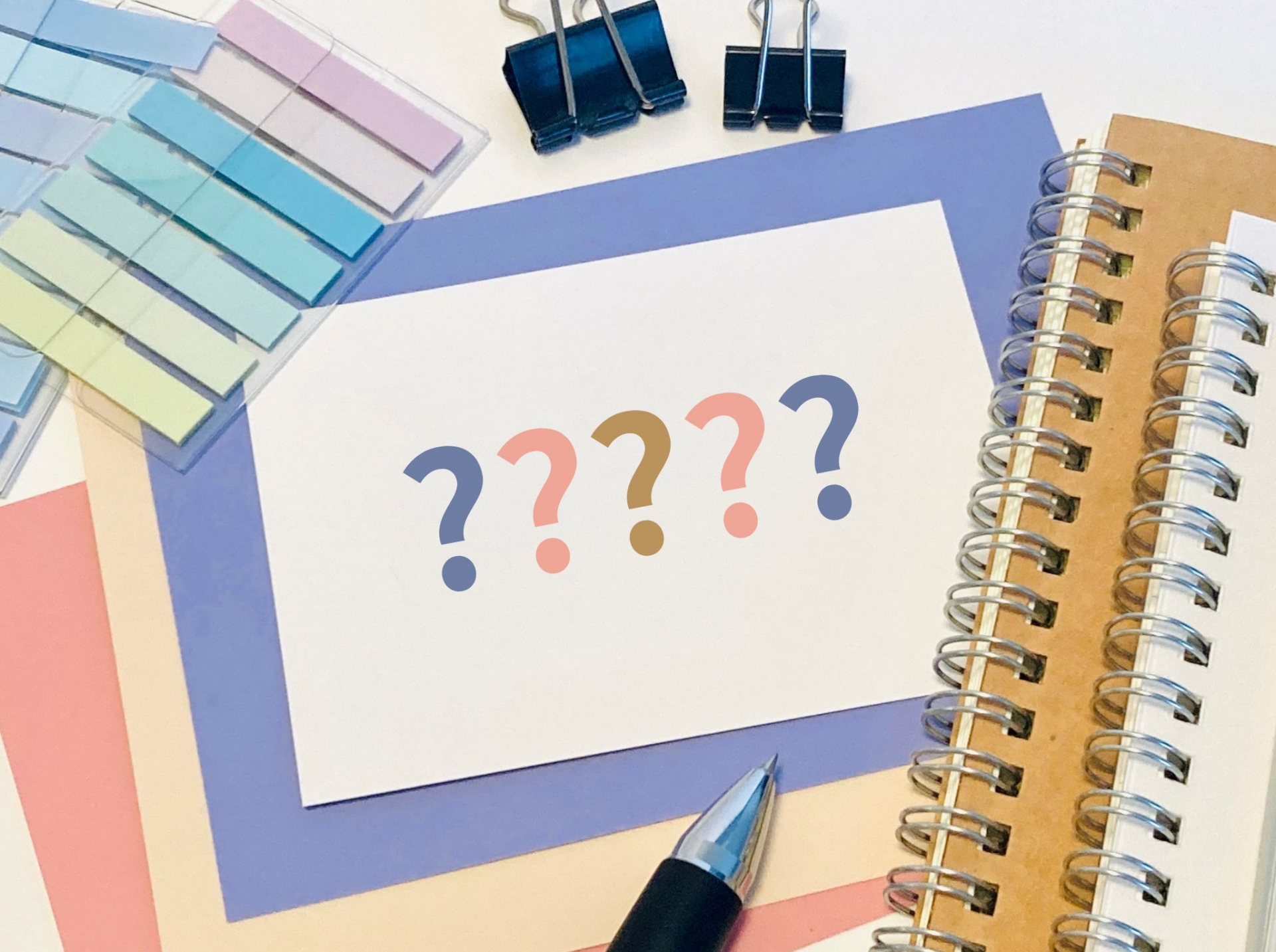
本文の文字数とは別に、タイトル(titleタグ)とメタディスクリプション(meta description)にも適切な文字数があります。
これらは検索結果に表示される重要な要素であり、クリック率に直接影響します。
タイトルの最適文字数は30文字程度
タイトルは、検索結果で最も目立つ要素であり、ユーザーがクリックするかどうかを左右する重要な要素です。
検索結果に表示されるタイトルの文字数には制限があり、それを超えると「…」と省略されてしまいます。
PCでの検索結果では約32文字まで、スマートフォンでは約40文字まで表示されます。
ただし、文字の種類(全角・半角)や記号の使用によって実際の表示文字数は変動します。
| デバイス | 表示文字数 | 推奨文字数 |
| PC | 約32文字 | 30文字前後 |
| スマートフォン | 約40文字 | 35文字前後 |
安全に全文を表示させたい場合は、30文字前後を目安にするのが賢明です。
ただし、文字数を優先するあまり、わかりにくいタイトルになってしまっては本末転倒です。
タイトルで伝えるべき内容は、以下の3つです。
まず、どのようなテーマの記事なのかが一目でわかること。
次に、読むことでどのようなメリットがあるのかが伝わること。
そして、対策キーワードが含まれていること。
たとえば、「SEO対策と文字数の関係|上位表示のための最適な文字数を徹底解説」というタイトルは33文字ですが、テーマ、メリット、キーワードがすべて含まれています。
重要なキーワードはタイトルの前半に配置することも大切です。
万が一省略されても、重要な情報は表示されるようにするためです。
また、具体的な数字を入れることで、クリック率が向上する傾向があります。
「5つのポイント」「3ステップで」「2024年最新版」といった表現は、ユーザーの興味を引きやすくなります。
株式会社エッコでは、クライアント様のサイトのタイトル最適化も支援しており、クリック率向上を通じたアクセス増加をサポートしています。
メタディスクリプションの推奨文字数
メタディスクリプションとは、検索結果のタイトルの下に表示される説明文です。
SEOの順位には直接影響しませんが、クリック率に大きく影響する重要な要素です。
メタディスクリプションの表示文字数も、デバイスによって異なります。
PCでは約120文字、スマートフォンでは約70文字までが表示されます。
近年はスマートフォンからの検索が主流になっているため、70文字以内に重要な情報を盛り込むことが推奨されます。
| デバイス | 表示文字数 | 推奨される書き方 |
| PC | 約120文字 | 詳細な説明を記載 |
| スマートフォン | 約70文字 | 最初の70文字に重要情報 |
効果的なメタディスクリプションのポイントは以下の通りです。
まず、記事の内容を簡潔に要約し、読むメリットを明確に伝えます。
「この記事では〜について解説します」といった定型文ではなく、「〜の方法がわかります」「〜の悩みを解決できます」といった、読者にとっての価値を強調します。
次に、対策キーワードを自然に含めます。
検索結果では、ユーザーが検索したキーワードがメタディスクリプション内で太字で表示されるため、関連性が視覚的に伝わります。
そして、行動を促す表現を加えます。
「詳しくはこちら」「今すぐチェック」といった表現は、クリックを促す効果があります。
ただし、メタディスクリプションを設定しなくても、Googleが自動的に本文から適切な部分を抽出して表示することもあります。
しかし、意図した内容を確実に表示させるためには、自分で設定しておくことが推奨されます。
メタディスクリプションは、検索結果という「お店の看板」のようなものです。
魅力的な看板があれば、多くの人が興味を持ってクリックしてくれます。
タイトルとメタディスクリプションの最適化は、比較的簡単に実施できる施策でありながら、効果が大きいため、優先的に取り組むべきSEO対策の一つです。
まとめ

ここまで、SEOと文字数の関係について、詳しく解説してきました。
最後に、重要なポイントをまとめておきましょう。
Googleは文字数そのものを評価基準としていません。
これは、Googleのジョン・ミューラー氏が公式に明言している事実です。
「1,000文字書けば上位表示される」「3,000文字必要」といった固定的な基準は存在しないのです。
それでも、上位表示されるサイトの多くが文字数が多い傾向にあるのは、ユーザーの検索意図を満たす網羅的な情報を提供した結果、自然と文字数が増えているからです。
つまり、文字数が多いから評価されているのではなく、質の高いコンテンツを作った結果として文字数が増えているのです。
キーワードによって最適な文字数は異なります。
情報収集型のキーワードでは4,000〜7,000文字、商品比較型では5,000〜10,000文字が必要になることもあります。
しかし、これもあくまで目安であり、重要なのはユーザーが求める情報を過不足なく提供することです。
質の高いコンテンツを作るためには、文字数ではなく以下の要素に注力しましょう。
検索意図を正確に理解し、顕在ニーズと潜在ニーズの両方に応える。
情報の網羅性を高め、ユーザーが知りたいことをすべて網羅する。
読みやすさを重視し、ユーザー体験を向上させる。
E-E-A-Tを意識し、経験、専門性、権威性、信頼性を示す。
これらを実践することで、文字数に頼らない、本質的なSEO効果の高いコンテンツを作ることができます。
タイトルは30文字程度、メタディスクリプションは70文字以内を目安にすることで、検索結果でのクリック率を高めることができます。
SEO対策は、検索エンジンのためではなく、ユーザーのために行うものです。
文字数という目に見える指標に振り回されるのではなく、「読者にとって本当に価値のある情報は何か」を常に考え続けることが、長期的なSEO成果につながります。
株式会社エッコは、名古屋を拠点にWebコンサルティングサービスを提供しています。
文字数にとらわれない本質的なSEO対策、ユーザーに価値を提供するコンテンツ制作、そして持続的な集客力を持つWebサイトの構築をサポートしています。
SEO対策でお悩みの方、コンテンツマーケティングを強化したい方は、ぜひ株式会社エッコにご相談ください。
お客様の業界特性やターゲット層を深く理解した上で、最適なWeb戦略をご提案いたします。
この記事が、あなたのSEO対策の参考になれば幸いです。
文字数という数字に惑わされず、ユーザーに寄り添ったコンテンツ制作を心がけていきましょう。



