Google検索で商品を調べたとき、価格や評価が星マークで表示されていたり、レシピを検索したときに調理時間やカロリーが一目でわかる表示を見たことはありませんか?
これらはリッチリザルトと呼ばれる検索結果の表示形式です。
通常のタイトルとURLだけの検索結果に比べて、視覚的に目立ち、多くの情報を提供できるため、ユーザーのクリック率を大幅に向上させることができます。
実際、大手食品メーカーのNestléはリッチリザルトを導入することで、クリック率を82%も向上させたという事例があります。
本記事では、リッチリザルトの基礎知識から実装方法、2023年以降の重要な変更点まで、Web担当者が知っておくべき情報を網羅的に解説します。
自社サイトへの流入を増やしたい方、SEO対策の次の一手をお探しの方は、ぜひ最後までお読みください。
Index
リッチリザルトとは

リッチリザルトについて、まずは基本的な定義や通常の検索結果との違いを理解しましょう。
ここでは、リッチリザルトが登場した背景や、名称の変遷についても詳しく解説します。
リッチリザルトの定義
リッチリザルトとは、Googleの検索結果において通常の青色リンクよりも高度な機能を持つ表示形式のことです。
Googleの公式定義では「視覚的な機能や操作機能が追加された検索結果」とされています。
具体的には、検索結果ページに表示されるタイトル、URL、説明文(スニペット)といった基本要素に加えて、画像、カルーセル、評価の星マーク、価格情報、在庫状況、イベント日時、よくある質問などの付加情報を含んだ検索結果全般を指します。
たとえば「オムライス レシピ」と検索すると、調理時間やカロリー、材料などが画像とともに表示されます。
これがリッチリザルトの代表例です。
| 基本要素 | 付加情報の例 |
| タイトル | 画像、カルーセル |
| URL | 評価(星マーク) |
| 説明文 | 価格、在庫状況 |
| – | イベント日時、FAQ |
ユーザーは検索結果画面上でより多くの情報を得られるため、クリックする前にページの内容を判断しやすくなります。
サイト運営者にとっては、競合サイトとの差別化を図り、より多くのクリックを獲得できる強力なツールとなります。
通常の検索結果との違い
通常の検索結果は、タイトル(青色のリンク)、URL(緑色の文字)、スニペット(説明文)の3要素で構成されるシンプルな表示です。
一方、リッチリザルトではこれらの基本要素に加えて、視覚的・操作的な要素が追加されます。
通常の検索結果との主な違いは以下の通りです。
まず、情報量の差が挙げられます。
通常の検索結果では限られたテキスト情報しか表示されませんが、リッチリザルトでは画像、評価、価格、日時など、ユーザーが求める具体的な情報を検索結果画面で直接確認できます。
次に、視認性の高さです。
テキストのみの検索結果が並ぶ中で、画像や星マーク、色付きの要素が含まれるリッチリザルトは、ユーザーの目に留まりやすくなります。
さらに、ユーザーの意思決定を支援する機能も重要な違いです。
リッチリザルトによって、ユーザーはクリックする前にページの内容をより正確に判断でき、自分のニーズに合ったページを選びやすくなります。
これらの違いにより、リッチリザルトを実装したページは、通常の検索結果よりも高いクリック率を実現できる傾向にあります。
リッチスニペット・リッチカードとの関係
リッチリザルトという用語が使われる以前は、「リッチスニペット」や「リッチカード」という名称が使われていました。
これらの関係性を理解することで、リッチリザルトの全体像がより明確になります。
リッチスニペットは、スニペット(説明文)部分に追加情報を表示する拡張機能として登場しました。
評価の星マークやレビュー件数、価格情報などを説明文の近くに表示するのが特徴です。
リッチカードは、特にモバイルデバイスでの表示に最適化された、カード型のビジュアル表示形式です。
レシピや映画などのコンテンツを、画像を中心とした横スクロール可能なカルーセル形式で表示します。
| 名称 | 特徴 |
| リッチスニペット | スニペット部分の拡張表示 |
| リッチカード | カード型のビジュアル表示 |
| リッチリザルト | 両者を統合した総称(2018年〜) |
2018年にGoogleは、これら複数の名称を「リッチリザルト」という統一名称に変更しました。
現在では、構造化データを用いて実現される検索結果の拡張表示全般を、リッチリザルトと呼んでいます。
過去の記事や資料では異なる名称が使われていることがありますが、現在はすべて「リッチリザルト」という用語で統一されている点を覚えておきましょう。
リッチリザルトのSEO効果

リッチリザルトを実装することで、どのようなSEO効果が期待できるのでしょうか。
ここでは、具体的なデータや事例を交えながら、リッチリザルトがもたらす4つの主要な効果について詳しく解説します。
クリック率(CTR)の向上
リッチリザルトがもたらす最も直接的かつ測定可能な効果がクリック率の向上です。
視覚的に魅力的で多くの情報を提供する検索結果は、ユーザーにとってクリックする価値が高いと判断されやすくなります。
実際の数値データを見てみましょう。
Googleが公開したケーススタディでは、大手食品メーカーのNestléがレシピのリッチリザルトを導入したことで、ページのクリック率が82%向上したと報告されています。
また、映画レビューサイトのRotten Tomatoesでは、クチコミのリッチリザルトによってクリック率が25%増加しました。
さらに別の調査によれば、リッチリザルトが表示された検索結果は、表示されなかった場合に比べて58%多くのクリックを獲得するというデータもあります。
- Nestlé:クリック率82%向上(レシピのリッチリザルト)
- Rotten Tomatoes:クリック率25%増加(クチコミのリッチリザルト)
- 一般的な傾向:リッチリザルト表示で58%多くのクリック
これらのデータが示すように、同じ検索順位であっても、リッチリザルトを表示させることで大幅なトラフィック増加が期待できます。
特にECサイトやレシピサイト、求人サイトなど、具体的な情報提供が重要な業種では、リッチリザルトの効果が顕著に表れる傾向があります。
視認性の改善効果
検索結果ページは、ユーザーの注目を獲得するための競争の場です。
リッチリザルトは、テキストのみの検索結果が並ぶ中で視覚的に際立つため、ユーザーの注意を強く引きつけます。
視認性が向上する主な要素として、まずカラフルな要素の使用が挙げられます。
評価の星マークはオレンジや黄色で表示され、画像は鮮やかな色彩を持つため、モノトーンに近い通常の検索結果の中で目立ちます。
次に、情報の密度と配置も重要です。
リッチリザルトは、限られたスペースに多くの情報を視覚的に整理して表示するため、ユーザーは一目で内容を把握できます。
さらに、画面占有率の向上も見逃せません。
画像やFAQなどを含むリッチリザルトは、通常の検索結果よりも縦方向のスペースを多く占めるため、特にモバイルデバイスではファーストビューを独占できる可能性があります。
この視認性の向上は、ブランド認知度の向上にも貢献します。
ユーザーが複数回検索を行う際、視覚的に印象に残ったサイトは記憶に残りやすく、次回以降の検索でも選ばれる確率が高まります。
ユーザー体験の向上
リッチリザルトは、単にクリック数を増やすだけでなく、トラフィックの質を高める効果も持っています。
検索結果画面で価格、在庫状況、評価などの重要な情報が事前に提示されるため、ユーザーはより多くの情報に基づいた判断を下すことができます。
これは「事前フィルタリング機能」として働きます。
たとえば、ECサイトで商品価格が予算を超えているユーザーや、レストランの評価が期待値より低いと感じたユーザーは、クリックせずに次の選択肢を探すでしょう。
結果として、サイトを訪れるのは提供する商品やサービスに対して関心が高く、購入や問い合わせに至る可能性が高いユーザー層に絞り込まれます。
| メリット | 効果 |
| 事前情報提供 | ミスマッチの減少 |
| 質の高いトラフィック | コンバージョン率の向上 |
| 直帰率の低下 | サイト滞在時間の増加 |
このような質の高いトラフィックは、サイト訪問後の直帰率を低下させ、コンバージョン率の向上に直接的に貢献します。
リッチリザルトは、量だけでなく質の面でも、サイトへの流入を最適化する強力な手段なのです。
間接的な検索順位への影響
リッチリザルトの実装自体は、Googleの検索順位を直接引き上げるランキング要因ではないとGoogleは公式に述べています。
構造化データは、あくまでページの内容を検索エンジンに理解しやすく伝えるためのシグナルです。
しかし、リッチリザルトがもたらすクリック率の向上は、間接的にSEO評価に好影響を与える可能性があります。
高いクリック率は、Googleのアルゴリズムに対して「このページはユーザーの検索意図に非常に関連性が高い」という強力なポジティブシグナルを送ります。
ユーザーから支持されているページをGoogleがより高く評価するのは自然なことです。
また、構造化データの実装により、クローラーがページ内容を正確に理解しやすくなります。
これは検索結果の正確性向上につながり、適切なキーワードでの表示機会が増える可能性があります。
- クリック率の向上 → ユーザーエンゲージメントの向上
- クローラビリティの改善 → ページ内容の正確な理解
- ユーザー満足度の向上 → 検索順位の安定・向上の可能性
実際、Googleのジョン・ミュラー氏は2018年のTwitterで、構造化データが「Googleがコンテンツを理解するのに役立ち、ランキングを向上させることができる」と述べています。
これらの良好なユーザーエンゲージメントが、長期的に見て検索順位の安定や向上に寄与する可能性があるのです。
名古屋のWebコンサルティング会社である株式会社エッコでは、リッチリザルトを含む包括的なSEO対策により、クライアント企業の検索流入を大幅に改善した実績があります。
リッチリザルトと強調スニペットの違い

リッチリザルトとよく混同されるのが「強調スニペット」です。
両者は検索結果を豊かにする点で共通していますが、その生成メカニズムやサイト運営者の関与方法が根本的に異なります。
ここでは、3つの観点から両者の違いを明確に解説します。
表示のされ方の違い
リッチリザルトは、通常の検索結果の一部として、各ページの情報を拡張表示する形式です。
タイトル、URL、説明文という基本要素に、画像や評価、価格などの付加情報が追加されます。
検索結果ページの中で、他の検索結果と同じ位置関係を保ちながら、より多くの情報を提供します。
強調スニペットは、ユーザーの質問形式の検索(たとえば「リッチリザルトとは」)に対して、最も的確な回答を提供していると判断されたページの一部を自動的に抽出し、検索結果の最上部(通称「ポジションゼロ」)に表示します。
強調スニペットの表示形式には、段落形式、リスト形式、表形式、動画形式などがあります。
| 項目 | リッチリザルト | 強調スニペット |
| 表示形式 | 拡張された検索結果 | 抜粋された回答 |
| 表示内容 | 構造化データに基づく情報 | ページ本文から抽出 |
| 視覚的特徴 | 画像、星マーク、価格など | 枠で囲まれた回答ボックス |
リッチリザルトは各ページの情報を豊かにするのに対し、強調スニペットはユーザーの質問に対する直接的な回答を提供するという違いがあります。
実装の可否
リッチリザルトと強調スニペットの最も重要な違いは、サイト運営者がコントロールできるかどうかという点です。
リッチリザルトは、サイト運営者が積極的に実装できます。
具体的には、ページ内に「構造化データ」と呼ばれる特定のコード形式でマークアップすることで、その表示を促すことができます。
JSON-LD形式やMicrodata形式で記述された構造化データを適切に実装すれば、Googleがそれを認識し、リッチリザルトとして表示する可能性が高まります。
つまり、サイト側からの能動的な働きかけが表示の前提となります。
- リッチリザルト:サイト運営者が構造化データで実装可能
- 強調スニペット:Googleのアルゴリズムが自動的に選択
一方、強調スニペットはサイト運営者が直接コントロールできません。
構造化データのマークアップは必須ではなく、Googleのアルゴリズムが「この内容がユーザーの質問に最も適切に答えている」と判断したページを自動的に選び出します。
ただし、ページ内容を質問と回答の形式で明確に記述したり、適切な見出し構造を使用したりすることで、強調スニペットに選ばれる可能性を高める工夫はできます。
また、自社のページが強調スニペットに表示されることを望まない場合は、特定のタグを使用して表示を拒否することも可能です。
表示位置の違い
表示位置の違いも、両者を区別する重要なポイントです。
リッチリザルトは、通常の検索順位に従って表示されます。
1位のページが1位の位置に、2位のページが2位の位置に表示され、その際に情報が拡張されているだけです。
つまり、リッチリザルトを実装したからといって、検索順位そのものが変わるわけではありません。
10位のページにリッチリザルトを実装しても、それだけで上位表示されることはなく、あくまで10位の位置でより目立つ表示になります。
| 表示位置 | 特徴 |
| リッチリザルト | 元の検索順位のまま情報拡張 |
| 強調スニペット | 検索結果の最上部(ポジションゼロ) |
強調スニペットは、通常の検索結果よりも上、検索結果の最上部に表示されます。
これは「ポジションゼロ」とも呼ばれ、広告枠の下、オーガニック検索結果の1位よりも上に位置します。
たとえ元のページの検索順位が5位や10位であっても、強調スニペットに選ばれれば最上部に表示されるため、非常に高い視認性とクリック率を獲得できます。
ただし、強調スニペットは質問形式の検索でのみ表示される傾向があり、すべての検索クエリで表示されるわけではありません。
この表示位置の違いを理解することで、リッチリザルトは検索順位を補完し、強調スニペットは検索順位を超越するという特性が明確になります。
主要なリッチリザルトの種類

Googleは2025年時点で30種類以上のリッチリザルトをサポートしています。
ここでは、特に多くのWebサイトで活用されている主要なリッチリザルトについて、具体的な表示例と活用方法を詳しく解説します。
FAQ(よくある質問)
FAQのリッチリザルトは、ユーザーからよく寄せられる質問とその回答を、検索結果に直接表示する形式です。
表示例と特徴
FAQのリッチリザルトは、アコーディオン形式で質問と回答を表示します。
検索結果には質問文が展開された状態で表示され、ユーザーがクリックすると回答部分が開閉します。
通常、上位3件の質問と回答が表示され、「すべて表示」ボタンをクリックすることで、ページ内のすべてのFAQを確認できます。
この形式の大きな特徴は、検索結果画面の占有面積が大きくなる点です。
複数の質問と回答が表示されるため、他の検索結果よりも目立ち、ユーザーの注意を引きやすくなります。
| 表示内容 | 詳細 |
| 質問文 | 明確で簡潔な質問形式 |
| 回答文 | 質問に対する直接的な回答 |
| 表示件数 | 上位3件が初期表示 |
| 操作性 | アコーディオン形式で開閉可能 |
ただし、2023年8月以降、FAQのリッチリザルトは表示条件が大きく変更されました。
現在では「よく知られた、権威ある政府機関および医療関連のウェブサイト」に限定して表示されるようになり、一般的な企業サイトやブログでは表示されなくなっています。
適用場面
FAQのリッチリザルトは、ユーザーが商品やサービスについて持つ疑問を事前に解消するのに効果的でした。
2023年8月以前は、多くのサイトで活用されていました。
たとえば、ECサイトでは「返品は可能ですか?」「送料はいくらですか?」といった購入前の不安を解消する情報を提供できました。
BtoBサービスのサイトでは「導入までの期間は?」「サポート体制は?」といったビジネス上の懸念に答えることができました。
- ECサイト:返品・送料・配送期間などの質問
- サービスサイト:料金・契約期間・サポート内容などの質問
- 観光・施設サイト:営業時間・アクセス・予約方法などの質問
現在では政府機関や医療機関以外のサイトでは表示されないため、一般企業がリソースを投入する優先度は低くなっています。
ただし、構造化データとしてマークアップすることで、将来的な仕様変更に備えたり、音声検索などで活用される可能性はあります。
株式会社エッコでは、最新のGoogle仕様に基づき、現在効果的なリッチリザルトの選定と実装支援を行っています。
パンくずリスト
パンくずリストは、最も基本的で、ほぼすべてのWebサイトで実装が推奨されるリッチリザルトです。
サイトの階層構造を明示し、ユーザビリティとSEOの両面でメリットをもたらします。
URL欄での表示
パンくずリストのリッチリザルトを実装すると、検索結果のURL欄が階層構造を示す表示に変わります。
通常、URLは「https://example.com/category/subcategory/page.html」のように表示されますが、パンくずリストを実装すると「ホーム > カテゴリ > サブカテゴリ > ページ名」のように、日本語で階層構造が表示されます。
この表示により、ユーザーは一目でそのページがサイト内のどの位置にあるのかを把握できます。
たとえば、ECサイトで商品ページを検索した際、「ホーム > 家電 > カメラ > デジタル一眼レフ」のように表示されれば、商品のカテゴリが明確にわかります。
| 通常のURL表示 | パンくずリスト表示 |
| example.com/cat/sub/page | ホーム > カテゴリ > サブカテゴリ > ページ名 |
| URLの文字列 | 日本語の階層構造 |
| 技術的な情報 | ユーザーフレンドリーな情報 |
また、パンくずリストの各階層はクリック可能なリンクとして機能するため、ユーザーは検索結果から上位階層のページに直接アクセスすることもできます。
階層構造の明示
パンくずリストのリッチリザルトは、サイトの構造を検索エンジンに正確に伝える役割も果たします。
構造化データを使ってパンくずリストをマークアップすることで、Googleはページ間の関係性や階層構造を明確に理解できます。
これはクローラビリティの向上につながります。
検索エンジンがサイトの構造を正確に把握することで、より効率的なクロールが可能になり、重要なページが適切にインデックスされやすくなります。
- サイト構造の可視化
- クローラビリティの向上
- 関連ページの発見性向上
また、ユーザーにとっても、ページの位置づけが明確になることで、サイト内の他のページへの移動がスムーズになります。
特に大規模なECサイトや情報サイトでは、パンくずリストによる階層構造の明示が、ユーザーの回遊性向上に大きく貢献します。
パンくずリストの実装は比較的簡単で、WordPress などの主要なCMSでは標準機能やプラグインでサポートされています。
商品(Product)
商品のリッチリザルトは、ECサイトにとって最も重要なリッチリザルトの一つです。
商品の詳細情報を検索結果に直接表示することで、購入意欲の高いユーザーにアプローチできます。
価格・在庫・レビュー表示
商品のリッチリザルトでは、以下のような情報を検索結果に表示できます。
まず、価格情報が最も重要です。
商品の現在価格や、セール価格、通常価格からの割引率などを表示できます。
価格が明示されることで、ユーザーは予算に合うかどうかを事前に判断できます。
次に、在庫状況も表示可能です。
「在庫あり」「在庫わずか」「取り寄せ」などのステータスを表示することで、すぐに購入できるかどうかをユーザーに伝えられます。
| 表示情報 | 効果 |
| 価格 | 予算判断の支援 |
| 在庫状況 | 購入可能性の明示 |
| レビュー評価 | 信頼性の向上 |
| 配送情報 | 購入判断の材料 |
さらに、レビュー評価も重要な要素です。
星マーク(通常は5つ星)での評価と、レビュー件数を表示できます。
これは社会的証明として機能し、商品の信頼性を大きく高めます。
実際の調査では、レビュー評価が表示された商品ページのクリック率は、表示されないページに比べて大幅に向上することが確認されています。
加えて、商品画像、ブランド名、商品説明なども表示可能で、検索結果画面を小さなショーケースのように活用できます。
ECサイトでの活用
ECサイトにとって、商品のリッチリザルトはコンバージョン率向上の強力な武器となります。
まず、顕在層へのアプローチが可能です。
具体的な商品名で検索するユーザーは、すでに購入意欲が高い顕在層である可能性が高く、詳細な商品情報を提供することで、そのまま購入につなげやすくなります。
同時に、潜在層への訴求も可能です。
まだ特定の商品を決めていないユーザーが、カテゴリやキーワードで検索した際、魅力的な商品画像と高評価が表示されれば、興味を引いて新たな購入機会を創出できます。
- 顕在層:詳細情報提供で購入を後押し
- 潜在層:魅力的な情報で興味を喚起
- 比較検討:他社商品との差別化
また、競合との差別化にも有効です。
同じ商品カテゴリで競合他社と並んで表示される際、リッチリザルトがあるサイトとないサイトでは、クリック率に大きな差が生まれます。
特に、自社商品のレビュー評価が高い場合、それを積極的に表示することで競合優位性を明確に示せます。
商品情報は常に最新の状態に保つことが重要です。
価格変更や在庫状況の更新を怠ると、ユーザーに誤った情報を提供することになり、信頼を損なう可能性があります。
レシピ
レシピのリッチリザルトは、料理ブログや食品メーカーのサイトで非常に効果的です。
調理時間、カロリー、材料、手順などの情報を視覚的に表示できます。
レシピを検索するユーザーは、「簡単に作れるか」「時間はどれくらいかかるか」「カロリーは高すぎないか」といった具体的な判断基準を持っています。
リッチリザルトでこれらの情報を事前に提供することで、ユーザーのニーズに合致したレシピページへの誘導が可能になります。
表示できる主な情報は以下の通りです。
| 表示項目 | 例 |
| 調理時間 | 準備15分、調理30分 |
| カロリー | 1人分350kcal |
| レビュー評価 | 星4.5、レビュー127件 |
| 画像 | 完成写真のサムネイル |
特に効果的なのが、カルーセル形式での表示です。
「パスタ レシピ」のような広いキーワードで検索すると、複数のレシピが横並びのカード形式で表示され、ユーザーは画像を見ながら好みのレシピを選べます。
これは検索結果ページの最上部や目立つ位置に表示されるため、非常に高い視認性を誇ります。
レシピのリッチリザルトを実装するには、調理手順を適切な構造で記述し、必要な情報(材料、分量、調理時間など)を漏れなくマークアップする必要があります。
求人情報
求人情報のリッチリザルトは、採用活動を行う企業にとって必須の機能です。
Googleしごと検索(Google for Jobs)に自社の求人情報を表示できます。
Googleしごと検索は、ユーザーが職種や勤務地で検索した際に、Google検索結果の上部に専用の求人情報ボックスを表示する機能です。
求人情報のリッチリザルトを実装することで、この枠内に自社の求人が掲載される可能性が高まります。
- 職種名・役職
- 勤務地(複数拠点可)
- 給与情報(月給、年収など)
- 雇用形態(正社員、契約社員など)
- 企業ロゴ
表示される情報には、職種名、勤務地、給与範囲、雇用形態、企業ロゴなどが含まれます。
ユーザーは検索結果画面で複数の求人を比較検討でき、自分に合った条件の求人を効率的に探せます。
求人情報のリッチリザルトで特に重要なのが、情報の鮮度管理です。
募集が終了した求人情報をページ上に残したまま、あるいは構造化データ内に含めたままにしておくと、Googleのガイドライン違反と見なされ、手動による対策(ペナルティ)の対象となる可能性があります。
これは検索順位の大幅な低下や、最悪の場合は検索結果からの除外につながるため、求人情報は常に最新の状態に保つ必要があります。
採用サイトを運営する企業は、求人情報のリッチリザルトを必ず実装することをお勧めします。
イベント
イベントのリッチリザルトは、セミナー、コンサート、展示会、ウェビナーなどの開催情報を検索結果に表示します。
表示される情報には、イベント名、開催日時、場所(またはオンライン開催の表示)、イベント詳細ページへのリンクなどが含まれます。
特に便利なのが、複数日程のイベントを一覧表示できる点です。
同じイベントが複数の日程で開催される場合、最大3件までの日程が検索結果に表示されます。
| イベント情報の表示内容 |
| イベント名 |
| 開催日時(最大3件まで) |
| 開催場所またはオンライン開催 |
| イベントの説明文 |
| 申込ページへのリンク |
イベントのリッチリザルトは、空席状況や申込状況も表示可能です。
「空席あり」「残席わずか」「満席」などのステータスを示すことで、参加を検討しているユーザーに緊急性を伝えられます。
また、完売したイベントは自動的に表示されなくなるため、無駄なクリックを防げます。
オンラインイベントの場合は、「オンラインイベント」という表示が追加され、物理的な場所の制約がないことが明示されます。
これは特に、遠方のユーザーにもアプローチできる大きなメリットです。
イベントの構造化データを実装する際は、各日程ごとに個別のイベントとしてマークアップすることがポイントです。
ハウツー(HowTo)
ハウツーのリッチリザルトは、「〇〇する方法」といった手順を説明するコンテンツに使用される形式でした。
何かを実現するための一連の手順を、画像、動画、テキストを使って段階的に説明できました。
しかし、2023年9月以降、ハウツーのリッチリザルトは表示されなくなりました。
Googleは検索結果のシンプル化を目的として、まずモバイルでの表示を停止し、その後デスクトップでも表示を廃止しました。
| 時期 | 変更内容 |
| 2023年8月 | モバイルでの表示停止 |
| 2023年9月 | デスクトップでの表示停止 |
| 現在 | リッチリザルトとしてのサポート終了 |
現在、ハウツーのリッチリザルトは完全に非推奨となっており、新規に実装しても検索結果には表示されません。
過去に実装済みの構造化データも、リッチリザルトとして機能しなくなっています。
ただし、ハウツー形式の構造化データ自体が無駄というわけではありません。
音声検索やスマートスピーカーでの情報提供に活用される可能性や、将来的な仕様変更で再び利用される可能性はゼロではありません。
しかし、現時点でリソースを投入する優先度は非常に低いと言えます。
ハウツーコンテンツを持つサイトは、リッチリザルトよりも、コンテンツ自体の質を高めることに注力すべきです。
レビュー・評価
レビュー・評価のリッチリザルトは、商品やサービス、店舗などに対する評価を星マークで表示します。
オレンジ色の星マークは検索結果の中で非常に目立ち、高い視認性を誇ります。
レビューのリッチリザルトには、主に2つのタイプがあります。
個別レビューは、特定のレビュー記事や評価記事に対するもので、記事執筆者の評価を表示します。
たとえば、「○○スマートフォンをレビュー!」という記事で、筆者が星4つの評価をつけた場合、その評価が検索結果に表示されます。
**総合評価(Aggregate Rating)**は、複数のユーザーレビューを集計した平均評価です。
「星4.2、レビュー357件」のように、平均評価とレビュー総数が表示されます。
- 個別レビュー:記事執筆者の評価
- 総合評価:ユーザーレビューの平均
- 表示形式:星マーク(5段階評価)
レビュー・評価のリッチリザルトは、商品ページだけでなく、比較記事やレビューサイトでも活用できます。
「ベスト5選」のような比較記事でも、各商品の評価を表示することで、ユーザーに有益な情報を提供できます。
ただし、自作自演のレビューや虚偽の評価をマークアップすることは厳禁です。
Googleのガイドライン違反となり、ペナルティの対象となります。
実際のユーザーレビューが存在し、それを正確に反映したマークアップのみが許可されます。
動画
動画のリッチリザルトは、動画コンテンツの情報を検索結果に表示し、ユーザーの興味を引きます。
YouTube、Vimeo、自社サイトに埋め込んだ動画など、さまざまな動画コンテンツに対応します。
表示される情報には、動画のサムネイル画像、タイトル、説明文、公開日、動画の長さなどが含まれます。
サムネイル画像は静止画よりも目を引くため、検索結果での視認性が大幅に向上します。
| 動画リッチリザルトの表示要素 |
| サムネイル画像 |
| 動画タイトル |
| 動画の長さ |
| 公開日 |
| 視聴回数(プラットフォームによる) |
動画のリッチリザルトで特に効果的なのが、ライブ配信やプレミア公開の表示です。
「ライブ配信中」や「○月○日公開予定」といったバッジが表示され、リアルタイム性や限定性を訴求できます。
また、**動画内の重要なシーンを示すキーモーメント(Key Moments)**も表示可能です。
長時間の動画で、特定の章やセクションにジャンプできる目次のような機能を提供できます。
これはユーザーが求める情報に素早くアクセスできるため、ユーザー体験の向上につながります。
動画コンテンツを持つサイトは、VideoObject スキーマを使って構造化データをマークアップすることで、動画のリッチリザルトを実装できます。
リッチリザルトを表示させる方法

リッチリザルトを実装するには、「構造化データ」をWebページに追加する必要があります。
ここでは、構造化データの基礎知識から具体的な実装方法まで、ステップバイステップで解説します。
構造化データとは
構造化データは、リッチリザルトを実現するための技術的基盤です。
その役割と機能を正しく理解することで、効果的な実装が可能になります。
構造化データの役割
構造化データとは、Webページの内容を検索エンジンが理解しやすい形式で記述したデータのことです。
HTMLで書かれたページは人間には読みやすいですが、コンピュータ(検索エンジンのクローラー)にとっては、どの情報が「価格」で、どの情報が「著者名」なのかを正確に判断するのが困難です。
構造化データは、この情報に明確なラベルを付ける役割を果たします。
たとえば、ページ内に「3,980円」という数字があったとき、それが商品価格なのか、配送料なのか、サイズの数値なのかは、テキストだけでは判断できません。
| 通常のHTML | 構造化データ付きHTML |
| 3,980円(意味不明) | price: 3,980円(価格として明示) |
| 田中太郎(ただの文字列) | author: 田中太郎(著者名として明示) |
構造化データを使うと「これは商品価格であり、値は3,980円です」と明確に伝えられます。
これにより、検索エンジンはページの内容を正確に理解し、適切な検索クエリで表示したり、リッチリザルトとして情報を抽出したりできるようになります。
また、構造化データはセマンティックWeb(意味のあるWeb)を実現する技術の一つです。
Web上の情報に意味を持たせることで、コンピュータが人間と同じようにコンテンツを理解し、より高度な情報処理が可能になります。
メタデータとしての機能
構造化データは、「データのデータ」すなわちメタデータとして機能します。
メタデータとは、データそのものではなく、データを説明する情報のことです。
たとえば、写真ファイルには、画像データ本体とは別に、撮影日時、カメラの機種、撮影場所などの情報(メタデータ)が付随しています。
同様に、Webページにも、ページ本体の内容とは別に、その内容を説明する構造化データを付加できます。
- ページ本体:ユーザーが見るコンテンツ
- 構造化データ:検索エンジンが理解するためのメタデータ
構造化データはユーザーには直接表示されませんが、検索エンジンのクローラーが読み取り、リッチリザルトの表示や検索結果の改善に活用します。
これは、書籍に例えると、本文が「ページ本体」で、裏表紙に書かれた著者名、出版日、ISBN番号などが「構造化データ」に相当します。
読者は本文を読みますが、図書館の司書や検索システムは、これらのメタデータを使って本を分類し、適切に検索できるようにします。
構造化データも同じように、検索エンジンがWebページを適切に分類・理解・表示するための補助情報として機能します。
名古屋を拠点とする株式会社エッコでは、構造化データの適切な実装により、クライアント企業のWebサイトの検索流入を改善するサポートを行っています。
構造化データのマークアップ方法
構造化データを記述するには、いくつかの形式(シンタックス)があります。
ここでは、主要な3つの形式について、それぞれの特徴と使い分けを解説します。
JSON-LD形式
JSON-LD(JavaScript Object Notation for Linked Data)は、Googleが最も推奨する構造化データの記述形式です。
JSON-LD形式の最大の特徴は、HTMLの本文とは独立して、scriptタグ内にまとめて記述できる点です。
通常のHTMLコードを一切変更せずに、構造化データを後から追加できるため、既存サイトへの実装が非常に容易です。
記述形式はJavaScript Object Notation(JSON)と呼ばれるデータ形式を使用し、キーと値のペアで情報を定義します。
| JSON-LD形式の特徴 |
| scriptタグ内に記述 |
| HTMLから独立 |
| 後付け・削除が容易 |
| メンテナンス性が高い |
| Google推奨 |
JSON-LD形式の記述例を見てみましょう。
商品情報を記述する場合、以下のようなコードをページのheadセクションまたはbodyセクション内に追加します。
ここでは実際のコード例は割愛しますが、@contextでschema.orgを指定し、@typeで種類(Productなど)を指定し、必要なプロパティ(name、price、descriptionなど)を記述していきます。
JSON-LD形式は、プログラマーでなくても理解しやすい構造を持っています。
階層構造が明確で、どの情報がどの項目に対応するかが一目でわかります。
また、バリデーション(検証)が容易で、構文エラーも発見しやすいというメリットがあります。
これらの理由から、新規に構造化データを実装する場合は、JSON-LD形式を選択することを強く推奨します。
Microdata形式
Microdata形式は、HTML要素に直接属性を追加して構造化データを記述する方式です。
HTMLタグの中に「itemscope」「itemtype」「itemprop」といった属性を追加することで、既存のHTML要素に意味を持たせます。
たとえば、商品名を表示する部分のHTMLが「商品名」だったとき、Microdata形式では「商品名」のように記述します。
これにより、「この部分は商品名である」という情報を検索エンジンに伝えられます。
- itemscope:構造化データの範囲を定義
- itemtype:データの種類を指定(Product、Recipeなど)
- itemprop:具体的なプロパティ名を指定(name、priceなど)
Microdata形式の利点は、構造化データの項目がページ内の実際のコンテンツと完全に一致していることが保証される点です。
ユーザーに表示されている情報をそのまま構造化データとしてマークアップするため、「ユーザーには見えない情報をマークアップする」というガイドライン違反のリスクが低くなります。
ただし、デメリットもあります。
HTMLの構造変更時に、Microdataの属性が失われるリスクがあります。
デザインの変更やCMSのアップデートなどでHTMLが書き換わると、せっかく追加した属性が消えてしまう可能性があります。
また、コードの可読性が低下するという問題もあります。
HTML本文に多くの属性が追加されるため、コードが複雑になり、メンテナンスが難しくなります。
これらの理由から、現在ではJSON-LD形式が主流となっており、Microdata形式は徐々に使用が減っています。
RDFa形式
RDFa(Resource Description Framework in Attributes)形式も、HTMLタグに属性を追加して構造化データを記述する方式です。
Microdata形式と似ていますが、より柔軟で表現力の高い記述が可能です。
RDFa形式では、「vocab」「typeof」「property」といった属性を使用します。
この形式はセマンティックWebの標準技術として開発され、より複雑なデータ構造や関係性を表現できるという特徴があります。
| RDFa形式の特徴 |
| HTML属性として記述 |
| 複雑なデータ構造に対応 |
| 学習コストが高い |
| 使用頻度は低い |
ただし、RDFa形式は記述が複雑で、学習コストが高いというデメリットがあります。
Microdata形式よりもさらに多くの属性や概念を理解する必要があり、初心者には扱いにくい形式です。
また、Googleが特に推奨しているわけでもないため、多くのWebサイトではJSON-LD形式またはMicrodata形式を選択しています。
RDFa形式は、学術機関や研究データベースなど、非常に複雑なデータ構造を扱う必要がある特殊なケースで選択されることがありますが、一般的なWebサイトで使用する必要性は低いでしょう。
結論として、これから構造化データを実装する場合は、JSON-LD形式を選択することを強く推奨します。
構造化データマークアップ支援ツールの活用
構造化データを手動でコーディングするのが難しい場合、Googleが提供する無料ツールを活用することで、効率的に実装できます。
Googleの「構造化データ マークアップ支援ツール」は、ページを読み込んで、マウス操作だけで構造化データを生成できる便利なツールです。
使い方は非常にシンプルです。
まず、ツールのページでマークアップしたいページのURLを入力するか、HTML コードを直接貼り付けます。
次に、表示されたページ上で、構造化データとしてマークアップしたい部分をマウスで選択します。
たとえば、記事のタイトル部分を選択して「名前」プロパティを割り当て、著者名部分を選択して「著者」プロパティを割り当てる、といった操作を行います。
| 支援ツールの手順 |
| 1. URLまたはHTMLを入力 |
| 2. マークアップしたい箇所を選択 |
| 3. プロパティを割り当て |
| 4. 生成されたコードをコピー |
| 5. サイトに実装 |
必要な項目をすべて選択し終えたら、ツールがJSON-LD形式の構造化データコードを自動生成してくれます。
生成されたコードをコピーして、自サイトのHTML に貼り付けるだけで実装完了です。
このツールの大きなメリットは、コーディングの知識がなくても構造化データを作成できる点です。
JSON-LDの文法や、schema.orgの仕様を細かく理解していなくても、視覚的な操作だけで正しい構造化データが生成されます。
ただし、注意点もあります。
構造化データ マークアップ支援ツールは、すべての種類のリッチリザルトに対応しているわけではありません。
対応している種類は限定されているため、実装したいリッチリザルトが対応しているか、事前に確認する必要があります。
また、生成されたコードは基本的な項目のみを含むことが多く、より詳細な情報を追加したい場合は手動での編集が必要になります。
それでも、構造化データ実装の第一歩として、非常に有用なツールです。
実装の具体的手順
構造化データを実際にWebサイトに実装する具体的な手順を、ステップごとに解説します。
ステップ1:実装するリッチリザルトの種類を決定する
まず、自社のWebサイトやページの内容に最も適したリッチリザルトの種類を選択します。
ECサイトなら商品、ブログ記事なら記事(Article)、イベントサイトならイベント、といった具合です。
Googleの公式ドキュメント「検索ギャラリー」には、サポートされているリッチリザルトの種類が一覧で掲載されているため、ここから選択します。
ステップ2:必須プロパティと推奨プロパティを確認する
選んだリッチリザルトの種類ごとに、Googleが定義する「必須プロパティ」と「推奨プロパティ」を確認します。
必須プロパティは、一つでも欠けていると構造化データが無効になる重要な項目です。
推奨プロパティは、記述することでより豊富なリッチリザルトが表示される可能性が高まる項目です。
| プロパティの種類 | 重要度 | 影響 |
| 必須プロパティ | 必ず記述 | 欠けると無効 |
| 推奨プロパティ | できる限り記述 | リッチリザルトが充実 |
ステップ3:JSON-LDコードを作成する
必要なプロパティが明確になったら、JSON-LD形式のコードを作成します。
Googleの公式ドキュメントには各リッチリザルトのコード例が掲載されているため、それをベースに自社の情報に書き換えます。
あるいは、前述の構造化データ マークアップ支援ツールを使用して、自動生成することもできます。
ステップ4:コードをHTMLに埋め込む
作成したJSON-LDコードを、対象ページのHTMLソース内に埋め込みます。
埋め込む場所は、headセクション内が一般的ですが、bodyセクション内でも問題なく動作します。
scriptタグで囲むことを忘れないようにしましょう。
ステップ5:リッチリザルトテストで検証する
コードを埋め込んだら、公開する前に必ずGoogleの「リッチリザルト テスト」ツールで検証します。
URLを入力するか、コードを直接貼り付けて、エラーがないかを確認します。
「有効」と判断されれば、実装は成功です。
- エラーがある場合:表示される指摘内容に従って修正
- 警告がある場合:推奨プロパティの追加を検討
- 有効と判断:公開して問題なし
ステップ6:ページを公開し、インデックスを待つ
検証をクリアしたら、ページを公開します。
Googleにクロールされ、インデックスされるまで、通常は数日から数週間かかります。
Google Search Consoleの「URL検査」ツールを使って、インデックス登録をリクエストすることで、処理を早められる場合があります。
以上の手順を踏むことで、構造化データを確実に実装し、リッチリザルトの表示を実現できます。
リッチリザルトの確認とテスト方法

構造化データを実装した後は、正しく動作しているか、エラーがないかを確認する必要があります。
ここでは、Googleが提供する公式ツールを使った確認方法を詳しく解説します。
リッチリザルトテストツールの使い方
リッチリザルトテストツール**は、構造化データが正しく実装されているかを確認するための、Googleが提供する無料の公式ツールです。
このツールを使用することで、リッチリザルトが表示される可能性があるか、エラーや警告がないかを事前にチェックできます。
リッチリザルトテストツールには、URLを使った検証とコードを使った検証の2つの方法があります。
それぞれの使い方と、どのような場面で活用すべきかを見ていきましょう。
URLでのテスト
URLでのテストは、すでに公開されているWebページの構造化データを検証する方法です。
既存のページにリッチリザルトが正しく実装されているかを確認したい場合に使用します。
使い方は非常にシンプルです。
リッチリザルトテストツールのページを開き、「テストするURLを入力」の欄に、確認したいページの完全なURLを入力します。
そして「URLをテスト」ボタンをクリックするだけです。
| URLテストの手順 |
| 1. テストツールページを開く |
| 2. 対象ページのURLを入力 |
| 3. 「URLをテスト」をクリック |
| 4. 結果を確認 |
テストが実行されると、Googleのクローラーが実際にそのページにアクセスし、HTML全体を解析して構造化データを検出します。
この際、Googlebotが実際にページをどのように認識しているかを確認できるため、JavaScriptで動的に生成される構造化データも正しく検証できます。
検証結果は、「有効なアイテムが検出されました」「エラーがあります」「警告があります」といった形で表示されます。
有効なアイテムが検出された場合は、どのリッチリザルトが認識されたかが具体的に示されます。
また、「結果をプレビュー」ボタンをクリックすると、実際の検索結果でどのように表示されるかをシミュレーション画像で確認できます。
ただし、プレビュー表示と実際の検索結果が完全に一致するとは限らない点に注意が必要です。
URLテストの制約として、対象ページがクロール可能である必要があります。
robots.txtでクロールをブロックしていたり、noindexタグが設定されていたりすると、テストが失敗します。
また、認証が必要なページ(ログイン後のページなど)も、Googleのクローラーがアクセスできないため、URLテストは使用できません。
コードでのテスト
コードでのテストは、まだ公開していないページや、開発中のHTMLコードを検証する方法です。
公開前に構造化データの動作を確認したい場合や、修正を繰り返しながらテストしたい場合に非常に便利です。
使い方は、リッチリザルトテストツールのページで「コード」タブに切り替え、「テストするコードを貼り付け」の欄に、HTMLコード全体または構造化データ部分のコードを貼り付けます。
そして「コードをテスト」ボタンをクリックします。
- HTML全体を貼り付け:ページ全体の構造を含めて検証
- 構造化データのみ貼り付け:JSON-LD部分だけを検証
コードテストの大きな利点は、その場で修正してすぐに再テストできる点です。
エラーが表示された場合、コード欄で直接修正し、再度テストボタンをクリックすれば、即座に結果が確認できます。
これにより、試行錯誤しながら正しい構造化データを作り上げることができます。
また、コードテストでは、公開前のページや、ローカル環境で開発中のページも検証できるため、実装の初期段階から品質を確保できます。
さらに、ユーザーエージェント(デバイス種別)を選択できる機能もあります。
スマートフォン用とPC用のどちらでテストするかを切り替えられるため、レスポンシブデザインのサイトで両方のデバイスでの動作を確認できます。
コードテストで「有効」と判断されたコードを、そのままサイトに実装すれば、高い確率でリッチリザルトが表示されます。
テスト結果は90日間保存され、URLをブックマークすることで、後から結果を確認することも可能です。
Googleサーチコンソールでの確認
リッチリザルトテストツールが個別ページの検証に適しているのに対し、Googleサーチコンソールはサイト全体の構造化データを一覧で管理できます。
実装後の継続的な監視や、エラーの早期発見に非常に有効です。
拡張レポートの見方
Googleサーチコンソールにサイトを登録すると、構造化データを実装したページがクロールされた後、左側のナビゲーションメニューの「拡張」セクションに、リッチリザルトの種類が自動的に表示されます。
たとえば、パンくずリストを実装していれば「パンくずリスト」、商品の構造化データを実装していれば「商品」という項目が表示されます。
各項目をクリックすると、有効なページ数、エラーのあるページ数、警告のあるページ数がグラフで確認できます。
グラフは時系列で表示されるため、いつエラーが発生したか、改善されたかを視覚的に把握できます。
| 拡張レポートで確認できる情報 |
| 有効なアイテム数 |
| エラーのあるアイテム数 |
| 警告のあるアイテム数 |
| 時系列での推移 |
| 具体的なエラー内容 |
レポートをさらに詳しく見ると、「アイテムが無効な理由」という項目に、具体的なエラーの種類とその影響を受けているページのURLが一覧表示されます。
エラーの種類をクリックすると、該当するページのリストが表示され、個別に確認できます。
拡張レポートの大きなメリットは、サイト全体の構造化データの健全性を一目で把握できる点です。
数百、数千ページあるサイトでも、どこにエラーがあるかを効率的に特定できます。
また、構造化データの実装後、Googleがいつクロールし、いつインデックスに反映されたかも時系列で確認できるため、リッチリザルトが表示されるまでの経過を追跡できます。
エラーの対処方法
拡張レポートでエラーが表示された場合の対処手順を見ていきましょう。
まず、エラーの種類と内容を正確に理解することが重要です。
サーチコンソールは、「必須プロパティが不足しています」「値の型が正しくありません」「解析エラー」など、具体的なエラーメッセージを表示します。
エラーの種類によって対処方法が異なるため、まずメッセージの意味を理解しましょう。
- 必須プロパティが不足:必要な項目を追加
- 値の型が正しくない:データ型を修正
- 解析エラー:JSON-LDの構文を修正
次に、エラーの影響を受けているページを特定します。
エラーの種類をクリックすると、該当するページのURLが一覧表示されるため、それらのページを確認します。
そして、該当ページの構造化データを修正します。
エラーメッセージに従って、不足しているプロパティを追加したり、誤った値を修正したりします。
修正の際は、リッチリザルトテストツールを併用すると効率的です。
修正したコードをリッチリザルトテストツールで検証し、エラーが解消されたことを確認してから、サイトに反映させます。
修正が完了したら、サーチコンソールの該当エラーページで**「修正を検証」ボタンをクリック**します。
これにより、Googleに対して「このエラーを修正したので、再度クロールして確認してください」というリクエストが送信されます。
検証には数日から数週間かかる場合があり、その間、サーチコンソールに検証の進捗状況が表示されます。
すべてのエラーが解消され、「合格」となれば、対処完了です。
エラーが再発しないよう、定期的に拡張レポートを確認する習慣をつけることをお勧めします。
株式会社エッコでは、サーチコンソールを活用したサイト全体の健全性チェックとエラー対応のサポートも提供しています。
スキーママークアップ検証ツールとの違い
構造化データの検証ツールとして、リッチリザルトテストツールの他に**「スキーママークアップ検証ツール」**も存在します。
両者は名前が似ていますが、目的と機能が異なるため、使い分けが重要です。
リッチリザルトテストツールは、Googleのリッチリザルトとして表示されるかどうかを検証するツールです。
つまり、「この構造化データは、Googleの検索結果でリッチリザルトとして機能するか」を確認します。
Googleがサポートしているリッチリザルトの種類のみを対象とし、それ以外の構造化データは検証対象外となります。
一方、**スキーママークアップ検証ツール(Schema Markup Validator)**は、schema.org規格への準拠を確認するツールです。
こちらは「構造化データの文法や構文が正しいか」「schema.orgの仕様に従っているか」を検証しますが、Googleのリッチリザルトとして表示されるかは判定しません。
| 項目 | リッチリザルトテスト | スキーママークアップ検証 |
| 検証内容 | Googleのリッチリザルト対象か | schema.org規格への準拠 |
| 対象範囲 | Googleサポートの種類のみ | すべての構造化データ |
| プレビュー | 表示イメージあり | 表示イメージなし |
たとえば、WebSiteスキーマやOrganizationスキーマなど、リッチリザルトとして検索結果に直接表示されないが、Googleがサイトを理解するために有用な構造化データがあります。
これらはリッチリザルトテストツールでは「対象外」と判定されますが、スキーママークアップ検証ツールでは有効と判定されます。
したがって、使い分けとしては、次のようになります。
リッチリザルトとして検索結果に表示させたい構造化データ(商品、レシピ、FAQなど)を実装する場合は、リッチリザルトテストツールを使用します。
これにより、実際に検索結果で表示される可能性があるかを確認できます。
一方、リッチリザルトではないが、SEO上有用な構造化データ(サイト情報、企業情報など)を実装する場合は、スキーママークアップ検証ツールを使用します。
これにより、構文エラーがないか、schema.org規格に準拠しているかを確認できます。
理想的には、両方のツールを使用して総合的に検証することで、構造化データの品質を最大限に高められます。
リッチリザルトが表示されない原因と対策

構造化データを正しく実装したつもりでも、リッチリザルトが検索結果に表示されないことがあります。
ここでは、表示されない主な原因と、それぞれの対策を詳しく解説します。
構造化データの記述エラー
最も基本的で、かつ最も頻繁に発生する原因が、構造化データの記述ミスです。
わずかな構文エラーでも、構造化データ全体が無効になり、リッチリザルトが表示されなくなります。
よくある記述エラーとして、まずJSON-LDの構文エラーが挙げられます。
カンマの位置が間違っている、閉じ括弧が不足している、ダブルクォーテーションが片方だけ、といった基本的なミスです。
これらは、プログラミングに不慣れな方が手動でコードを書く際に起こりやすいエラーです。
次に、必須プロパティの欠落も頻繁に見られます。
各リッチリザルトには、必ず記述しなければならない必須プロパティが定義されています。
たとえば、商品のリッチリザルトでは「name(商品名)」「image(画像)」「offers(価格情報)」などが必須です。
| よくある記述エラー | 例 |
| カンマの不足・過剰 | “name”: “商品A” “price”: 1000 |
| 括弧の不一致 | { “name”: “商品A” |
| 必須プロパティの欠落 | nameがない商品スキーマ |
| データ型の間違い | price: “千円”(数値で記述すべき) |
さらに、データ型の間違いもエラーの原因となります。
価格を記述すべき場所に文字列を入れたり、日付形式が規定と異なっていたりすると、エラーとなります。
対策としては、必ずリッチリザルトテストツールで検証することが最も確実です。
コードを記述したら、すぐにテストツールで確認し、エラーが表示されたら、その指摘内容に従って修正します。
また、コードエディタの構文チェック機能を活用することも有効です。
Visual Studio Codeなどの高機能なエディタは、JSON-LDの構文エラーをリアルタイムで指摘してくれます。
さらに、Googleの公式ドキュメントのコード例をベースにすることで、構文エラーのリスクを大幅に減らせます。
ゼロから書くのではなく、公式の正しいコード例をコピーして、自社の情報に書き換える方法が安全です。
Googleのガイドライン違反
構造化データの構文が正しくても、内容がGoogleの品質ガイドラインに違反している場合、リッチリザルトは表示されません。
最悪の場合、手動による対策(ペナルティ)の対象となり、リッチリザルトだけでなく検索順位自体にも悪影響が及びます。
最も重要なガイドラインは、**「ユーザーに表示されているコンテンツと、構造化データの内容が一致していること」**です。
構造化データにのみ存在し、ページ本文にはない情報をマークアップすることは禁止されています。
たとえば、ページには「3,980円」と表示されているのに、構造化データには「2,980円」と記述するのは、明確なガイドライン違反です。
- ページに表示されていない情報のマークアップ:違反
- 虚偽のレビューや評価のマークアップ:違反
- 無関係なコンテンツのマークアップ:違反
また、虚偽のレビューや評価をマークアップすることも厳禁です。
実際には存在しないユーザーレビューを捏造したり、評価を不当に高く表示したりすると、ユーザーを欺く行為と見なされます。
さらに、ページの内容と関係ないリッチリザルトを実装することも違反となります。
たとえば、単なるブログ記事にレシピの構造化データを追加したり、商品ページでもないページに商品スキーマを使用したりすることは不適切です。
対策としては、常にユーザー視点でコンテンツを作成することが基本です。
構造化データは、ページ上に実際に存在する情報を、検索エンジンが理解しやすい形で伝えるためのものです。
ユーザーに見えない情報を追加しようとしている時点で、方向性が間違っています。
また、Googleの公式ガイドラインを定期的に確認する習慣をつけましょう。
ガイドラインは更新されることがあり、以前は許可されていた手法が、突然違反とされることもあります。
検索クエリの特性
構造化データが完璧で、ガイドラインも遵守していても、検索クエリ(検索キーワード)の特性によって、リッチリザルトが表示されないことがあります。
Googleは、すべての検索クエリでリッチリザルトを表示するわけではありません。
ユーザーの検索意図を分析し、リッチリザルトを表示することが検索体験の向上につながると判断した場合にのみ表示します。
たとえば、「オムライス レシピ」と検索した場合、多くのユーザーが具体的なレシピを求めていることが明確なため、レシピのリッチリザルトが表示されやすくなります。
しかし、「オムライス 歴史」と検索した場合、ユーザーは料理手順ではなく歴史的背景を知りたいため、レシピのリッチリザルトは表示されない可能性が高いです。
| 検索クエリの特性とリッチリザルト表示 |
| 具体的な情報を求めるクエリ → 表示されやすい |
| 曖昧・抽象的なクエリ → 表示されにくい |
| ナビゲーショナルクエリ → 表示されにくい |
また、地域やデバイスによっても表示が変わることがあります。
モバイル検索では表示されるが、デスクトップでは表示されない、あるいはその逆、ということもあります。
対策としては、自社のターゲットキーワードで実際に検索してみて、他のサイトのリッチリザルトが表示されているかを確認することが重要です。
他のサイトでもリッチリザルトが表示されていない場合、そのキーワードではGoogleがリッチリザルトを表示しない判断をしている可能性があります。
その場合、構造化データを実装しても表示される可能性は低いため、他のSEO施策に注力する方が効率的かもしれません。
一方、競合サイトでリッチリザルトが表示されているのに、自社サイトでは表示されない場合は、実装に問題がある可能性が高いため、再度検証が必要です。
反映までの時間
構造化データを実装してから、実際に検索結果にリッチリザルトが表示されるまでには、一定の時間がかかります。
実装直後にすぐに表示されないからといって、失敗したわけではありません。
リッチリザルトが表示されるまでのプロセスは、以下の通りです。
まず、Googleのクローラーがページを訪問する必要があります。
新しいページやあまり更新されないページの場合、クロールされるまでに数日から数週間かかることがあります。
次に、クロールされたページがインデックスに登録されます。
クロールとインデックスは別のプロセスであり、クロールされてもすぐにインデックスされるとは限りません。
- ステップ1:ページのクロール(数日〜数週間)
- ステップ2:インデックスへの登録(数時間〜数日)
- ステップ3:構造化データの処理(数時間〜数日)
- ステップ4:リッチリザルトの表示(即時〜数日)
そして、インデックスされたページの構造化データが処理されます。
Googleは構造化データを解析し、有効かどうかを判定します。
最後に、検索結果にリッチリザルトとして反映されます。
このプロセス全体で、早ければ数時間、通常は数日から2週間程度、場合によっては1ヶ月以上かかることもあります。
ただし、FAQなど一部のリッチリザルトは、設定後30分以内に反映されるという報告もあります(現在はFAQの表示条件が変更されているため、この速度は一般サイトでは体験できませんが)。
対策としては、Google Search Consoleの「URL検査」ツールを活用することが有効です。
実装したページのURLを入力し、「インデックス登録をリクエスト」ボタンをクリックすることで、優先的にクロールしてもらえる可能性が高まります。
ただし、これはあくまで「リクエスト」であり、即座にインデックスされる保証はありません。
また、サイトマップを送信することで、新しいページや更新されたページをGoogleに通知できます。
構造化データを実装したページは、サイトマップに含めて送信しましょう。
そして何より、焦らず待つことが重要です。
実装から2週間程度は、反映を待つ期間と考えましょう。
2週間以上経過しても表示されない場合は、他の原因(記述エラー、ガイドライン違反など)を疑い、再度検証する必要があります。
リッチリザルト実装の注意点
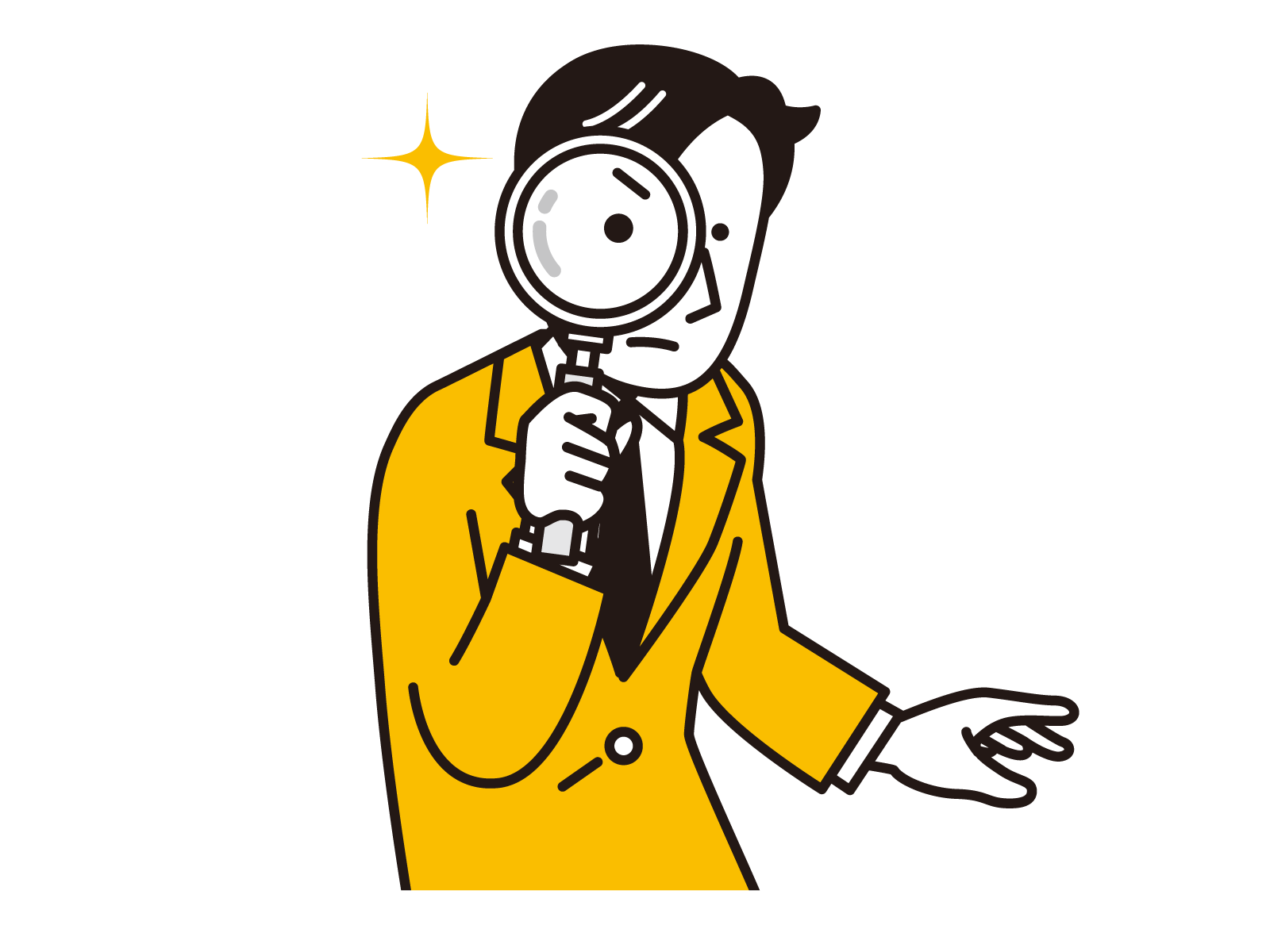
リッチリザルトを効果的に活用するには、技術的な実装だけでなく、運用面での注意点も理解しておく必要があります。
ここでは、長期的にリッチリザルトのメリットを享受するための重要なポイントを解説します。
Googleのガイドライン遵守
リッチリザルトの実装において、Googleのガイドラインを遵守することは絶対条件です。
ガイドライン違反は、リッチリザルトが表示されないだけでなく、サイト全体の評価を下げる可能性があります。
Googleが定める主要なガイドラインを確認しましょう。
まず、コンテンツに関するガイドラインです。
構造化データでマークアップする情報は、すべてページ上でユーザーが視認できる内容でなければなりません。
ユーザーには見えない隠しテキストや、ページに存在しない情報を構造化データに含めることは禁止されています。
| ガイドラインの主要項目 |
| コンテンツの可視性(ユーザーに見える情報のみ) |
| 情報の正確性(虚偽情報の禁止) |
| 関連性(ページ内容と一致) |
| スパム行為の禁止 |
次に、品質に関するガイドラインです。
虚偽のレビュー、誇大広告、誤解を招く情報などは厳禁です。
たとえば、実際には星3つの評価しか得ていないのに、構造化データには星5つと記述するのは明確な違反です。
また、スパム行為の禁止も重要です。
無関係なキーワードを含めたり、過度に商業的な内容を構造化データに詰め込んだりすることは避けなければなりません。
さらに、技術的な要件も遵守する必要があります。
Googleが推奨するJSON-LD形式を使用すること、正しいschema.orgのプロパティを使用すること、必須プロパティをすべて含めることなどです。
ガイドライン違反が発覚した場合、**手動による対策(ペナルティ)**の対象となります。
これは、特定のページまたはサイト全体がリッチリザルトの表示資格を剥奪されるだけでなく、検索順位にも悪影響を及ぼす可能性があります。
対策としては、実装前にGoogleの公式ガイドラインを必ず確認することが基本です。
ガイドラインは、Google Search Centralの「構造化データに関する一般的なガイドライン」ページで詳しく説明されています。
また、定期的なセルフチェックも重要です。
構造化データを実装した後も、定期的にリッチリザルトテストツールやサーチコンソールで確認し、警告やエラーが出ていないかをモニタリングしましょう。
最新情報の定期更新
リッチリザルトに含まれる情報は、常に最新の状態に保つことが非常に重要です。
古い情報や誤った情報が表示されると、ユーザーの信頼を損なうだけでなく、ガイドライン違反となる可能性もあります。
特に重要なのが、価格情報の更新です。
ECサイトで商品の価格が変更された場合、ページ本文だけでなく、構造化データの価格情報も必ず更新する必要があります。
セールやキャンペーンで一時的に価格が変わる場合も、構造化データを忘れずに更新しましょう。
次に、在庫状況の更新も欠かせません。
「在庫あり」と表示していた商品が売り切れた場合、構造化データも「在庫切れ」に更新する必要があります。
在庫がないのに「在庫あり」と表示し続けると、ユーザーを誤解させるだけでなく、ガイドライン違反となります。
- 価格情報:セール・キャンペーンを含めて即時更新
- 在庫状況:売り切れ・再入荷を反映
- イベント情報:日時・会場の変更を反映
- 求人情報:募集終了したら即座に削除
イベント情報も、開催日時や場所が変更された場合、速やかに更新する必要があります。
中止になったイベントの情報を残しておくことは、ユーザーに不利益を与えるため、絶対に避けなければなりません。
求人情報の更新は、特に厳格に管理する必要があります。
募集が終了した求人をページ上や構造化データに残しておくと、Googleから手動による対策の対象とされる可能性が高いです。
求人が充足したら、即座にページを削除するか、構造化データを削除し、「募集終了」と明示しましょう。
情報更新を効率化するには、CMSやデータベースと構造化データを連動させることが効果的です。
たとえば、商品データベースの価格を更新したら、自動的にページと構造化データの両方が更新される仕組みを構築すれば、更新漏れを防げます。
また、定期的な棚卸しも重要です。
月に一度など、定期的にサイト全体の構造化データを見直し、古い情報や誤った情報がないかをチェックする習慣をつけましょう。
株式会社エッコでは、構造化データの実装だけでなく、継続的な更新・管理のサポートも提供しており、クライアント企業が常に最新の情報を提供できる体制づくりをお手伝いしています。
虚偽情報の禁止
虚偽情報や誤解を招く情報を構造化データに含めることは、絶対に避けなければなりません。
これはGoogleのガイドラインで明確に禁止されており、違反した場合の影響は深刻です。
虚偽情報の代表例として、自作自演のレビューや評価が挙げられます。
実際にはユーザーレビューが存在しないのに、「星5つ、レビュー100件」のように表示することは、ユーザーを欺く行為です。
また、少数の身内や関係者だけの好意的なレビューを、あたかも多数の一般ユーザーの評価であるかのように見せることも不適切です。
次に、誇大広告や根拠のない主張も虚偽情報に含まれます。
「業界No.1」「最高品質」「100%効果あり」といった表現を、客観的な根拠なく構造化データに含めることは避けるべきです。
| 虚偽情報の例 | なぜ問題か |
| 存在しないレビュー | ユーザーを欺く |
| 実際と異なる価格 | 誤解を招く |
| 誇大広告 | 信頼性を損なう |
| 他社商品の情報 | 関係ない情報 |
また、競合他社の商品情報を自社ページに含めることも、関連性のない情報として問題視されます。
たとえば、自社のスマートフォンのページに、競合メーカーのスマートフォンの構造化データを含めることは不適切です。
虚偽情報が発覚した場合、手動による対策が実施され、リッチリザルトの表示資格が剥奪されます。
最悪の場合、サイト全体の検索順位が大幅に下落したり、検索結果から除外されたりする可能性もあります。
対策の基本は、正直であることです。
ユーザーレビューがまだ集まっていなければ、無理に表示する必要はありません。
価格が競合より高ければ、それを正直に表示することが、長期的には信頼につながります。
また、レビューの収集プロセスを透明化することも重要です。
実際にユーザーからレビューを募集し、良い評価も悪い評価も公平に表示することで、自然で信頼性の高いレビュー評価を構築できます。
虚偽情報に頼るのではなく、本質的な商品・サービスの質を高めることに注力することが、最も確実なリッチリザルト活用法です。
2023年以降の変更点

リッチリザルトに関するGoogleの方針は、常に進化しています。
2023年には、一部のリッチリザルトについて大きな変更が実施されました。
これは、Web担当者にとって非常に重要な情報であり、戦略の見直しが必要です。
FAQ・HowToの表示条件変更
2023年8月、Googleは検索結果のシンプル化を目的として、FAQとHowToのリッチリザルトに関する大きな方針変更を発表しました。
この変更は、多くのWebサイト運営者に影響を与えた重要なアップデートです。
まず、FAQのリッチリザルトについてです。
2023年8月以前は、適切にFAQPageスキーマを実装すれば、多くのサイトでFAQのリッチリザルトが表示されていました。
質問と回答をアコーディオン形式で表示することで、検索結果の占有面積を大きくでき、高いクリック率を実現できました。
しかし、2023年8月以降、FAQのリッチリザルトは「よく知られた、権威ある政府機関および医療関連のウェブサイト」に限定されるようになりました。
具体的には、政府の公式サイト、公的医療機関、大学病院などの信頼性の高いサイトのみが対象です。
| 変更項目 | 変更前 | 変更後 |
| FAQ表示対象 | すべてのサイト | 政府・医療機関のみ |
| 一般企業サイト | 表示される | 表示されない |
| ブログ・メディア | 表示される | 表示されない |
一般的な企業サイト、ECサイト、ブログ、メディアサイトなどでは、FAQPageスキーマを正しく実装しても、リッチリザルトとして表示されなくなりました。
次に、HowToのリッチリザルトについてです。
HowToスキーマは、手順を段階的に説明するコンテンツに使用され、特にDIYや料理、修理方法などのページで活用されていました。
しかし、2023年9月、HowToのリッチリザルトは完全に廃止されました。
まず2023年8月にモバイルでの表示が停止され、その後2023年9月13日にデスクトップでも表示が停止されました。
現在、HowToスキーマはリッチリザルトとしてのサポートが完全に終了しています。
- 2023年8月:モバイルで表示停止
- 2023年9月13日:デスクトップで表示停止
- 現在:完全に非推奨
Googleは公式ブログで、「検索結果をシンプルにする取り組みを継続する」ことを理由として挙げています。
FAQやHowToのリッチリザルトが検索結果ページで大きなスペースを占めるようになり、ユーザーにとってスクロールの負担が増えたことが、変更の背景にあると考えられます。
影響と対応策
この変更により、多くのWebサイトはFAQとHowToのリッチリザルトによるクリック率向上効果を失いました。
特に、これらのリッチリザルトに依存していたサイトでは、流入数の減少が見られた可能性があります。
では、Web担当者はどのように対応すべきでしょうか。
まず、既存のFAQPageやHowToスキーマを削除する必要はありません。
リッチリザルトとしては表示されませんが、構造化データ自体がマイナスに働くことはありません。
音声検索やAIアシスタントでの情報提供に活用される可能性や、将来的な仕様変更で再び利用される可能性もゼロではありません。
ただし、新規実装の優先度は大幅に低下しました。
限られたリソースを、FAQやHowToの構造化データ実装に投入するよりも、他のリッチリザルト(商品、パンくずリスト、レビューなど)や、コンテンツの質向上に注力する方が効果的です。
| 対応策 | 推奨度 |
| 既存の実装を削除 | 不要(そのまま残してOK) |
| 新規実装 | 優先度低(他を優先) |
| 他のリッチリザルトへ注力 | 強く推奨 |
| コンテンツ質の向上 | 最優先 |
代替戦略として、他のリッチリザルトの実装に注力することが推奨されます。
商品のリッチリザルト、パンくずリスト、レビュー・評価、レシピ、イベント、求人情報など、2025年現在も表示されているリッチリザルトは多数あります。
これらを優先的に実装することで、検索流入の最大化を図りましょう。
また、FAQ的なコンテンツは、強調スニペットを狙う形式に変更することも一つの戦略です。
質問と回答を明確に記述し、適切な見出し構造を使用することで、強調スニペットに選ばれる可能性が高まります。
強調スニペットはリッチリザルトとは異なりますが、検索結果の最上部(ポジションゼロ)に表示されるため、高い視認性とクリック率を期待できます。
さらに、コンテンツの本質的な質を高めることが、最も重要です。
リッチリザルトは検索流入を増やす有効な手段ですが、それはあくまで補助的なものです。
ユーザーにとって本当に価値のある情報を提供し、疑問を解決し、問題を解消できるコンテンツを作ることが、長期的なSEO成功の鍵です。
このように、最新の動向を常に把握し、柔軟に戦略を調整することが、リッチリザルトを効果的に活用するために不可欠です。
株式会社エッコでは、Googleの最新動向を常にキャッチアップし、クライアント企業に最適なリッチリザルト戦略をご提案しています。
まとめ

リッチリザルトは、Google検索結果において通常の青色リンクよりも豊富な情報を表示する機能であり、クリック率の向上、視認性の改善、ユーザー体験の向上といった多くのメリットをもたらします。
実際の事例では、リッチリザルトの実装によってクリック率が25%〜82%も向上したというデータがあり、その効果は実証されています。
リッチリザルトを実装するには、JSON-LD形式での構造化データのマークアップが必要です。
パンくずリスト、商品、レシピ、イベント、求人情報、レビュー、動画など、サイトの内容に合わせて適切なリッチリザルトを選択し、正しく実装することが重要です。
ただし、2023年以降、FAQとHowToのリッチリザルトは表示条件が大きく変更されました。
一般企業サイトではFAQは表示されなくなり、HowToは完全に廃止されたため、これらへの新規投資は優先度が低いといえます。
実装後は、リッチリザルトテストツールやGoogleサーチコンソールで継続的に確認し、エラーがないか、正しく表示されているかをモニタリングすることが不可欠です。
また、価格や在庫状況、イベント日時などの情報は常に最新の状態に保ち、虚偽情報を絶対に含めないことが、ガイドライン遵守の観点から極めて重要です。
リッチリザルトは、適切に実装・運用することで、検索流入を大幅に増やし、ビジネス成果に直結する強力なSEO施策です。
まだ実装していない方は、まずはパンくずリストなど比較的簡単なものから始めて、段階的に拡大していくことをお勧めします。
名古屋を拠点とする株式会社エッコでは、リッチリザルトの実装から継続的な運用サポートまで、包括的なWebコンサルティングサービスを提供しています。
構造化データの実装にお困りの際や、SEO対策全般についてご相談されたい場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
貴社のWebサイトの検索流入最大化を、専門知識と豊富な経験でサポートいたします。



