「ホームページを公開したのに、会社名で検索しても全く出てこない…」
「以前は表示されていたのに、いつの間にか検索結果から消えてしまった…」
こうしたお悩みを抱えている企業のWeb担当者の方は少なくありません。
実は、サイトが検索結果に表示されないのには必ず理由があります。
検索エンジンの仕組みを理解し、適切な対処を行えば、多くの場合は解決できる問題です。
この記事では、検索しても出てこない原因を体系的に整理し、今すぐ実践できる具体的な対処法をわかりやすく解説します。
初心者の方でも理解できるよう、専門用語はできるだけ避け、実際の画面イメージや手順を交えながらご説明していきます。
名古屋を拠点にWebコンサルティングを行う株式会社エッコでも、多くの企業様からこの種のご相談をいただいてきました。
その経験から、実務で本当に役立つ情報を厳選してお届けします。
検索結果への表示は、Webサイトで集客を実現するための第一歩です。
この記事を読み終える頃には、あなたのサイトが検索結果に表示されない原因が特定でき、具体的な解決策が見えてくるはずです。
Index
検索結果に出てこない主な原因

サイトが検索結果に表示されない原因は、大きく分けて4つのパターンに分類できます。
それぞれの原因によって適切な対処法が異なるため、まずは自社サイトがどのパターンに該当するのかを見極めることが重要です。
ここでは、検索エンジンの仕組みと照らし合わせながら、主な原因を詳しく解説していきます。
原因を正しく理解することで、効果的な対策につながります。
インデックス登録されていない
検索結果に表示されない最も基本的な原因が、Googleのデータベースに登録されていない、つまり「インデックス登録されていない」状態です。
Googleの検索エンジンは、クローラーと呼ばれるロボットがインターネット上を巡回し、見つけたページを自社のデータベースに登録することで、検索結果に表示する仕組みになっています。
このデータベースへの登録作業を「インデックス」と呼びます。
インデックス登録されていなければ、どんなに優れたコンテンツを作成しても、検索結果には一切表示されません。
インデックス登録されていない理由は、主に2つのパターンに分けられます。
新規サイト特有のタイムラグによるものと、クローラーが巡回できていない技術的な問題です。
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
新規サイトのタイムラグ
新しくサイトを公開した場合、インデックス登録までには一定の時間がかかります。
Googleのクローラーは常にインターネット上を巡回していますが、新規サイトを発見してインデックスに登録するまでには、通常1日から数週間程度の期間を要します。
これは決して異常なことではなく、検索エンジンの通常の動作です。
クローラーは既存のサイトからリンクを辿って新しいページを発見するため、外部からのリンクがほとんどない新規サイトは発見されにくい傾向があります。
また、サイトの規模や構造、コンテンツの量なども、発見されるまでの時間に影響を与えます。
- 新規ドメインの場合、信頼性の構築に時間がかかる
- 外部リンクが少ないと、クローラーが辿り着きにくい
- サイト内のページ数が少ないと、優先度が下がりやすい
- 既存の評価されているサイトと比べて、巡回頻度が低い
新規サイトの場合は、ある程度の待ち時間が必要であることを理解しておくことが大切です。
ただし、後述するGoogleサーチコンソールを活用することで、この待ち時間を大幅に短縮できます。
焦らず、適切な対策を行いながら、インデックス登録を待ちましょう。
クロールされていない状態
インデックス登録の前段階として、クローラーによる「クロール」が必要です。
クロールとは、クローラーがサイトを訪問し、ページの内容を読み取る作業のことを指します。
クロールされなければインデックス登録も行われず、当然ながら検索結果にも表示されません。
クロールされていない状態には、いくつかの技術的な原因が考えられます。
サイトの構造上、クローラーがページにたどり着けない場合や、意図せずクロールを拒否する設定になっている場合などです。
特に多いのが、サイト内の内部リンクが適切に設置されておらず、孤立したページになってしまっているケースです。
- トップページから該当ページへのリンクが存在しない
- サイトマップにURLが含まれていない
- JavaScriptでのみ表示されるリンクになっている
- サイトの階層が深すぎて、クローラーがたどり着けない
また、サーバーの不具合やメンテナンス中など、一時的にアクセスできない状態が続いている場合も、クロールが行われません。
クロールされているかどうかは、Googleサーチコンソールの「URL検査」機能で確認できます。
クロールされていない場合は、サイト構造の見直しや、後述する対処法を実施する必要があります。
クローラビリティの問題
クローラビリティとは、検索エンジンのクローラーがサイトを巡回しやすい状態を指す言葉です。
クローラビリティが低いと、クローラーがページを見つけられない、または内容を正しく理解できないため、検索結果に表示されにくくなります。
クローラビリティの問題は、多くの場合、サイトの設定ミスによって引き起こされます。
特に、開発段階やテスト段階で設定した内容を、本番環境でも残してしまっているケースが頻繁に見られます。
また、CMS(コンテンツ管理システム)の設定画面で誤ったオプションを選択していることもあります。
ここでは、クローラビリティを低下させる代表的な2つの設定ミスについて解説します。
これらは比較的簡単にチェックでき、修正も容易なので、必ず確認しておきましょう。
robots.txtの設定ミス
robots.txtは、クローラーに対して「このページはクロールしないでください」と指示するためのファイルです。
サイトのルートディレクトリ(トップページと同じ階層)に設置することで、クローラーの動きを制御できます。
意図せずrobots.txtでクロールをブロックしてしまうと、該当ページは検索結果に表示されなくなります。
robots.txtの設定ミスは、特に以下のような状況で発生しやすくなります。
開発環境で使用していたrobots.txtを本番環境にそのまま移行してしまった場合や、不要なページをブロックしようとして、誤って重要なページまでブロックしてしまった場合などです。
robots.txtが正しく設定されているかは、ブラウザで「https://あなたのドメイン/robots.txt」にアクセスすることで確認できます。
| 記述例 | 意味 | 影響 |
| User-agent: * | すべてのクローラーに適用 | 全検索エンジンが対象 |
| Disallow: / | サイト全体へのアクセスを禁止 | サイト全体が検索されない |
| Disallow: /admin/ | 特定ディレクトリを禁止 | 該当ディレクトリのみ影響 |
| Allow: / | すべてのページを許可 | 正常にクロールされる |
もし「Disallow: /」という記述が存在する場合は、サイト全体がクロールされない設定になっています。
すぐに該当行を削除するか、「Allow: /」に変更する必要があります。
ただし、注意すべきはrobots.txtでブロックしてもインデックスされる可能性があるという点です。
他のサイトからリンクを受けている場合、クロールはされなくてもインデックスには登録されることがあります。
完全にインデックスを防ぎたい場合は、後述するnoindexタグを使用しましょう。
noindexタグの誤設定
noindexタグは、ページのHTMLコード内に記述することで、「このページはインデックスに登録しないでください」とGoogleに指示するタグです。
robots.txtがクロールを制御するのに対し、noindexタグはインデックス登録を直接的に拒否します。
このタグが設定されていると、クロールは行われてもインデックスされないため、検索結果には絶対に表示されません。
noindexタグの誤設定は、実務上最も頻繁に発生する問題の一つです。
特にWordPressなどのCMSを使用している場合、設定画面で簡単にnoindexを設定できるため、誤って有効にしてしまうケースが多発しています。
また、テスト環境で設定したnoindexタグを本番環境でも外し忘れるというミスも典型的です。
- WordPressの「検索エンジンでの表示」にチェックが入っている
- SEOプラグインでページごとにnoindexが設定されている
- テーマファイルに直接noindexタグが記述されている
- 開発時の設定がそのまま残っている
noindexタグは、HTMLの<head>セクション内に以下のような形で記述されます。
「<meta name=”robots” content=”noindex”>」
この記述がある場合、そのページはインデックス登録されません。
ページのソースコードを表示して(ブラウザで右クリック→「ページのソースを表示」)、このタグが含まれていないか確認しましょう。
WordPressの場合は、管理画面の「設定」→「表示設定」から、「検索エンジンがサイトをインデックスしないようにする」のチェックが外れているか確認してください。
Googleペナルティを受けている
Googleペナルティとは、Googleのガイドラインに違反したサイトに対して課される制裁措置です。
ペナルティを受けると、検索順位が大幅に下落したり、最悪の場合は検索結果から完全に削除されたりします。
ペナルティには、Google担当者が手動で判定する「手動ペナルティ」と、アルゴリズムによって自動的に判定される「自動ペナルティ」の2種類があります。
手動ペナルティの場合は、Googleサーチコンソールに通知が届くため、比較的気づきやすいのが特徴です。
一方、自動ペナルティの場合は通知が来ないため、突然の順位下落によって初めて気づくことになります。
ペナルティの原因として代表的なものには以下があります。
| ペナルティの原因 | 具体例 | 影響度 |
| 不自然なリンク | リンクの購入、大量の相互リンク | 重大 |
| コピーコンテンツ | 他サイトからの無断転載 | 重大 |
| キーワードスタッフィング | 不自然なキーワードの詰め込み | 中程度 |
| 隠しテキスト | 背景色と同じ色の文字 | 重大 |
| クローキング | ユーザーと検索エンジンで異なる内容を表示 | 重大 |
| 低品質なコンテンツ | 内容の薄いページの大量生産 | 中程度 |
特に注意が必要なのは、過去に中古ドメインを購入した場合です。
前の所有者がペナルティを受けていた場合、その影響が引き継がれてしまう可能性があります。
また、悪意のある第三者からのスパムリンク(ネガティブSEO)によって、知らないうちにペナルティを受けるケースもあります。
ペナルティを受けているかどうかは、Googleサーチコンソールの「手動による対策」レポートで確認できます。
もしペナルティを受けていた場合は、原因を特定して修正した上で、再審査リクエストを送信する必要があります。
詳しい対処法については、後述の「ペナルティ対策と解除方法」の章で詳しく解説します。
コンテンツ品質の問題
インデックス登録されていても、コンテンツの品質が低いと判断されると、検索結果に表示されない、または極端に順位が低くなることがあります。
Googleは「ユーザーにとって有益な情報を提供する高品質なページを上位表示する」という基本方針を持っています。
そのため、ユーザーのニーズを満たさないページは、たとえインデックスされていても検索結果の上位には表示されません。
コンテンツ品質の問題には、いくつかのパターンがあります。
最も多いのが、情報量が少なすぎる、または内容が薄すぎるページです。
数十文字程度の短い文章しかないページや、具体的な情報がほとんど含まれていないページは、低品質と判断されやすくなります。
また、他のサイトと似たような内容ばかりで独自性がないページも、評価が低くなる傾向にあります。
- テキストの量が極端に少ない(300文字未満など)
- 他サイトのコピーまたは類似性が高い内容
- ユーザーの検索意図と合致していない
- 情報が古く、現在は正確ではない内容
- 専門性や信頼性に欠ける記述
特に注意が必要なのは、Googleサーチコンソールで「クロール済み – インデックス未登録」と表示されているページです。
これは、クローラーはページを見つけて内容を確認したものの、品質が基準に満たないためインデックス登録しないと判断された状態を示しています。
この状態のページは、コンテンツの大幅な改善が必要です。
情報量を増やし、ユーザーにとって本当に価値のある内容に作り変えることで、インデックス登録される可能性が高まります。
コンテンツ品質の具体的な改善方法については、「コンテンツ品質の改善方法」の章で詳しく解説します。
名古屋を拠点とする株式会社エッコでは、コンテンツ品質の診断から改善提案まで、トータルでサポートしています。
自社だけでは判断が難しい場合は、専門家の意見を聞くことも有効な選択肢です。
検索状況の確認方法

サイトが検索結果に表示されない原因を特定するには、まず現在の状況を正確に把握することが重要です。
自己判断だけでなく、客観的なデータに基づいて現状を確認することで、適切な対処法が見えてきます。
ここでは、誰でも簡単に実践できる3つの確認方法をご紹介します。
特別なツールがなくても確認できる方法から、Googleが公式に提供する無料ツールを使った詳細な診断方法まで、段階的に解説していきます。
これらの確認作業を行うことで、問題の所在が明確になり、次に取るべきアクションが具体的に見えてくるはずです。
site:検索での確認手順
最も手軽で即座に確認できる方法が、Googleの検索窓を使った「site:検索」です。
この方法は、特別なツールのアカウント登録も不要で、今すぐ実行できるのが大きなメリットです。
site:検索を使うと、指定したドメイン内のページがGoogleにインデックス登録されているかどうかを確認できます。
確認手順は非常にシンプルです。
Googleの検索窓に「site:あなたのドメイン」と入力して検索するだけです。
例えば、あなたのサイトのURLが「https://example.com/」の場合、「site:example.com」と入力して検索します。
検索結果にサイトのページが表示されれば、そのページはインデックス登録されている証拠です。
- トップページだけでなく、個別ページも確認できる
- 「site:example.com/about/」のように特定ページを指定可能
- インデックス数の概算も把握できる
- アカウント登録不要で今すぐ確認できる
ただし、site:検索には注意点もあります。
この方法で表示されるのは「Googleの表示基準を満たしているページ」のみです。
インデックスはされていても、品質が低いと判断されたページは表示されない場合があります。
より正確な情報を知りたい場合は、次に紹介するGoogleサーチコンソールを使用しましょう。
また、site:検索の結果に「一致する情報は見つかりませんでした」と表示された場合は、サイト全体がインデックスされていない可能性が高いです。
この場合は、早急に後述する対処法を実施する必要があります。
site:検索は、定期的に実施することをおすすめします。
新しく公開したページがインデックスされているか、既存ページが問題なく表示され続けているかを、継続的に確認する習慣をつけましょう。
Googleサーチコンソールでの診断
Googleサーチコンソール(Google Search Console)は、Googleが無料で提供しているサイト管理者向けのツールです。
site:検索よりも詳細で正確な情報が得られるため、本格的にサイトを運営するなら必ず登録しておくべきツールといえます。
サーチコンソールでは、インデックス状況だけでなく、検索パフォーマンスやクロールの状況、エラーの有無など、さまざまな情報を確認できます。
登録方法は、Googleアカウントがあれば比較的簡単です。
サーチコンソールのサイトにアクセスし、サイトのURLを登録して、所有権の確認を行えば完了します。
所有権の確認方法にはいくつかの選択肢がありますが、HTMLタグを自サイトの<head>セクションに追加する方法が一般的です。
サーチコンソールには多くの機能がありますが、ここでは特に重要な2つのレポートについて詳しく解説します。
カバレッジレポートとクロール統計です。
これらを定期的にチェックすることで、サイトの健全性を維持し、問題の早期発見につながります。
カバレッジレポートの見方
カバレッジレポートは、サイト内の各ページがどのような状態にあるかを一覧で確認できる機能です。
サーチコンソールの左メニューから「インデックス作成」→「ページ」を選択すると表示されます。
このレポートを見ることで、どのページが正常にインデックスされていて、どのページに問題があるかが一目で分かります。
カバレッジレポートでは、ページの状態が4つのカテゴリーに分類されて表示されます。
それぞれのカテゴリーの意味を理解することが、問題解決の第一歩です。
「エラー」は最も深刻な状態で、ページが全くインデックスされていない状態を示します。
「警告あり」は、インデックスはされているものの、何らかの問題が検出されている状態です。
| ステータス | 意味 | 対応の必要性 |
| エラー | インデックスできていない | 即座に対応が必要 |
| 警告あり | インデックスされているが問題あり | 早めの対応を推奨 |
| 有効 | 正常にインデックスされている | 問題なし |
| 除外 | 意図的またはその他の理由で除外 | 内容を確認 |
特に注意すべきは「除外」のカテゴリーです。
除外には様々な理由があり、noindexタグによる除外のように意図的なものもあれば、「クロール済み – インデックス未登録」のように品質の問題でインデックスされていないケースもあります。
「クロール済み – インデックス未登録」は、Googleがページを訪問して内容を確認したものの、インデックスする価値がないと判断された状態を意味します。
このステータスのページは、コンテンツの大幅な改善が必要です。
また、「検出 – インデックス未登録」は、ページの存在は認識しているものの、まだクロールが行われていない状態を示します。
サーバーの負荷やクロールの優先順位の問題で、クロールが後回しにされている可能性があります。
各ステータスをクリックすると、該当するページのURLリストが表示されます。
問題のあるページを一つずつ確認し、適切な対処を行いましょう。
クロール統計の確認
クロール統計は、Googleのクローラーがサイトをどのくらいの頻度で訪問しているかを確認できる機能です。
サーチコンソールの「設定」→「クロールの統計情報」から確認できます。
クロール頻度が極端に低い場合、新しいページのインデックスが遅れたり、更新した内容が反映されるまでに時間がかかったりする可能性があります。
クロール統計では、主に以下の3つの指標を確認できます。
「クロールリクエストの合計」は、指定期間内にクローラーがサイトを訪問した総回数を示します。
「ダウンロードサイズの合計」は、クローラーがダウンロードしたデータの総量です。
「平均応答時間」は、サーバーがクローラーのリクエストに応答するまでにかかった時間を示します。
- クロール頻度が急激に減少していないか
- サーバーの応答時間が長すぎないか(理想は200ms以下)
- ダウンロードサイズが適切な範囲内か
- エラー率が高くないか
クロール頻度が低い原因としては、サイトの規模が小さい、更新頻度が低い、サーバーの応答が遅いなどが考えられます。
また、robots.txtで多くのページをブロックしている場合も、クロール頻度が下がることがあります。
平均応答時間が長い場合は、サーバーのスペック不足や、ページの読み込みに時間がかかりすぎている可能性があります。
サーバーの応答速度を改善することで、クローラビリティが向上し、インデックスの速度も上がります。
定期的にクロール統計を確認し、異常な変化がないかチェックする習慣をつけましょう。
インデックス登録状況の把握
インデックス登録状況を正確に把握するには、Googleサーチコンソールの「URL検査」ツールを使用します。
この機能は、個別のページが現在どのような状態にあるかを、最も詳細に確認できる方法です。
site:検索やカバレッジレポートでは全体像を把握できますが、URL検査では1ページずつ詳しい診断結果を見ることができます。
URL検査の使い方は簡単です。
サーチコンソールの上部にある検索窓に、確認したいページのURLを入力して検索するだけです。
数秒から数十秒ほど待つと、そのページの現在の状態が詳しく表示されます。
検査結果では、インデックスされているかどうかだけでなく、以下のような詳細情報も確認できます。
| 確認項目 | 内容 | 重要度 |
| インデックス登録の可否 | ページが登録されているか | 最重要 |
| クロール日時 | 最後にクロールされた日時 | 重要 |
| ユーザーが指定した正規URL | canonicalタグの設定状況 | 重要 |
| Googleが選択した正規URL | Googleが判断した正規URL | 重要 |
| クロール許可の有無 | robots.txtでブロックされていないか | 最重要 |
| インデックス登録許可 | noindexタグの有無 | 最重要 |
| ページエクスペリエンス | モバイルユーザビリティなど | 中程度 |
「URLはGoogleに登録されています」と表示されれば、そのページは正常にインデックスされています。
一方、「URLがGoogleに登録されていません」と表示された場合は、その下に表示される理由を確認しましょう。
「検出 – インデックス未登録」「クロール済み – インデックス未登録」「noindexタグで除外されています」など、具体的な理由が示されます。
URL検査の結果画面には「インデックス登録をリクエスト」というボタンがあります。
インデックスされていないページについては、このボタンを押すことで、優先的にクロールとインデックスを依頼できます。
新しく公開したページや、大幅に更新したページについては、積極的にインデックス登録をリクエストすることをおすすめします。
ただし、リクエストしたからといって即座にインデックスされるわけではありません。
通常、リクエストから実際にインデックスされるまでには数時間から数日かかります。
焦らず、定期的に確認しながら待ちましょう。
株式会社エッコでは、サーチコンソールの設定から日常的な運用方法まで、実践的なサポートを提供しています。
データの見方や活用方法がわからない場合は、お気軽にご相談ください。
すぐに実施すべき対処法

原因が特定できたら、次は具体的な対処法を実施していきます。
ここで紹介する対処法は、技術的な専門知識がなくても実践できるものが中心です。
順番に確認しながら、自社サイトの状況に合った対策を進めていきましょう。
対処法は優先順位をつけて実施することが重要です。
まずはGoogleにサイトの存在を知らせること、次に技術的な問題を解消すること、そして最後にサイト構造を最適化することの順で進めていきます。
これらの対処法を適切に実施することで、多くの場合、サイトは検索結果に表示されるようになります。
Googleサーチコンソールへの登録
サイトを公開したら、真っ先に行うべきなのがGoogleサーチコンソールへの登録です。
サーチコンソールに登録することで、Googleに対してサイトの存在を明確に伝えることができます。
また、前述したような詳細な診断機能や、問題が発生した際の通知機能も利用できるようになります。
サーチコンソールへの登録は無料で、Googleアカウントさえあれば誰でも利用できます。
登録手順は以下の通りです。
まず、Google Search Consoleの公式サイトにアクセスし、「今すぐ開始」をクリックします。
Googleアカウントでログインし、「プロパティを追加」からサイトのURLを入力します。
次に、サイトの所有権を確認する作業が必要です。
- HTMLファイルをアップロードする方法
- HTMLタグをサイトに追加する方法
- Google Analyticsアカウントを使用する方法
- Googleタグマネージャーを使用する方法
- ドメイン名プロバイダを使用する方法
最も一般的なのは、HTMLタグをサイトの<head>セクションに追加する方法です。
サーチコンソールが表示するタグをコピーし、サイトのHTMLに貼り付けて、「確認」ボタンを押せば完了です。
WordPressを使用している場合は、多くのSEOプラグインがサーチコンソールとの連携機能を提供しているため、より簡単に設定できます。
登録が完了すると、数日以内にサイトのデータが蓄積され始めます。
サーチコンソールは登録後すぐに全機能が使えるわけではなく、データの収集には数日から1週間程度かかることを覚えておきましょう。
サイトマップの送信方法
サーチコンソールへの登録が完了したら、次に行うべきはサイトマップの送信です。
サイトマップとは、サイト内のページ構造を整理して一覧化したファイルのことで、クローラーがサイトを効率的に巡回するための地図のような役割を果たします。
サイトマップを送信することで、クローラーがサイト内のすべてのページを漏れなく発見しやすくなり、インデックスの速度も向上します。
サイトマップには、ユーザー向けの「HTMLサイトマップ」と、検索エンジン向けの「XMLサイトマップ」の2種類があります。
サーチコンソールに送信するのは、XMLサイトマップです。
XMLサイトマップの作成方法は、使用しているCMSやサイトの規模によって異なります。
WordPressを使用している場合は、プラグインで簡単に作成できます。
| プラグイン名 | 特徴 | おすすめ度 |
| XML Sitemaps | シンプルで使いやすい | 高 |
| Yoast SEO | SEO機能が充実 | 高 |
| All in One SEO | 多機能で柔軟 | 中 |
| Rank Math | 最新機能が豊富 | 高 |
プラグインをインストールして有効化すれば、自動的にXMLサイトマップが生成されます。
通常、「https://yourdomain.com/sitemap.xml」というURLでアクセスできるようになります。
サイトマップが作成できたら、サーチコンソールから送信します。
サーチコンソールの左メニューから「サイトマップ」を選択し、サイトマップのURLを入力して「送信」ボタンを押すだけです。
送信後、「成功しました」と表示されれば完了です。
ただし、サイトマップが必須なのは、ページ数が500ページを超える大規模サイトや、内部リンクが少ないサイトです。
小規模なサイトの場合は、サイトマップがなくてもクローラーは十分に巡回できます。
しかし、あって困るものではないので、できれば設定しておくことをおすすめします。
URL検査ツールの活用
URL検査ツールは、サーチコンソールの中でも特に重要な機能の一つです。
前述の「インデックス登録状況の把握」でも説明しましたが、このツールを使うことで、個別のページに対して直接インデックス登録をリクエストできます。
新しいページを公開した直後や、既存ページを大幅に更新した後は、このツールを積極的に活用しましょう。
URL検査ツールの使い方をステップごとに解説します。
まず、サーチコンソールにログインし、画面上部の検索窓にインデックスさせたいページのURLを入力します。
数秒待つと、そのページの現在の状態が表示されます。
「URLがGoogleに登録されていません」と表示された場合は、「インデックス登録をリクエスト」ボタンが表示されます。
- URLを正確に入力する(コピー&ペーストを推奨)
- 「インデックス登録をリクエスト」ボタンをクリック
- 1〜2分待つとテストが完了
- 「インデックス登録をリクエスト済み」と表示されれば成功
- 実際のインデックスには数時間〜数日かかる
リクエストを送信すると、Googleのクローラーが優先的にそのページを訪問してくれます。
ただし、リクエストできる回数には制限があるため、本当に必要なページに絞って使用することをおすすめします。
また、すでにインデックスされているページについても、更新内容を早く反映させたい場合にこのツールが使えます。
「URLはGoogleに登録されています」と表示されているページでも、「インデックス登録をリクエスト」は実行できます。
URL検査ツールは、問題の診断とインデックス登録の促進という2つの役割を果たす、非常に便利な機能です。
日常的なサイト運営の中で、習慣的に使いこなせるようにしましょう。
robots.txtとメタタグの確認
前述の通り、robots.txtやnoindexタグの誤設定は、サイトが検索結果に表示されない主要な原因の一つです。
これらの設定を定期的に確認し、適切な状態を維持することが重要です。
特にサイトの更新作業やリニューアルを行った後は、設定が意図せず変更されていないか必ずチェックしましょう。
ここでは、robots.txtとメタタグの確認方法と、問題があった場合の修正方法について詳しく解説します。
これらは技術的な知識が多少必要な部分もありますが、基本的な確認であれば誰でも実施できます。
自社で対応が難しい場合は、制作会社や株式会社エッコのようなWebコンサル会社に相談することも検討してください。
noindex・nofollowの確認手順
noindexタグとnofollowタグは、検索エンジンの動作を制御するメタタグです。
noindexは「このページをインデックスしないでください」、nofollowは「このページのリンクを辿らないでください」という指示をGoogleに出します。
意図せずこれらのタグが設定されていると、検索結果に表示されなくなります。
確認方法は複数ありますが、最も簡単なのはブラウザの開発者ツールを使う方法です。
確認したいページをブラウザで開き、右クリックして「検証」または「ページのソースを表示」を選択します。
表示されたHTMLコードの<head>セクション内を確認し、以下のようなタグがないかチェックします。
「<meta name=”robots” content=”noindex”>」
「<meta name=”robots” content=”nofollow”>」
「<meta name=”robots” content=”noindex, nofollow”>」
これらのタグが存在する場合、そのページはインデックスされません。
| タグの種類 | 効果 | 使用すべき場面 |
| noindex | インデックスを拒否 | 低品質ページ、重複ページ |
| nofollow | リンクを辿らない | 信頼できないリンク先 |
| noindex, nofollow | 両方を適用 | 完全に検索から除外したいページ |
| index, follow | 両方を許可(デフォルト) | 通常のページ |
WordPressを使用している場合は、より簡単に確認できます。
投稿編集画面を開き、使用しているSEOプラグインの設定を確認してください。
Yoast SEOやRank Mathなどのプラグインでは、投稿画面の下部に「検索エンジンにこのページのインデックスを許可しますか?」のような設定項目があります。
また、サイト全体に対してnoindexが設定されていないかも確認が必要です。
WordPressの場合、管理画面の「設定」→「表示設定」から、「検索エンジンがサイトをインデックスしないようにする」のチェックボックスを確認します。
ここにチェックが入っていると、サイト全体がnoindexになってしまうため、必ずチェックを外してください。
定期的にこれらの設定を確認する習慣をつけることで、意図しないインデックス拒否を防げます。
適切な設定への修正
noindexタグやrobots.txtによる問題が見つかった場合は、速やかに修正する必要があります。
修正方法は、設定されている場所によって異なります。
最も一般的なケースごとに、具体的な修正手順を説明します。
HTMLファイルに直接記述されている場合は、該当するタグを削除します。
<head>セクション内から「<meta name=”robots” content=”noindex”>」の行を見つけて削除し、ファイルを保存してサーバーにアップロードします。
WordPressの全体設定で有効になっている場合は、管理画面から修正できます。
「設定」→「表示設定」を開き、「検索エンジンがサイトをインデックスしないようにする」のチェックを外して「変更を保存」をクリックします。
SEOプラグインで設定されている場合は、各投稿の編集画面から修正します。
- Yoast SEOの場合:投稿編集画面下部の「高度な設定」から変更
- Rank Mathの場合:投稿編集画面のRank Mathメタボックスから変更
- All in One SEOの場合:投稿編集画面のAIOSEO設定から変更
robots.txtの修正は、FTPソフトなどでサーバーにアクセスして行います。
サイトのルートディレクトリにあるrobots.txtファイルをダウンロードし、テキストエディタで開きます。
「Disallow: /」の行を削除するか、「Allow: /」に変更して保存し、サーバーにアップロードし直します。
修正後は、必ずGoogleサーチコンソールのURL検査ツールで確認しましょう。
「インデックス登録を許可?」の項目が「はい」になっていれば、修正は正しく反映されています。
その後、インデックス登録をリクエストすることで、より早くインデックスされるようになります。
内部リンク構造の改善
内部リンクとは、自サイト内のページ同士をつなぐリンクのことです。
適切な内部リンク構造を構築することで、クローラーがサイト内を効率的に巡回できるようになり、インデックスの速度と範囲が改善します。
また、ユーザーにとっても関連情報に辿り着きやすくなるため、利便性が向上します。
内部リンク構造の改善は、SEO対策の基本中の基本です。
新しいページを公開する際は、必ず既存の関連ページから適切にリンクを設置しましょう。
また、既存ページについても、定期的にリンク構造を見直すことが重要です。
内部リンクを設置する際のポイントは以下の通りです。
まず、トップページから全てのページに、3クリック以内で到達できる構造を目指します。
階層が深すぎると、クローラーが到達しにくくなり、インデックスが遅れる原因になります。
| 改善ポイント | 具体的な施策 | 効果 |
| パンくずリストの設置 | サイトの階層構造を明示 | クローラビリティ向上 |
| 関連記事の紹介 | コンテンツ間の関連性を示す | 回遊率向上 |
| グローバルナビゲーション | 主要ページへの導線確保 | アクセス性向上 |
| フッターリンク | サイト全体からのアクセス | 孤立ページの防止 |
| サイドバーリンク | 重要ページの露出増加 | インデックス促進 |
内部リンクを設置する際は、リンクテキスト(アンカーテキスト)にも注意が必要です。
「こちら」や「詳細はこちら」といった曖昧な表現ではなく、「検索順位を上げる方法」のように、リンク先の内容が具体的にわかる文言を使いましょう。
これにより、クローラーとユーザーの両方がリンク先の内容を理解しやすくなります。
また、孤立したページ(他のページからリンクされていないページ)がないか定期的にチェックすることも重要です。
サーチコンソールの「リンク」レポートを見ると、各ページへの内部リンク数を確認できます。
内部リンクが0のページは、クローラーが発見しにくい状態になっているため、適切なページから内部リンクを追加しましょう。
内部リンクの最適化は、一度行えば終わりではなく、サイトの成長に合わせて継続的に見直していく必要があります。
新しいコンテンツを追加するたびに、既存のコンテンツとの関連性を考え、適切なリンクを設置する習慣をつけましょう。
サイトマップXMLの作成と設置
前述のサイトマップ送信の章でも触れましたが、XMLサイトマップはクローラーの巡回効率を高める重要なファイルです。
ここでは、XMLサイトマップの具体的な作成方法と、設置後の管理方法について詳しく解説します。
XMLサイトマップは、サイト内の全ページのURLと、その優先度や更新頻度などの情報をXML形式で記述したファイルです。
このファイルをGoogleサーチコンソールから送信することで、クローラーがサイト構造を理解しやすくなります。
WordPressサイトの場合、XMLサイトマップの作成は非常に簡単です。
前述したプラグインのいずれかをインストールして有効化するだけで、自動的にXMLサイトマップが生成され、さらに自動更新もされます。
静的なHTMLサイトの場合は、オンラインのXMLサイトマップ生成ツールを使用します。
- sitemap.xml Editor(日本語対応、無料)
- XML-Sitemaps.com(英語、1,000ページまで無料)
- Screaming Frog SEO Spider(デスクトップツール、500URLまで無料)
これらのツールにサイトのURLを入力すると、自動的にサイトをクロールしてXMLサイトマップを生成してくれます。
生成されたXMLファイルをダウンロードし、FTPソフトなどでサイトのルートディレクトリにアップロードします。
XMLサイトマップを設置したら、必ずGoogleサーチコンソールから送信しましょう。
送信方法は前述の通り、サーチコンソールの「サイトマップ」メニューから行います。
送信後、ステータスが「成功しました」になっていれば、Googleに正しく認識されています。
ただし、先述の通り、XMLサイトマップが必須なのは大規模サイトや特殊な構造のサイトです。
ページ数が500ページ未満の中小規模サイトで、内部リンクが適切に設置されている場合は、XMLサイトマップがなくてもクローラーは十分に巡回できます。
それでも、あって損はないため、可能であれば設置しておくことをおすすめします。
XMLサイトマップは、サイトの更新に合わせて定期的に更新する必要があります。
WordPressプラグインを使用している場合は自動更新されますが、手動で作成した場合は、新しいページを追加するたびにサイトマップも更新しましょう。
株式会社エッコでは、サイト構造の最適化からXMLサイトマップの設定まで、トータルでサポートしています。
技術的な部分でお困りの場合は、お気軽にご相談ください。
コンテンツ品質の改善方法
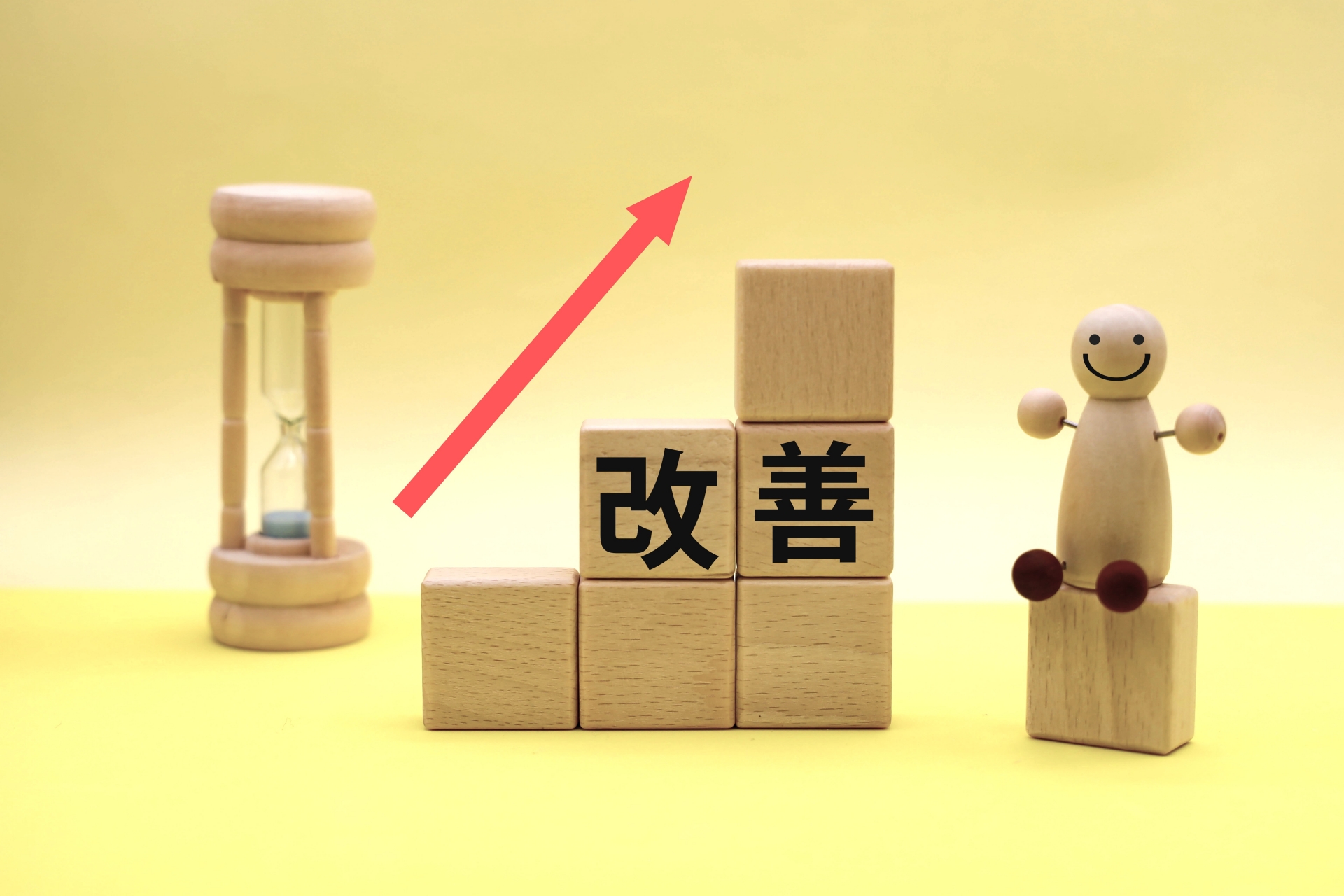
インデックスされても検索結果の上位に表示されなければ、ユーザーにサイトを見てもらうことはできません。
検索順位を決定する最も重要な要素が、コンテンツの品質です。
Googleは「ユーザーにとって最も有益な情報を提供するページを上位表示する」という方針を明確にしています。
そのため、高品質なコンテンツを作成することが、SEO対策の本質といえます。
ここでは、コンテンツ品質を改善するための具体的な方法を4つの観点から解説します。
どれも重要な要素なので、一つずつ丁寧に取り組んでいきましょう。
検索意図に沿ったコンテンツ作成
検索意図とは、ユーザーがそのキーワードで検索した時に「何を知りたいのか」「何を解決したいのか」という目的のことです。
検索意図を正しく理解し、それに応えるコンテンツを作成することが、SEO成功の最重要ポイントです。
どんなに文章が上手でも、ユーザーの求める情報がなければ、そのページは評価されません。
検索意図を理解するための最も効果的な方法は、実際にそのキーワードで検索して、上位表示されているページを分析することです。
上位に表示されているページは、Googleが「このキーワードで検索するユーザーにとって有益」と判断したページです。
つまり、上位ページに共通する要素が、そのキーワードの検索意図を表しているといえます。
上位10サイトを確認し、以下の点をチェックしましょう。
- どのような構成になっているか
- どのような見出しが使われているか
- どのような情報が含まれているか
- どのような切り口で説明しているか
- 図表や画像はどのように使われているか
共通して含まれている情報は、ユーザーが求めている必須の情報です。
これらを漏れなく自社のコンテンツに盛り込みましょう。
ただし、単純にコピーするのではなく、自社ならではの視点や情報を加えることが重要です。
検索意図には、大きく分けて4つのタイプがあります。
| 検索意図のタイプ | ユーザーの目的 | キーワード例 | コンテンツの方向性 |
| Know(知りたい) | 情報や知識を得たい | 〇〇とは、〇〇方法 | 詳しい解説記事 |
| Go(行きたい) | 特定のサイトに行きたい | 企業名、ブランド名 | 公式サイト |
| Do(したい) | 何かを実行したい | 〇〇方法、〇〇やり方 | ハウツー記事 |
| Buy(買いたい) | 商品を購入したい | 〇〇通販、〇〇価格 | 商品ページ、比較記事 |
キーワードごとに主要な検索意図が異なるため、それぞれに適したコンテンツを用意する必要があります。
例えば、「SEO対策 方法」というキーワードなら、具体的な実践方法を詳しく解説する記事が求められます。
一方、「SEOとは」なら、SEOの基本概念をわかりやすく説明する初心者向けの記事が適しています。
また、1つのキーワードに複数の検索意図が含まれることもあります。
その場合は、主要な検索意図をメインに据えつつ、副次的な意図にも対応できる包括的なコンテンツを作成しましょう。
検索意図に沿ったコンテンツ作成は、ユーザー満足度を高めるだけでなく、直帰率の低下や滞在時間の増加にもつながります。
これらのユーザー行動データもGoogleの評価要素となるため、結果的に検索順位の向上につながります。
オリジナリティの確保
Googleは2017年のアップデートで、独自性のあるコンテンツを高く評価する方針を明確に打ち出しました。
他のサイトにある情報をまとめただけのページではなく、オリジナルの情報や独自の視点を含むページが上位表示されやすくなっています。
特に競合が多いキーワードでは、オリジナリティの有無が順位を大きく左右します。
オリジナリティを出すためには、以下のような方法が効果的です。
まず最も強力なのが、自社独自の調査データやアンケート結果を掲載することです。
一次情報は他のサイトが真似できないため、非常に高い価値を持ちます。
自社の顧客やユーザーにアンケートを実施し、その結果をコンテンツに盛り込みましょう。
- 自社で実施したアンケート調査の結果
- 実際に試した商品やサービスのレビュー
- 業務経験から得られた実践的なノウハウ
- 専門家としての独自の見解や考察
- 顧客事例や成功事例(許可を得た上で)
- 業界のトレンド分析や将来予測
また、実体験に基づく情報も強力なオリジナリティになります。
「実際にこの方法を試したところ、〇〇という結果になった」という具体的な体験談は、他のサイトには書けない情報です。
可能な限り、自分自身や自社の経験を記事に盛り込みましょう。
専門知識を持つ企業であれば、その専門性を活かした深い考察や分析を加えることも有効です。
表面的な情報をまとめるだけでなく、「なぜそうなるのか」「どうすればより良くなるのか」といった深い洞察を提供しましょう。
ただし、オリジナリティを意識しすぎて、事実と異なる情報や根拠のない主張を書くのは厳禁です。
オリジナリティは「独自性」であって「独自性」ではありません。
正確性と信頼性を保ちながら、自社ならではの情報を加えることが重要です。
画像や図表も、オリジナリティを出す有効な手段です。
他サイトからの引用画像ではなく、自社で作成したオリジナルの図解やグラフを使用することで、視覚的なオリジナリティも高まります。
複雑な概念を説明する際は、独自の図解を作成することをおすすめします。
名古屋を拠点とする株式会社エッコでは、地域企業の強みを活かしたオリジナルコンテンツの企画・制作をサポートしています。
自社の経験や知見を効果的にコンテンツ化する方法について、お気軽にご相談ください。
ユーザーにとって有益な情報提供
検索エンジン最適化(SEO)の本質は、検索エンジンを騙すことではなく、ユーザーにとって本当に役立つ情報を提供することです。
Googleのアルゴリズムは年々進化しており、小手先のテクニックではなく、真にユーザーのためになるコンテンツを評価するようになっています。
ユーザーにとって有益なコンテンツとは、具体的にどのようなものでしょうか。
最も重要なのは、ユーザーの疑問や悩みを完全に解決できる情報が含まれていることです。
部分的な答えではなく、そのページを読めば問題が解決するという包括的な内容が求められます。
また、情報の正確性と信頼性も欠かせません。
間違った情報や古い情報では、ユーザーに不利益を与えてしまう可能性があります。
情報源を明示し、最新のデータに基づいた内容を提供しましょう。
| 有益なコンテンツの条件 | 具体的な実践方法 |
| 完全性 | 一つの記事で疑問が解決する網羅的な内容 |
| 正確性 | 信頼できる情報源からのデータを引用 |
| 最新性 | 定期的に情報を更新し、古い内容を修正 |
| 具体性 | 抽象的な表現を避け、具体例を豊富に掲載 |
| 実用性 | すぐに実践できる手順やノウハウを提供 |
| わかりやすさ | 専門用語を避け、平易な言葉で説明 |
読みやすさも重要な要素です。
どんなに有益な情報でも、読みにくければユーザーは途中で離脱してしまいます。
適度に見出しを設けて内容を区切り、箇条書きや表を活用して視認性を高めましょう。
また、文章だけでなく、図解や画像、動画などを組み合わせることで、より理解しやすいコンテンツになります。
特に専門的な内容や手順の説明では、スクリーンショットや図解を用いることで、テキストだけでは伝わりにくい情報を補完できます。
初心者にもわかりやすく、専門家も納得できる深い内容を目指すことが理想です。
基本的な説明から始めて、徐々に詳しい内容に進むという構成にすると、幅広い読者に対応できます。
また、ユーザーが求めている情報を素早く見つけられるよう、目次を設置することも効果的です。
特に長文の記事では、目次から該当箇所へジャンプできる機能があると、ユーザビリティが大幅に向上します。
信頼性を高めるためには、著者情報を明記することも重要です。
誰が書いた記事なのか、その人物や企業にどのような専門性があるのかを示すことで、コンテンツの信頼性が高まります。
特に医療や金融など、専門性が求められる分野では、著者の資格や実績を明示することが推奨されています。
さらに、情報の出典を明確にすることも信頼性向上につながります。
統計データや調査結果を引用する際は、必ず情報源を記載しましょう。
公的機関や信頼できる企業、学術論文などからの引用であることを示すことで、記事全体の信頼性が向上します。
ユーザーの滞在時間や再訪問率なども、Googleがコンテンツの品質を判断する際の参考にしていると考えられています。
ユーザーにとって本当に役立つコンテンツを作成することで、これらの指標も自然と改善していきます。
重複コンテンツの解消
重複コンテンツとは、同じ内容または非常に似た内容が複数のページに存在する状態を指します。
重複コンテンツがあると、Googleはどのページを検索結果に表示すべきか判断できず、結果的にどちらのページも表示されなくなる可能性があります。
意図的なコピーコンテンツだけでなく、意図せず重複してしまうケースも多いため注意が必要です。
重複コンテンツが発生する典型的なパターンには以下のようなものがあります。
まず、URLのバリエーションによる重複です。
「http://example.com」と「https://example.com」、「www.example.com」と「example.com」など、異なるURLで同じコンテンツにアクセスできる場合、Googleは別々のページとして認識してしまいます。
また、ECサイトでは商品の並び替えやフィルタリング機能によって、同じ商品が複数のURLで表示されることがあります。
- URLのバリエーション(http/https、www有無など)
- URLパラメータによる重複(?page=1、?sort=priceなど)
- PCページとモバイルページの分離
- プリントページや印刷用ページ
- 内容が酷似している複数の記事
Googleサーチコンソールの「カバレッジ」レポートで「重複しています。ユーザーにより、正規ページとして選択されていません」と表示されたページは、重複コンテンツとして判定されています。
重複コンテンツを解消する方法はいくつかあります。
最も推奨される方法は、canonicalタグを使用することです。
canonicalタグは、「このページの正規版はこちらです」とGoogleに伝えるためのタグです。
重複しているページのHTMLの<head>セクション内に、以下のようなタグを追加します。
「<link rel=”canonical” href=”https://example.com/正規ページのURL”>」
このタグを設置することで、Googleは指定されたURLを正規版として認識し、検索結果にはそのページを優先的に表示するようになります。
| 重複コンテンツの対処法 | 使用場面 | 効果 |
| canonicalタグ | 内容が似ているページ | 正規URLを指定 |
| 301リダイレクト | 完全に統合する場合 | 恒久的な転送 |
| noindexタグ | 検索に出したくないページ | インデックス拒否 |
| URLの統一 | URLのバリエーション対策 | 根本的な解決 |
| コンテンツの書き直し | 似た記事の差別化 | オリジナリティ確保 |
URLのバリエーションによる重複は、.htaccessファイルやサーバー設定でリダイレクトを設定することで解消できます。
例えば、wwwなしのURLに統一する場合は、wwwありのURLにアクセスしたら自動的にwwwなしのURLにリダイレクトする設定を行います。
内容が似ている複数の記事がある場合は、記事を統合するか、それぞれの記事に独自性を持たせる必要があります。
統合する場合は、情報量が多い方の記事に一本化し、もう一方の記事から301リダイレクトを設定します。
それぞれを残す場合は、切り口や対象読者を変えて、明確に差別化しましょう。
ECサイトのようにURLパラメータが多いサイトでは、Googleサーチコンソールの「URLパラメータ」機能を使って、パラメータの扱い方をGoogleに指示することもできます。
ただし、この機能は上級者向けなので、不安な場合は専門家に相談することをおすすめします。
重複コンテンツの問題は、サイトが大きくなるにつれて複雑化していきます。
定期的にサイト全体をチェックし、不要な重複がないか確認する習慣をつけましょう。
ペナルティ対策と解除方法

Googleペナルティは、検索結果に表示されなくなる原因の中でも特に深刻なものです。
ペナルティを受けると、一夜にしてサイトへのアクセスが激減する可能性があります。
しかし、適切な対処を行えば、多くの場合はペナルティを解除できます。
ここでは、ペナルティの種類と確認方法、そして解除に至るまでの具体的な手順を詳しく解説します。
万が一ペナルティを受けてしまった場合でも、冷静に対処すれば必ず解決できます。
焦らず、一つずつ確実に対策を進めていきましょう。
ペナルティの種類と確認方法
Googleペナルティには、大きく分けて「手動ペナルティ」と「アルゴリズムペナルティ」の2種類があります。
それぞれ原因も対処法も異なるため、まずは自社サイトがどちらのペナルティを受けているのかを正確に判断する必要があります。
ペナルティの種類によって、通知の有無や解除までの手順が大きく変わってきます。
また、ペナルティと単なる順位低下を混同しないことも重要です。
検索順位が下がったからといって、必ずしもペナルティを受けているとは限りません。
アルゴリズムの変更や競合サイトの成長によって順位が下がることもあります。
ペナルティかどうかを判断するには、まずGoogleサーチコンソールを確認しましょう。
手動ペナルティを受けている場合は、必ずサーチコンソールに通知が届きます。
一方、アルゴリズムペナルティの場合は通知がないため、状況から判断する必要があります。
手動ペナルティ
手動ペナルティは、Googleの担当者が目視でサイトを確認し、ガイドライン違反があると判断した場合に課されるペナルティです。
手動ペナルティを受けると、Googleサーチコンソールの「手動による対策」レポートに通知が届きます。
そのため、手動ペナルティは比較的発見しやすいという特徴があります。
手動ペナルティの通知には、違反の種類と対象範囲が記載されています。
対象範囲は「サイト全体」の場合と「一部のページ」の場合があり、サイト全体へのペナルティの方が当然ながら影響が大きくなります。
手動ペナルティの主な種類と原因は以下の通りです。
| ペナルティの種類 | 主な原因 | 影響範囲 | 深刻度 |
| 不自然なリンク | 有料リンクの購入、大量の相互リンク | サイト全体または一部 | 非常に高い |
| 価値のない質の低いコンテンツ | 自動生成コンテンツ、内容の薄いページ | サイト全体 | 高い |
| クローキング | 検索エンジンとユーザーで異なる内容表示 | 該当ページ | 非常に高い |
| 不正なリダイレクト | 意図的な誤誘導 | 該当ページ | 高い |
| 隠しテキスト・リンク | 背景色と同色の文字、極小文字 | 該当ページ | 高い |
| キーワードの乱用 | 不自然なキーワードの詰め込み | 該当ページ | 中程度 |
手動ペナルティを確認するには、Googleサーチコンソールにログインし、左メニューから「セキュリティと手動による対策」→「手動による対策」を選択します。
「問題は検出されませんでした」と表示されていれば、手動ペナルティは受けていません。
何らかの問題が検出されている場合は、具体的な違反内容と、影響を受けているページのリストが表示されます。
通知には「例」として、問題があると判断されたページのURLも記載されることがあります。
手動ペナルティは、適切に対処して再審査リクエストを送信することで解除できます。
ただし、問題を完全に解決していない状態でリクエストを送ると、却下されてしまうため注意が必要です。
再審査リクエストの方法については、後述の「再審査リクエストの方法」で詳しく解説します。
手動ペナルティは深刻ですが、通知が来るため発見しやすく、また適切に対処すれば確実に解除できるという点では、むしろ対処しやすいペナルティといえます。
アルゴリズムペナルティ
アルゴリズムペナルティは、Googleの検索アルゴリズムによって自動的に判定されるペナルティです。
手動ペナルティと異なり、通知が一切届かないため、突然の順位下落によって初めて気づくことが多いという特徴があります。
アルゴリズムペナルティは、厳密にはペナルティというよりも、アルゴリズムの基準を満たさなくなったことによる評価の低下です。
しかし、実質的には検索結果から消えてしまうこともあるため、ペナルティと呼ばれています。
アルゴリズムペナルティの原因として代表的なものには以下があります。
低品質なコンテンツ、薄いコンテンツ、重複コンテンツなどがまず挙げられます。
Googleのパンダアップデートと呼ばれるアルゴリズムが、これらの問題を検出して順位を下げます。
また、不自然なリンクもアルゴリズムペナルティの原因になります。
- 低品質なコンテンツ(パンダアップデート対象)
- 不自然な被リンク(ペンギンアップデート対象)
- モバイルフレンドリーでない(モバイルアップデート対象)
- ページ速度が遅い(スピードアップデート対象)
- ユーザーエクスペリエンスが悪い(コアウェブバイタル対象)
アルゴリズムペナルティを受けているかどうかを判断するのは、手動ペナルティよりも難しいです。
主な判断材料は、検索順位の急激な変動です。
特に、Googleがコアアルゴリズムアップデートを実施したタイミングで順位が大幅に下落した場合は、アルゴリズムペナルティの可能性が高いといえます。
Googleは年に数回、大規模なアルゴリズムアップデートを実施しています。
これらのアップデート情報は、Googleの公式ブログやSEO関連のニュースサイトで確認できます。
自社サイトの順位が大きく変動した時期と、アルゴリズムアップデートの時期が一致していないか確認しましょう。
アルゴリズムペナルティの解除は、手動ペナルティよりも時間がかかることが多いです。
なぜなら、再審査リクエストという仕組みがなく、サイトを改善してから、次回のクロールとアルゴリズム評価を待つしかないためです。
問題のあるコンテンツを改善し、サイト全体の品質を高めることで、徐々に順位が回復していきます。
ただし、改善の効果が現れるまでには数週間から数ヶ月かかることもあります。
アルゴリズムペナルティは予防が最も重要です。
日頃からGoogleのガイドラインに沿った運営を心がけ、ユーザーファーストのコンテンツ作りを継続することが、最大の対策となります。
ペナルティ解除の手順
ペナルティを受けてしまった場合、適切な手順で対処することで解除できます。
焦って不完全な対処をするよりも、時間をかけてでも確実に問題を解決することが重要です。
ここでは、ペナルティ解除に向けた具体的な手順を段階的に解説します。
まず最初に行うべきは、ペナルティの原因を正確に特定することです。
手動ペナルティの場合は、Googleサーチコンソールの通知に原因が記載されているので、それを確認します。
アルゴリズムペナルティの場合は、サイトの問題点を自分で見つける必要があります。
原因が特定できたら、その問題を完全に解決します。
「完全に」というのがポイントで、中途半端な対処では再審査に通らないか、順位が回復しません。
例えば、不自然なリンクが原因の場合は、問題のあるリンクをすべて削除するか、リンク否認ツールで無効化する必要があります。
| ペナルティ解除の手順 | 具体的なアクション | 所要時間 |
| 1. 原因の特定 | サーチコンソール確認、サイト分析 | 1〜3日 |
| 2. 問題の完全解決 | 該当ページ修正、リンク削除など | 1週間〜1ヶ月 |
| 3. 再審査リクエスト(手動のみ) | サーチコンソールから申請 | 即日 |
| 4. 審査結果の確認 | Googleからの回答待ち | 数日〜数週間 |
| 5. 追加対応(必要な場合) | 不足している対処の実施 | 状況による |
不自然なリンクが原因の場合、まずはリンク元のサイト管理者に連絡してリンクの削除を依頼します。
連絡しても削除してもらえない場合や、連絡先が不明な場合は、Googleのリンク否認ツールを使用します。
リンク否認ツールは、Googleに対して「このリンクは評価しないでください」と伝えるツールです。
サーチコンソールの「リンク否認」機能から、否認したいリンクのリストをアップロードします。
低品質なコンテンツが原因の場合は、該当するページの内容を大幅に改善するか、削除します。
内容が薄いページは統合して情報量を増やすか、十分な情報量を持つページに作り直します。
どうしても改善が難しいページは、思い切って削除することも選択肢の一つです。
重複コンテンツが原因の場合は、前述した方法でcanonicalタグを設定するか、コンテンツを書き直して差別化します。
完全に同じ内容のページがある場合は、一方を削除して301リダイレクトを設定しましょう。
問題をすべて解決したら、その内容をドキュメントにまとめておくことをおすすめします。
どのような問題があって、どのように対処したかを記録しておくと、再審査リクエストの際に役立ちます。
また、同じ問題を繰り返さないための予防策にもなります。
名古屋を拠点とする株式会社エッコでは、ペナルティ診断から解除サポートまで、専門的な支援を提供しています。
自社だけでは対処が難しい場合は、早めに専門家に相談することで、解除までの時間を短縮できます。
再審査リクエストの方法
手動ペナルティを受けた場合、問題を解決した後に「再審査リクエスト」を送信する必要があります。
再審査リクエストとは、問題を解決したことをGoogleに報告し、ペナルティの解除を依頼する手続きです。
適切な再審査リクエストを送ることで、ペナルティを解除してもらえる可能性が高まります。
再審査リクエストを送る前に、問題が完全に解決されていることを再度確認してください。
不完全な状態でリクエストを送ると却下されてしまい、再度リクエストを送るまでに時間がかかってしまいます。
特に以下の点を入念にチェックしましょう。
該当するすべてのページで問題が解決されているか、同様の問題が他のページにも存在していないか、今後同じ問題が発生しないような対策を講じたかなどです。
- 指摘されたすべてのページで問題を解決したか
- 他のページにも同様の問題がないか確認したか
- 原因となった手法や方針を根本的に改めたか
- 今後同じ問題が発生しない仕組みを作ったか
確認が済んだら、Googleサーチコンソールから再審査リクエストを送信します。
「手動による対策」レポートを開き、該当する問題の「審査をリクエスト」ボタンをクリックします。
すると、テキストボックスが表示されるので、そこに対応内容を記入します。
再審査リクエストの文章は、具体的で誠実な内容にすることが重要です。
どのような問題があったのか、それをどのように解決したのか、今後の再発防止策は何かを、明確に説明しましょう。
テンプレート的な文章や、責任転嫁するような内容は避けてください。
| 再審査リクエストに記載すべき内容 | 具体例 |
| 問題の認識 | 「不自然なリンクの問題を確認しました」 |
| 調査内容 | 「バックリンクを全件確認し、215件の問題リンクを特定」 |
| 対処内容 | 「リンク元に削除依頼、応答なし113件は否認ツールで対応」 |
| 再発防止策 | 「リンク構築の方針を見直し、社内ガイドラインを策定」 |
| 今後の姿勢 | 「ガイドラインを遵守し、質の高いコンテンツ作成に注力」 |
文章の長さは、問題の深刻さや対応の複雑さに応じて調整します。
簡単な問題なら数行でも構いませんが、深刻な問題の場合は詳細に説明した方が好印象です。
ただし、冗長にならないよう、要点を押さえた簡潔な文章を心がけましょう。
再審査リクエストを送信すると、通常は数日から数週間で審査結果が届きます。
審査結果はGoogleサーチコンソールのメッセージとして通知されます。
承認されれば、ペナルティは解除され、サイトは正常に検索結果に表示されるようになります。
却下された場合は、対応が不十分だったということです。
却下の理由が記載されているので、それを参考に追加の対応を行い、再度リクエストを送信します。
再審査リクエストは何度でも送信できますが、不完全な状態で何度も送るのは避けましょう。
Googleの審査担当者の心証を悪くする可能性があります。
確実に問題を解決してから、自信を持ってリクエストを送ることが大切です。
なお、アルゴリズムペナルティには再審査リクエストの仕組みがありません。
問題を解決してクローラーが再訪問するのを待ち、アルゴリズムによる再評価を待つしかありません。
これには数週間から数ヶ月かかることもあるため、根気強く待つ必要があります。
新規サイトの検索表示を早める方法

新規にサイトを公開した場合、通常のプロセスではインデックスされるまでに時間がかかります。
しかし、いくつかの施策を組み合わせることで、検索結果への表示を早めることができます。
ここでは、新規サイトが検索エンジンに早く認識され、インデックスされるための効果的な方法を3つ紹介します。
これらの方法は、新規サイトだけでなく、既存サイトに新しいページを追加した場合にも有効です。
積極的に活用して、サイトの立ち上げ期間を短縮しましょう。
インデックス登録リクエストの活用
新規サイトで最も効果的な方法は、Googleサーチコンソールからインデックス登録をリクエストすることです。
前述したURL検査ツールの機能を使えば、Googleに対して直接「このページをインデックスしてください」と依頼できます。
この方法を使うことで、自然にクローラーが訪問するのを待つよりも、大幅に時間を短縮できます。
新規サイトを公開したら、まずはGoogleサーチコンソールに登録しましょう。
登録方法は前述の通りです。
登録が完了したら、すぐにトップページのインデックス登録をリクエストします。
トップページがインデックスされれば、そこからリンクを辿って他のページも発見されやすくなります。
優先的にインデックスさせたいページの順番は以下の通りです。
| 優先順位 | ページの種類 | 理由 |
| 最優先 | トップページ | サイトの入り口、他ページへの導線 |
| 高 | 主要カテゴリページ | サイト構造の骨格 |
| 高 | 重要な商品・サービスページ | コンバージョンに直結 |
| 中 | 詳細コンテンツページ | 情報の充実度を示す |
| 低 | お問い合わせ・会社概要など | 必要だが優先度は低め |
すべてのページを一度にリクエストする必要はありません。
インデックス登録リクエストには1日あたりの上限があるため、重要なページから順番にリクエストしていきましょう。
トップページがインデックスされ、内部リンクが適切に設置されていれば、他のページも自然とクロールされていきます。
リクエストを送信してから実際にインデックスされるまでには、通常数時間から数日かかります。
気長に待ちながら、サイトのコンテンツを充実させていきましょう。
また、XMLサイトマップの送信も同時に行うことをおすすめします。
サイトマップを送信しておけば、個別にリクエストしなかったページも、クローラーが効率的に発見してくれます。
新規サイトの場合、最初の1〜2週間は頻繁にサーチコンソールをチェックして、インデックス状況を確認しましょう。
エラーや警告が出ていないか、順調にページがインデックスされているかを把握することで、早期に問題を発見できます。
被リンク獲得による認知拡大
検索エンジンのクローラーは、既存のサイトからリンクを辿って新しいサイトを発見します。
そのため、他のサイトから被リンクを獲得することで、クローラーに発見されやすくなり、インデックスが早まります。
また、質の高い被リンクは、サイトの信頼性を示すシグナルとしても機能します。
新規サイトでも獲得しやすい被リンクには、いくつかの種類があります。
まず最も確実なのは、自社が運営する他のメディアやSNSアカウントからのリンクです。
既存のブログやメディアがあれば、そこから新サイトへリンクを設置しましょう。
外部からの被リンクを獲得する方法としては、以下のようなものがあります。
- Googleビジネスプロフィールへの登録
- 業界団体や商工会議所のサイトへの掲載
- プレスリリースの配信
- 関連する企業やパートナーサイトへの掲載依頼
- 地域情報サイトやポータルサイトへの登録
- 取引先や顧客企業のサイトからのリンク
特に新規サイトの立ち上げ初期に効果的なのが、プレスリリースの配信です。
プレスリリース配信サービスを利用すれば、多数のメディアサイトに情報が掲載され、そこからのリンクが獲得できます。
ただし、被リンクを獲得する際は、量よりも質を重視することが重要です。
関連性が低いサイトや、明らかにSEO目的だけのリンクは、逆効果になる可能性があります。
自然な形で、自社と関連性のあるサイトからリンクを獲得することを心がけましょう。
また、リンクの購入や、大量の相互リンクなど、Googleのガイドラインに違反する方法は絶対に使用しないでください。
短期的には効果があるように見えても、後でペナルティを受けるリスクが非常に高いです。
名古屋エリアの企業であれば、地域の商工会議所や業界団体に加入することで、自然な被リンクを獲得できることがあります。
株式会社エッコでも、地域企業のネットワークを活かした被リンク戦略のご提案が可能です。
被リンクの獲得は、新規サイトの立ち上げ期だけでなく、サイト運営全体を通じて継続的に取り組むべき施策です。
焦らず、着実に質の高いリンクを増やしていきましょう。
SNSでの拡散
SNSでの情報発信は、直接的なSEO効果は限定的ですが、サイトの認知度を高め、間接的にインデックスやアクセスの増加に貢献します。
特に新規サイトの場合、SNSを通じてサイトの存在を広く知ってもらうことで、自然な被リンクやアクセスの獲得につながります。
主要なSNSプラットフォームには、それぞれ特徴があります。
自社のターゲット層が多く利用しているプラットフォームを中心に活用しましょう。
X(旧Twitter)は情報の拡散スピードが速く、リアルタイム性が高いのが特徴です。
新しい記事を公開したらすぐに投稿することで、早期のアクセス獲得が期待できます。
Facebookは幅広い年齢層にリーチでき、特にビジネス向けの情報発信に適しています。
企業ページを作成し、定期的に更新情報を発信しましょう。
| SNSプラットフォーム | 主なユーザー層 | 活用方法 | 期待効果 |
| X(旧Twitter) | 20〜40代、情報感度高 | 記事公開の即時告知 | 拡散による認知拡大 |
| 30〜50代、幅広い | コミュニティ形成 | 継続的な関係構築 | |
| 20〜30代、ビジュアル重視 | 画像・動画での訴求 | ブランドイメージ向上 | |
| ビジネスパーソン | 専門的な情報発信 | B2B向けリーチ | |
| YouTube | 全年代 | 動画コンテンツ | 詳しい情報提供 |
Instagramは視覚的な訴求力が高く、商品やサービスのイメージを伝えるのに適しています。
ストーリーズ機能を使ってサイトへのリンクを設置することもできます。
LinkedInはB2B向けビジネスに特に有効で、専門的な記事の共有や業界内での認知度向上に役立ちます。
YouTubeは動画を通じて詳しい情報を提供でき、動画の説明欄にサイトへのリンクを設置できます。
SNSでの拡散を効果的に行うには、いくつかのポイントがあります。
まず、定期的かつ継続的に投稿することが重要です。
不定期な投稿では、フォロワーの関心を維持することが難しくなります。
投稿内容は、単なるサイトへの誘導だけでなく、SNS上で完結する有益な情報も含めましょう。
ユーザーにとって価値のある情報を提供し続けることで、自然とフォロワーが増え、拡散力も高まります。
また、ハッシュタグを適切に活用することで、自社のフォロワー以外にもリーチを広げられます。
関連性の高いハッシュタグを選び、投稿に含めましょう。
ただし、過剰なハッシュタグの使用は逆効果になるため、3〜5個程度に抑えることをおすすめします。
SNSでの拡散は、新規サイトの立ち上げ時だけでなく、継続的なサイト運営においても重要な施策です。
質の高いコンテンツを作成し、SNSを通じて積極的に発信していくことで、サイトの成長を加速できます。
検索表示までの期間と注意点

サイトが検索結果に表示されるまでの期間は、様々な要因によって変動します。
焦って誤った対策を行うよりも、適切な期間を理解し、正しい方向で継続的に取り組むことが重要です。
ここでは、一般的な期間の目安と、その間に注意すべきポイントを解説します。
特に新規サイトの場合は、結果が出るまでに時間がかかることを理解し、焦らず着実に対策を進めることが成功への近道です。
通常の反映期間の目安
サイトやページが検索結果に表示されるまでの期間は、状況によって大きく異なります。
最も早いケースでは数時間、遅い場合は数週間かかることもあります。
一般的な目安としては、新規ページのインデックスには1日から1週間程度かかると考えておくとよいでしょう。
インデックス登録までの期間に影響を与える主な要因は以下の通りです。
まず、サイトの年齢や信頼性が大きく影響します。
運営歴が長く、定期的に更新されているサイトは、クローラーの巡回頻度が高いため、新しいページも早くインデックスされます。
一方、新規サイトや更新頻度の低いサイトは、クローラーの訪問頻度が低いため、時間がかかりやすくなります。
| サイトの状態 | インデックス期間の目安 | 上位表示までの期間 |
| 既存の評価されているサイト | 数時間〜数日 | 数週間〜数ヶ月 |
| 新規サイト | 1週間〜2週間 | 3ヶ月〜6ヶ月 |
| 更新頻度の低いサイト | 1週間〜数週間 | 数ヶ月〜1年 |
| ペナルティ履歴のあるサイト | 数週間〜数ヶ月 | 半年〜1年以上 |
外部リンクの数と質も、インデックス速度に影響します。
信頼性の高いサイトからのリンクがあるページは、クローラーが早く発見しやすくなります。
また、サイト内の内部リンク構造も重要です。
トップページから2〜3クリックで到達できるページは、クローラーに発見されやすく、インデックスも早まります。
深い階層にあるページや、内部リンクがほとんどないページは、発見されるまでに時間がかかります。
コンテンツの品質も、インデックス速度に影響を与える可能性があります。
高品質で独自性のあるコンテンツは、Googleが優先的にインデックスする傾向があります。
逆に、低品質と判断されたページは、クロールされてもインデックスされないことがあります。
Googleサーチコンソールからインデックス登録をリクエストした場合は、通常よりも早くインデックスされることが多いです。
リクエストから数時間で反映されることもあれば、数日かかることもあります。
ただし、インデックスされることと、検索結果の上位に表示されることは別の話です。
インデックスは比較的早く行われますが、上位表示されるまでには、さらに時間がかかります。
新規サイトの場合、キーワードにもよりますが、上位表示までには3ヶ月から6ヶ月、場合によっては1年以上かかることも珍しくありません。
これは、Googleがサイトの信頼性を評価するのに時間がかかるためです。
焦らず、継続的にコンテンツの質を高めていくことが重要です。
焦らず継続的に対策する重要性
SEO対策は、短期間で劇的な効果が出るものではありません。
長期的な視点を持ち、焦らず着実に対策を継続することが、最終的な成功につながります。
特に新規サイトの場合は、結果が出るまでに時間がかかることを理解し、途中で諦めずに取り組み続けることが大切です。
多くの企業が、SEO対策を始めて1〜2ヶ月で結果が出ないと、「効果がない」と判断して中止してしまいます。
しかし、これは非常にもったいないことです。
SEO対策の効果が本格的に現れ始めるのは、通常3ヶ月以降です。
継続的に対策を行っているサイトと、途中でやめてしまったサイトでは、半年後、1年後の成果に大きな差が生まれます。
焦りから間違った対策を実施してしまうことも避けなければなりません。
早く結果を出したいからといって、リンクの購入やキーワードの詰め込みなど、ブラックハットSEOと呼ばれる手法に手を出すのは絶対にやめましょう。
- 定期的なコンテンツの追加と更新
- サイト構造の継続的な最適化
- ユーザーフィードバックの反映
- 検索順位やアクセス数の定点観測
- 競合サイトの動向チェック
- Googleアルゴリズム更新への対応
継続的に対策を行う際は、PDCAサイクルを回すことが重要です。
施策を実施したら、その効果を測定し、うまくいった点は継続し、うまくいかなかった点は改善していきます。
この繰り返しによって、サイトは徐々に成長していきます。
効果測定には、Googleサーチコンソールやアクセス解析ツールを活用しましょう。
どのページへのアクセスが増えているか、どのキーワードで流入しているか、どのページの滞在時間が長いかなどを定期的にチェックします。
データに基づいて次の施策を決めることで、効率的に改善を進められます。
途中で結果が出ないように感じても、正しい方向で努力を続けていれば、必ず成果は現れます。
SEOは、一度軌道に乗れば、継続的に安定したアクセスをもたらしてくれる資産になります。
短期的な視点ではなく、長期的な資産構築だと考えて、地道に取り組んでいきましょう。
もし自社だけでは継続的な対策が難しい場合は、株式会社エッコのようなWebコンサルティング会社に相談することも一つの選択肢です。
専門家のサポートを受けることで、効率的に成果を出せる可能性が高まります。
まとめ

サイトが検索結果に表示されない原因は、インデックス登録の問題、クローラビリティの問題、ペナルティ、コンテンツ品質の問題など、様々なパターンがあります。
まずは現状を正確に把握し、原因を特定することが解決への第一歩です。
Googleサーチコンソールを活用することで、多くの問題は自分で診断できます。
原因が特定できたら、この記事で紹介した対処法を一つずつ実践していきましょう。
技術的な問題であれば、設定を修正するだけで解決することも多くあります。
コンテンツ品質の問題であれば、ユーザーにとって本当に価値のある情報を提供することを心がけてください。
検索エンジン最適化は、検索エンジンを騙すためのテクニックではありません。
ユーザーにとって有益なサイトを作ることこそが、最も重要なSEO対策です。
Googleのガイドラインに沿って、正しい方向で努力を続けていれば、必ずサイトは評価されるようになります。
新規サイトの場合は、結果が出るまでに時間がかかることを理解し、焦らず継続的に対策を行うことが大切です。
3ヶ月、半年、1年と時間をかけて、着実にサイトを成長させていきましょう。
もし自社だけでは対応が難しい、または早く確実に結果を出したいという場合は、専門家のサポートを受けることも検討してください。
名古屋を拠点とする株式会社エッコでは、検索結果に表示されない原因の診断から、具体的な改善施策の実施まで、トータルでサポートしています。
中小企業様の実情に合わせた現実的なご提案を心がけており、技術的な専門知識がない方でも安心してご相談いただけます。
地域密着型の企業だからこそ、きめ細かいサポートが可能です。
サイトの検索表示でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
あなたのサイトが検索結果に表示され、多くのユーザーに見てもらえる日が、一日でも早く訪れることを願っています。
この記事が、その実現の一助となれば幸いです。



