スマートフォンでGoogleアプリを開いたとき、検索していないのに興味のある記事が次々と表示された経験はありませんか?
それが「Google Discover」です。
従来の検索エンジンは、ユーザーがキーワードを入力して情報を探す「プル型」のサービスでした。
しかし、Google Discoverは、ユーザーの興味関心に基づいて自動的にコンテンツを届ける「プッシュ型」のサービスです。
この仕組みによって、Webサイト運営者は検索以外からも大量のトラフィックを獲得できるようになりました。
実際、一部のメディアサイトでは、Google Discoverからの流入が通常の検索流入を上回るケースも報告されています。
日本のSEO業界では「Google砲」とも呼ばれ、短期間で爆発的なアクセスを生み出す現象として注目を集めています。
本記事では、Google Discoverの基本的な仕組みから、表示されるための具体的な最適化方法まで、Webサイト運営者が知っておくべき情報を網羅的に解説します。
2025年の最新アップデート情報も含めて、実践的なノウハウをお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。
Index
Google Discoverとは

Google Discoverの概要と特徴
Google Discoverは、Googleが提供するパーソナライズされたコンテンツフィード機能です。
ユーザーの検索履歴、Webサイトの閲覧行動、位置情報などのデータをもとに、AIが興味のあるコンテンツを自動的に選んで表示します。
この機能は、2012年にリリースされた「Google Now」を起源とし、2016年には「Google Feed」へと進化しました。
そして2018年9月に現在の「Google Discover」へと名称が変更され、機能も大幅に拡張されています。
特に重要な変更点は、最新の記事だけでなく、ユーザーの興味関心にマッチすれば古いコンテンツも表示されるようになったことです。
この仕様変更により、過去に公開した記事であっても、突然大量のアクセスを獲得する可能性が生まれました。
2025年9月には、さらなるアップデートが実施され、InstagramやX(旧Twitter)の投稿、YouTube Shortsなど、Webサイトの記事以外のコンテンツも表示されるようになっています。
また、「Follow」機能が追加され、ユーザーが気に入ったパブリッシャーやクリエイターをフォローできるようになりました。
現在、Google Discoverの月間利用者数は8億人を超えており、Webマーケティングにおいて無視できない存在となっています。
| 項目 | 内容 |
| サービス開始 | 2012年(Google Nowとして) |
| 現在の名称に変更 | 2018年9月 |
| 月間利用者数 | 8億人以上 |
| 主な利用デバイス | スマートフォン、タブレット |
| 最新アップデート | 2025年9月(Follow機能、SNS投稿統合) |
| 利用可能地域 | 全世界(言語により機能差あり) |
通常のGoogle検索との違い
Google Discoverと通常のGoogle検索には、根本的な違いがあります。
最も大きな違いは、ユーザーが能動的にキーワードを入力するかどうかです。
通常のGoogle検索では、ユーザーが「東京 カフェ おすすめ」のように具体的なキーワードを入力して情報を探します。
一方、Google Discoverでは、ユーザーがキーワードを入力する必要がなく、アプリを開くだけで自動的にコンテンツが表示されます。
この違いは、コンテンツ制作者にとって重要な意味を持ちます。
通常の検索では特定のキーワードで上位表示を目指しますが、Discoverではユーザーの潜在的な興味を引きつけることが重要になります。
また、検索結果が比較的安定しているのに対し、Discoverの表示は流動的です。
検索順位は一度上位に表示されれば一定期間維持される傾向がありますが、Discoverでは表示されるコンテンツが常に入れ替わります。
実際の調査によると、Google Discoverに表示されたコンテンツの大半は、3〜4日間でトラフィックのピークを迎え、その後は急速に減少します。
トラフィックの大部分は、表示開始から1〜2日目に集中する傾向があります。
さらに、検索結果では検索クエリとの関連性が最重視されますが、Discoverでは「ユーザーの興味との一致度」と「コンテンツの新鮮さ」が重要な評価基準となります。
このため、SEO対策だけでなく、タイムリーな話題を取り上げることや、視覚的に魅力的なコンテンツを作成することが求められます。
| 比較項目 | Google検索 | Google Discover |
| ユーザーの行動 | キーワード入力が必要 | キーワード入力不要 |
| 表示のトリガー | 検索クエリ | 興味・関心データ |
| 評価の重点 | 検索クエリとの関連性 | ユーザーの興味との一致度 |
| トラフィックの持続性 | 比較的安定 | 短期集中型(3〜4日) |
| コンテンツの鮮度 | 鮮度は相対的に低い優先度 | 鮮度が高く評価される |
どこでDiscoverが利用できるか
Google Discoverは、主にモバイルデバイスで利用されるサービスです。
最も一般的な利用方法は、AndroidまたはiPhoneにGoogleアプリをインストールして使用することです。
Androidデバイスの場合、Googleアプリを開くか、一部の機種ではホーム画面を右にスワイプするだけでDiscoverのフィードが表示されます。
iPhoneやiPadでも、Googleアプリをインストールすれば同様にDiscoverを利用できます。
また、Google ChromeのモバイルブラウザでGoogle.comにアクセスした場合も、Discoverのフィードが表示されることがあります。
Discoverを利用するには、Googleアカウントにログインしている必要があります。
これは、Discoverがユーザーの検索履歴やWeb・アプリのアクティビティを分析して、パーソナライズされたコンテンツを表示するためです。
2023年12月頃からは、一部のユーザーに対してデスクトップ版のDiscoverも提供され始めていますが、基本的にはモバイルファーストの設計となっています。
Follow機能については、現在のところ以下の地域でのみ利用可能です。
Chrome Androidではアメリカ、ニュージーランド、南アフリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアの英語ユーザーが対象です。
Chrome iOSではアメリカの英語ユーザーのみが対象となっています。
日本のユーザーは、まだFollow機能を完全には利用できない状況ですが、今後の展開が期待されています。
名古屋のWebコンサルティング会社である株式会社エッコでは、Google Discoverへの最適化を含めた包括的なSEO支援を提供しています。
モバイルファーストの時代において、Discoverからのトラフィック獲得は重要な施策の一つです。
| デバイス・ブラウザ | 利用可否 | アクセス方法 |
| Android(Googleアプリ) | ○ | アプリを開く、またはホーム画面スワイプ |
| iPhone/iPad(Googleアプリ) | ○ | アプリを開く |
| Chrome モバイル | ○ | Google.comにアクセス |
| デスクトップブラウザ | △(一部ユーザーのみ) | Google.comにアクセス |
| Safari、Firefox等 | × | 非対応 |
Google Discoverに表示される仕組み
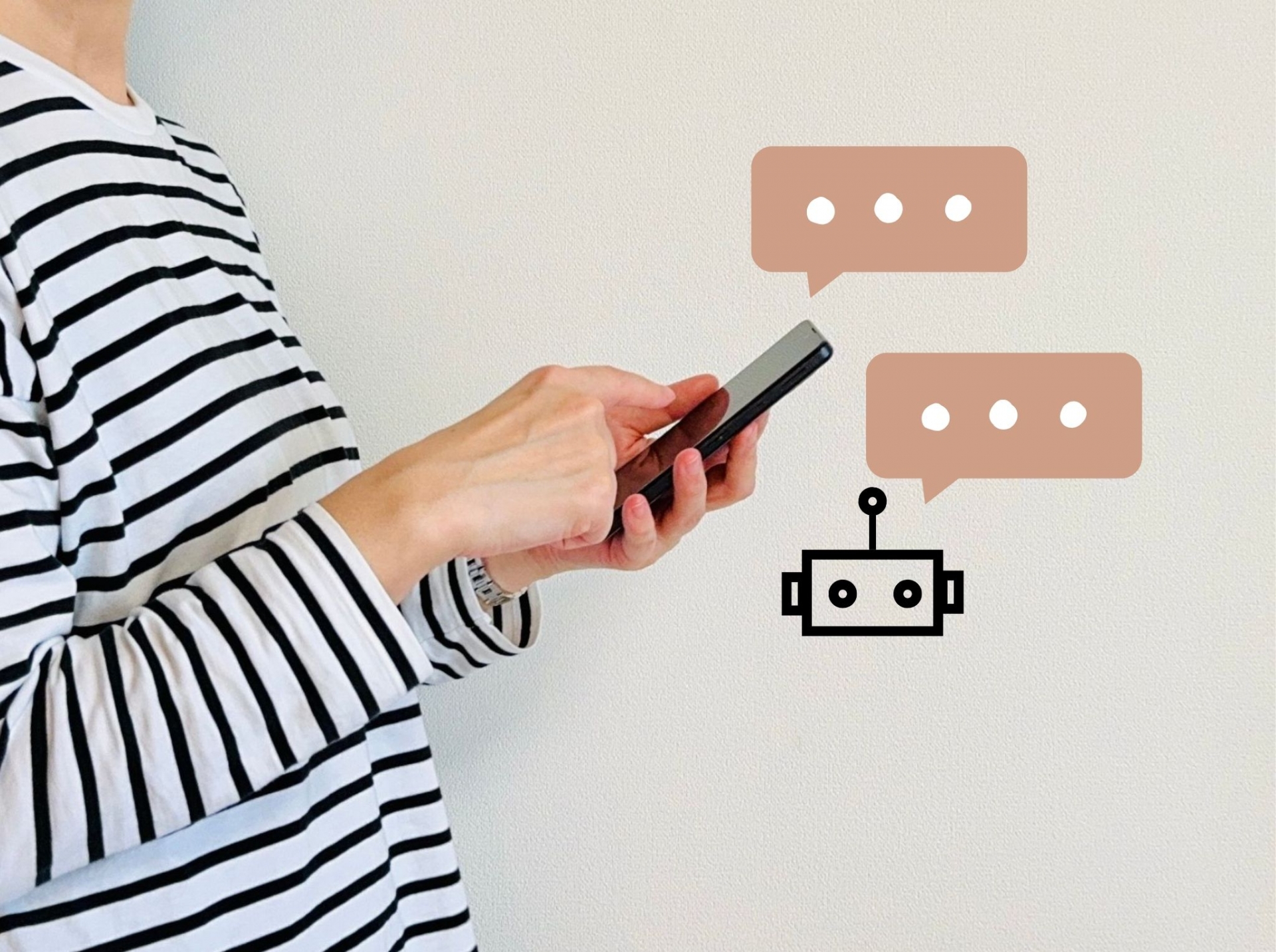
ユーザーの興味・関心データの活用
Google Discoverは、複数のデータソースを組み合わせて、ユーザーの興味・関心を判断しています。
最も重要なデータソースは、Googleアカウントに紐づいた「Web・アプリのアクティビティ」です。
この設定がオンになっていると、ユーザーがGoogleで検索したキーワード、閲覧したWebサイト、使用したアプリなどの情報が記録されます。
Discoverは、これらの履歴データを分析することで、ユーザーが何に興味を持っているかを推測します。
たとえば、特定のスポーツチームについて頻繁に検索しているユーザーには、そのチームに関連するニュースや記事が優先的に表示されます。
また、位置情報も重要な判断材料として活用されています。
ユーザーの現在地や自宅・職場として設定された場所の情報をもとに、地域に関連したコンテンツが表示されやすくなります。
実際、ローカル情報を扱うブログやメディアサイトは、Discoverとの相性が非常に良いことが知られています。
さらに、Discover上でのユーザーの行動も、表示内容に影響を与えます。
どの記事をタップしたか、どの記事を長く読んだか、どのトピックを「興味がない」と設定したかなどの情報が、次に表示されるコンテンツに反映されます。
特に重要なのは、一度タップしたサイトがその後も表示されやすくなるというアルゴリズムの特性です。
あるサイトの記事をタップすると、そのユーザーのフィードには同じサイトの他の記事が表示されやすくなります。
そして、それらの記事も継続的にタップされると、さらに表示される頻度が高まります。
この仕組みにより、定期的に更新されるブログやニュースサイトは、一度ユーザーに認知されると、安定したトラフィックを得やすくなるのです。
- Web・アプリのアクティビティ(検索履歴、閲覧履歴)
- 位置情報(現在地、自宅・職場の設定)
- YouTube視聴履歴
- Discover上での行動履歴(タップ、長期閲覧、フィードバック)
- タップしたサイトの継続的な表示
- デバイスの使用言語設定
- Googleアカウントの基本情報
アルゴリズムが重視する要素
Google Discoverのアルゴリズムは、複数の要素を総合的に評価してコンテンツを選択しています。
最も重視されるのは「コンテンツの鮮度」です。
Discoverに表示されるコンテンツの大半は、24時間以内に公開されたものが占めています。
これは、Discoverが「今話題になっていること」「最新の情報」を提供することを目的としているためです。
ただし、ユーザーの興味関心に強くマッチする場合は、古いコンテンツでも表示される可能性があります。
次に重要なのが「トピックとユーザーの興味との関連性」です。
Googleは、各コンテンツが主にどのトピックについて書かれているかを識別します。
そして、ユーザーの検索履歴や閲覧行動から判断した興味関心のトピックと照合し、マッチ度の高いコンテンツを選択します。
このため、記事のタイトルや本文に、明確にトピックを示すキーワードを含めることが重要です。
「コンテンツの品質」も大きな評価要素となります。
Discoverは、Google検索と同じランキングシステムの多くを共有しており、専門性、権威性、信頼性(E-E-A-T)が高いコンテンツを優先します。
また、視覚的な魅力も評価対象です。
高品質で大きな画像を使用しているコンテンツは、ユーザーの注目を集めやすく、Discoverでの表示が優遇される傾向があります。
エンゲージメントの高さも重要な指標です。
多くのユーザーにタップされ、長時間閲覧されるコンテンツは、他のユーザーにも表示されやすくなります。
調査によると、Discoverに表示されるコンテンツの46%がニュースサイト、44%がEコマース関連サイトとなっており、タイムリーな情報や実用的な情報が好まれる傾向があります。
| 評価要素 | 重要度 | 具体的な内容 |
| コンテンツの鮮度 | 非常に高い | 24時間以内の公開が理想的 |
| トピックとの関連性 | 非常に高い | ユーザーの興味と強くマッチすること |
| コンテンツの品質 | 高い | E-E-A-T、正確性、独自性 |
| 視覚的魅力 | 高い | 高品質で大きな画像の使用 |
| エンゲージメント | 中〜高 | クリック率、滞在時間、リピート率 |
| モバイル対応 | 中 | スマートフォンでの読みやすさ |
コンテンツポリシーと表示基準
Google Discoverに表示されるためには、Googleが定めるコンテンツポリシーを遵守する必要があります。
まず大前提として、コンテンツがGoogleにインデックスされている必要があります。
Discoverは、Googleの検索インデックスに含まれているページの中から、適切なコンテンツを選択して表示する仕組みだからです。
また、Google ニュースのコンテンツポリシーに違反していないことも必須条件です。
具体的には、暴力的なコンテンツ、ヘイトスピーチ、ハラスメント、露骨な性的表現、危険または違法な行為を助長するコンテンツなどは表示対象外となります。
Discoverは、ユーザーに「役立つ情報」を提供することを目的としているため、コンテンツの種類にも制限があります。
求人応募フォーム、請願書、アンケート、ソースコードリポジトリ、風刺的なコンテンツ(文脈が不明確な場合)などは、Discoverに表示されにくいとされています。
これらは、興味関心に基づくフィードには適さないと判断されているためです。
さらに、SafeSearchの設定も適用されます。
SafeSearchがオンになっているユーザーには、成人向けコンテンツや過激な内容が含まれる可能性のあるページは表示されません。
誤解や混乱を招く可能性のあるコンテンツも避けるべきです。
Discoverは、ユーザーがフィードを流し見する中で情報を得るサービスであるため、誤った情報や文脈なしでは理解できないコンテンツは、ユーザー体験を損なう恐れがあります。
株式会社エッコでは、Google Discoverのコンテンツポリシーを遵守しながら、効果的なコンテンツ戦略を立案するサポートを行っています。
ポリシー違反によるペナルティを避けつつ、最大限の成果を得るための専門的なアドバイスを提供しています。
- Googleにインデックスされていること
- Google ニュースのコンテンツポリシーに準拠していること
- 暴力的、ヘイトフル、危険なコンテンツでないこと
- 露骨な性的表現を含まないこと
- SafeSearchの基準を満たしていること
- フィード形式に適したコンテンツであること
- 誤解を招く情報や虚偽の情報でないこと
- ユーザーに価値を提供する内容であること
Google Discoverに表示されるメリット

検索以外からのトラフィック獲得
Google Discoverの最大のメリットは、検索キーワードに依存しない大量のトラフィックを獲得できることです。
従来のSEOでは、特定のキーワードで上位表示を目指す必要がありましたが、Discoverではその制約がありません。
ユーザーは能動的に検索していないため、競合サイトとの直接的な比較がなく、コンテンツそのものの魅力で勝負できます。
実際、一部のメディアサイトでは、Discoverからの流入が通常の検索流入を上回るケースも報告されています。
特に、最新ニュースやトレンド記事を扱うサイトでは、検索エンジンからの流入が月間10万PVであるのに対し、Discoverからは月間50万PV以上を獲得している事例もあります。
日本では「Google砲」と呼ばれる現象が有名です。
これは、Discoverに掲載されることで、短期間に爆発的なアクセスが集中する現象を指します。
通常は1日あたり数百PV程度のサイトが、Discoverに掲載されたことで、1日で10万PV以上を記録することも珍しくありません。
ただし、前述の通り、Discoverからのトラフィックは短期集中型です。
多くの場合、表示開始から1〜2日目にトラフィックのピークを迎え、3〜4日後には大幅に減少します。
しかし、定期的に更新されるサイトの場合、一度認知されると継続的に表示されやすくなります。
あるユーザーがあなたのサイトの記事をタップすると、そのユーザーのフィードには同じサイトの他の記事が表示されやすくなる仕組みがあるためです。
これにより、新しい記事を公開するたびに、既存の読者に自動的に届けられるという好循環が生まれます。
また、検索では見つけられなかった潜在的な読者層にリーチできるのも大きなメリットです。
あなたのコンテンツに興味を持つ可能性があるものの、具体的な検索キーワードを思いつかなかったユーザーにも、情報を届けられるのです。
| メリットの種類 | 具体的な効果 |
| トラフィック量 | 短期間で通常の数十倍〜数百倍のアクセスが可能 |
| 競合との差別化 | 検索順位に依存せず、コンテンツの魅力で勝負できる |
| 継続的な露出 | 定期更新により安定したトラフィックを確保 |
| 潜在読者へのリーチ | 検索キーワードを思いつかないユーザーにも届く |
| 費用対効果 | 広告費をかけずに大量の新規ユーザーを獲得できる |
ブランド認知度の向上
Google Discoverは、ブランドの認知度を飛躍的に高める効果があります。
Discoverに表示されることで、これまで自社ブランドを知らなかったユーザーにも、コンテンツを届けられるからです。
通常の検索では、ユーザーは特定の情報を探しており、複数のサイトを比較検討します。
一方、Discoverでは、ユーザーが興味を持ちそうなコンテンツが自動的に提示されるため、ブランド名を知らなくても記事を読んでもらえる可能性が高まります。
特に、視覚的に魅力的なサムネイル画像と、興味を引くタイトルを組み合わせることで、ユーザーの注目を集めやすくなります。
Discover上には、サイト名とFavicon(ファビコン)が表示されるため、繰り返し表示されることでブランドの視認性が向上します。
あるユーザーが一度あなたのサイトの記事をタップすると、その後もそのユーザーのフィードには同じサイトの記事が表示されやすくなります。
これにより、ユーザーは自然とブランド名を覚え、親しみを感じるようになります。
実際、Discoverに継続的に表示されているサイトでは、ブランド名での指名検索が大幅に増加する傾向があります。
また、新規ユーザーの獲得コストを大幅に削減できます。
広告を使ってブランド認知度を高めようとすると、多額の費用がかかります。
しかし、Discoverは無料でユーザーにリーチできるため、費用対効果が非常に高いマーケティングチャネルと言えます。
さらに、権威性や専門性の高いコンテンツが継続的にDiscoverに表示されることで、ユーザーからの信頼も獲得できます。
特定の分野で有益な情報を提供し続けるサイトとして認識されれば、その分野における第一想起ブランドとなる可能性も高まります。
名古屋に拠点を置く株式会社エッコでは、Discoverを活用したブランディング戦略の立案から実行まで、一貫したサポートを提供しています。
- 新規ユーザーへの大規模なリーチ
- ブランド名とFaviconの反復表示による認知度向上
- 指名検索の増加
- 広告費を抑えたブランド認知活動
- 特定分野での権威性・専門性の確立
- ユーザーからの信頼獲得
- リピーターの自然な増加
エンゲージメント率の向上
Google Discoverからの訪問者は、一般的な検索からの訪問者と比べて、高いエンゲージメントを示す傾向があります。
これは、Discoverがユーザーの興味関心に強くマッチしたコンテンツのみを表示する仕組みだからです。
通常の検索では、ユーザーは特定の疑問や問題を解決するために訪問します。
そのため、答えが見つかればすぐに離脱してしまうことも多く、サイト内での回遊率は必ずしも高くありません。
一方、Discoverからの訪問者は、「興味があるから読みたい」という動機で訪問するため、コンテンツをじっくり読む傾向があります。
実際のデータでも、Discoverからの訪問者は、平均ページ滞在時間が検索からの訪問者よりも長いことが確認されています。
Google公式の発表によると、大きな画像を使用することで、ページの閲覧時間が平均3%向上し、ユーザー満足度も3%向上するとされています。
さらに、クリック率(CTR)も5%向上すると報告されています。
また、Discoverからの訪問者は、サイト内の他のページも閲覧する傾向が強いことが分かっています。
これは、最初の記事に満足したユーザーが、同じサイトの他のコンテンツにも興味を持つためです。
結果として、直帰率が低下し、1セッションあたりのページビュー数が増加します。
さらに、質の高いコンテンツがDiscoverに表示されることで、ソーシャルメディアでのシェアも増える傾向があります。
興味深い情報を見つけたユーザーは、それを友人や家族と共有したくなるものです。
これにより、Discoverからの直接的なトラフィックだけでなく、間接的にソーシャルメディアからのトラフィックも増加する好循環が生まれます。
エンゲージメントの高いユーザーは、将来的に顧客となる可能性も高く、ビジネスの成長に直結する重要な指標です。
株式会社エッコでは、Discoverからのトラフィックの質を高め、最終的なコンバージョンにつなげるための戦略立案をサポートしています。
| 指標 | Discoverからの訪問者の特徴 |
| 平均滞在時間 | 検索ユーザーより長い傾向 |
| 直帰率 | 検索ユーザーより低い傾向 |
| ページ/セッション | 検索ユーザーより多い傾向 |
| ソーシャルシェア率 | 興味関心が強いため高い |
| リピート率 | フォロー機能により向上 |
| コンバージョン率 | 潜在的な関心が高く、良好 |
Google Discoverの最適化方法

高品質で魅力的なコンテンツの作成
Google Discoverで成功するための最も基本的かつ重要な要素は、高品質なコンテンツを作成することです。
Discoverは、Googleの検索アルゴリズムと多くのシステムを共有しており、「役立つ、信頼できる、人を第一に考えたコンテンツ」を評価します。
つまり、通常のSEO対策と同様に、ユーザーに価値を提供するコンテンツを作ることが最優先です。
まず、コンテンツは正確で信頼できる情報に基づいている必要があります。
事実に基づかない推測や、根拠のない主張は、ユーザーの信頼を損なうだけでなく、Googleからの評価も下げます。
情報源を明示し、可能な限り一次情報や公式データを参照することが重要です。
次に、独自の視点や洞察を提供することが求められます。
他のサイトと同じ情報を繰り返すだけでは、ユーザーにとっての価値は低くなります。
独自の調査結果、専門家としての分析、実体験に基づく具体的なアドバイスなど、あなただけが提供できる情報を含めましょう。
また、タイムリーなトピックを取り上げることも効果的です。
Discoverは新鮮なコンテンツを優先するため、最新のニュース、トレンド、季節のイベントなどを素早く記事化することで、表示される可能性が高まります。
ただし、話題性だけを追求するのではなく、あなたの専門性が活かせる分野で、質の高い分析や解説を加えることが重要です。
コンテンツの長さも考慮すべきポイントです。
Discoverでは、じっくり読める詳細な記事が好まれる傾向があります。
表面的な情報だけでなく、テーマを深く掘り下げた包括的なコンテンツを目指しましょう。
さらに、読みやすさにも配慮が必要です。
モバイルデバイスでの閲覧を前提として、適切な段落分け、見出しの活用、箇条書きの使用などにより、視認性を高めましょう。
名古屋のWebコンサルティング会社である株式会社エッコでは、Discoverに最適化されたコンテンツ制作の支援を行っています。
- 正確で信頼できる情報の提供
- 独自の視点や洞察の追加
- タイムリーなトピックの選定
- 専門性を活かした深い分析
- 包括的で詳細な内容
- モバイルでの読みやすさへの配慮
- 適切な見出し構造の設計
- ユーザーの疑問に答える構成
大きくて高品質な画像の使用
Google Discoverにおいて、画像は極めて重要な役割を果たします。
Discoverのフィードでは、各コンテンツがサムネイル画像とともに表示されるため、画像の質と大きさが、ユーザーのクリック行動に直接影響します。
Google公式の発表によると、大きな画像を使用することで、クリック率が5%向上し、ページの閲覧時間が3%向上し、ユーザー満足度も3%向上することが確認されています。
これらの数値は一見小さく見えますが、大量のトラフィックが見込めるDiscoverにおいては、非常に大きな差となります。
まず、画像は視覚的に魅力的で、コンテンツの内容を適切に表現しているものを選びましょう。
ユーザーがフィードをスクロールする中で、思わず目を止めてしまうような印象的な画像が理想的です。
ストック写真も使えますが、可能な限りオリジナルの画像や、独自に加工した画像を使用することで、他のコンテンツとの差別化が図れます。
また、画像は記事の内容と関連性が高いものを選ぶことが重要です。
クリックベイトとなるような、内容と無関係な誇張された画像は避けるべきです。
これは、ユーザーの期待を裏切ることになり、結果的にサイトの信頼性を損ないます。
さらに、サイトのロゴだけを画像として使用することは推奨されていません。
ロゴは企業サイトやブランドサイトでは重要ですが、Discoverのフィードでは、コンテンツの内容を伝える具体的な画像の方が効果的です。
画像の品質も重要な要素です。
低解像度のぼやけた画像や、圧縮によって劣化した画像は、プロフェッショナルな印象を損ないます。
高解像度で鮮明な画像を使用することで、サイト全体の品質が高いという印象をユーザーに与えられます。
| 画像選定のポイント | 具体的な基準 |
| 視覚的魅力 | ユーザーの目を引く印象的なビジュアル |
| 内容との関連性 | 記事のテーマを適切に表現している |
| 独自性 | オリジナル画像または加工による差別化 |
| 解像度 | 高解像度で鮮明であること |
| 避けるべき要素 | サイトロゴのみ、誇張された画像 |
推奨される画像サイズと設定
Discoverで大きな画像を表示させるためには、適切な画像サイズと技術的な設定が必要です。
最も重要なのは、画像の横幅を1,200ピクセル以上にすることです。
これは、Google公式のガイドラインで明示されている推奨サイズです。
1,200ピクセル未満の画像でも表示されることはありますが、小さなサムネイルとしてしか表示されず、ユーザーの注目を集めにくくなります。
画像のアスペクト比(縦横比)も考慮すべき点です。
一般的に、16:9または4:3の横長の画像が、Discoverのフィードに適しています。
正方形や縦長の画像も使用できますが、横長の画像の方が、Discoverのレイアウトにマッチしやすい傾向があります。
画像のファイル形式については、JPEG、PNG、WebPなどの一般的な形式であれば問題ありません。
ただし、ファイルサイズが大きすぎると、ページの読み込み速度が低下するため、適切に圧縮することが重要です。
現代的なWebPフォーマットを使用すると、画質を保ちながらファイルサイズを小さくできるため、推奨されます。
画像には、適切なalt属性(代替テキスト)を設定することも忘れてはいけません。
alt属性は、画像が表示されない場合にテキストで内容を伝えるだけでなく、検索エンジンが画像の内容を理解する手助けとなります。
画像の内容を簡潔かつ正確に説明するテキストを記述しましょう。
また、OGP(Open Graph Protocol)画像の設定も重要です。
og:image タグで指定された画像は、ソーシャルメディアでのシェア時だけでなく、Discoverでも使用されることがあります。
記事のメイン画像とog:imageを一致させることで、一貫性のあるビジュアル表現が可能になります。
- 横幅: 1,200ピクセル以上(必須)
- アスペクト比: 16:9 または 4:3(推奨)
- ファイル形式: JPEG、PNG、WebP
- ファイルサイズ: 圧縮により最適化(目安: 200KB以下)
- alt属性: 画像内容を正確に説明
- OGP画像: メイン画像と一致させる
max-image-previewタグの設定
大きな画像をDiscoverに表示させるためには、画像サイズだけでなく、Webサイトのメタタグ設定も重要です。
特に重要なのが「max-image-preview」メタタグです。
このタグは、検索エンジンやDiscoverなどのサービスに対して、どのサイズの画像プレビューを表示してよいかを指示するものです。
設定方法は非常にシンプルで、HTMLの<head>セクション内に以下のコードを追加します。
<meta name=”robots” content=”max-image-preview:large”>
このタグを設定することで、Googleは最大サイズの画像プレビューを表示できるようになります。
逆に、このタグが設定されていない場合や、”max-image-preview:standard”や”max-image-preview:none”が設定されている場合、大きな画像は表示されず、小さなサムネイルのみの表示となります。
AMP(Accelerated Mobile Pages)を実装しているサイトの場合、このタグの設定は不要です。
AMPページは自動的に大きな画像プレビューが有効になるためです。
ただし、現在ではAMPの必要性は以前ほど高くないため、通常のHTMLページにmax-image-previewタグを設定する方法が一般的です。
このタグは、ページ全体に適用されるため、一度設定すれば、サイト内のすべてのページで有効になります。
WordPressなどのCMSを使用している場合、テーマのheader.phpファイルや、SEOプラグインの設定画面から追加できます。
多くの人気SEOプラグイン(Yoast SEO、All in One SEO、Rank Mathなど)では、この設定を簡単に有効化できるオプションが用意されています。
設定後は、Google Search Consoleで正しく認識されているか確認することをおすすめします。
特に、Discoverのレポートで大きな画像が表示されているかをチェックすることで、設定が正しく機能しているか判断できます。
| 設定方法 | 具体的な手順 |
| HTMLでの直接追加 | <head>内に<meta name=”robots” content=”max-image-preview:large”>を追加 |
| WordPressテーマ | header.phpの<head>セクションに追加 |
| Yoast SEO | SEO → 検索での見え方 → コンテンツタイプ |
| All in One SEO | 検索の外観 → 高度な設定 |
| Rank Math | 一般設定 → 画像 → 大きな画像プレビュー |
| 確認方法 | Google Search ConsoleのDiscoverレポートで確認 |
E-E-A-Tの強化
Google Discoverで継続的に成功するためには、E-E-A-T(Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness)の強化が不可欠です。
E-E-A-Tとは、経験、専門性、権威性、信頼性の4つの要素を指し、Googleがコンテンツの品質を評価する際の重要な基準となっています。
まず「Experience(経験)」は、2022年12月にGoogleが新たに追加した評価基準です。
コンテンツ制作者が実際に経験したことに基づいて書かれているかが評価されます。
たとえば、レストランのレビューであれば、実際にそこで食事をした人が書いた記事の方が、間接的な情報だけで書かれた記事よりも価値が高いと判断されます。
実体験に基づく具体的な描写、写真、詳細な感想などを含めることで、経験を示すことができます。
次に「Expertise(専門性)」は、そのトピックに関する深い知識や技能を持っているかという観点です。
専門的な資格、長年の実務経験、該当分野での実績などが、専門性を示す要素となります。
記事の中で、専門的な知識に基づいた詳細な解説や、一般的には知られていない情報を提供することで、専門性を示すことができます。
「Authoritativeness(権威性)」は、その分野での評判や認知度を指します。
他の権威あるサイトからのリンク、業界内での言及、メディアへの掲載実績などが、権威性を高める要素です。
また、著者のプロフィールを充実させ、過去の実績や受賞歴などを明示することも効果的です。
最後に「Trustworthiness(信頼性)」は、サイトやコンテンツが信頼できるかという観点です。
正確な情報の提供、情報源の明示、透明性のある運営、セキュリティの確保(HTTPS化)などが、信頼性を構成する要素です。
特に、YMYL(Your Money or Your Life)と呼ばれる、お金や健康に関わるトピックでは、信頼性が厳しく評価されます。
株式会社エッコでは、E-E-A-Tを総合的に強化するための戦略立案と実行支援を提供しています。
専門家の監修体制の構築、著者プロフィールの最適化、信頼性を高めるサイト構造の設計など、多角的なアプローチでサポートいたします。
| E-E-A-T要素 | 強化方法の例 |
| Experience(経験) | 実体験に基づく記事、オリジナル写真、詳細な感想 |
| Expertise(専門性) | 専門資格の明示、詳細な専門知識の提供、実務経験の記載 |
| Authoritativeness(権威性) | 被リンクの獲得、業界での認知度向上、メディア掲載 |
| Trustworthiness(信頼性) | 情報源の明示、運営者情報の開示、HTTPS化、プライバシーポリシー |
クリックベイトの回避
Google Discoverで長期的な成功を収めるためには、クリックベイトを避けることが重要です。
クリックベイトとは、ユーザーの好奇心を過度に煽り、実際のコンテンツ内容と一致しない誇張されたタイトルや画像を使う手法を指します。
「驚愕の結果が明らかに!」「この方法を知らないと損をします」「業界に激震!」といった、過度に煽情的な表現は、短期的にはクリック率を高めるかもしれません。
しかし、実際のコンテンツが期待に応えられない場合、ユーザーはすぐに離脱し、サイトへの信頼を失います。
Googleは、このようなクリックベイトを明確に禁止しており、発見された場合、Discoverでの表示が大幅に減少する可能性があります。
具体的に避けるべきクリックベイトの手法として、以下のようなものがあります。
まず、内容を理解するために必要な重要情報を意図的に隠すことです。
「この食品を食べると驚きの変化が!」といったタイトルで、実際に何の食品なのかを隠すような手法は避けるべきです。
次に、タイトルや画像で誇張や誤解を招く表現を使うことです。
実際には小さな効果しかないのに、「劇的に変わる」「革命的な方法」といった過度な表現を使うことは、ユーザーの期待を裏切ります。
また、コンテンツの本質とは無関係な衝撃的な画像を使用することも問題です。
記事の内容とは関係のない、ただ注目を集めるためだけの画像は、ユーザー体験を損ないます。
では、どのようなタイトルと画像が適切なのでしょうか。
タイトルは、記事の本質を正確に伝えつつ、読者の興味を引くものを目指しましょう。
具体的な数字や固有名詞を含めることで、クリックベイトに頼らずとも魅力的なタイトルを作れます。
たとえば、「検索順位を上げる10の方法」「名古屋で人気のカフェ5選」といったタイトルは、具体的でありながら興味を引きます。
画像についても、記事の内容を正直に表現するものを選びましょう。
記事で紹介する商品の実際の写真、データを視覚化したグラフ、記事のテーマに直接関連する風景写真などが適切です。
| クリックベイトの例 | 適切な表現の例 |
| 「この方法で人生が変わった!」 | 「月収を20%増やした副業の始め方」 |
| 「誰も知らない裏技を公開」 | 「Excel作業を効率化する5つの関数」 |
| 「業界騒然の新事実」 | 「2025年のSEOトレンド分析」 |
| 「信じられない結果に」 | 「3ヶ月で10kg減量した食事法」 |
モバイル対応の徹底
Google Discoverは、主にモバイルデバイスで利用されるサービスであるため、モバイル対応は必須です。
モバイルフレンドリーでないサイトは、そもそもDiscoverに表示されにくい傾向があります。
まず基本となるのが、レスポンシブデザインの採用です。
レスポンシブデザインとは、画面サイズに応じてレイアウトが自動的に調整されるWebデザインの手法です。
これにより、スマートフォン、タブレット、デスクトップのどのデバイスでも、最適な表示が実現できます。
特に重要なのが、文字サイズと行間の設定です。
スマートフォンの小さな画面でも読みやすいよう、本文のフォントサイズは最低でも16ピクセル、できれば18ピクセル以上に設定しましょう。
行間も適切に取ることで、視認性が大幅に向上します。
また、タップしやすいボタンやリンクの設計も重要です。
スマートフォンでは指でタップするため、ボタンやリンクは十分な大きさ(最低44×44ピクセル)を確保し、周囲に適切な余白を設けましょう。
ページの読み込み速度も、モバイル対応における重要な要素です。
モバイルネットワークはデスクトップの有線接続よりも遅いことが多いため、ページが素早く表示されることが求められます。
画像の最適化、不要なスクリプトの削除、キャッシュの活用などにより、読み込み速度を改善できます。
Googleが提供するPageSpeed Insightsやlighthouse などのツールを使って、現在のページ速度を測定し、改善点を特定しましょう。
さらに、コンテンツの構造も重要です。
長い文章は適切に段落分けし、見出しを効果的に使って、スマートフォンでもスキャンしやすい構成にしましょう。
箇条書きや表を適切に使用することで、情報を整理して提示できます。
ポップアップやインタースティシャル広告にも注意が必要です。
スマートフォンの画面全体を覆うような広告は、ユーザー体験を大きく損ないます。
Googleは、侵入的なインタースティシャルを使用するサイトをペナルティの対象としています。
名古屋のWebコンサルティング会社である株式会社エッコでは、モバイルファーストのWebサイト設計と最適化をサポートしています。
- レスポンシブデザインの実装
- 適切な文字サイズ(16px以上)と行間の設定
- タップしやすいボタンサイズ(44×44px以上)
- 画像の最適化による高速読み込み
- 不要なスクリプトの削減
- 見出しと段落による読みやすい構造
- 侵入的な広告の回避
- PageSpeed Insightsでの定期的な速度チェック
Google Discoverのトラフィック測定

Google Search Consoleでの確認方法
Google Discoverからのトラフィックを正確に測定するには、Google Search Consoleの使用が不可欠です。
Google Analyticsでは、Discoverからの流入は「Direct」(直接流入)として分類されてしまうため、正確な測定ができません。
一方、Google Search Consoleには、Discover専用のレポート機能が用意されており、詳細なデータを確認できます。
まず、Google Search Consoleにアクセスし、左側のメニューから「Discover」を選択します。
ただし、このメニューが表示されるのは、実際にDiscoverからのトラフィックが一定以上ある場合のみです。
まだDiscoverに表示されたことがないサイトでは、このメニュー自体が表示されません。
Discoverレポートでは、以下のような情報を確認できます。
まず「クリック数」は、Discoverに表示されたあなたのコンテンツが、実際にクリックされた回数です。
これは、実際にサイトへ流入したユーザー数を示す最も重要な指標です。
次に「表示回数」は、Discoverのフィードに、あなたのコンテンツが表示された回数です。
ユーザーがフィードをスクロールする中で、画面に表示された回数がカウントされます。
「CTR(Click Through Rate)」は、表示回数に対するクリック数の割合です。
この数値が高いほど、タイトルや画像が魅力的で、ユーザーの関心を引いていることを示します。
レポートでは、日付範囲を指定してデータを確認できます。
デフォルトでは過去16ヶ月間のデータが保存されているため、長期的なトレンドを分析できます。
また、個別のURLごとにデータを確認することもできます。
どの記事がDiscoverで人気だったのか、どのような傾向があるのかを分析することで、今後のコンテンツ戦略に活かせます。
さらに、国や言語別にデータを絞り込むこともできます。
これにより、どの地域でコンテンツが人気なのかを把握し、地域に特化したコンテンツ戦略を立てることも可能です。
なお、Google Search Consoleのデータには若干の遅延があり、最新のデータが表示されるまで2〜3日かかることがあります。
| 確認できるデータ | 説明 |
| クリック数 | 実際にサイトに流入したユーザー数 |
| 表示回数 | Discoverフィードに表示された回数 |
| 平均CTR | クリック数 ÷ 表示回数の割合 |
| URL別データ | どの記事が人気かを個別に確認 |
| 国別データ | どの地域で人気かを確認 |
| デバイス別データ | モバイル、タブレット、デスクトップ別の内訳 |
| 期間別推移 | 最大16ヶ月間のトレンド分析 |
表示回数とクリック率の分析
Google Search Consoleで取得したDiscoverのデータを分析することで、コンテンツ戦略の改善点を見つけられます。
最初に注目すべき指標は、表示回数の推移です。
表示回数が増加傾向にある場合、あなたのサイトがDiscoverでより多くのユーザーにリーチできていることを示します。
これは、コンテンツの質が評価され、Googleのアルゴリズムがより多くのユーザーに推薦していることを意味します。
一方、表示回数が減少している場合は、コンテンツの更新頻度が下がっていないか、トピックの選定が適切かを見直す必要があります。
次に重要なのが、CTR(クリック率)の分析です。
Discoverの平均的なCTRは、通常2〜5%程度とされています。
あなたのサイトのCTRがこの範囲よりも低い場合、タイトルや画像の改善が必要かもしれません。
逆に、CTRが高い場合は、タイトルと画像がユーザーの興味を効果的に引いていると評価できます。
URL別のデータを分析することで、どのようなコンテンツがDiscoverで成功しているかのパターンを見つけられます。
たとえば、特定のトピックや記事形式が高いパフォーマンスを示している場合、同様のコンテンツを増やす戦略が有効です。
また、表示回数は多いがCTRが低い記事を特定することで、タイトルや画像の改善対象を明確にできます。
これらの記事は、多くのユーザーに露出しているにもかかわらず、興味を引けていない状態です。
タイトルをより具体的で魅力的なものに変更したり、画像をより印象的なものに差し替えたりすることで、CTRの改善が期待できます。
表示回数が少ない記事については、トピックの選定やキーワードの使い方を見直しましょう。
Googleが記事のトピックを正しく認識できていない可能性があります。
タイトルや本文の最初の段落で、記事の主題を明確に示すことで、改善できることがあります。
時系列でデータを分析することも重要です。
特定の曜日や時間帯に表示回数やクリック数が増える傾向がある場合、その時間に合わせて記事を公開することで、より多くのトラフィックを獲得できる可能性があります。
株式会社エッコでは、Google Search Consoleのデータを詳細に分析し、具体的な改善施策を提案するサービスを提供しています。
| 分析の視点 | 具体的なチェックポイント |
| 表示回数の推移 | 増加傾向か減少傾向か、季節変動はあるか |
| CTRの水準 | 平均2〜5%と比較してどうか |
| 高パフォーマンス記事の特徴 | トピック、タイトル形式、画像スタイル |
| 低CTR記事の改善 | タイトルと画像の見直し |
| トピック認識の確認 | 意図したトピックで表示されているか |
| 時系列パターン | 曜日・時間帯による変動 |
改善施策の立案
Discoverのデータ分析から得られた洞察をもとに、具体的な改善施策を立案することが重要です。
データに基づいた改善を継続的に行うことで、Discoverからのトラフィックを安定的に増やせます。
まず、CTRが低い記事に対しては、タイトルと画像の改善を優先的に実施しましょう。
タイトルについては、より具体的な数字や固有名詞を含める、ユーザーの興味を引く問いかけ形式にする、などの工夫が効果的です。
ただし、クリックベイトにならないよう、記事の内容と一致した正直な表現を心がけることが重要です。
画像については、より視覚的にインパクトのあるものに差し替えることを検討しましょう。
オリジナルの写真やインフォグラフィックを作成することで、他のコンテンツとの差別化が図れます。
また、画像に短いテキストを重ねることで、内容をより明確に伝えることも効果的です。
表示回数そのものを増やすためには、更新頻度の向上が有効です。
**Discoverで継続的に表示されるサイトの多くは、毎日または2〜3日に1記事のペースで新しいコンテンツを公開しています。**
定期的な更新により、一度あなたのサイトをタップしたユーザーのフィードに、継続的に新しい記事が表示されるようになります。
これにより、安定したトラフィックの獲得が可能になります。
トピックの選定も改善施策の重要な要素です。
過去のデータから、どのようなトピックが高いパフォーマンスを示しているかを分析し、同様のテーマでコンテンツを増やすことが効果的です。
特に、ローカル情報、最新のトレンド、専門的な解説記事などは、Discoverとの相性が良い傾向があります。
また、季節性のあるトピックについては、適切なタイミングで記事を公開することも重要です。
たとえば、花見スポットの記事は3月初旬に、クリスマスプレゼントの記事は11月中旬に公開することで、最適なタイミングでDiscoverに表示される可能性が高まります。
コンテンツの深さと質を向上させることも、長期的な改善策として重要です。
表面的な情報だけでなく、独自の調査結果、専門家としての分析、実体験に基づく詳細な情報を提供することで、ユーザーの滞在時間が延び、エンゲージメントが向上します。
これらの指標が改善されると、Googleはそのコンテンツをより多くのユーザーに推薦するようになります。
さらに、過去に公開した記事の更新も効果的な施策です。
古い記事でも、最新の情報を追加したり、画像を差し替えたりすることで、再びDiscoverに表示される可能性があります。
特に、過去に一度Discoverで人気だった記事は、更新後に再び注目を集めやすい傾向があります。
名古屋のWebコンサルティング会社である株式会社エッコでは、データ分析から具体的な改善施策の立案・実行まで、一貫したサポートを提供しています。
Discoverからのトラフィック最大化を目指す企業様は、ぜひご相談ください。
- CTRが低い記事のタイトル・画像改善
- 更新頻度の向上(毎日〜2-3日に1記事)
- 高パフォーマンストピックの拡充
- 季節性を考慮した公開タイミングの最適化
- コンテンツの深さと質の向上
- 過去記事の更新による再表示の促進
- トピック認識を改善するための構造最適化
- A/Bテストによる継続的な改善
Follow機能とパーソナライゼーション

Followボタンの活用
2025年9月に導入されたFollow機能は、Google Discoverにおける大きな変化の一つです。
この機能により、ユーザーは気に入ったパブリッシャーやクリエイターを「フォロー」できるようになりました。
フォローされると、そのサイトの新しいコンテンツが、ユーザーのDiscoverフィードに優先的に表示されるようになります。
これは、従来のアルゴリズムベースの表示に加えて、ユーザーが明示的に興味を示したサイトを重視する仕組みです。
Followボタンは、Discoverのフィード上で各コンテンツの右上に表示されます。
ユーザーがパブリッシャー名やクリエイター名をタップすると、そのサイトの専用ページが表示され、過去の記事、YouTube動画、ソーシャルメディアの投稿などを一覧で確認できます。
この専用ページで「Follow」ボタンをタップすることで、フォローが完了します。
現在、Follow機能は以下の地域で利用可能です。
Chrome Androidではアメリカ、ニュージーランド、南アフリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアの英語ユーザーが対象です。
Chrome iOSではアメリカの英語ユーザーのみが対象となっています。
日本ではまだ完全には展開されていませんが、今後拡大される可能性が高いと考えられます。
サイト運営者として、Follow機能を最大限活用するためには、RSSまたはAtomフィードの設定が重要です。
デフォルトでは、Googleがサイトの構造を分析して自動的にフィードを生成しますが、明示的にフィードを指定することで、より適切なコンテンツをユーザーに届けられます。
HTMLの<head>セクションに、以下のようなコードを追加することで、フィードを指定できます。
RSSの場合:
<link rel=”alternate” type=”application/rss+xml” href=”https://example.com/feed.rss”>
“`
Atomの場合:
“`
<link rel=”alternate” type=”application/atom+xml” href=”https://example.com/feed.atom”>
複数のフィードがある場合、最も関連性の高いフィードを優先順位順に記載することも可能です。
たとえば、ニュースサイトで全体のフィードとカテゴリ別のフィードがある場合、そのページに最も関連するフィードを最初に記載します。
Followされることの最大のメリットは、継続的かつ安定したトラフィックを得られることです。
一度フォローされれば、新しいコンテンツを公開するたびに、そのフォロワーのフィードに自動的に表示されます。
これにより、一時的な「Google砲」だけでなく、長期的なファンベースを構築できるようになりました。
| Follow機能の特徴 | 詳細 |
| 利用可能地域 | 米国、英国、カナダ、豪州、NZ、南アフリカ(英語) |
| デバイス | Chrome Android、Chrome iOS(一部) |
| フィードの種類 | RSS、Atom、またはGoogle自動生成 |
| 表示される内容 | 記事、YouTube動画、SNS投稿 |
| ユーザーメリット | 好きなサイトの更新を見逃さない |
| サイトメリット | 安定した継続的なトラフィック獲得 |
SNS投稿やYouTube Shortsの統合
2025年9月のアップデートにより、Google DiscoverはWebサイトの記事だけでなく、ソーシャルメディアの投稿やYouTube Shortsも表示するようになりました。
これは、Discoverが単なるニュースフィードから、より包括的なコンテンツディスカバリープラットフォームへと進化したことを意味します。
現在、統合されているプラットフォームには、Instagram、X(旧Twitter)、YouTube Shortsが含まれており、今後さらに多くのプラットフォームが追加される予定です。
これにより、ユーザーは一つのフィード内で、記事、動画、ソーシャル投稿など、様々な形式のコンテンツを発見できるようになりました。
コンテンツクリエイターやメディア企業にとって、この変化は大きな機会を提供します。
従来は、Webサイトに記事を公開することがDiscoverに表示される唯一の方法でしたが、今では複数のチャネルでコンテンツを発信することで、より多くの露出機会を得られます。
たとえば、ブログ記事を公開すると同時に、その内容を要約したInstagram投稿や、短い動画としてYouTube Shortsにアップロードすることで、Discover上での存在感を高められます。
重要なのは、各プラットフォームに最適化されたコンテンツを作成することです。
ブログ記事は詳細な情報を提供し、Instagram投稿は視覚的に魅力的な要約を示し、YouTube Shortsは短時間で核心を伝える動画にする、といった使い分けが効果的です。
また、複数のプラットフォームで一貫したブランドイメージを維持することも重要です。
プロフィール画像、ブランドカラー、トーン&マナーなどを統一することで、ユーザーがどのプラットフォームでコンテンツを見ても、同じブランドだと認識しやすくなります。
Discoverの専用ページでは、パブリッシャーやクリエイターの各プラットフォームへのリンクも表示されます。
これにより、ユーザーは興味を持ったクリエイターを、他のプラットフォームでもフォローしやすくなります。
したがって、各プラットフォームのプロフィールを充実させ、相互にリンクを設定しておくことが重要です。
Googleの調査によると、ユーザーはDiscoverで記事だけでなく、動画やソーシャル投稿など、多様なコンテンツを見ることを好む傾向があるとされています。
この変化に対応し、マルチチャネルでのコンテンツ展開を行うことが、今後のDiscover最適化において重要になるでしょう。
株式会社エッコでは、Webサイトだけでなく、ソーシャルメディアやYouTubeを含めた包括的なコンテンツ戦略の立案をサポートしています。
各プラットフォームの特性を理解し、最大限の効果を得るための戦略を提供いたします。
- Webサイトの記事を核としたコンテンツ制作
- Instagram用の視覚的な要約投稿
- X(Twitter)での話題性のある短文投稿
- YouTube Shortsでの短編動画制作
- 各プラットフォーム間の相互リンク設定
- 一貫したブランドイメージの維持
- プラットフォームごとの最適化
- クロスプロモーションによる相乗効果
ユーザー設定のカスタマイズ方法
Google Discoverは高度にパーソナライズされたサービスですが、ユーザー自身が設定を調整することも可能です。
ユーザーがこれらの設定を理解し活用することで、より満足度の高いコンテンツ体験が得られます。
サイト運営者としても、ユーザーがどのように設定を変更できるかを理解しておくことは、Discover最適化において有益です。
まず、ユーザーは各コンテンツカードの右下にある「もっと見る」ボタンから、様々なアクションを実行できます。
「このようなコンテンツをもっと見る」を選択すると、類似のトピックがより多く表示されるようになります。
逆に、「興味なし」を選択すると、そのトピックやサイトが表示されにくくなります。
「このサイトのコンテンツを表示しない」を選択すると、特定のサイトからのコンテンツが完全にブロックされます。
このため、サイト運営者としては、ユーザーにとって価値のあるコンテンツを提供し続けることが重要です。
低品質なコンテンツや、興味と一致しないコンテンツを繰り返し表示すると、ブロックされるリスクが高まります。
また、ユーザーは「設定」メニューから、より詳細なパーソナライゼーション設定を行えます。
「興味関心の管理」では、フォローしているトピック、ブロックしているトピック、好きだと示したコンテンツなどを一覧で確認し、編集できます。
「Web・アプリのアクティビティ」をオフにすると、Discoverのパーソナライゼーションは大幅に制限されます。
この設定をオフにしているユーザーには、一般的に人気のあるコンテンツが表示されるようになり、個別の興味に基づく表示は行われなくなります。
「パーソナル検索結果」の設定も、Discoverに影響します。
この機能がオンになっていると、Googleは保存されたアクティビティを使用して、よりパーソナライズされた結果を提供します。
動画の自動再生設定も変更可能です。
デフォルトでは、Discoverに表示される動画は音声なしで自動再生されますが、これをWi-Fi接続時のみ、またはオフに設定することもできます。
言語設定により、特定の言語のコンテンツを非表示にすることも可能です。
多言語でコンテンツを提供している場合、各言語版を適切に設定することで、より多くのユーザーにリーチできます。
さらに、位置情報の設定も重要です。
自宅や職場の場所を設定すると、その地域に関連するローカル情報がより多く表示されるようになります。
このため、ローカルビジネスやエリアに特化したメディアは、位置情報に最適化されたコンテンツを作成することで、効果的にターゲットユーザーにリーチできます。
| 設定項目 | 影響 |
| もっと見る/興味なし | 個別コンテンツの表示頻度調整 |
| サイトのブロック | 特定サイトを完全非表示 |
| 興味関心の管理 | フォロー・ブロックトピックの編集 |
| Web・アプリのアクティビティ | パーソナライゼーションの有効/無効 |
| パーソナル検索結果 | 保存されたアクティビティの利用 |
| 動画の自動再生 | 常時/Wi-Fiのみ/オフ |
| 言語設定 | 表示する言語の選択 |
| 位置情報 | ローカルコンテンツの表示 |
まとめ

Google Discoverは、従来の検索エンジンとは異なるアプローチで、大量のトラフィックをもたらす可能性を持つサービスです。
月間8億人以上のユーザーが利用するこのプラットフォームを活用することで、検索順位に依存しない新しいトラフィック源を確保できます。
本記事では、Google Discoverの基本的な仕組みから、表示されるための具体的な最適化方法まで、包括的に解説してきました。
重要なポイントを改めて整理すると、以下のようになります。
まず、Discoverに表示されるためには、コンテンツがGoogleにインデックスされ、コンテンツポリシーを遵守していることが大前提です。
その上で、ユーザーの興味関心に強くマッチする、高品質で新鮮なコンテンツを提供することが求められます。
技術的な最適化としては、横幅1,200ピクセル以上の魅力的な画像を使用し、max-image-previewタグを適切に設定することが効果的です。
また、モバイルフレンドリーなデザインを採用し、ページの読み込み速度を最適化することも重要です。
コンテンツの質を高めるためには、E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)の強化が不可欠です。
実体験に基づく情報、専門的な知識、信頼できる情報源の明示などにより、Googleとユーザーの両方から高い評価を得られます。
同時に、クリックベイトを避け、タイトルと内容が一致した正直なコンテンツを提供することも重要です。
短期的にはクリック率を高められても、長期的にはユーザーとGoogleの信頼を失う結果となります。
効果測定には、Google Search Consoleの活用が必須です。
Discoverからのクリック数、表示回数、CTRを定期的に分析し、データに基づいた改善施策を継続的に実施することで、トラフィックを着実に増やせます。
2025年に導入されたFollow機能やソーシャルメディアの統合により、Discoverはさらに進化を続けています。
これらの新機能を活用し、マルチチャネルでのコンテンツ展開を行うことで、より多くのユーザーにリーチできるようになりました。
Discoverからのトラフィックは、短期集中型であることを理解した上で、定期的な更新により継続的な流入を目指すことが重要です。
毎日または2〜3日に1記事のペースで質の高いコンテンツを公開し続けることで、安定したトラフィックを確保できます。
名古屋のWebコンサルティング会社である株式会社エッコでは、Google Discoverの最適化から、総合的なWebマーケティング戦略まで、幅広いサポートを提供しています。
Discoverを含む多角的なトラフィック獲得戦略により、ビジネスの成長をサポートいたします。
検索以外からのトラフィック獲得に課題を感じている方、Discoverからの流入を増やしたい方は、ぜひ株式会社エッコにご相談ください。
豊富な実績と専門知識を持つコンサルタントが、あなたのサイトに最適な戦略を提案し、実行までサポートいたします。
Google Discoverは、適切な戦略と継続的な改善により、大きな成果をもたらすマーケティングチャネルです。
本記事で紹介した方法を実践し、新しいトラフィック源を開拓することで、ビジネスのさらなる成長を実現してください。



