「SEO対策のためにキーワードをたくさん入れた方がいいのでは?」
このような疑問を抱いている方は少なくありません。
かつてのSEO対策では、ページ内にキーワードを多く配置することが効果的とされていた時代もありました。
しかし、現在のGoogleアルゴリズムでは、キーワードを多く入れすぎることが逆効果になる可能性があります。
不自然なほどキーワードを詰め込んだコンテンツは、ユーザーにとって読みにくいだけでなく、検索エンジンからペナルティを受けるリスクさえあるのです。
では、SEOにおいて適切なキーワード数とはどの程度なのでしょうか。
また、キーワードをどのように配置すれば、検索エンジンとユーザーの両方から評価されるコンテンツになるのでしょうか。
本記事では、SEOキーワードと数の関係性から、具体的な設定方法、実践的なテクニックまでを詳しく解説します。
キーワード設定に悩んでいる方や、SEO対策を見直したい方は、ぜひ最後までお読みください。
Index
SEOキーワードと数の関係

キーワード数がSEOに与える影響
SEOにおけるキーワード数の影響について、まず理解しておくべき重要な事実があります。
それは、現代の検索エンジンでは、キーワードの使用回数や出現率が検索順位に与える直接的な影響は非常に小さいということです。
以前の検索エンジンは、ページ内容を理解する能力が限られていたため、キーワードの数や出現率を重要な判断材料としていました。
そのため、「キーワード出現率を5%以上にする」といった具体的な数値目標を掲げたSEO対策が主流だった時代もあります。
しかし、Googleの自然言語処理技術は飛躍的に進化しました。
現在では、文脈や文章全体の意味を理解し、ユーザーの検索意図に最も合致するコンテンツを評価できるようになっています。
そのため、キーワードを単純に多く使用するだけでは、検索順位の向上にはつながりません。
むしろ、ユーザーにとって有益な情報を提供しているか、読みやすい文章になっているかといった「コンテンツの質」が重視されるようになりました。
| 時期 | 評価基準 | キーワード数の重要度 |
| 過去のSEO | キーワード出現率や数を重視 | 非常に高い |
| 現在のSEO | コンテンツの質とユーザー満足度を重視 | 低い(自然な使用が前提) |
とはいえ、キーワードがまったく必要ないというわけではありません。
検索エンジンがページの内容を理解するためには、対策キーワードが適切に含まれている必要があります。
重要なのは、**「何回使うか」ではなく「どのように使うか」**です。
名古屋のWebコンサル会社である株式会社エッコでは、クライアント様のコンテンツ制作において、キーワードの自然な配置とユーザー目線の文章作成を重視しています。
キーワードの詰め込みすぎによるリスク
キーワードを多く入れすぎることには、いくつかの深刻なリスクが存在します。
最も重要なリスクは、Googleからのペナルティと、ユーザー体験の低下です。
キーワードスタッフィングとは
キーワードスタッフィング(keyword stuffing)とは、検索順位を上げる目的で、ページ内に対策キーワードを不自然なほど大量に詰め込む手法のことです。
具体的には、以下のような行為が該当します。
- 同じキーワードや類似表現を不自然に繰り返す
- ページの内容と関係のないキーワードを羅列する
- ユーザーには見えない場所(背景と同色の文字など)にキーワードを配置する
- タイトルや見出しに過剰にキーワードを盛り込む
例えば、「当社では、カスタムメイド葉巻ケースを販売しています。当社のカスタムメイド葉巻ケースは手作りです。カスタムメイド葉巻ケースの購入をお考えでしたら、当社のカスタムメイド葉巻ケース スペシャリストまでお問い合わせください」というような文章です。
この例では、「カスタムメイド葉巻ケース」というキーワードが不自然に繰り返されており、読者にとって非常に読みにくい文章になっています。
一昔前まで、このような手法が一定の効果を持っていた時期もありました。
しかし、現在ではGoogleのアルゴリズムが進化し、このような不正な手法を容易に検出できるようになっています。
| キーワードスタッフィングの例 | 該当する行為 |
| 同一キーワードの過度な繰り返し | 「SEO対策はSEO対策会社にSEO対策を依頼…」 |
| 関連性のないキーワード羅列 | 商品ページに無関係な人気キーワードを列挙 |
| 隠しテキストの使用 | 白背景に白文字でキーワードを大量配置 |
| メタタグへの過剰な詰め込み | meta keywordsタグに100個以上のキーワード |
キーワードスタッフィングは、ブラックハットSEO(検索エンジンのガイドライン違反となる手法)の代表例として知られています。
Googleペナルティの可能性
キーワードスタッフィングを行うと、Googleからペナルティを受ける可能性があります。
Googleの「ウェブ検索のスパムに関するポリシー」では、キーワードの乱用が明確に禁止事項として記載されています。
ペナルティを受けた場合、以下のような深刻な影響が発生します。
- 検索順位の大幅な下落(10位以内から圏外へなど)
- インデックスからの削除(検索結果に一切表示されなくなる)
- サイト全体の評価低下(他のページにも悪影響が及ぶ)
- 回復までに長期間を要する(数ヶ月以上かかることも)
特に注意が必要なのは、出現率が8%以上になると、ペナルティのリスクが高まるという指摘があることです。
また、Googleのジョン・ミューラー氏は、「ユーザーにとって不自然に見える繰り返しは避けるべき」と公式に発言しています。
ただし、ECサイトのカテゴリページなど、やむを得ず同じキーワードが多く表示される場合については、Googleはその状況を理解して区別できるとも述べています。
| ペナルティの種類 | 影響範囲 | 回復の難易度 |
| 自動ペナルティ | 該当ページのみ | 比較的容易 |
| 手動ペナルティ | サイト全体に及ぶ可能性 | 非常に困難 |
キーワードの使用については、常に**「ユーザーにとって読みやすいか」を最優先**に考えることが重要です。
現代のSEOアルゴリズムの考え方
現代のSEOアルゴリズムは、かつてのような単純な仕組みではありません。
Googleは、ユーザーにとって最も有益なコンテンツを上位表示するという明確な方針を持っています。
Googleの使命は「世界中の情報を整理し、世界中の人がアクセスできて使えるようにすること」です。
この使命を実現するため、Googleは検索アルゴリズムを頻繁にアップデートし、より精度の高い検索結果を提供しようと努めています。
現在の検索エンジンは、以下のような高度な技術を用いてコンテンツを評価しています。
- 自然言語処理(NLP):文章の意味や文脈を理解する
- 意味検索:キーワードの同義語や関連語も認識する
- ユーザー行動の分析:滞在時間や直帰率などから満足度を判断する
- トピッククラスター:関連性の高いコンテンツ群を評価する
つまり、キーワードが何回出現するかよりも、そのコンテンツがユーザーの疑問や課題を解決できるかが重視されているのです。
例えば、「ノートパソコン おすすめ」というキーワードで検索したユーザーは、単に「ノートパソコン」という単語が多く含まれたページを求めているわけではありません。
選び方のポイント、具体的な製品比較、価格帯別のおすすめ、用途別の選択肢など、購入判断に役立つ総合的な情報を求めています。
| 評価される要素 | 具体的な内容 |
| E-E-A-T | 専門性・経験・権威性・信頼性 |
| ユーザー体験 | ページ速度、モバイル対応、読みやすさ |
| コンテンツの質 | 独自性、正確性、網羅性、最新性 |
| 検索意図との合致度 | ユーザーが求める情報を提供できているか |
株式会社エッコでは、このような現代のSEOアルゴリズムを深く理解した上で、クライアント様のWebサイト改善をサポートしています。
名古屋を拠点に、ユーザーファーストのコンテンツ制作とSEO戦略をご提案しておりますので、お気軽にご相談ください。
適切なキーワード設定の基本原則

1ページ1キーワードが基本
SEO対策における最も重要な原則の一つが、「1ページ1キーワード」というルールです。
これは、1つのページで対策するメインキーワードを1つに絞るという考え方です。
メインキーワードの選定方法
メインキーワードの選定は、SEO戦略の成否を左右する重要なステップです。
適切なメインキーワードを選ぶためには、以下のポイントを押さえる必要があります。
まず、検索ボリュームと競合性のバランスを考慮しましょう。
検索ボリュームが多すぎるキーワードは競合が激しく、上位表示が困難です。
逆に、検索ボリュームが少なすぎると、上位表示できても十分な集客効果が得られません。
次に、自社のビジネスやコンテンツとの関連性を確認します。
いくら検索ボリュームが多くても、自社の商品やサービスと関係のないキーワードでは意味がありません。
また、ユーザーの検索意図を明確に想定できるキーワードを選ぶことも重要です。
例えば、「SEO対策」というキーワードだけでは、ユーザーが「SEOとは何か知りたい」のか、「SEO対策の方法を学びたい」のか、「SEO対策会社を探している」のか判断できません。
一方、「SEO対策 やり方」であれば、具体的な方法を知りたいという意図が明確です。
- 検索ボリュームが適度にある(月間100~1,000回程度から始める)
- 自社のビジネスやコンテンツと関連性が高い
- ユーザーの検索意図が明確に推測できる
- 競合サイトの強さを考慮して現実的に上位表示を狙える
メインキーワードを選定したら、そのキーワードを軸にコンテンツ全体を構成していきます。
検索意図に沿った構成
メインキーワードを選定したら、次に重要なのがそのキーワードで検索するユーザーの意図を深く理解することです。
検索意図とは、ユーザーがそのキーワードで検索する際に「何を知りたいのか」「何を解決したいのか」という目的のことです。
検索意図は、大きく分けて以下の4つのタイプに分類されます。
- 情報収集型(Know):特定の情報や知識を得たい
- ナビゲーション型(Go):特定のWebサイトにアクセスしたい
- 取引型(Do):商品購入やサービス利用などの行動をしたい
- 調査型(Know Simple):簡単な事実や答えを知りたい
例えば、「SEO キーワード 多すぎ」で検索するユーザーは、情報収集型に該当します。
このユーザーは、「キーワードを多く入れすぎるとどうなるのか」「適切なキーワード数はどれくらいか」といった情報を求めています。
したがって、このキーワードで作成するコンテンツには、以下の要素が必要です。
| ユーザーが知りたいこと | コンテンツに含めるべき内容 |
| キーワードが多すぎる問題 | リスクやペナルティについての説明 |
| 適切なキーワード数 | 具体的な目安や基準の提示 |
| 正しい設定方法 | 実践的な手順やテクニック |
| 確認方法 | チェックツールの紹介と使い方 |
検索意図に沿った構成を作るには、実際にそのキーワードでGoogle検索を行い、上位表示されているページを分析することが効果的です。
上位10位程度のページがどのような内容を扱っているか、どのような構成になっているかを確認することで、Googleが評価しているコンテンツの傾向が見えてきます。
ただし、競合サイトをそのまま真似するのではなく、自社ならではの独自の視点や情報を加えることが重要です。
複数キーワードで上位表示される仕組み
「1ページ1キーワード」という原則がある一方で、実際には1つのページが複数のキーワードで上位表示されることがあります。
これは矛盾しているように感じるかもしれませんが、実は自然な結果なのです。
質の高いコンテンツを作成すると、メインキーワードだけでなく、関連する複数のキーワードでも検索エンジンに認識されます。
例えば、「ノートパソコン 選び方」をメインキーワードとした記事を作成した場合、自然と以下のようなキーワードも含まれるはずです。
- 「ノートパソコン おすすめ」
- 「ノートパソコン 初心者」
- 「軽量 ノートパソコン」
- 「ノートパソコン バッテリー」
これらのキーワードは、記事の中で自然に使用される関連語です。
Googleの検索エンジンは、これらの関連語も認識し、「このページはノートパソコンに関する総合的な情報を提供している」と判断します。
その結果、メインキーワード以外の関連キーワードでも検索結果に表示されるようになるのです。
重要なのは、無理に複数のキーワードを詰め込むのではなく、1つのテーマを深く掘り下げることです。
| 正しいアプローチ | 誤ったアプローチ |
| メインテーマを深く掘り下げる | 複数の異なるテーマを1ページに詰め込む |
| 関連キーワードが自然に含まれる | 意図的に多くのキーワードを羅列する |
| 結果的に複数キーワードで上位表示 | どのキーワードでも上位表示できない |
また、サイト全体のドメインパワー(サイトの信頼性や権威性)が高まると、より多くのキーワードで上位表示されやすくなります。
そのためには、継続的に質の高いコンテンツを増やしていくことが重要です。
キーワード出現率の適切な目安
キーワード出現率とは、ページ全体の単語数に対して、特定のキーワードが何回出現するかの割合を示す指標です。
以前は「キーワード出現率を5~7%にする」といった具体的な数値目標が推奨されていました。
しかし、現在では具体的な数値よりも「自然な使用」が重視されるようになっています。
とはいえ、完全に無視してよいわけではありません。
あまりにも少なすぎると、検索エンジンがページの内容を正確に理解できない可能性があります。
逆に多すぎると、キーワードスタッフィングと判断されるリスクがあります。
一般的な目安としては、以下のような数値が参考になります。
- メインキーワード:3~7%程度
- サブキーワード:2~5%程度
- 出現率が3%未満:やや少ない(効果が薄い可能性)
- 出現率が8%以上:多すぎる(ペナルティのリスク)
ただし、これらはあくまで参考値です。
コンテンツの内容や文字数によって適切な出現率は変わります。
例えば、専門的な技術記事では、専門用語が自然と多く出現するため、出現率が高くなる傾向があります。
一方、初心者向けの解説記事では、分かりやすさを優先するため、同じキーワードを繰り返すよりも言い換え表現を使うことが多くなります。
| コンテンツタイプ | 適切な出現率の傾向 | 理由 |
| 専門技術記事 | やや高め(5~7%) | 専門用語が自然と多く使用される |
| 初心者向け解説 | やや低め(3~5%) | 言い換えや具体例を多用する |
| 比較・まとめ記事 | 中程度(4~6%) | 複数の観点から説明する |
最も重要なのは、出現率の数値にこだわるよりも、読者にとって分かりやすく読みやすい文章を書くことです。
自然な文章を書いた結果として適切な出現率に収まっているというのが理想的な状態です。
株式会社エッコでは、キーワード出現率のチェックだけでなく、コンテンツ全体の質を総合的に評価したSEOコンサルティングを提供しています。
キーワードを配置すべき場所
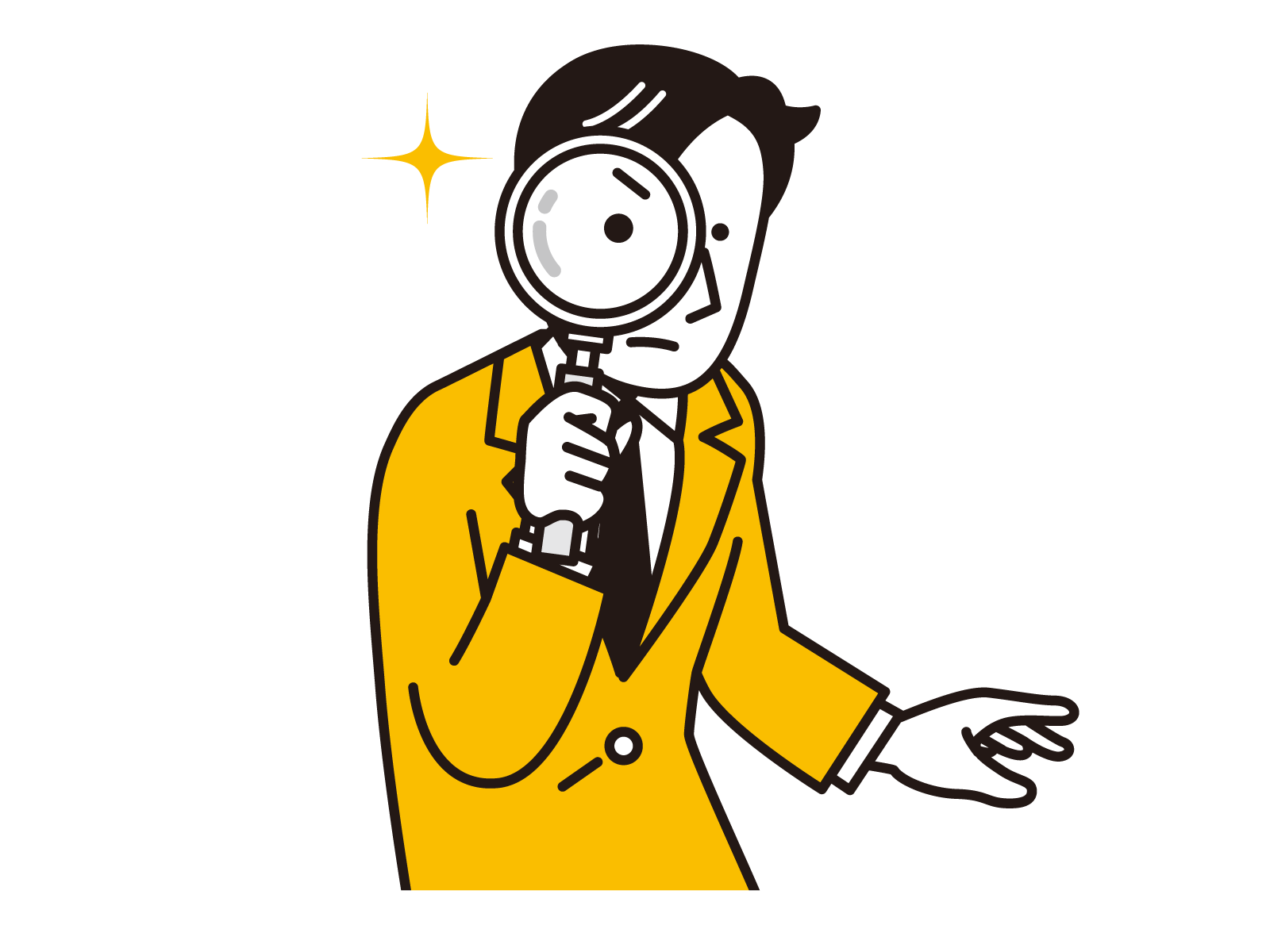
タイトルタグでの最適な使用
タイトルタグは、SEOにおいて最も重要な要素の一つです。
検索結果に表示されるタイトルは、ユーザーがクリックするかどうかを判断する最初の情報となります。
また、検索エンジンにとっても、そのページが何について書かれているかを理解する重要な手がかりとなります。
タイトルタグにキーワードを配置する際の基本ルールは以下の通りです。
- メインキーワードは必ず含める
- キーワードはタイトルの前半(左側)に配置する
- 同じキーワードを複数回繰り返さない
- タイトルの長さは30~35文字程度に収める
- 自然で魅力的な文章にする
特に重要なのが、キーワードをタイトルの前半に配置することです。
人の視線は左から右に移動するため、前半にあるキーワードの方が目に留まりやすくなります。
また、検索結果に表示されるタイトルは30文字程度で切れてしまうため、後半にキーワードを配置すると表示されない可能性があります。
| 良いタイトル例 | 改善が必要なタイトル例 |
| SEOキーワードは多すぎるとNG?適切な設定方法 | これだけは知っておきたい!上位表示を達成するためにコンテンツに含めるべきSEOキーワードの適切な数を徹底解説 |
| ノートパソコンの選び方│初心者向け完全ガイド | 初心者の方にも分かりやすく解説!失敗しないノートパソコン |
良いタイトルの例では、メインキーワードが前半に配置され、かつ内容が明確に伝わります。
一方、改善が必要な例では、タイトルが長すぎて途中で切れてしまい、重要なキーワードが表示されない可能性があります。
また、キーワードを無理に詰め込もうとすると、不自然な文章になってしまいます。
「SEO対策とは?SEO対策のやり方やSEO会社にSEO対策を依頼する費用を解説!」のように、同じキーワードを何度も繰り返すタイトルは避けましょう。
ユーザーの興味を引き、かつ内容を正確に伝えるタイトルを心がけることが重要です。
見出し(h2・h3)への自然な配置
見出しタグ(h2、h3など)は、コンテンツの構造を示す重要な要素です。
見出しにキーワードを含めることで、そのセクションが何について説明しているかを明確に伝えることができます。
ただし、タイトルタグと同様に、無理にキーワードを詰め込むのは逆効果です。
見出しは、読者がコンテンツの内容を素早く把握するためのものでもあります。
目次として表示されることも多いため、読みやすく分かりやすい見出しを作ることが重要です。
特にh2タグ(大見出し)には、メインキーワードや関連キーワードを含めることが効果的です。
一方、h3タグ以下の小見出しでは、キーワードを含めることにこだわりすぎる必要はありません。
内容を適切に表現した結果として、自然にキーワードが含まれる程度で十分です。
- h2タグには意識的にキーワードを含める(ただし自然な文章で)
- h3タグ以下は内容を優先し、無理にキーワードを入れない
- 同じ見出しの繰り返しを避ける
- ユーザーが内容を理解しやすい見出しにする
例えば、本記事の見出し構成を見てみましょう。
h2「SEOキーワードと数の関係」では、メインキーワードである「SEOキーワード」と「数」が自然に含まれています。
h3「キーワード数がSEOに与える影響」では、「キーワード数」と「SEO」が含まれていますが、文章として自然です。
一方、h4「メインキーワードの選定方法」では、「キーワード」という単語は含まれていますが、無理に「SEO」を入れる必要はありません。
このように、見出しの階層が下がるにつれて、キーワードの使用頻度は下がっても問題ありません。
むしろ、すべての見出しに同じキーワードを含めようとすると、不自然で読みにくい構成になってしまいます。
本文中での効果的な使い方
本文中でのキーワードの使い方は、SEO効果とユーザー体験の両方に影響します。
まず押さえておくべきポイントは、導入部分(ページ上部)にキーワードを含めることです。
ユーザーは、ページを開いた直後に「このページには自分が求める情報があるのか」を判断します。
導入部分にメインキーワードが含まれていれば、ユーザーは「このページで正しい」と安心できます。
また、検索エンジンも、ページの上部にあるテキストをより重要なものとして扱う傾向があります。
本文中でキーワードを使用する際は、以下の点に注意しましょう。
- 文章の最初の段落(導入文)にキーワードを含める
- 各セクションの冒頭や結論部分にキーワードを自然に配置する
- 同じキーワードを連続して使わない
- 言い換え表現や関連語を積極的に活用する
- ユーザーにとって読みやすい文章を最優先する
例えば、「SEO対策」というキーワードを使う場合、毎回「SEO対策」と書くのではなく、「検索エンジン最適化」「SEO施策」「SEOの取り組み」など、文脈に応じて言い換えることで、文章が単調にならず読みやすくなります。
| 配置場所 | 重要度 | ポイント |
| 導入文(最初の段落) | 非常に高い | 必ずメインキーワードを含める |
| 各セクションの冒頭 | 高い | 自然な形でキーワードを使用 |
| まとめ・結論部分 | 高い | キーワードを含めて内容を総括 |
| 本文の中盤 | 中程度 | 過度な使用は避ける |
また、キーワードを太字(ボールド)にすることで、重要なポイントを強調できます。
ただし、すべてのキーワードを太字にするのは逆効果です。
本当に重要なポイントだけを太字にすることで、メリハリのある読みやすい文章になります。
メタディスクリプションでの活用
メタディスクリプションは、検索結果のタイトル下に表示される説明文です。
HTMLのmetaタグで設定する内容で、通常120文字程度が表示されます。
メタディスクリプションは、検索順位に直接影響しないとGoogleが公式に述べています。
しかし、クリック率(CTR)には大きく影響するため、SEO戦略において無視できない要素です。
メタディスクリプションを設定する際のポイントは以下の通りです。
- メインキーワードを1~2回含める
- ページの内容を正確に要約する
- ユーザーの興味を引く魅力的な文章にする
- 120文字程度に収める(スマートフォンでは短く表示される)
- 行動を促す表現を含める(「詳しく解説」「分かりやすく説明」など)
メタディスクリプションにキーワードを含める最大のメリットは、検索結果画面でそのキーワードが太字表示されることです。
ユーザーが「SEO キーワード 多すぎ」で検索した場合、これらのキーワードが含まれているディスクリプションでは、該当部分が太字で強調表示されます。
これにより、ユーザーの目に留まりやすくなり、クリック率が向上します。
| 良いディスクリプション例 | 改善が必要な例 |
| SEOキーワードは多すぎるとペナルティのリスクがあります。本記事では、適切なキーワード数の目安や、自然な配置方法について詳しく解説します。 | このページではSEOについて説明しています。SEO対策、SEOキーワード、SEO施策など様々な情報を掲載していますのでぜひご覧ください。 |
良い例では、ページの内容が具体的に説明され、メインキーワードも自然に含まれています。
一方、改善が必要な例では、キーワードの羅列になっており、具体的な内容が伝わりません。
ただし、メタディスクリプションを設定しても、Googleが別のテキストを表示することもあります。
特に、検索クエリによっては、ページ本文から関連性の高い部分を自動的に抽出して表示する場合があります。
これは、より適切な情報をユーザーに提供するためのGoogleの仕組みです。
画像のalt属性への設定
画像のalt属性(代替テキスト)は、画像が表示されない場合に代わりに表示されるテキストです。
また、視覚障害のある方がスクリーンリーダーを使用する際にも読み上げられます。
SEOの観点では、検索エンジンが画像の内容を理解するための重要な情報源となります。
alt属性にキーワードを含めることで、以下のメリットがあります。
- 画像検索での表示機会が増える
- ページ全体のテーマとの関連性を強化できる
- アクセシビリティが向上する(すべてのユーザーに配慮したサイトとして評価される)
ただし、alt属性も他の要素と同様に、無理にキーワードを詰め込むのは避けるべきです。
画像の内容を正確に説明する文章を書き、その中に自然にキーワードが含まれることが理想です。
- 画像の内容を具体的に説明する
- メインキーワードを自然な形で含める
- すべての画像に同じalt属性を設定しない
- 装飾的な画像には空のalt属性(alt=””)を設定する
例えば、「SEOキーワードの適切な配置を示す図解」という画像であれば、alt属性は「SEOキーワードの適切な配置を示す図解」とするのが適切です。
一方、「SEO、SEO対策、SEOキーワード、キーワード設定、検索エンジン最適化」のようにキーワードを羅列するのは不適切です。
これもキーワードスタッフィングと見なされる可能性があります。
また、すべての画像にalt属性を設定する必要はありません。
デザイン上の装飾画像や、本文で既に説明されている内容と重複する画像には、空のalt属性(alt=””)を設定することで、スクリーンリーダーが不要な読み上げをしなくなります。
キーワード以外で重要な要素

関連キーワードと共起語の活用
SEO対策では、メインキーワードだけでなく、関連キーワードや共起語を適切に使用することが非常に重要です。
関連キーワードとは、メインキーワードと関連性の高い言葉のことです。
例えば、「SEO対策」がメインキーワードであれば、「検索エンジン」「上位表示」「キーワード選定」「コンテンツ」などが関連キーワードになります。
一方、共起語とは、特定のキーワードと一緒に使われることが多い言葉のことです。
「SEO対策」の共起語には、「Google」「検索順位」「アクセス数」「内部対策」「外部対策」などがあります。
関連キーワードや共起語を使用するメリットは以下の通りです。
- ページのテーマがより明確になる
- 同じキーワードの繰り返しを避けられる
- コンテンツの専門性が高まる
- より多くの検索クエリでヒットする可能性が高まる
Googleの検索エンジンは、これらの関連語を総合的に判断して、ページの内容を理解しています。
メインキーワードだけを多用するよりも、関連キーワードや共起語を豊富に含めた方が、コンテンツの質が高いと評価される傾向があります。
| 使用する言葉の種類 | 役割 | 使用頻度の目安 |
| メインキーワード | テーマの中心 | 適度に(3~7%) |
| 関連キーワード | テーマの補強 | 積極的に使用 |
| 共起語 | 専門性の証明 | 自然に含める |
| 同義語・類義語 | 読みやすさ向上 | 言い換えとして活用 |
関連キーワードや共起語を調べるには、専用のツールを使うと便利です。
無料で使えるツールとしては、Googleの検索結果に表示される「他のキーワード」や、ラッコキーワードなどがあります。
株式会社エッコでは、効果的な関連キーワードの選定と、自然な形でのコンテンツへの組み込みをサポートしています。
サジェストキーワードの取り入れ方
サジェストキーワードとは、Google検索で検索窓にキーワードを入力した際に、自動的に表示される候補のことです。
これらは実際に多くのユーザーが検索しているキーワードの組み合わせであり、ユーザーのニーズを知る重要な手がかりとなります。
例えば、「SEO キーワード」と入力すると、「SEO キーワード 選び方」「SEO キーワード 数」「SEO キーワード ツール」などのサジェストが表示されます。
これらのサジェストキーワードを記事に取り入れることで、より多くのユーザーの検索意図に応えることができます。
ただし、注意すべき点があります。
それは、すべてのサジェストキーワードを無理に詰め込もうとしないことです。
サジェストキーワードの中には、メインキーワードと検索意図が異なるものも含まれています。
例えば、「SEO キーワード 英語」というサジェストは、英語でのSEO対策を知りたいユーザーの検索意図であり、日本語のSEO対策を解説する記事とは異なります。
- メインキーワードと検索意図が一致するサジェストを選ぶ
- 1つの記事で対応できる範囲のサジェストに絞る
- サジェストキーワードは見出しに含めると効果的
- 無関係なサジェストは別記事で対応する
サジェストキーワードの取り入れ方として効果的なのは、h3やh4の見出しに使用することです。
例えば、「SEO キーワード 選び方」がサジェストであれば、「メインキーワードの選定方法」という見出しで対応できます。
このように、サジェストキーワードを意識しながらも、自然な文章構成を保つことが重要です。
また、サジェストキーワードは定期的に変化します。
トレンドや季節によって検索されるキーワードが変わるためです。
そのため、定期的にサジェストキーワードを確認し、必要に応じてコンテンツを更新することも効果的なSEO戦略です。
ユーザーの検索意図への対応
SEO対策において最も重要なのは、ユーザーの検索意図を正確に理解し、それに応えるコンテンツを提供することです。
どれだけキーワードを適切に配置しても、ユーザーの求める情報がなければ、検索エンジンから高い評価は得られません。
検索意図を理解するためには、以下の方法が効果的です。
まず、そのキーワードで実際にGoogle検索を行い、上位表示されているページを分析します。
どのような内容が書かれているか、どのような構成になっているか、どのような情報が提供されているかを確認しましょう。
次に、検索結果画面の「他のユーザーも行った質問」セクションを確認します。
ここには、そのキーワードに関連してユーザーがよく検索する質問が表示されます。
また、Googleの検索結果の最下部に表示される「他のキーワード」も参考になります。
これらの情報を総合することで、ユーザーが本当に知りたいことが見えてきます。
- 上位表示ページの内容を分析する
- 「他のユーザーも行った質問」を確認する
- 関連検索キーワードを調査する
- SNSやQ&Aサイトでユーザーの悩みを調べる
例えば、「ノートパソコン 選び方」というキーワードで検索するユーザーは、単にノートパソコンの種類を知りたいわけではありません。
「自分の用途に合ったノートパソコンを選びたい」「失敗しない選び方を知りたい」「価格と性能のバランスを理解したい」といった具体的なニーズを持っています。
したがって、このキーワードに対応する記事では、用途別の選び方、チェックすべきスペック、予算別のおすすめなど、購入判断に必要な情報を網羅的に提供する必要があります。
| ユーザーの検索意図 | 提供すべき情報 |
| 知識を得たい | 基本的な説明、用語解説 |
| 方法を知りたい | 手順、やり方、ステップ |
| 比較したい | 選択肢の提示、比較表、メリット・デメリット |
| 問題を解決したい | 原因の説明、解決方法、具体的な対策 |
ユーザーの検索意図に応えることで、滞在時間が延び、直帰率が下がり、結果として検索エンジンからの評価も高まります。
コンテンツの質と網羅性
SEOにおいて、コンテンツの質と情報の網羅性は、キーワード数よりもはるかに重要な要素です。
Googleは「有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成」を推奨しています。
質の高いコンテンツとは、以下の要素を満たすものです。
- 正確で信頼できる情報を提供している
- ユーザーの疑問や課題を解決できる
- 独自の視点や経験に基づいた内容が含まれる
- 読みやすく理解しやすい構成になっている
- 最新の情報に更新されている
また、情報の網羅性も重要です。
ユーザーがそのトピックについて知りたいことを、1つのページで完結できることが理想的です。
ただし、網羅性を追求するあまり、不要な情報まで詰め込むのは逆効果です。
ユーザーの検索意図に関連する情報を過不足なく提供することが重要です。
- ユーザーが知りたい情報を漏れなく含める
- 逆に、検索意図と関係ない情報は含めない
- 専門用語には説明を加える
- 図表や画像を使って視覚的に分かりやすくする
- 信頼できる情報源を引用する
例えば、「SEO キーワード 多すぎ」で検索するユーザーは、以下の情報を求めています。
- キーワードが多すぎるとどうなるのか(リスク)
- 適切なキーワード数の目安
- キーワードの正しい配置方法
- チェック方法や具体的なテクニック
これらの情報を網羅的に、かつ分かりやすく提供することで、質の高いコンテンツとなります。
一方、「SEOとは何か」「SEO対策会社の選び方」といった、検索意図と直接関係のない情報を含める必要はありません。
| 質の高いコンテンツ | 質の低いコンテンツ |
| ユーザーの疑問を解決する | 一般的な情報の寄せ集め |
| 独自の視点や経験がある | 他サイトのコピー |
| 最新の情報に更新されている | 古い情報のまま放置 |
| 読みやすく構成されている | 読みにくく理解しづらい |
株式会社エッコでは、キーワード設定だけでなく、ユーザーに真に価値あるコンテンツの企画・制作をサポートしています。
名古屋でWebコンサルティングをお探しの方は、ぜひご相談ください。
キーワード数のチェック方法

キーワード出現率チェックツール
キーワード出現率をチェックするためのツールは、無料で利用できるものがいくつか存在します。
これらのツールを活用することで、自分のコンテンツがキーワードを適切に使用できているかを客観的に確認できます。
代表的なツールとしては、以下のものがあります。
- ohotuku.jp キーワード出現率チェックツール
- ファンキーレイティング キーワード出現率チェッカー
- SEOチェキ!(総合的なSEOチェックツール)
これらのツールの基本的な使い方は共通しています。
チェックしたいページのURLを入力し、対象キーワードを指定すると、そのキーワードがページ内に何回出現しているか、出現率は何パーセントかが表示されます。
ただし、これらのツールを使う際には注意点があります。
それは、ツールの数値に過度にこだわらないことです。
ツールが示す数値はあくまで参考情報であり、その数値を達成することが目的ではありません。
| ツールの活用方法 | 推奨される使い方 | 避けるべき使い方 |
| 現状確認 | 現在の出現率を知る | 数値目標として固執する |
| 過剰使用の防止 | 8%以上になっていないか確認 | 5%にするために無理に調整 |
| 競合比較 | 競合サイトとの傾向を比較 | 競合と全く同じ数値を目指す |
キーワード出現率チェックツールは、主に「キーワードを詰め込みすぎていないか」を確認するために使用するのが適切です。
出現率が8%を超えている場合は、不自然にキーワードを使いすぎている可能性があるため、文章を見直すきっかけになります。
逆に、出現率を人為的に上げるためにツールを使うのは本末転倒です。
自然な文章を書いた結果として、適切な出現率に収まっていることが理想です。
競合サイトとの比較分析
自分のコンテンツが適切なキーワード使用になっているかを判断する方法として、競合サイトとの比較分析が有効です。
対策キーワードで実際にGoogle検索を行い、上位10位程度のページを分析しましょう。
競合サイトを分析する際にチェックすべきポイントは以下の通りです。
- キーワード出現率(前述のツールを使用)
- タイトルや見出しでのキーワード使用方法
- コンテンツの構成や文字数
- 関連キーワードや共起語の使用状況
- ユーザーへの情報提供の仕方
特に注目すべきは、上位3~5位のサイトです。
これらは、Googleが現在最も高く評価しているコンテンツと言えます。
ただし、単純にコピーするのではなく、「なぜこのコンテンツが評価されているのか」を分析することが重要です。
- 上位3~5位のサイトの共通点を探す
- キーワード出現率の中央値を参考にする
- 自分のコンテンツとの差異を明確にする
- 競合にない独自の価値を加える
例えば、上位5サイトのキーワード出現率が4.2%、4.8%、5.1%、4.5%、5.3%だった場合、中央値は4.8%程度です。
この場合、自分のコンテンツも4~5%程度を目安にするのが妥当でしょう。
ただし、この数値はあくまで参考です。
より重要なのは、競合サイトがどのような情報を提供しているか、ユーザーのどのようなニーズに応えているかを理解することです。
競合分析を通じて、自分のコンテンツに不足している情報や、改善すべきポイントが見えてきます。
過剰使用の判断基準
キーワードの過剰使用を判断する基準は、数値だけではありません。
**最も重要な判断基準は「ユーザーにとって読みやすいか」**です。
以下のチェックリストを使って、自分のコンテンツを客観的に評価してみましょう。
- 声に出して読んでみて不自然な繰り返しはないか
- 同じキーワードが連続して出現していないか
- キーワードを含めるために不自然な文章になっていないか
- 読者が「しつこい」と感じる可能性はないか
- 情報の質よりもキーワードの使用を優先していないか
もし1つでも該当する項目があれば、キーワードを過剰に使用している可能性があります。
数値的な判断基準としては、以下を参考にしてください。
| 判断基準 | 評価 | 対応 |
| 出現率3%未満 | やや少ない | 自然な範囲で増やすことを検討 |
| 出現率3~7% | 適切 | 特に調整の必要なし |
| 出現率7~8% | やや多い | 不自然な繰り返しがないか確認 |
| 出現率8%以上 | 多すぎる | 言い換え表現を使って調整 |
また、Googleサーチコンソールのデータも参考になります。
特定のページで「クリック率が低い」「平均掲載順位は高いのに流入が少ない」といった傾向が見られる場合、タイトルやディスクリプションでのキーワード使用が不適切な可能性があります。
キーワードの過剰使用かどうかを判断する際は、第三者に読んでもらうことも効果的です。
自分では気づかない不自然さを指摘してもらえることがあります。
株式会社エッコでは、プロの視点からコンテンツの質とキーワード使用のバランスを客観的に評価し、改善提案を行っています。
キーワード最適化の実践テクニック

自然な文章での使用を心がける
キーワードを効果的に使用するための最も重要なテクニックは、自然な文章の中でキーワードを使うことです。
SEO対策を意識するあまり、不自然な文章になってしまっては本末転倒です。
自然な文章でキーワードを使用するためのコツは以下の通りです。
まず、キーワードありきで文章を書くのではなく、伝えたい内容をまず考え、その中にキーワードを自然に組み込むという順序で進めます。
例えば、「SEO対策でキーワードを適切に設定することは重要です」という文章は自然です。
一方、「SEO対策のキーワード設定はSEO対策において重要なSEO対策の一つです」という文章は明らかに不自然です。
次に、接続詞や助詞を適切に使用して、文章の流れを滑らかにします。
「SEO対策では、キーワードの選定が重要です。しかし、選定したキーワードを詰め込みすぎると逆効果になります」のように、論理的なつながりを意識しましょう。
- 伝えたい内容を先に考える
- 一文が長くなりすぎないようにする
- 同じ文章構造の繰り返しを避ける
- 接続詞を効果的に使う
- 読者に語りかけるような自然なトーンを保つ
また、文章のリズムも重要です。
短い文と長い文を適度に組み合わせることで、読みやすく飽きさせない文章になります。
キーワードを含む文章が連続する場合は、間に別の表現を挟むことで単調さを避けられます。
自然な文章かどうかを確認する簡単な方法は、声に出して読んでみることです。
読みにくい部分、つっかえる部分があれば、そこは不自然な文章である可能性が高いです。
同義語や言い換え表現の活用
同じキーワードを繰り返し使うのではなく、同義語や言い換え表現を積極的に活用することで、文章の質が大きく向上します。
これは、読みやすさの向上とSEO効果の両方に寄与します。
例えば、「SEO対策」というキーワードを使う場合、以下のような言い換えが可能です。
- 検索エンジン最適化
- SEO施策
- 検索順位向上の取り組み
- SEOの取り組み
- 検索エンジン対策
これらを文脈に応じて使い分けることで、同じキーワードの繰り返しを避けられます。
また、Googleの検索エンジンは、これらの類義語を理解し、同じ意味として認識する能力があります。
したがって、無理に同じキーワードを使う必要はありません。
| メインキーワード | 言い換え表現の例 |
| Webサイト | ホームページ、サイト、Webページ |
| ユーザー | 読者、訪問者、利用者、閲覧者 |
| コンテンツ | 記事、情報、内容、ページ |
| 上位表示 | 検索上位、高順位、ランキング向上 |
言い換え表現を使う際のポイントは以下の通りです。
- 文脈に合った適切な言い換えを選ぶ
- 専門用語と平易な表現を使い分ける
- 初出時は正式な表現、2回目以降は簡潔な表現を使う
- 読者層に合わせた言葉選びをする
例えば、専門家向けの記事であれば「検索エンジン最適化」という正式な表現を多用しても問題ありませんが、初心者向けの記事では「SEO対策」という分かりやすい表現の方が適切です。
また、同じ段落内で同じキーワードが複数回出現する場合は、特に言い換え表現を使うことを意識しましょう。
同じ語句を3回以上連続して使うのは避けるのが基本です。
ユーザー目線のコンテンツ作成
SEO対策の本質は、ユーザーにとって価値あるコンテンツを提供することです。
キーワードの最適化も、この大原則の中で行うべきです。
ユーザー目線でコンテンツを作成するためには、以下のポイントを意識しましょう。
まず、読者がどのような悩みや疑問を持ってこのページに辿り着いたのかを想像します。
例えば、「SEO キーワード 多すぎ」で検索する人は、「自分のサイトはキーワードを使いすぎているのではないか」という不安を抱えているかもしれません。
そのような読者に対して、「キーワードが多すぎるとペナルティを受けます」と脅すだけでは不十分です。
「では、どうすれば適切なキーワード使用ができるのか」という解決策まで提示する必要があります。
次に、専門用語を使う際は、必ず説明を加えます。
「キーワードスタッフィング」という用語も、初めて聞く人には意味が分かりません。
「キーワードスタッフィング(キーワードの詰め込み)とは…」のように、括弧書きで補足したり、別途説明したりする配慮が必要です。
- 読者の知識レベルを想定する
- 専門用語には説明を加える
- 具体例を豊富に使う
- 読者の不安や疑問に寄り添う表現を使う
- 一方的な説明ではなく、対話的な文章にする
また、視覚的な分かりやすさも重要です。
長い文章が続くと読みづらくなるため、適度に表や箇条書きを使って情報を整理します。
重要なポイントは太字にして強調し、読者が流し読みをしても要点を把握できるようにします。
ユーザー目線のコンテンツを作成することで、滞在時間が長くなり、直帰率が下がります。
これらの指標は、Googleがページの品質を判断する際の重要な要素となります。
つまり、ユーザーのためにコンテンツを作ることが、結果的に最良のSEO対策になるのです。
定期的な見直しとリライト
一度作成したコンテンツも、定期的に見直しとリライトを行うことが重要です。
SEOアルゴリズムは常に進化していますし、ユーザーのニーズや検索トレンドも変化します。
また、競合サイトも日々コンテンツを改善しているため、過去に上位表示されていたページでも、放置すれば順位が下がる可能性があります。
定期的な見直しでチェックすべきポイントは以下の通りです。
まず、情報の鮮度を確認します。
データや統計、法律や制度に関する情報は、時間とともに古くなります。
最新の情報に更新することで、ユーザーにとっての価値が高まります。
次に、検索順位やアクセス数の変化を確認します。
GoogleサーチコンソールやGoogleアナリティクスを使って、どのページの順位が下がっているか、どのページのアクセスが減っているかを把握しましょう。
順位が下がっているページは、競合との比較分析を行い、不足している情報を追加します。
- 3~6ヶ月に1回は主要ページを見直す
- 最新の情報やデータに更新する
- ユーザーの新しいニーズに対応する
- 競合サイトの変化を確認する
- サーチコンソールのデータを分析する
リライトの際に、キーワードの使用方法も見直しましょう。
過去に作成したコンテンツでは、キーワードを多用しすぎていたり、逆に不足していたりする可能性があります。
現在のSEOの考え方に沿って、自然なキーワード使用に修正します。
また、新しい関連キーワードやサジェストキーワードが出現していないかも確認します。
トレンドの変化によって、ユーザーが使う検索語句も変わっていきます。
新しいキーワードに対応することで、より多くのユーザーにリーチできます。
| 見直しの頻度 | 対象ページ | チェック内容 |
| 毎月 | 主要な売上貢献ページ | 順位変動、アクセス数、コンバージョン率 |
| 3ヶ月ごと | 上位表示を狙うページ | 競合の動向、情報の鮮度 |
| 6ヶ月ごと | すべてのページ | 全体的な改善点、リンク切れ |
リライトを行う際は、変更前と変更後の効果を必ず測定しましょう。
どのような変更が効果的だったかを記録しておくことで、今後のコンテンツ制作に活かせます。
株式会社エッコでは、継続的なコンテンツ改善とSEO効果の測定をサポートしています。
名古屋でWebサイトの運用にお悩みの方は、ぜひご相談ください。
まとめ

SEOキーワードの適切な設定について、本記事では多くのポイントを解説してきました。
最も重要なことは、キーワードを多く入れることが目的ではなく、ユーザーにとって価値あるコンテンツを提供することが目的だということです。
現代のSEOでは、キーワードの数や出現率は検索順位への直接的な影響が小さくなっています。
Googleの検索エンジンは、文脈や文章全体の意味を理解し、ユーザーの検索意図に最も合致するコンテンツを評価できるようになりました。
したがって、キーワードを単純に多く使用するだけでは、検索順位の向上にはつながりません。
むしろ、キーワードを詰め込みすぎると、キーワードスタッフィングと判断され、Googleからペナルティを受けるリスクさえあります。
適切なキーワード設定のために、以下の基本原則を押さえておきましょう。
「1ページ1キーワード」の原則を守る
1つのページで対策するメインキーワードは1つに絞りましょう。
複数のテーマを1つのページで扱うと、検索エンジンもユーザーも内容を理解しづらくなります。
キーワードを配置すべき場所を理解する
タイトルタグ、見出しタグ、本文の導入部分など、重要な場所には意識的にキーワードを配置します。
ただし、すべての場所に無理に詰め込む必要はありません。
キーワード出現率は3~7%程度を目安にする
ただし、この数値に固執する必要はありません。
自然な文章を書いた結果として、この範囲に収まっていることが理想です。
関連キーワードや共起語を活用する
メインキーワードだけでなく、関連語を豊富に使うことで、コンテンツの専門性が高まります。
同義語や言い換え表現を積極的に使う
同じキーワードを繰り返すのではなく、文脈に応じて言い換えることで、読みやすい文章になります。
定期的な見直しとリライトを行う
一度作成したコンテンツも、情報の更新や改善を継続的に行うことで、長期的なSEO効果が期待できます。
そして何よりも重要なのは、常にユーザーを第一に考えることです。
「この情報は読者の役に立つか」「読者は満足できるか」という視点でコンテンツを作成すれば、自然とSEOにも効果的なコンテンツになります。
SEO対策は一朝一夕で結果が出るものではありません。
しかし、正しい方向性で継続的に取り組むことで、確実に成果を得ることができます。
名古屋のWebコンサル会社である株式会社エッコでは、このような現代のSEOに即したコンテンツ制作とキーワード戦略をサポートしています。
キーワード設定の適正化から、ユーザー目線のコンテンツ企画、継続的な改善支援まで、総合的なWebコンサルティングサービスを提供しています。
「自社のWebサイトのSEO対策を見直したい」
「キーワード設定が適切かどうか診断してほしい」
「ユーザーに評価されるコンテンツを作りたい」
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ株式会社エッコにご相談ください。
貴社のビジネス目標達成に向けて、最適なSEO戦略をご提案いたします。
本記事で解説した内容を実践し、ユーザーにとって本当に価値あるコンテンツを作成していきましょう。
適切なキーワード設定と質の高いコンテンツで、検索エンジンからもユーザーからも評価されるWebサイトを目指してください。



