ウェブサイトの検索順位を向上させるために、コンテンツの質やキーワード選定に力を入れている方は多いでしょう。
しかし、意外と見落とされがちなのが「URLの最適化」です。
URLは、インターネット上における各ページの住所であり、検索エンジンとユーザーの両方にとって重要な情報源となります。
適切に設計されたURLは、検索エンジンがページ内容を理解しやすくなるだけでなく、ユーザーがクリックしやすい要素としても機能します。
本記事では、SEOにおけるURLの重要性から、具体的な最適化手法、既存URLの改善方法まで、実践的なノウハウを詳しく解説していきます。
GoogleのJohn Mueller氏も「小さいながら確実な効果がある」と認めているURL最適化を、今日から実践していきましょう。
Index
SEOにおけるURLの重要性

URLとSEOの関係
URLがSEOに与える影響について、多くのウェブマスターが疑問を持っています。
結論から申し上げますと、URLは直接的なランキング要因としては小さいものの、間接的には確実にSEOに影響を与えます。
GoogleのJohn Mueller氏は、「URLにキーワードを含めることは検索順位にとって非常に小さな要素だが、効果はある」と明言しています。
つまり、URLだけで劇的に順位が上がるわけではありませんが、総合的なSEO戦略の一部として無視できない要素なのです。
URLは複数の側面からSEOに貢献します。
まず、検索エンジンのクローラーがページ内容を理解する手がかりとなります。
次に、検索結果画面に表示される要素として、ユーザーのクリック判断に影響を与えます。
さらに、SNSでシェアされたり、他サイトからリンクされたりする際に、URLそのものがアンカーテキストとして機能することもあります。
Google検索セントラルの公式ガイドラインでも、URL構造はできる限りシンプルで、ユーザーが理解しやすいものにすることが推奨されています。
これは、Googleがユーザー体験を最重視している証拠であり、分かりやすいURLがサイト全体の評価向上につながることを示しています。
| URLのSEO影響要素 | 直接的効果 | 間接的効果 | 重要度 |
| キーワード含有 | 小 | 中 | ★★★☆☆ |
| シンプルさ | 小 | 大 | ★★★★☆ |
| クリック率向上 | なし | 大 | ★★★★☆ |
| クローラビリティ | 中 | 大 | ★★★★★ |
| アンカーテキスト機能 | なし | 中 | ★★★☆☆ |
検索エンジンのURL認識
検索エンジンがURLをどのように認識し、処理しているのかを理解することは、効果的なURL設計の第一歩です。
Googleのクローラー「Googlebot」は、URLを通じてウェブページの構造と内容を把握します。
クローラーは、ドメイン名、ディレクトリ構造、ファイル名など、URLの各要素から情報を読み取り、そのページがサイト内でどのような位置づけにあるのかを判断します。
例えば、「https://example.com/blog/seo/url-optimization」というURLを見た場合、クローラーは「このサイトにはblogセクションがあり、その中にseoカテゴリーがあり、url-optimizationという記事が存在する」と理解します。
URLの構造が論理的で一貫性があれば、クローラーはサイト全体をより効率的に巡回できます。
逆に、「https://example.com/page?id=12345&category=abc&sort=desc」のような複雑なパラメータ付きURLは、クローラーにとって理解しにくく、同じ内容のページを異なるURLとして認識してしまう可能性があります。
Googleは公式に「非常に複雑な構造のURLもクロールできる」と述べていますが、それでもシンプルなURL構造の方が望ましいとされています。
検索エンジンは、URLに含まれるキーワードをページ内容を理解する補助情報として利用します。
タイトルタグやメタディスクリプション、本文コンテンツほどの重要性はありませんが、URLのキーワードも総合的な関連性判断の一要素となります。
特に、外部サイトからリンクされる際にURLがそのままアンカーテキストとして使用されるケースでは、URL内のキーワードがより大きな意味を持ちます。
ユーザー体験への影響
URLの設計は、技術的なSEO要素であると同時に、ユーザー体験(UX)に直結する重要な要素でもあります。
分かりやすく構造化されたURLは、ユーザーに安心感と信頼感を与えます。
例えば、オンラインショッピングで「https://shop.example.com/products/shoes/sneakers/nike-air-max」というURLを見れば、ユーザーは「このページはNike Air Maxのスニーカー商品ページだ」と瞬時に理解できます。
一方、「https://shop.example.com/p?pid=9876543&c=128&s=45」のようなURLでは、どのような内容のページなのか全く想像できません。
明確なURL構造は、サイト内でのナビゲーションを容易にします。
ユーザーは、URLのディレクトリ部分を削除することで、上位階層のカテゴリーページに戻ることができます。
例えば、上記の「/products/shoes/sneakers/nike-air-max」から「/nike-air-max」を削除すれば、スニーカーカテゴリーのトップページに移動できると予測できます。
このような直感的な操作性は、ユーザー満足度を高め、結果的にサイトの滞在時間やページビュー数の向上につながります。
URLの読みやすさは、共有やブックマークの促進にもつながります。
ソーシャルメディアで記事をシェアする際、URLがそのまま表示されることがあります。
短くて分かりやすいURLは、見た目が良く、信頼性を感じさせるため、クリックされる可能性が高まります。
また、ユーザーが後で見返すためにブックマークする際も、URLを見ただけで内容を思い出せる方が便利です。
- URLの明確さが高いと、ユーザーの信頼度が向上する
- 直感的なURL構造は、サイト内移動を容易にする
- 短く分かりやすいURLは、SNSでのシェア率が高まる
- ブックマークからの再訪問時に、内容を思い出しやすい
- モバイル環境でも視認性が良いURLは、UXを向上させる
クリック率(CTR)との関連
検索結果画面において、URLはタイトルとメタディスクリプションに次ぐ第三の表示要素として、ユーザーのクリック判断に影響を与えます。
Googleの検索結果では、各リスティングの上部にURLがパンくず形式で表示されます。
ユーザーは、このURLを見て「このページは自分が探している情報を提供してくれそうか」を判断します。
関連性の高いキーワードがURLに含まれていると、検索結果での視認性が向上します。
例えば、「WordPress SEO 設定」と検索したユーザーに対して、「https://example.com/wordpress-seo-setup」というURLは、一目でページ内容が分かるため、クリックされる可能性が高まります。
実際、Backlinko社の調査では、短いURL(50〜60文字程度)の方が、長いURLよりも高い検索順位を獲得している傾向が確認されています。
これは、短いURLがクリックされやすく、結果的にユーザーエンゲージメントが向上することが一因と考えられます。
検索結果画面では、URLは約50文字(335ピクセル)まで表示されます。
それを超える部分は「…」で省略されてしまうため、重要なキーワードはURLの前半に配置することが重要です。
例えば、「https://example.com/blog/2019/08/15/how-to-optimize-your-website-url-structure-for-better-seo-results」というURLでは、肝心の「url-structure」や「seo」が省略される可能性があります。
一方、「https://example.com/seo-url-optimization」なら、すべてのキーワードが表示されます。
さらに、URLの見た目がスパムっぽいと、ユーザーは警戒してクリックを避ける傾向があります。
「https://example.com/p=12345?ref=abc&utm_source=xyz&session=987654」のような長くて意味不明なパラメータが並ぶURLは、マルウェアサイトやフィッシングサイトを連想させる可能性があり、CTRの低下につながります。
清潔で分かりやすいURL構造は、サイトの信頼性を高め、クリック率の向上に貢献します。
| URL特性 | CTRへの影響 | 理由 |
| 短い(50文字以下) | ポジティブ | 全体が表示され、内容が明確 |
| キーワード含有 | ポジティブ | 関連性が視覚的に伝わる |
| シンプルな構造 | ポジティブ | 信頼性と安心感を与える |
| 複雑なパラメータ | ネガティブ | スパムっぽく見える |
| 日本語エンコード | ネガティブ | 意味不明な文字列に見える |
SEOに強いURLの基本原則

シンプルで短いURLを作る
SEOに強いURLの最も基本的な原則は、シンプルで短いURLを作ることです。
複雑で長いURLは、ユーザーにとって理解しにくいだけでなく、検索エンジンにとっても好ましくありません。
理想的なURL長は、ドメイン名を含めて75文字以内とされています。
これは、検索結果での表示制限(約50文字)を考慮しつつ、十分な情報を含められる長さです。
短いURLには複数のメリットがあります。
まず、ユーザーが一目で内容を把握できるため、クリック率が向上します。
次に、SNSでシェアする際に見栄えが良く、文字数制限のあるプラットフォームでも全体が表示されます。
さらに、モバイルデバイスでの視認性も高く、ユーザー体験の向上につながります。
Brafton社の調査では、短いURLの方がソーシャルメディアでのシェア数が多いという結果も報告されています。
URLを短くする際は、不要な単語を削除することがポイントです。
例えば、「the」「a」「and」などの冠詞や接続詞は、URLから省略しても意味が通じます。
「https://example.com/blog/the-ultimate-guide-to-seo」は「https://example.com/blog/seo-guide」に短縮できます。
ただし、短くすることだけを目的として、意味が不明瞭になってしまっては本末転倒です。
「短くシンプル」と「分かりやすさ」のバランスを取ることが重要です。
例えば、ECサイトの商品ページで「https://example.com/p/12345」のように極端に短縮すると、URLからは何の商品か全く分かりません。
「https://example.com/products/running-shoes」程度の長さなら、短さと明確さを両立できます。
実際の設計では、以下のような考え方で整理するとよいでしょう。
- ドメイン名:20〜30文字
- カテゴリー階層:1〜2階層(各10〜20文字)
- ページスラッグ:20〜30文字
- 合計:50〜75文字を目安とする
キーワードを含める
ターゲットキーワードの配置
URLには、そのページで上位表示を狙うターゲットキーワードを必ず含めるべきです。
検索エンジンは、URLに含まれるキーワードをページ内容を理解する手がかりの一つとして利用します。
Google検索エンジン最適化スターターガイドでも、「URLに関連性の高い単語を使用すること」が推奨されています。
例えば、「SEOツール」についての記事であれば、URLは「https://example.com/seo-tools」のようにキーワードを含めます。
キーワードの配置位置も重要です。
URLの前方に配置されたキーワードほど、検索エンジンに重要視される傾向があります。
これは、ユーザーがURLを見た際に最初に目に入る部分でもあるため、UX観点からも理にかなっています。
例えば、「WordPress SEO設定」の記事なら、「https://example.com/wordpress-seo-setup」のように、重要なキーワードを前方に配置します。
ディレクトリ構造にもキーワードを反映させることで、サイト全体の関連性を高められます。
例えば、SEO関連の記事を集めたセクションがあれば、「https://example.com/seo/」というディレクトリを作り、その下に各記事を配置します。
「https://example.com/seo/url-optimization」のようなURL構造にすれば、このページがSEOカテゴリーに属していることが明確になります。
ただし、キーワードを含めることと、URLの簡潔さのバランスを取ることが大切です。
無理に多くのキーワードを詰め込むと、URLが長く複雑になってしまいます。
最も重要なキーワード1〜2語に絞り、他は本文やタイトルタグで対策する方が効果的です。
| キーワード配置パターン | 例 | 評価 |
| ターゲットKWのみ | /seo-tools | ◎ 最もシンプル |
| カテゴリー+KW | /seo/tools | ◎ 構造が明確 |
| 複合キーワード | /wordpress-seo-tools | ○ 具体的 |
| 詳細すぎるKW | /best-wordpress-seo-tools-2025 | △ やや長い |
| KW詰め込み | /seo-seo-tools-seo-plugin | × スパム的 |
キーワードの詰め込みを避ける
URLにキーワードを含めることは重要ですが、過度なキーワードの詰め込みは逆効果となります。
Googleは、不自然にキーワードが繰り返されるURLを好みません。
これは、2000年代初頭に流行した「キーワードスタッフィング」というブラックハットSEO手法の名残を検索エンジンが警戒しているためです。
例えば、「https://example.com/seo-seo-seo-tools-seo-guide」のように同じキーワードを何度も繰り返すURLは、スパムと判断される可能性があります。
キーワードは基本的に1回の使用に留めるべきです。
どうしても複数回使用する必要がある場合でも、自然な文脈の中で使用し、意図的な繰り返しは避けます。
例えば、「WordPress用のSEOプラグイン」を紹介する記事であれば、「https://example.com/wordpress-seo-plugin」で十分です。
「https://example.com/wordpress-seo-plugin-seo-wordpress」のように冗長にする必要はありません。
キーワードの詰め込みは、ユーザー体験の観点からも問題があります。
長く複雑なURLは、ユーザーに不信感を与え、クリック率の低下につながります。
また、SNSでシェアする際にも見栄えが悪く、共有されにくくなります。
実際に海外のSEO調査では、キーワードが1〜2回含まれるURLが最も高いパフォーマンスを示しており、3回以上になると効果が減少する傾向が報告されています。
関連キーワードや同義語を使うことで、キーワードの詰め込みを避けられます。
例えば、「SEO対策」と「検索エンジン最適化」は同じ意味ですが、URLでは「seo-optimization」のように一度だけ使用します。
タイトルタグやメタディスクリプション、本文では異なる表現を使い分けることで、バリエーションを持たせながら関連性を高められます。
名古屋のWebコンサルティング会社「株式会社エッコ」では、キーワード戦略全体を考慮したURL設計のアドバイスも行っています。
- 同じキーワードはURL内で1回のみ使用する
- 複合キーワードでも自然な形で組み合わせる
- 関連語や同義語は本文やタイトルで使い分ける
- URL長が75文字を超える場合は、キーワードを絞る
- ユーザーが読んで違和感のない自然なURLを心がける
ハイフンを使った単語の区切り
URLで複数の単語を組み合わせる際は、必ずハイフン(-)で区切ります。
これは、Google公式ガイドラインでも明確に推奨されている方法です。
ハイフンを使用することで、検索エンジンとユーザーの両方が、URL内の各単語を正しく認識できるようになります。
例えば、「seo site audit」という3つの単語を含むURLを作る場合、「https://example.com/seo-site-audit」のようにハイフンで区切ります。
ハイフンなしの「seositeaudit」では、検索エンジンが「seositeaudit」という一つの単語と認識してしまいます。
これでは、「seo」「site」「audit」という個別のキーワードとしての効果が得られません。
ハイフンは、URLにおける「スペース」の役割を果たすため、単語の区切りを明確にする唯一の方法です。
実際のブラウザでは、URLにスペースを入れることはできないため、ハイフンが最も適切な選択肢となります。
ハイフン使用のメリットは、視認性の向上にもあります。
「wordpress-seo-plugin」というURLは、「wordpressせoplugin」よりも遥かに読みやすく、一目で内容が理解できます。
特に、モバイルデバイスでURLを確認する際や、検索結果画面でURLが表示される際に、この読みやすさが重要になります。
ユーザーがURLを見ただけで「このページには自分が探している情報がありそうだ」と判断できれば、クリック率の向上につながります。
ハイフンの使用は、技術的な観点からも正しい選択です。
Googleのウェブマスタートレンドアナリストも、「ハイフンは単語の区切りとして認識されるが、アンダースコアは認識されない」と明言しています。
つまり、「seo-tools」と「seo_tools」では、前者のみが「seo」と「tools」という2つの単語として検索エンジンに理解されます。
後者は「seo_tools」という一つの複合語として扱われるため、SEO効果が低下します。
| 単語区切り方法 | 例 | 検索エンジンの認識 | 推奨度 |
| ハイフン | /seo-site-audit | ○ 3つの単語として認識 | ◎ 推奨 |
| アンダースコア | /seo_site_audit | △ 1つの単語として認識 | × 非推奨 |
| 区切りなし | /seositeaudit | × 意味不明な文字列 | × 非推奨 |
| キャメルケース | /SeoSiteAudit | × 正しく認識されない | × 非推奨 |
小文字のみを使用する
URLの文字列は、すべて小文字(半角英数字)で統一するべきです。
これは、技術的な理由とユーザビリティの両面から推奨される重要なルールです。
ウェブサーバーの多くは、URLの大文字と小文字を区別して処理します。
つまり、「https://example.com/SEO-Guide」と「https://example.com/seo-guide」は、まったく別のページとして認識されます。
大文字と小文字が混在したURLは、重複コンテンツ問題を引き起こす可能性があります。
例えば、同じコンテンツが「/SEO-Guide」「/seo-guide」「/Seo-Guide」という3つの異なるURLでアクセスできる状態になると、Googleはこれらを別々のページとして評価しようとします。
結果として、ページの評価が分散し、本来得られるはずのSEO効果が薄まってしまいます。
この問題を解決するには、URLの正規化(canonical設定)や301リダイレクトの設定が必要になり、余計な手間がかかります。
小文字統一は、ユーザーがURLを手入力する際のエラーを防ぎます。
名刺や印刷物にURLを記載する場合、ユーザーが手動でアドレスバーに入力することがあります。
その際、大文字と小文字が混在していると、入力ミスによって404エラーが発生するリスクが高まります。
すべて小文字であれば、ユーザーは大文字・小文字を気にせずに入力でき、アクセス成功率が向上します。
小文字統一は、開発チームやコンテンツ制作チーム内でのルール統一も容易にします。
「タイトルの最初だけ大文字」「すべて小文字」など、ルールが複雑だと、チームメンバー間で表記がバラバラになりがちです。
「すべて小文字」という単純明快なルールであれば、誰でも迷わずに実践できます。
特に、WordPressなどのCMSでURL(スラッグ)を手動設定する際に、この統一ルールが活きてきます。
- すべてのアルファベットは小文字を使用する
- 数字は半角で表記する(1234のような表記)
- ドメイン名も小文字で統一する(大文字は自動変換されるが)
- 既存の大文字URLは、301リダイレクトで小文字URLに転送する
- 新規ページ作成時は、最初から小文字で設定する
HTTPSの使用
現代のウェブサイトでは、HTTPS(SSL/TLS暗号化)の使用が必須となっています。
HTTPSは、ウェブサイトとユーザーのブラウザ間の通信を暗号化し、データの盗聴や改ざんを防ぐセキュリティ技術です。
Googleは2014年に「HTTPSをランキングシグナルとして使用する」と公式に発表しており、HTTPS化はSEOの基本要件となりました。
実際、2017年以降、ウェブ全体の50%以上がHTTPSに移行し、現在ではその割合はさらに増加しています。
HTTPSの使用は、直接的なSEO効果があります。
Googleは、他の条件が同じであれば、HTTPSサイトをHTTPサイトよりも優先的にランク付けすると明言しています。
ただし、この効果は「非常に軽いランキングシグナル」とされており、コンテンツの質などの主要な要素と比べると影響は小さいです。
それでも、競合が激しいキーワードでは、この小さな差が順位を左右することもあります。
より重要なのは、HTTPSがユーザーの信頼性に与える影響です。
主要なブラウザ(Chrome、Firefox、Safariなど)は、HTTPサイトに対して「保護されていない通信」という警告を表示します。
この警告を見たユーザーは、サイトから離脱する可能性が高く、結果的にバウンス率の上昇やコンバージョン率の低下につながります。
特に、個人情報や決済情報を扱うECサイトやフォーム設置ページでは、HTTPSは絶対に必要です。
HTTPSへの移行は、技術的には比較的簡単です。
多くのレンタルサーバーやホスティングサービスでは、Let’s Encryptなどの無料SSL証明書が利用でき、ワンクリックでHTTPS化できる環境が整っています。
移行時の注意点としては、すべてのHTTP URLを HTTPS URLにリダイレクト(301リダイレクト)すること、内部リンクをHTTPSに更新すること、Google Search ConsoleでHTTPSプロパティを追加することなどが挙げられます。
名古屋の株式会社エッコでは、HTTPS移行に伴う技術的なサポートやSEO観点でのチェックも提供しています。
| HTTPとHTTPSの比較 | HTTP | HTTPS |
| 通信の暗号化 | なし | あり |
| SEO効果 | 標準 | 若干プラス |
| ブラウザ警告 | 「保護されていない」と表示 | 鍵マークで安全性表示 |
| ユーザー信頼度 | 低い | 高い |
| 導入コスト | なし | 無料〜有料(証明書次第) |
| 推奨度 | × 非推奨 | ◎ 必須 |
避けるべきURL構造

動的パラメータの問題
複雑なパラメータ付きURL
URLに多数のパラメータが含まれていると、SEOとユーザー体験の両面で問題が発生します。
動的パラメータとは、「?」や「&」で区切られたキーと値のペアで、ページの表示内容を制御するために使われる要素です。
例えば、「https://example.com/products?category=shoes&color=red&size=42&sort=price」のようなURLでは、カテゴリー、色、サイズ、並び順などがパラメータとして指定されています。
このようなURLは、ECサイトのフィルタリング機能やソート機能を実現する上では便利ですが、SEO上は好ましくありません。
複雑なパラメータは、検索エンジンのクローラーに負担をかけます。
パラメータの組み合わせによって、同じコンテンツが無数のURLでアクセス可能になってしまいます。
例えば、「?color=red&size=42」と「?size=42&color=red」は、パラメータの順序が違うだけで同じページを表示しますが、URLとしては別物です。
このような組み合わせが増えると、Googleは膨大な数のURLをクロールしなければならず、クロールバジェットを無駄に消費してしまいます。
パラメータ付きURLは、検索結果での見栄えも悪くなります。
「https://example.com/products?id=12345&ref=google&utm_source=cpc」のような長いURLは、検索結果画面で途中で切れてしまい、「…」で省略されます。
ユーザーにとっては、このURLから何のページなのかを判断することが困難です。
また、パラメータが多く含まれるURLは、スパムサイトやマルウェアサイトを連想させ、クリック率の低下につながります。
対策としては、URLリライト機能を使って静的なURLに変換することが推奨されます。
例えば、「/products?category=shoes&color=red」を「/products/shoes/red」のように、パラメータをディレクトリ構造に変換します。
これにより、URLがシンプルで分かりやすくなり、SEO効果も向上します。
また、フィルタリング結果ページにはcanonicalタグを設定し、メインカテゴリーページを正規URLとして指定する方法も有効です。
- 動的パラメータは最小限に抑える
- 可能であれば静的URLにリライトする
- パラメータの順序を統一してURL正規化を行う
- フィルター結果ページにはcanonicalタグを設定
- 必要最小限のパラメータのみクロール対象とする
セッションIDの使用
URLにセッションIDを含めることは、SEO上最も避けるべき行為の一つです。
セッションIDとは、ユーザーの訪問セッションを識別するための一意の文字列で、「https://example.com/products?sessionid=abc123xyz」のような形式でURLに付加されます。
かつては、ユーザーの状態管理のためにURLにセッションIDを含める手法が一般的でしたが、現在ではクッキー(Cookie)を使用するのが標準です。
セッションIDをURLに含めると、同じページに対して無数のURLが生成されてしまいます。
各ユーザーの訪問ごとに異なるセッションIDが生成されるため、「/products?sessionid=abc123」「/products?sessionid=xyz789」のように、実質的に同じページが異なるURLで存在することになります。
これは重複コンテンツ問題の最たる例であり、Googleのクローラーが同じページを何度もクロールする無駄な状況を生み出します。
セッションID付きURLは、外部サイトからリンクされる際にも問題となります。
ユーザーがセッションID付きのURLをSNSでシェアしたり、ブックマークしたりすると、そのURLは次に別のユーザーがアクセスした時には既に無効になっている可能性があります。
結果として、404エラーやセッションエラーが発生し、ユーザー体験を大きく損ないます。
また、このような無効なURLが外部リンクとして蓄積されると、サイトの評価にも悪影響を及ぼします。
Google公式ガイドラインでも、セッションIDの使用は明確に非推奨とされています。
代わりに、HTTP Cookieを使用してセッション情報を管理することが推奨されています。
Cookieを使用すれば、URLは常に「https://example.com/products」のようにシンプルな形を保ちながら、バックグラウンドでセッション情報を管理できます。
これにより、SEO上の問題を回避しつつ、必要な機能を実現できます。
| URL管理方法 | URL例 | SEO影響 | 推奨度 |
| クッキー使用 | /products | ◎ 問題なし | ◎ 推奨 |
| セッションID(URL) | /products?sid=abc123 | × 重複大量発生 | × 絶対回避 |
| セッションID(パス) | /abc123/products | × 構造が不明瞭 | × 非推奨 |
日付や数字の含有
URLに作成日や更新年を含めることは、一部のケースを除いて推奨されません。
かつてのWordPressでは、デフォルトのパーマリンク設定が「/2025/01/15/article-title」のような日付を含む形式でしたが、現在ではこの設定は推奨されていません。
日付を含むURLには、いくつかの深刻な問題があります。
まず、コンテンツを更新した際にURLと内容の不整合が生じます。
例えば、2020年に作成した「SEOトレンド2020」という記事を2025年に大幅更新して最新情報にした場合、URLが「/2020/seo-trends」のままだと、ユーザーは「これは古い情報では?」と疑問を持ちます。
日付はURLを不必要に長くし、視認性を低下させます。
「/2025/01/15/」という日付部分だけで11文字を消費してしまいます。
前述の通り、URLは短い方がSEO上もUX上も有利ですので、この11文字は大きな無駄です。
「/blog/seo-trends」のようにシンプルなURLの方が、一目で内容が分かり、クリック率も向上します。
また、日付が入っていると、検索結果画面でURLが古く見え、クリックされにくくなる傾向があります。
日付を含むべき例外的なケースも存在します。
ニュース記事、プレスリリース、イベント告知など、「いつ公開されたか」が情報の価値を左右するコンテンツでは、日付を含めることが適切です。
例えば、「/news/2025/01/product-launch」のようなURLは、ユーザーに「これは2025年1月の最新ニュースだ」と伝える役割を果たします。
ただし、この場合でも「/news/2025-01-15-product-launch」のように、日付をスラッグの一部として含める方法もあります。
数字の使用についても慎重に検討すべきです。
「10のSEOテクニック」という記事で「/10-seo-techniques」というURLを作った場合、後から内容を追加して「15のSEOテクニック」に更新すると、URLと内容が一致しなくなります。
この場合は「/seo-techniques-list」のように、数字を含めないURLの方が長期的に有効です。
ただし、「404エラー」のような固有の数字や、「iPhone 14」のような製品名に含まれる数字は問題ありません。
- 常緑コンテンツ(エバーグリーン記事)には日付を含めない
- ニュースやイベント記事では日付を含めてもよい
- 「10の方法」のような数字は避け、汎用的な表現にする
- 製品名や固有名詞の数字は問題なし
- 既存の日付入りURLは、301リダイレクトで修正を検討
特殊文字の使用
URLには、基本的な半角英数字とハイフン以外の特殊文字を使用すべきではありません。
特殊文字とは、「&」「%」「#」「?」「!」「$」「@」「+」「=」などの記号類を指します。
これらの文字は、URL内で特別な意味を持つ場合があり、意図しない動作やエラーを引き起こす可能性があります。
例えば、「&」はURLパラメータの区切り文字として使われるため、通常のテキストとして使用すると、ブラウザやサーバーが誤って解釈してしまいます。
特殊文字は、URLエンコーディング(パーセントエンコーディング)されてしまいます。
例えば、スペース(空白)は「%20」に、「#」は「%23」に自動変換されます。
結果として、「https://example.com/seo tips」というURLは「https://example.com/seo%20tips」として処理され、ユーザーにとって非常に読みにくくなります。
特に、日本語や全角文字を含むURLは、エンコード後に「%E3%81%82%E3%81%84」のような意味不明な文字列になり、SEO効果が大きく低下します。
スペースの代わりにはハイフンを使用するのが標準です。
前述の通り、「seo tips」は「seo-tips」のようにハイフンで区切ります。
アンダースコア「_」も技術的には使用可能ですが、Googleはハイフンを推奨しています。
また、全角スペースや全角ハイフンは絶対に使用せず、すべて半角文字で統一します。
日本語URLについては、特に注意が必要です。
日本人ユーザーにとっては「https://example.com/SEO対策」のようなURLは分かりやすく見えますが、実際には「https://example.com/%E3%80%80SEO%E5%AF%BE%E7%AD%96」のようにエンコードされます。
このURLをコピー&ペーストしてメールやSNSで共有すると、長くて醜い文字列が表示され、クリック率が大幅に低下します。
そのため、日本語サイトであっても、URLは英数字(ローマ字またはroman)で作成することが強く推奨されます。
| 特殊文字 | URL内での意味 | 使用可否 |
| – (ハイフン) | 単語の区切り | ◎ 推奨 |
| _ (アンダースコア) | 通常は文字の一部 | △ 非推奨 |
| & (アンパサンド) | パラメータ区切り | × 特別な用途のみ |
| ? (クエスチョン) | パラメータ開始 | × 特別な用途のみ |
| # (ハッシュ) | アンカー(フラグメント) | × 特別な用途のみ |
| % (パーセント) | エンコード記号 | × 自動生成のみ |
| 日本語・全角文字 | エンコード対象 | × 避けるべき |
アンダースコアの使用
URL内での単語区切りにアンダースコア(アンダーバー、_)を使用することは推奨されません。
これは、Googleのウェブマスタートレンドアナリストが公式に言及している重要なポイントです。
Google検索セントラルのドキュメントでも、「URLにはアンダースコア(_)ではなくハイフン(-)を使用することをおすすめします」と明記されています。
この理由は、検索エンジンがアンダースコアとハイフンを異なる方法で処理するためです。
ハイフンは単語の区切りとして認識されますが、アンダースコアは単語を連結するものと認識されます。
例えば、「seo-tools」というURLは「seo」と「tools」という2つの独立した単語として検索エンジンに理解されます。
一方、「seo_tools」は「seo_tools」という1つの複合語として認識されてしまいます。
結果として、「seo」や「tools」という個別のキーワードでの検索時に、ハイフンを使用したURLの方が高い関連性を示すことになります。
アンダースコアの使用は、プログラミングや技術的な命名規則の影響です。
多くのプログラミング言語では、変数名や関数名にハイフンを使用できないため、代わりにアンダースコアを使用します。
例えば、PHP言語では「function seo-tools()」と書けないため、「function seo_tools()」と書きます。
このような技術的背景から、開発者がURLにもアンダースコアを使用してしまうケースがありますが、SEOの観点からは好ましくありません。
既存サイトでアンダースコアを使用している場合の対処法を考えましょう。
すでに運用中のサイトでアンダースコア入りURLが多数存在する場合、すべてをハイフンに変更するのは大きな作業になります。
この場合、新規ページからはハイフンを使用し、既存ページは優先度を付けて段階的に修正していく方法が現実的です。
修正する際は、必ず301リダイレクトを設定し、古いURLから新しいURLへ適切に転送されるようにします。
- URLの単語区切りには必ずハイフン(-)を使用する
- アンダースコア(_)は使用しない
- ファイル名やプログラム名とURLを混同しない
- 既存のアンダースコアURLは、優先度を付けて修正
- 新規ページ作成時は最初からハイフンを使用する
過度に深い階層構造
URLの階層(ディレクトリ構造)が深すぎると、SEOとユーザビリティの両面で問題が生じます。
階層が深いとは、「/」で区切られたディレクトリの数が多い状態を指します。
例えば、「https://example.com/category/subcategory/sub-subcategory/item/detail」のように5階層、6階層と深くなると、様々な弊害が発生します。
深い階層構造は、重要なページへのアクセスを困難にします。
SEOの基本原則の一つに「重要なページはトップページから2〜3クリック以内でアクセスできるようにする」というものがあります。
これは、検索エンジンがトップページから近いページをより重要だと判断する傾向があるためです。
例えば、ECサイトの主力商品ページが「/products/electronics/computers/laptops/gaming/high-end/product123」のように7階層にあると、Googleはこのページをあまり重要でないと判断する可能性があります。
深い階層はURLを長くし、読みにくくします。
前述の通り、URLは短い方がSEO上有利ですが、階層が深いと必然的にURLが長くなります。
また、ユーザーがURLを見ても、どこに何があるのか把握しにくくなります。
「/products/gaming-laptops/product123」のように3階層程度であれば、「製品カテゴリーの中のゲーミングノートパソコンの商品ページだな」と直感的に理解できます。
階層の深さは、サイト構造の複雑さを示す指標でもあります。
必要以上に深い階層構造は、サイト設計が過度に細分化されていることを意味します。
例えば、記事数が100程度のブログサイトで、「/blog/year/month/category/subcategory/article」のような6階層構造は明らかに過剰です。
「/blog/category/article」の3階層で十分でしょう。
サイト規模に応じた適切な階層設計が重要です。
推奨される階層の深さは、サイトの規模や目的によって異なります。
一般的には、以下のような目安があります。
小規模サイト(100ページ未満):2〜3階層 中規模サイト(100〜1,000ページ):3〜4階層 大規模サイト(1,000ページ以上):4〜5階層
これ以上深くなる場合は、カテゴリー分類を見直すか、フラット構造の導入を検討すべきです。
名古屋の株式会社エッコでは、サイトの規模や目的に応じた最適なURL階層設計のコンサルティングも行っています。
| サイト規模 | 推奨階層 | URL例 |
| 小規模(〜100ページ) | 2〜3階層 | /blog/article-title |
| 中規模(100〜1,000) | 3〜4階層 | /category/subcategory/article |
| 大規模(1,000〜) | 4〜5階層 | /section/category/sub/article |
| 過度に深い | 6階層以上 | × 要見直し |
URL構造の設計方法
サイト階層の設計
ディレクトリ構造の考え方
効果的なURL構造を設計するには、まずサイト全体の情報アーキテクチャを明確にすることが重要です。
ディレクトリ構造とは、サイト内のコンテンツをどのように分類・整理するかを表す骨組みのことです。
これは、物理的なファイル保存場所というよりも、論理的なコンテンツの分類方法を指します。
適切なディレクトリ構造は、ユーザーが目的の情報に素早くたどり着けるナビゲーションを提供し、検索エンジンがサイト構造を正しく理解する助けとなります。
ディレクトリ構造の設計は、トップダウンアプローチで行います。
まず、サイト全体を大きなカテゴリーに分類します。
例えば、企業サイトなら「会社情報」「製品・サービス」「サポート」「ニュース」「採用情報」のような大カテゴリーを設定します。
次に、各大カテゴリーの下に、より具体的なサブカテゴリーを配置します。
「製品・サービス」の下には「製品A」「製品B」「サービスC」のように分類します。
各カテゴリーに対応するディレクトリ名は、分かりやすく一貫性のある命名規則で決定します。
例えば、英語サイトなら「/products/」「/services/」「/about/」のように英単語を使用し、日本語サイトでも「/products/」「/services/」のようにローマ字表記を使用します。
「/product/」と「/products/」のように単数形と複数形が混在すると混乱を招くため、サイト全体で統一したルールを適用します。
一般的には、カテゴリー名は複数形(products, articles)、個別ページは単数形や具体名(product-a, article-title)を使用します。
ディレクトリ階層は、コンテンツの重要度を反映すべきです。
トップページから1階層目(例:/products/)には、サイトの主要コンテンツカテゴリーを配置します。
2階層目(例:/products/software/)には、より具体的なサブカテゴリーを配置します。
3階層目以降(例:/products/software/product-name/)には、個別のコンテンツページを配置します。
重要な商品やサービスは、できるだけ浅い階層に配置することで、SEO的な評価を高めることができます。
- サイト全体を3〜7個程度の大カテゴリーに分類する
- カテゴリー名は分かりやすく簡潔な英単語を使用
- 単数形・複数形、動詞・名詞などの使い分けを統一する
- 重要なコンテンツは浅い階層に配置する
- カテゴリー構造は将来の拡張を考慮して設計する
- 各カテゴリーに対応するトップページ(インデックスページ)を用意する
フラット構造vs階層構造
URL構造には、大きく分けて「フラット構造」と「階層構造」の2つのアプローチがあります。
フラット構造とは、すべてのページをトップレベル(ドメイン直下)またはごく浅い階層に配置する方法です。
例えば、「https://example.com/about」「https://example.com/contact」「https://example.com/seo-guide」のように、すべてがドメイン直下にある状態です。
一方、階層構造は、「https://example.com/blog/seo/url-optimization」のように、カテゴリーやサブカテゴリーでコンテンツを階層化する方法です。
フラット構造のメリットは、シンプルさとクローラビリティの高さです。
すべてのページがトップレベルにあるため、クローラーは少ないステップですべてのコンテンツにアクセスできます。
また、URLが短くなるため、ユーザーにとっても覚えやすく、入力しやすくなります。
小規模サイト(50ページ以下程度)であれば、フラット構造でも十分に管理可能です。
実際、多くのランディングページや小規模な企業サイトは、フラット構造を採用しています。
しかし、フラット構造にはスケーラビリティの問題があります。
ページ数が増えると、コンテンツの分類や管理が困難になります。
「https://example.com/seo-guide-2023」「https://example.com/seo-guide-beginners」「https://example.com/advanced-seo-techniques」のように、関連するコンテンツがバラバラに配置され、ユーザーが全体像を把握しにくくなります。
また、サイト内検索やナビゲーションメニューの設計も複雑化します。
階層構造のメリットは、コンテンツの組織化とスケーラビリティです。
「/blog/seo/」というディレクトリを見れば、「ここにはSEO関連の記事がまとまっている」と分かります。
コンテンツが増えても、適切なカテゴリーに分類すれば管理が容易です。
また、パンくずリストや関連記事の表示など、ナビゲーション機能の実装も自然な形で行えます。
中規模以上のサイト(100ページ以上)では、階層構造が推奨されます。
実際には、両者のハイブリッドアプローチが最も効果的です。
例えば、企業情報や問い合わせフォームなどの静的ページはフラット構造(トップレベル)に配置し、ブログ記事や製品カタログなど量が多いコンテンツは階層構造で整理する方法です。
「https://example.com/about」「https://example.com/contact」はフラット、「https://example.com/blog/category/article」「https://example.com/products/category/item」は階層構造、という形です。
| 構造タイプ | 適したサイト | メリット | デメリット |
| フラット構造 | 小規模サイト(〜50ページ) | シンプル、クローラブル、URL短い | スケールしない、分類困難 |
| 階層構造 | 中大規模サイト(100ページ〜) | 組織的、拡張性高い、ナビ明確 | URL長くなる、階層設計必要 |
| ハイブリッド | ほとんどのサイト | 両方の利点を活かせる | 設計に工夫が必要 |
URLスラッグの最適化
URLスラッグとは、ドメイン名とディレクトリ構造の後に続く、個別ページを識別する部分です。
例えば、「https://example.com/blog/seo-url-optimization」というURLでは、「seo-url-optimization」がスラッグに相当します。
スラッグは、ページの内容を端的に表現し、ユーザーと検索エンジンの両方に分かりやすい情報を提供する重要な要素です。
WordPressなどのCMSでは、スラッグを個別に設定・編集できる機能が提供されています。
効果的なスラッグは、ページのメインキーワードを含みます。
例えば、「URLのSEO最適化」について解説する記事なら、「seo-url-optimization」や「url-seo-guide」のようなスラッグが適切です。
記事のタイトルが「完全版:URLのSEO最適化ガイド|初心者でも分かる設計方法」のように長い場合でも、スラッグは「seo-url-guide」のように、エッセンスだけを抽出した短い形にします。
タイトルをそのままスラッグにすると、「complete-guide-url-seo-optimization-beginners-design-methods」のように冗長になってしまいます。
スラッグからは、冠詞や助詞など不要な単語を削除します。
英語の「the」「a」「and」「of」、日本語の「の」「を」「に」などは、スラッグには含めません。
例えば、「The Ultimate Guide to SEO」というタイトルなら、スラッグは「ultimate-seo-guide」ではなく「seo-guide」で十分です。
このような停止語(ストップワード)を削除することで、URLをより簡潔にしつつ、重要なキーワードを際立たせることができます。
スラッグは、記事公開後も変更可能ですが、変更する際は注意が必要です。
既に公開されて外部リンクを獲得しているページのスラッグを変更すると、それまでのSEO評価が失われる可能性があります。
そのため、記事を公開する前に、最適なスラッグを慎重に決定することが重要です。
どうしても変更が必要な場合は、必ず301リダイレクトを設定し、古いURLから新しいURLへ適切に転送されるようにします。
優れたスラッグの特徴をまとめます。
- ページの主要キーワードを1〜3語含む
- 20〜50文字程度の長さ(短すぎず長すぎず)
- ハイフンで単語を区切る
- すべて小文字の英数字を使用
- 冠詞や助詞などの不要語を削除
- 記事の内容を正確に反映する
- 将来的にも変更の必要がないよう慎重に選ぶ
- 他のページと重複しないユニークな文字列にする
サブドメインとサブディレクトリ
SEO観点での違い
**サブドメインとサブディレクトリは、サイトの一部を区分する2つの異なる方法ですが、SEOへの影響は大きく異なります**。
サブドメインは、「blog.example.com」のようにドメイン名の前に付ける形式で、技術的には独立したウェブサイトとして扱われます。
一方、サブディレクトリ(サブフォルダー)は、「example.com/blog/」のようにドメインの後ろに付ける形式で、メインサイトの一部として扱われます。
この違いは、SEO効果に重要な影響を与えます。
Googleは、サブドメインとメインドメインを別々のサイトとして評価する傾向があります。
つまり、メインサイト(example.com)で獲得した被リンクやドメイン権威は、サブドメイン(blog.example.com)には直接的には継承されません。
一方、サブディレクトリ(example.com/blog/)は、メインサイトと同じドメインの一部として評価されるため、ドメイン全体の権威を共有できます。
この違いにより、多くのSEO専門家はサブディレクトリの使用を推奨しています。
実際のケーススタディでも、サブドメインからサブディレクトリへの移行でトラフィックが増加した事例が報告されています。
ある企業が「blog.example.com」を「example.com/blog/」に移行したところ、検索トラフィックが大幅に増加したという報告があります。
これは、メインドメインが持つSEO評価がブログセクションにも適用されるようになったためと考えられます。
特に、メインドメインが既に強力な被リンクプロフィールを持っている場合、この効果は顕著に現れます。
ただし、Googleの公式見解は「サブドメインとサブディレクトリを同等に扱う」というものです。
John Mueller氏は、「Googleはサブドメインとサブディレクトリを技術的には同じように処理できる」と述べています。
しかし実際には、サブドメインは独立したサイトとして扱われることが多く、クロール予算も別々に配分される傾向があります。
そのため、特別な理由がない限り、サブディレクトリを選択する方が安全な選択と言えます。
サブドメインとサブディレクトリでは、クロール効率にも差が生じます。
サブディレクトリは、メインサイトのクロール予算を共有するため、新しいコンテンツが比較的早くインデックスされます。
一方、サブドメインは独立したクロール予算を持つため、特にサブドメインが新しい場合や更新頻度が低い場合、クロールされるまでに時間がかかることがあります。
大量のコンテンツを頻繁に公開する場合は、この点も考慮すべきです。
| 項目 | サブドメイン | サブディレクトリ |
| 形式 | blog.example.com | example.com/blog/ |
| SEO評価の継承 | △ 部分的 | ◎ 完全に継承 |
| ドメイン権威 | 独立して構築 | メインと共有 |
| クロール予算 | 別々に配分 | メインと共有 |
| 設定の複雑さ | やや複雑 | シンプル |
| 推奨度 | △ 特定用途のみ | ◎ 一般的に推奨 |
使い分けの判断基準
サブドメインを使用すべき明確な理由がある場合を除き、基本的にはサブディレクトリを選択すべきです。
しかし、いくつかの特定状況では、サブドメインの使用が適切、または必要となります。
ここでは、サブドメインとサブディレクトリの使い分け基準を具体的に解説します。
サブドメインを使用すべきケースの一つは、明確に異なるサービスや機能を提供する場合です。
例えば、メインサイトがコーポレートサイトで、まったく別のプラットフォームで運営されるECサイトや採用サイトを展開する場合、サブドメインの使用が適切です。
「shop.example.com」(ECサイト)、「recruit.example.com」(採用サイト)のように、技術的にも内容的にも独立性が高い場合は、サブドメインで明確に区分する方がユーザーにとって分かりやすくなります。
異なる地域や言語向けのサイトを運営する場合も、サブドメインが選択肢となります。
例えば、「us.example.com」「jp.example.com」「uk.example.com」のように、国や地域ごとにサブドメインを分ける方法があります。
ただし、この場合は「example.com/us/」「example.com/jp/」のようなサブディレクトリでも対応可能で、むしろサブディレクトリの方がSEO的には有利です。
そのため、多言語・多地域サイトの場合は、ccTLD(国別トップレベルドメイン)、サブドメイン、サブディレクトリの3つの選択肢を総合的に検討する必要があります。
一方、サブディレクトリを使用すべきケースは、コンテンツがメインサイトと関連性が高い場合です。
ブログ、ニュース、製品カタログ、サポートセンターなど、メインビジネスと密接に関連するコンテンツは、すべてサブディレクトリで管理すべきです。
例えば、「example.com/blog/」「example.com/news/」「example.com/products/」「example.com/support/」のように、すべてメインドメインの配下に配置することで、ドメイン全体のSEO評価を最大化できます。
技術的な制約がある場合は、サブドメインを選択せざるを得ないこともあります。
例えば、メインサイトはWordPressで運営しているが、ECサイトはShopifyやBASEなどの外部プラットフォームを使用する場合、技術的にサブディレクトリでの統合が困難なことがあります。
この場合、「shop.example.com」のようなサブドメインを使用し、できる限りメインサイトとの視覚的統一性やリンク構造を保つことで、SEO上の不利を最小限に抑えます。
名古屋の株式会社エッコでは、サイトの目的や技術環境を総合的に分析し、最適なドメイン構造の設計をサポートしています。
- メインサイトと密接に関連するコンテンツ → サブディレクトリ
- 独立したサービスや機能を提供 → サブドメイン検討
- ブログ、ニュース、製品情報 → サブディレクトリ推奨
- 外部プラットフォーム利用時 → 技術的制約でサブドメイン
- SEOを最優先する場合 → サブディレクトリを強く推奨
- 迷った場合は → サブディレクトリを選ぶ
パンくずリストとの連携
パンくずリストは、URL構造と密接に連携すべきナビゲーション要素です。
パンくずリストとは、「ホーム > カテゴリー > サブカテゴリー > 現在のページ」のように、サイト内での現在位置を示すナビゲーションリンクのことです。
このパンくずリストとURL構造を一致させることで、ユーザーと検索エンジンの両方にとって分かりやすいサイト設計が実現できます。
パンくずリストとURL構造が一致していると、ユーザーは直感的にサイト構造を理解できます。
例えば、「https://example.com/products/electronics/smartphones/」というURLのページで、パンくずリストが「ホーム > 製品 > 家電 > スマートフォン」と表示されれば、URLとパンくずが完全に対応しており、非常に分かりやすくなります。
ユーザーは、パンくずリストをクリックして上位階層に移動できると同時に、URLから「/smartphones/」を削除すれば家電カテゴリーのトップに戻れることを理解できます。
Googleは、検索結果画面でパンくずリストをURLの代わりに表示することがあります。
構造化データ(Schema.org)を使ってパンくずリストをマークアップすると、Googleはこれを認識し、検索結果に「example.com › 製品 › 家電 › スマートフォン」のようなパンくず形式でURLを表示します。
これにより、ユーザーは検索結果を見ただけで、そのページがサイト内のどこに位置するかを把握でき、クリック率の向上につながります。
パンくずリストの実装には、構造化データ(BreadcrumbList)を使用します。
JSON-LD形式で構造化データを記述することで、Googleにパンくずリストの構造を正確に伝えることができます。
この構造化データは、URL構造と完全に一致させることが重要です。
例えば、URLが「/products/smartphones/」なら、パンくずリストも「ホーム > 製品 > スマートフォン」という階層構造にし、各リンク先も対応するURLに設定します。
パンくずリストとURL構造の不一致は、避けるべき状態です。
例えば、URLが「/products/item-123」のようなフラット構造なのに、パンくずリストが「ホーム > カテゴリーA > サブカテゴリーB > 商品」のように深い階層を示していると、ユーザーと検索エンジンの両方が混乱します。
理想的には、URLの階層構造とパンくずリストの階層が完全に一致し、パンくずの各リンクがURLの各セグメントに対応している状態です。
| 要素 | 良い例 | 悪い例 |
| URL | /blog/seo/url-guide | /article?id=123 |
| パンくず | ホーム > ブログ > SEO > URL解説 | ホーム > 記事 |
| 一致性 | ◎ 完全一致 | × 不一致 |
| ユーザビリティ | ◎ 分かりやすい | × 混乱する |
既存URLの改善方法

リダイレクトの設定
301リダイレクトの実装
URLを変更する際に最も重要なのが、301リダイレクトの正しい実装です。
301リダイレクトとは、「恒久的な移動」を意味するHTTPステータスコードで、古いURLから新しいURLへ訪問者を自動的に転送する仕組みです。
このリダイレクトを適切に設定することで、変更前のURLが持っていたSEO評価(ページランクや被リンクの価値)を新しいURLに引き継ぐことができます。
301リダイレクトがなければ、URLを変更した時点でそれまで積み上げたSEO評価がすべて失われてしまいます。
301リダイレクトは、複数の方法で実装できます。
最も一般的な方法は、サーバーの設定ファイル(.htaccessファイル)を使用する方法です。
Apacheサーバーを使用している場合、.htaccessファイルに「Redirect 301 /old-url.html https://example.com/new-url」のように記述します。
WordPressを使用している場合は、「Redirection」や「Yoast SEO」などのプラグインを使用することで、コードを書かずに簡単に301リダイレクトを設定できます。
大量のURLを変更する場合は、リダイレクトマップを作成します。
サイトリニューアルなどで数十、数百のURLを変更する場合、一つひとつ手動でリダイレクトを設定するのは非現実的です。
この場合、まず既存URLのリストを作成し、それぞれの新しいURLを対応付けたリダイレクトマップ(対応表)を作ります。
例えば、ExcelやGoogleスプレッドシートで「旧URL | 新URL」という2列の表を作成します。
その後、このマップを基に一括でリダイレクト設定を行います。
リダイレクトチェーンは避けるべきです。
リダイレクトチェーンとは、URL A → URL B → URL C のように、複数回リダイレクトが発生する状態を指します。
例えば、最初に「/old-url」を「/temp-url」にリダイレクトし、後に「/temp-url」を「/new-url」にリダイレクトした場合、訪問者は2回のリダイレクトを経験することになります。
これは、ページ表示速度の低下や、SEO評価の減少につながるため、「/old-url」から「/new-url」へ直接リダイレクトするように修正すべきです。
301リダイレクトの効果は、Googleが新しいURLをクロールするまでに時間がかかります。
リダイレクトを設定した直後は、古いURLでの検索順位がそのまま維持されますが、Googleが新しいURLを認識すると、徐々に新しいURLの順位が表示されるようになります。
この移行期間は、サイトの規模やクロール頻度によって異なりますが、通常は数週間から数ヶ月かかります。
そのため、URLの変更は慎重に計画し、繁忙期を避けるなどの配慮が必要です。
- 古いURLから新しいURLへ必ず301リダイレクトを設定
- .htaccessファイルまたはプラグインで実装
- 大量変更時はリダイレクトマップを作成
- リダイレクトチェーンは避け、直接転送を設定
- 設定後は必ずテストして動作確認
- Google Search Consoleで移行状況を監視
302リダイレクトとの違い
301リダイレクトと302リダイレクトは、用途と効果が大きく異なります。
301リダイレクトが「恒久的な移動」を意味するのに対し、302リダイレクトは「一時的な移動」を意味するHTTPステータスコードです。
この違いは、検索エンジンの扱い方に大きな影響を与えます。
301リダイレクトでは、古いURLのSEO評価が新しいURLに引き継がれますが、302リダイレクトでは基本的に引き継がれません。
302リダイレクトを使用すべきケースは限られています。
例えば、ウェブサイトのメンテナンス中に一時的にメンテナンスページに誘導する場合や、キャンペーン期間中だけ特設ページに転送する場合などです。
「このURLは後で元の場所に戻る予定だ」という場合に302リダイレクトを使用します。
逆に言えば、URLを恒久的に変更する場合(サイトリニューアル、URL構造の変更、コンテンツの統合など)には、必ず301リダイレクトを使用すべきです。
誤って302リダイレクトを使用すると、SEO上の損失が発生します。
例えば、サイトリニューアルで全ページのURLを変更したにもかかわらず、302リダイレクトを設定してしまった場合を考えます。
この場合、Googleは「このリダイレクトは一時的なものだ」と判断し、古いURLのインデックスを維持しようとします。
結果として、新しいURLがなかなかインデックスされず、古いURLのランキングが徐々に低下していくという最悪の状況になる可能性があります。
301と302を正しく使い分けることが重要です。
一般的なルールとして、「今後6ヶ月以上この転送を維持する予定か?」を判断基準とします。
答えがYESなら301リダイレクト、NOなら302リダイレクトを選択します。
迷った場合は、301リダイレクトを選択する方が安全です。
なぜなら、302リダイレクトによるSEO損失は回復が困難ですが、301リダイレクトを後から302に変更することは比較的容易だからです。
| リダイレクト種類 | 意味 | SEO評価の継承 | 使用ケース |
| 301 | 恒久的な移動 | ◎ 完全に継承 | URL構造変更、統合、リニューアル |
| 302 | 一時的な移動 | × 継承されない | メンテナンス、一時的キャンペーン |
| 307 | 一時的な移動(HTTP/1.1) | × 継承されない | 302の厳密版 |
| 308 | 恒久的な移動(HTTP/1.1) | ◎ 継承される | 301の厳密版 |
変更時の注意点
URLを変更する際は、慎重な計画と段階的な実施が不可欠です。
URL変更は、サイト移行(マイグレーション)の一種であり、適切に実施しないと検索順位の大幅な低下やトラフィックの損失を招く可能性があります。
まず重要なのは、「本当にURLを変更する必要があるか」を再検討することです。
既に確立されたURLは貴重な資産であり、軽微な理由での変更は避けるべきです。
URLの変更前に、必ず完全なバックアップを取得します。
これには、現在のURL一覧、各ページのコンテンツ、内部リンク構造、外部からの被リンク情報などが含まれます。
Google Search ConsoleやScreaming Frog SEO Spiderなどのツールを使用して、サイト全体のURLリストをエクスポートしておきます。
万が一、変更後に問題が発生した場合、このバックアップがあれば原因の特定や復旧が容易になります。
変更のタイミングも重要な考慮事項です。
繁忙期やキャンペーン期間中にURLを変更すると、万が一トラフィックが減少した場合のビジネス影響が大きくなります。
できれば、トラフィックが比較的少ない時期(例えば、年末年始やゴールデンウィーク明けなど)に実施することで、リスクを最小化できます。
また、大規模な変更は一度に行わず、段階的に実施することも検討すべきです。
内部リンクの更新は、URL変更と同時に行うべきです。
301リダイレクトがあれば古いURLでもアクセスできますが、サイト内の全リンクを新しいURLに更新することで、ユーザー体験とクロール効率が向上します。
データベースの一括置換機能を使用して、サイト内のすべての内部リンクを新しいURLに更新します。
特に、ナビゲーションメニュー、フッター、サイトマップなどの重要なリンクは、漏れがないよう念入りにチェックします。
XMLサイトマップとrobots.txtファイルも更新が必要です。
XMLサイトマップには新しいURLのみを含め、古いURLは削除します。
これにより、Googleに「これらが現在の正しいURLです」と明確に伝えることができます。
robots.txtファイルで特定のディレクトリをクロール対象外にしている場合は、新しいURL構造に合わせて設定を更新します。
更新後は、必ずGoogle Search Consoleにサイトマップを再送信します。
名古屋の株式会社エッコでは、URL変更に伴うリスク分析から実施計画の策定、変更後のモニタリングまで、包括的なサポートを提供しています。
- URL変更の必要性を慎重に検討する
- 実施前に完全なバックアップを取得
- トラフィックが少ない時期に実施
- 段階的な変更を検討(可能であれば)
- 内部リンクを新しいURLに一括更新
- XMLサイトマップとrobots.txtを更新
- 変更後2〜3ヶ月は順位とトラフィックを注意深く監視
内部リンクの更新
URL変更後の内部リンク更新は、SEOとユーザー体験の両面で重要です。
内部リンクとは、サイト内のあるページから別のページへのリンクを指します。
301リダイレクトを設定すれば、古いURLでもアクセスできますが、すべての内部リンクを新しいURLに更新することで、より効率的なサイト運営が可能になります。
内部リンクが古いURLのままだと、ユーザーがリンクをクリックするたびにリダイレクトが発生し、ページ表示速度がわずかに低下します。
内部リンク更新の優先順位を決めます。
すべての内部リンクを一度に更新するのが理想ですが、大規模サイトでは数千、数万のリンクが存在する可能性があります。
この場合、まず重要度の高いリンクから更新します。
具体的には、(1)グローバルナビゲーション、(2)フッターリンク、(3)サイドバーウィジェット、(4)人気記事からのリンク、(5)その他の記事本文内リンク、という順序で更新します。
WordPressなどのCMSでは、データベース一括置換ツールが利用できます。
「Better Search Replace」や「Velvet Blues Update URLs」などのプラグインを使用すると、データベース内のすべてのURLを一括で置換できます。
例えば、「https://example.com/old-category/」を「https://example.com/new-category/」に一括変換できます。
ただし、この作業は非常にリスクが高いため、必ず事前にデータベースの完全バックアップを取得し、テスト環境で動作確認してから本番環境で実行します。
手動で内部リンクを確認する方法もあります。
Screaming Frog SEO SpiderやAhrefs、Semrushなどのツールを使用して、サイト内のすべてのリンクをクロールし、古いURLへのリンクを特定できます。
これらのツールは、「どのページから、どのURLへリンクが張られているか」を詳細にレポートしてくれるため、手動更新が必要な箇所を効率的に特定できます。
特に、ハードコーディングされたHTMLファイルやJavaScriptファイル内のリンクは、データベース置換では更新されないため、手動確認が必要です。
内部リンク更新の効果を測定します。
更新後、Google Search ConsoleやGoogle Analyticsで、以下の指標を監視します。
(1)ページ表示速度の改善、(2)クロール効率の向上(クロールされるページ数の増加)、(3)インデックスカバレッジの状態、(4)ユーザーの直帰率やページビュー数の変化。
これらの指標が改善していれば、内部リンク更新が正しく機能している証拠です。
- グローバルナビとフッターリンクを最優先で更新
- CMSのプラグインやデータベース置換ツールを活用
- 実行前に必ずバックアップを取得
- クローリングツールで漏れがないか確認
- JavaScriptやCSS内のリンクも忘れずにチェック
- 更新後はGoogle Search Consoleで効果を測定
Search Consoleでの確認
URL変更後は、Google Search Consoleでの継続的な監視が不可欠です。
Google Search Consoleは、Googleがサイトをどのように認識し、インデックスしているかを確認できる無料ツールです。
URL変更という大きな変更を行った後は、このツールを使って、変更が適切に処理されているか、問題が発生していないかを定期的にチェックする必要があります。
適切なモニタリングにより、問題を早期に発見し、対処することができます。
まず、「アドレス変更ツール」を使用します。
ドメイン全体を変更した場合(例:old-domain.com → new-domain.com)は、Search Consoleの「設定」から「アドレス変更」ツールにアクセスし、新旧ドメインの関連付けを行います。
これにより、Googleに「このサイトは移転しました」と正式に通知でき、移行プロセスがスムーズになります。
ただし、このツールは同じドメイン内でのURL構造変更(example.com/old/ → example.com/new/)には使用できません。
「カバレッジレポート」で、インデックス状況を確認します。
URL変更後、数週間から数ヶ月かけて、古いURLがインデックスから削除され、新しいURLがインデックスに追加されていきます。
「カバレッジ」レポートの「除外」セクションで、「リダイレクトされました」というステータスが増加していれば、Googleが301リダイレクトを正しく認識している証拠です。
同時に、「有効」セクションで新しいURLがインデックスされていることを確認します。
「URL検査ツール」で個別ページをチェックします。
特に重要なページや、トラフィックの多いページについては、URL検査ツールを使って個別に状況を確認します。
新しいURLを入力して検査すると、「URLはGoogleに登録されています」「最終クロール日時」「検出されたリダイレクト」などの情報が表示されます。
ここで「インデックス登録をリクエスト」をクリックすることで、Googleに優先的にクロールしてもらうことができます。
「エクスペリエンスレポート」でエラーを確認します。
「ページエクスペリエンス」や「モバイルユーザビリティ」レポートで、新しいURLに移行後、エラーが増加していないかチェックします。
URL変更に伴って、意図せず404エラーやリダイレクトループが発生している可能性があります。
これらのエラーは、ユーザー体験を損なうだけでなく、SEOにも悪影響を与えるため、早急に修正する必要があります。
| Search Console機能 | 確認項目 | 望ましい状態 |
| アドレス変更ツール | ドメイン変更の通知 | 新ドメインと関連付け完了 |
| カバレッジレポート | インデックス状況 | 新URLが増加、旧URLが減少 |
| URL検査ツール | 個別ページの状態 | 新URLがインデックス済み |
| エクスペリエンスレポート | エラーの有無 | エラー数が増加していない |
| 検索パフォーマンス | トラフィック推移 | 大幅な減少がない |
URLとクローラビリティ

robots.txtの活用
robots.txtファイルは、検索エンジンのクローラーに対して、どのURLをクロールしてよいか、してはいけないかを指示するファイルです。
このファイルをサイトのルートディレクトリ(https://example.com/robots.txt)に配置することで、クロール予算を効率的に使用し、重要なコンテンツを優先的にインデックスさせることができます。
特に、大規模サイトや動的なURLを多く含むサイトでは、robots.txtの適切な設定が、SEO効果を大きく左右します。
robots.txtで除外すべきURLの典型例を挙げます。
まず、管理画面やログインページ(例:/admin/, /wp-admin/, /login/)は、検索結果に表示される必要がないため、クロール対象外にします。
次に、重複コンテンツを生成する動的パラメータ(例:/products?sort=price, /search?q=keyword)も除外候補です。
また、PDFや画像などのメディアファイルが大量にある場合、これらもクロール予算を消費するため、必要に応じて除外を検討します。
robots.txtの記述方法は比較的シンプルです。
基本的な構文は、「User-agent」でクローラーを指定し、「Disallow」で除外するパス、「Allow」で許可するパスを記述します。
例えば、「User-agent: * / Disallow: /admin/ / Disallow: /wp-admin/」と記述すると、すべてのクローラーに対して、/admin/と/wp-admin/ディレクトリのクロールを禁止します。
より高度な例として、「Disallow: /?s= 」と記述すると、検索結果ページ(example.com/?s=keyword)のクロールを防げます。
注意すべきは、robots.txtはセキュリティツールではないということです。
robots.txtに記述された「Disallow」ルールは、協力的なクローラーに対する「お願い」であり、強制力はありません。
悪意のあるボットやスクレイパーは、robots.txtを無視してクロールする可能性があります。
そのため、本当に非公開にしたいコンテンツは、パスワード保護や.htaccessによるアクセス制限など、別の方法で保護する必要があります。
robots.txtの設定ミスは、重大なSEO損失を招く可能性があります。
過去には、サイト全体を誤ってDisallowに設定してしまい、インデックスから完全に削除されてしまった事例も報告されています。
robots.txtを編集した後は、必ずGoogle Search Consoleの「robots.txtテスター」ツールで動作確認を行います。
また、主要なURLがブロックされていないか、「URL検査ツール」でも確認します。
名古屋の株式会社エッコでは、サイトの構造に応じた最適なrobots.txt設定のアドバイスも提供しています。
- 管理画面やログインページはDisallowに設定
- 動的パラメータURLは必要に応じて除外
- XMLサイトマップの場所をrobots.txtに記載
- 設定後はSearch Consoleでテスト
- 定期的に設定を見直し、最適化
- セキュリティ目的では使用しない
XMLサイトマップでの指定
XMLサイトマップは、サイト内の全URLをリスト化し、検索エンジンに伝えるためのファイルです。
robots.txtが「クロールしないでほしいURL」を指定するのに対し、XMLサイトマップは「ぜひクロールしてほしいURL」を積極的に伝える役割を果たします。
このファイルをGoogle Search Consoleに送信することで、Googleがサイト内のすべてのページを効率的に発見し、インデックスすることができます。
特に、新しく公開したページや、内部リンクが少ないページのインデックスを促進する効果があります。
XMLサイトマップには、クロール・インデックスしてほしいURLのみを含めます。
つまり、robots.txtでDisallowに設定したURLや、noindexタグを設定したページ、リダイレクト設定されたURLなどは、サイトマップから除外します。
サイトマップには、正規URL(canonical URL)のみを含めることで、Googleに「これらが正式なURLです」と明確に伝えることができます。
重複コンテンツや一時的なURLをサイトマップに含めると、Googleが混乱し、クロール効率が低下する可能性があります。
XMLサイトマップには、優先度と更新頻度の情報を含めることができます。
<priority>タグでは、0.0〜1.0の値でページの重要度を指定します(1.0が最重要)。
<changefreq>タグでは、ページの更新頻度を「daily」「weekly」「monthly」などで指定します。
ただし、Googleはこれらの情報を参考程度にしか扱わないため、過度に期待すべきではありません。
それよりも、最終更新日時を示す<lastmod>タグを正確に設定する方が重要です。
大規模サイトでは、サイトマップを分割します。
1つのサイトマップファイルには最大50,000URLまで、ファイルサイズは50MB以下という制限があります。
これを超える場合は、複数のサイトマップファイルに分割し、「サイトマップインデックス」ファイルでそれらをまとめます。
例えば、sitemap-posts.xmlとsitemap-pages.xmlに分割し、sitemap_index.xmlから両者を参照する構造です。
サイトマップは自動生成ツールを使用するのが一般的です。
WordPressでは「Yoast SEO」「Rank Math」などのプラグインが自動的にサイトマップを生成・更新してくれます。
静的サイトジェネレーターや独自CMSを使用している場合は、「XML Sitemap Generator」などのオンラインツールを利用できます。
自動生成により、新しいページを公開するたびにサイトマップが自動更新され、常に最新の状態を保つことができます。
| サイトマップ設定項目 | 推奨設定 | 理由 |
| 含めるURL | canonical URLのみ | 正規URLを明確化 |
| 除外するURL | noindex、リダイレクトURL | クロール効率を最大化 |
| 更新頻度 | 実際の更新に即した設定 | Googleの信頼を得る |
| ファイル分割 | 50,000URL以上なら分割 | 制限を守る |
| 送信先 | Google Search Console | インデックス促進 |
クロール効率の向上
クロール効率とは、検索エンジンのクローラーが限られたクロール予算の中で、どれだけ効率的にサイトをクロールできるかを指します。
クロール予算(Crawl Budget)とは、Googleが特定のサイトに対して割り当てるクロールリソースの上限のことで、サイトの規模、更新頻度、サーバーの応答速度などによって決まります。
大規模サイトや更新頻度が高いサイトでは、このクロール予算を最適化することで、新しいコンテンツが素早くインデックスされ、SEO効果が向上します。
クロール効率を向上させる第一の方法は、不要なURLのクロールを防ぐことです。
前述のrobots.txtとXMLサイトマップを適切に設定し、クローラーが重要なページに集中できるようにします。
例えば、ECサイトで無数のフィルター結果ページが生成される場合、これらをrobots.txtでブロックするか、canonicalタグでメインカテゴリーページを正規URLとして指定します。
また、404エラーページを放置すると、クローラーが無駄に404ページをクロールし続けるため、定期的に404エラーを修正します。
サーバーの応答速度も、クロール効率に大きく影響します。
ページの読み込みが遅いと、クローラーは限られた時間内にクロールできるページ数が減少します。
そのため、サーバーのパフォーマンス最適化、CDNの導入、画像圧縮、キャッシュの活用などにより、ページ表示速度を改善することが重要です。
Google Search Consoleの「クロールの統計情報」レポートで、クロールリクエスト数や応答時間を確認し、問題がないかチェックします。
内部リンク構造を最適化することで、クローラーがサイト内を効率的に巡回できます。
すべての重要なページが、トップページから2〜3クリック以内でアクセスできるようにします。
孤立したページ(どこからもリンクされていないページ)がないよう、関連記事リンクやサイトマップページを活用します。
また、深い階層にある重要なページは、トップページやカテゴリートップページから直接リンクを張ることで、クローラーの到達を容易にします。
定期的な更新とコンテンツの鮮度も、クロール頻度に影響します。
頻繁に更新されるサイトは、Googleがより頻繁にクロールするようになります。
ブログ記事を定期的に公開したり、既存記事を更新したりすることで、クローラーの訪問頻度を高めることができます。
ただし、意味のない微細な変更を繰り返すのは逆効果なので、ユーザーにとって価値のある更新を行うことが重要です。
- robots.txtで不要なURLをクロール対象外にする
- XMLサイトマップに重要なURLのみを含める
- サーバー応答速度を改善(目標:200ms以下)
- 内部リンク構造を最適化し、孤立ページをなくす
- 404エラーやリダイレクトチェーンを定期的に修正
- 定期的にコンテンツを更新し、サイトの活性度を維持
- Search Consoleでクロール統計を監視
URL最適化のチェックリスト

新規ページ作成時の確認事項
新しいページを公開する前に、URLが適切に設定されているかチェックすることで、後の修正作業を回避できます。
URL変更は301リダイレクトの設定など手間がかかるため、公開前に正しいURLを設定することが重要です。
以下のチェックリストを参考に、新規ページのURL設定を確認しましょう。
すべての項目をクリアしてから公開することで、SEO効果を最大化できます。
まず、URLにターゲットキーワードが含まれているか確認します。
そのページで上位表示を狙うキーワードが、URLに自然な形で含まれているかチェックします。
例えば、「SEO対策の基礎」について書いた記事なら、「/seo-basics」や「/seo-guide」のようなキーワードを含むURLが適切です。
ただし、キーワードを無理に詰め込むのではなく、1〜2語に絞って簡潔に表現します。
次に、URLの長さが適切かチェックします。
ドメイン名を含めて75文字以内、スラッグ部分だけなら50文字以内が理想的です。
もしURLが長すぎる場合は、不要な単語(冠詞や助詞など)を削除したり、より簡潔な表現に言い換えたりします。
例えば、「/the-complete-guide-to-seo-url-optimization-for-beginners」は、「/seo-url-guide」に短縮できます。
文字種と記号の使用も確認します。
- すべての文字は小文字の半角英数字か確認
- 単語の区切りはハイフン(-)を使用しているか確認
- アンダースコア(_)や特殊文字を使用していないか確認
- 日本語やの全角文字を使用していないか確認
階層構造が適切かチェックします。
そのページがサイト内でどのような位置づけなのかを考慮し、適切なディレクトリに配置されているか確認します。
ブログ記事なら「/blog/category/article-title」、製品ページなら「/products/category/product-name」のように、論理的な階層構造になっているかチェックします。
階層が深すぎる(5階層以上)場合は、構造を見直します。
HTTPSが使用されているか最終確認します。
新規ページのURLが「https://」で始まっているか、「http://」になっていないかを確認します。
また、内部リンクやcanonicalタグも、すべてHTTPSのURLを指定しているかチェックします。
混在コンテンツ(HTTPSページ内にHTTPリソースがある状態)も避けます。
| チェック項目 | 良い例 | 悪い例 |
| キーワード含有 | /seo-url-guide | /page123 |
| URL長 | 50文字以内 | 100文字以上 |
| 文字種 | seo-guide | SEO_Guide |
| 階層の深さ | /blog/seo-guide | /a/b/c/d/e/seo-guide |
| プロトコル | https:// | http:// |
既存ページの監査方法
定期的に既存URLを監査することで、SEO上の問題を早期に発見し、改善することができます。
サイトは時間とともに成長し、構造が複雑化するため、定期的(四半期に1回程度)なURL監査が推奨されます。
ここでは、既存ページのURLを体系的にチェックする方法を解説します。
大規模サイトでは自動化ツールを活用し、小規模サイトでは手動チェックも併用します。
まず、サイト全体のURLリストを取得します。
Screaming Frog SEO Spider、Ahrefs、Semrushなどのクローリングツールを使用して、サイト内のすべてのURLをエクスポートします。
このリストをExcelやGoogleスプレッドシートで開き、以下の項目ごとに問題URLを特定していきます。
数百ページ以上のサイトでは、フィルター機能やピボットテーブルを活用すると効率的です。
URL長の分析を行います。
URLリストにURL長の列を追加し、75文字を超えるURLを抽出します。
これらのURLは、SEO効果が低下している可能性があるため、短縮を検討します。
ただし、すべてのURLを一度に変更するのは現実的ではないため、トラフィックが多いページや重要なページから優先的に修正します。
短縮したURLには、必ず301リダイレクトを設定します。
大文字・特殊文字のチェックを行います。
URLリスト内で、大文字を含むURL、アンダースコアを含むURL、日本語やエンコードされた文字列を含むURLを検索します。
例えば、「%」を含むURLを検索すると、日本語がエンコードされたURLが見つかります。
これらのURLは、重複コンテンツ問題や視認性の低下を招く可能性があるため、修正を検討します。
階層構造の分析を行います。
URLの「/」の数をカウントし、階層が5階層以上のURLを抽出します。
これらのURLは、トップページから遠すぎてSEO評価が低い可能性があります。
可能であれば、より浅い階層に移動するか、トップページや主要カテゴリーページから直接リンクを張ることで、リンク階層を浅くします。
404エラーとリダイレクトチェーンを特定します。
Screaming Frog SEO SpiderやGoogle Search Consoleを使用して、404エラーを返すURLや、複数回リダイレクトが発生しているURLを特定します。
404エラーは、適切なページへの301リダイレクトを設定するか、削除された場合は410ステータスを返すよう設定します。
リダイレクトチェーンは、最終的な到達先URLへ直接リダイレクトするよう修正します。
- 四半期に1回、定期的なURL監査を実施
- クローリングツールでURL全体をエクスポート
- 長すぎるURL、不適切な文字種を含むURLを特定
- 優先度を付けて段階的に修正
- 修正時は必ず301リダイレクトを設定
- 監査結果と修正履歴をドキュメント化
ツールを使った診断
URLの最適化状況を効率的に診断するには、専門ツールの活用が不可欠です。
手動での確認には限界があるため、自動化されたツールを使用することで、短時間で包括的な診断が可能になります。
ここでは、URL最適化に役立つ主要なツールと、その使い方を紹介します。
無料ツールと有料ツールを組み合わせることで、コストを抑えながら効果的な診断ができます。
Screaming Frog SEO Spiderは、URL診断の定番ツールです。
このツールは、サイト全体をクロールし、すべてのURLとその詳細情報(タイトル、メタディスクリプション、ステータスコード、リダイレクト先など)を収集します。
無料版では500URLまで、有料版(年間£259)では無制限にクロールできます。
URL長、ステータスコード、リダイレクトの有無などでフィルタリングすることで、問題のあるURLを素早く特定できます。
Google Search Consoleは、Googleの視点からURL状況を確認できる無料ツールです。
「カバレッジ」レポートでは、インデックス状況やエラーの有無を確認できます。
「URL検査」ツールでは、個別URLがGoogleにどう認識されているかを詳細に確認できます。
「ページエクスペリエンス」レポートでは、Core Web Vitalsなどのパフォーマンス指標も含めて、URL単位での問題を特定できます。
AhrefsやSemrushなどの統合SEOツールも、URL分析に有効です。
これらのツールは、サイトの技術的SEO監査機能を備えており、URL構造の問題を自動的に検出してくれます。
例えば、Ahrefsの「Site Audit」機能では、長すぎるURL、重複URL、リダイレクトチェーンなどを自動的にレポートしてくれます。
また、競合サイトのURL構造を分析し、自社サイトと比較することもできます。
PageSpeed InsightsやGTmetrixは、URL単位でのページ速度を測定します。
これらのツールを使用して、個別URLの読み込み速度を測定し、ボトルネックを特定します。
URLが長い場合や、リダイレクトチェーンがある場合、ページ速度にも影響が出る可能性があるため、URL最適化と並行してパフォーマンス改善も行います。
| ツール名 | 価格 | 主な機能 | 推奨用途 |
| Screaming Frog | 無料〜£259/年 | サイト全体クロール、詳細分析 | URL一覧取得、詳細診断 |
| Google Search Console | 無料 | インデックス状況、エラー検出 | Google視点での状態確認 |
| Ahrefs | $129〜/月 | Site Audit、競合分析 | 包括的なSEO監査 |
| Semrush | $139.95〜/月 | サイト監査、トラッキング | 継続的なモニタリング |
| PageSpeed Insights | 無料 | ページ速度測定 | パフォーマンス確認 |
WordPressでのURL設定
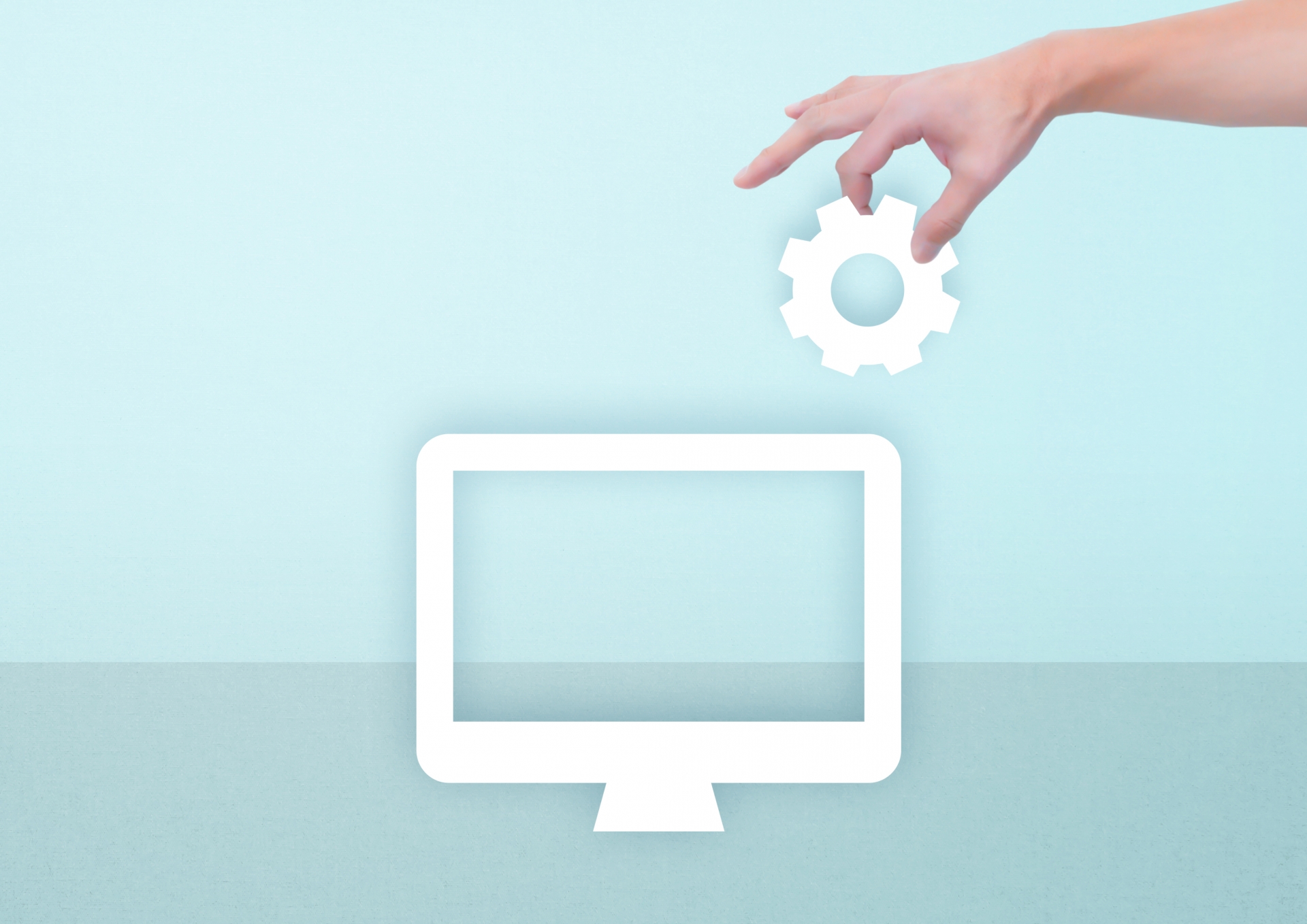
パーマリンク設定の推奨構造
WordPressでのURL設定は、「設定」→「パーマリンク」から行います。
パーマリンクとは、WordPressにおけるURL構造の設定のことで、ブログ記事や固定ページのURLがどのような形式で生成されるかを決定します。
WordPressは複数のパーマリンク構造を提供していますが、SEO観点から推奨される構造は限られています。
適切なパーマリンク設定を最初に行うことで、後の変更作業を避けることができます。
最も推奨されるのは「投稿名」形式です。
「設定」→「パーマリンク」画面で「投稿名」を選択すると、URLは「https://example.com/sample-post」のような形式になります。
この形式では、記事のスラッグがそのままURLとなるため、キーワードを含めやすく、短くシンプルなURLを作成できます。
実際、多くのSEO専門家やWordPress公式ドキュメントでも、この「投稿名」形式が推奨されています。
避けるべきは「日付と投稿名」形式です。
この形式では、URLが「https://example.com/2025/01/15/sample-post」のように、日付が含まれてしまいます。
前述の通り、日付を含むURLは、コンテンツ更新時に問題が生じるため推奨されません。
また、「数字ベース」(example.com/?p=123)や「月と投稿名」形式も、SEO上のメリットがないため避けるべきです。
カスタム構造を使用する方法もあります。
「カスタム構造」を選択すると、「/%category%/%postname%/」のように、カテゴリーを含むURL構造を設定できます。
この場合、URLは「https://example.com/seo/url-optimization」のようになり、カテゴリー情報が含まれるため、サイト構造が明確になります。
ただし、後から記事のカテゴリーを変更すると、URLも変わってしまうため、注意が必要です。
パーマリンク設定は、サイト開設時に決定し、以後は変更しないのが原則です。
すでに運用中のサイトでパーマリンク設定を変更すると、すべての記事URLが変わってしまい、大規模な301リダイレクト設定が必要になります。
そのため、パーマリンク設定は慎重に選択し、一度決めたら変更しないことが重要です。
どうしても変更が必要な場合は、「Permalink Manager Lite」などのプラグインを使用して、リダイレクトを自動設定します。
| パーマリンク形式 | URL例 | SEO評価 | 推奨度 |
| 投稿名 | /sample-post | ◎ | ◎ 最推奨 |
| カスタム(%category%/%postname%/) | /seo/sample-post | ○ | ○ 推奨 |
| 日付と投稿名 | /2025/01/15/sample-post | △ | × 非推奨 |
| 数字ベース | /?p=123 | × | × 非推奨 |
スラッグの手動編集
WordPressでは、各ページ・投稿のスラッグを個別に編集できます。
スラッグとは、URLの最後の部分(例:「/seo-url-guide」の「seo-url-guide」部分)のことです。
WordPressは、記事タイトルから自動的にスラッグを生成しますが、この自動生成されたスラッグは往々にして長く、最適ではありません。
公開前に手動でスラッグを編集することで、SEOに適したURLを作成できます。
スラッグの編集は、投稿編集画面の右サイドバーから行います。
投稿編集画面(ブロックエディター)で、右サイドバーの「パーマリンク」セクションにある「URLスラッグ」欄を見つけます。
ここに表示されているスラッグをクリックすると、編集可能になります。
新しいスラッグを入力したら、「更新」ボタンをクリックして保存します。
なお、既に公開済みの記事のスラッグを変更すると、URLが変わってしまうため、注意が必要です。
効果的なスラッグ作成のコツをまとめます。
まず、記事のターゲットキーワードを1〜3語含めます。
例えば、「URLのSEO最適化ガイド」という記事なら、「seo-url-guide」や「url-optimization」のようなスラッグが適切です。
次に、不要な単語を削除します。
WordPressは日本語タイトルから自動的にローマ字スラッグを生成することがありますが、これは非常に長くなるため、必ず英語のスラッグに変更します。
スラッグに日本語を使用することは避けるべきです。
WordPressでは、「URLのSEO最適化」のような日本語スラッグも設定できますが、実際には「%E3%81%A…」のようにエンコードされてしまいます。
これは非常に醜く長いURLになるため、必ず英語(またはローマ字)のスラッグに変更します。
例えば、「url-seo-optimization」や「url-seo-guide」のようなシンプルな英語スラッグを使用します。
スラッグの命名規則を統一します。
サイト全体で一貫したスラッグ命名規則を採用することで、管理が容易になります。
例えば、「how-to」で始める、「guide」で終わる、などのパターンを決めておくと、後から見直す際に分かりやすくなります。
また、複数の編集者がいる場合は、スラッグ作成のガイドラインをドキュメント化し、全員が同じルールに従うようにします。
- 記事公開前に必ずスラッグを確認・編集する
- ターゲットキーワードを1〜3語含める
- 日本語スラッグは使用せず、必ず英語に変更
- 20〜50文字程度の長さに収める
- 冠詞や助詞など不要な単語を削除
- サイト全体で一貫した命名規則を採用
- 既に公開済みの記事のスラッグ変更は慎重に判断
さに収める
- 冠詞や助詞など不要な単語を削除
- サイト全体で一貫した命名規則を採用
- 既に公開済みの記事のスラッグ変更は慎重に判断
プラグインによる最適化
WordPressプラグインを活用することで、URL最適化作業を効率化できます。
WordPressには、URL管理やSEO最適化を支援する多数のプラグインが存在します。
これらのプラグインを適切に選択・設定することで、技術的な知識がなくても、SEOに強いURL構造を実現できます。
ここでは、URL最適化に特に有効なプラグインとその活用方法を紹介します。
Yoast SEOは、最も人気のあるSEOプラグインの一つです。
このプラグインは、記事編集画面でスラッグを簡単に編集できる機能や、XMLサイトマップの自動生成機能を提供します。
特に便利なのが、記事公開前にURLのSEOスコアを評価してくれる機能です。
URLが長すぎる場合や、キーワードが含まれていない場合は、警告を表示してくれるため、公開前に最適化できます。
また、パンくずリストの自動生成や構造化データの出力も行ってくれます。
Redirectionは、301リダイレクト管理に特化したプラグインです。
URLを変更する際に、このプラグインを使用すると、簡単に301リダイレクトを設定できます。
管理画面から、旧URLと新URLを入力するだけで、リダイレクトが設定されます。
また、404エラーが発生したURLを自動的に記録し、どのURLで404エラーが多発しているかを確認できます。
これらの404URLに対して、適切なページへのリダイレクトを設定することで、ユーザー体験とSEOの改善につながります。
Rank Mathは、Yoast SEOの代替として人気が高まっているプラグインです。
Yoast SEOと同様の機能を持ちながら、より軽量で高速に動作します。
URL最適化に関しては、スラッグの提案機能、リダイレクト管理機能、XMLサイトマップ生成機能などを備えています。
特に、記事編集画面でURL分析を行い、「URLが長すぎます」「キーワードが含まれていません」などの具体的な改善提案をしてくれる点が便利です。
無料版でも十分な機能を利用できます。
Permalink Manager Liteは、パーマリンク設定変更時に役立ちます。
サイト全体のパーマリンク構造を変更する際、このプラグインを使用すると、自動的に301リダイレクトを設定してくれます。
また、個別の投稿やページのURLを自由にカスタマイズできる機能も提供します。
例えば、「/%category%/%postname%/」というパーマリンク設定で運用しているが、特定の記事だけ「/%postname%/」にしたい、といった柔軟な設定が可能です。
プラグインの導入時は、互換性と必要性を慎重に検討します。
多数のプラグインを導入すると、サイトの表示速度が低下したり、プラグイン同士の競合が発生したりする可能性があります。
そのため、本当に必要な機能を提供するプラグインだけを厳選して導入します。
特に、同じ機能を持つプラグイン(例:Yoast SEOとRank Mathの両方)を同時に有効化することは避けるべきです。
名古屋の株式会社エッコでは、WordPressサイトの最適なプラグイン構成や設定方法についてもアドバイスを提供しています。
| プラグイン名 | 主な機能 | 推奨用途 | 価格 |
| Yoast SEO | スラッグ編集、サイトマップ、SEO分析 | 総合的なSEO対策 | 無料〜有料 |
| Rank Math | SEO分析、リダイレクト、サイトマップ | Yoast代替 | 無料〜有料 |
| Redirection | 301リダイレクト、404監視 | URL変更時の管理 | 無料 |
| Permalink Manager | パーマリンクカスタマイズ | 柔軟なURL設定 | 無料〜有料 |
| Simple 301 Redirects | シンプルなリダイレクト管理 | 小規模なリダイレクト | 無料 |
まとめ

URLの最適化は、SEO対策の基盤となる重要な要素です。
本記事では、URLとSEOの関係から、具体的な設計方法、既存URLの改善手法まで、包括的に解説してきました。
URLは直接的なランキング要因としては小さいものの、検索エンジンのクロール効率、ユーザーのクリック率、サイト全体の構造理解など、多方面からSEOに影響を与えます。
適切に設計されたURLは、ユーザーと検索エンジンの両方にとって分かりやすく、サイトの評価向上につながります。
効果的なURL最適化の核心は、シンプルさと分かりやすさです。
短く、キーワードを含み、論理的な階層構造を持つURLが理想的です。
具体的には、50〜75文字以内、ハイフンで単語を区切り、すべて小文字の英数字で構成し、HTTPSを使用するという基本原則を守ることが重要です。
また、日付や複雑なパラメータ、特殊文字、アンダースコアなど、避けるべき要素も明確に理解しておく必要があります。
既存サイトでURL構造に問題がある場合でも、適切な手順で改善できます。
301リダイレクトを正しく設定し、内部リンクを更新し、Google Search Consoleで移行状況を監視することで、SEO評価を維持しながらURL構造を改善できます。
ただし、URL変更は慎重に計画し、必要性を十分に検討した上で実施すべきです。
大規模な変更の場合は、段階的なアプローチを取ることでリスクを軽減できます。
URL最適化は、単独で実施するのではなく、総合的なSEO戦略の一部として捉えるべきです。
URL構造だけを完璧にしても、コンテンツの質が低ければ上位表示は望めません。
逆に、優れたコンテンツを持ちながら、URL構造が不適切であれば、その価値が十分に伝わりません。
URL最適化、コンテンツ戦略、技術的SEO、被リンク獲得など、すべての要素をバランスよく実施することが、持続的なSEO成功の鍵となります。
定期的な監査とメンテナンスも忘れてはいけません。
サイトは常に成長し変化するため、四半期に一度程度、URL構造を見直すことが推奨されます。
新しいコンテンツを追加する際は、既存のURL構造との一貫性を保ち、404エラーやリダイレクトチェーンなどの問題を放置しないことが重要です。
Screaming Frog SEO SpiderやGoogle Search Consoleなどのツールを活用し、継続的にURL状況を監視しましょう。
URL最適化で困ったときは、専門家のサポートを受けることも有効な選択肢です。
特に、大規模サイトのURL構造変更や、複雑な技術的問題の解決には、専門的な知識と経験が必要になります。
名古屋のWebコンサルティング会社「株式会社エッコ」では、URL構造の診断から最適化プランの策定、実装支援、変更後のモニタリングまで、包括的なサポートを提供しています。
SEOの観点だけでなく、ユーザー体験やビジネス目標も考慮した最適なURL設計をご提案いたします。
最後に、URL最適化は一度やれば終わりではなく、継続的な改善プロセスです。
検索エンジンのアルゴリズムは常に進化し、ユーザーの行動パターンも変化します。
本記事で紹介した原則を基盤としながら、自社サイトのデータを分析し、PDCAサイクルを回すことで、常に最適なURL構造を維持できます。
小さな改善の積み重ねが、長期的には大きなSEO効果となって現れることを忘れないでください。
今日から、あなたのサイトのURL最適化を始めましょう。
最初のステップは、現状のURL構造を確認し、本記事のチェックリストと照らし合わせることです。
そこから優先度の高い改善項目を特定し、一つずつ実装していくことで、確実にSEO効果を高めることができます。
適切なURL構造は、あなたのウェブサイトの成功を支える重要な基盤となるはずです。



