Webサイトを運営していると、「ユーザーがすぐに離脱してしまう」「知りたい情報にたどり着けず、サイト内をさまよってしまう」といった課題に直面することがあります。
こうした問題を解決する重要な技術のひとつが、アンカーリンクです。
アンカーリンクを適切に設置することで、ユーザーは欲しい情報にすばやくアクセスでき、快適にサイトを閲覧できるようになります。
さらに、検索エンジンからの評価向上やコンバージョン率の改善にもつながるため、SEO対策としても効果的です。
本記事では、アンカーリンクの基本的な定義から、具体的な設定方法、SEO効果、注意点まで、Webサイト運営に必要な知識を網羅的に解説します。
名古屋でWebコンサルティングを提供する株式会社エッコでは、アンカーリンクを活用したサイト改善支援も行っており、実践的なノウハウをもとに、わかりやすくお伝えします。
ぜひ最後までお読みいただき、あなたのWebサイトの改善にお役立てください。
Index
アンカーリンクとは
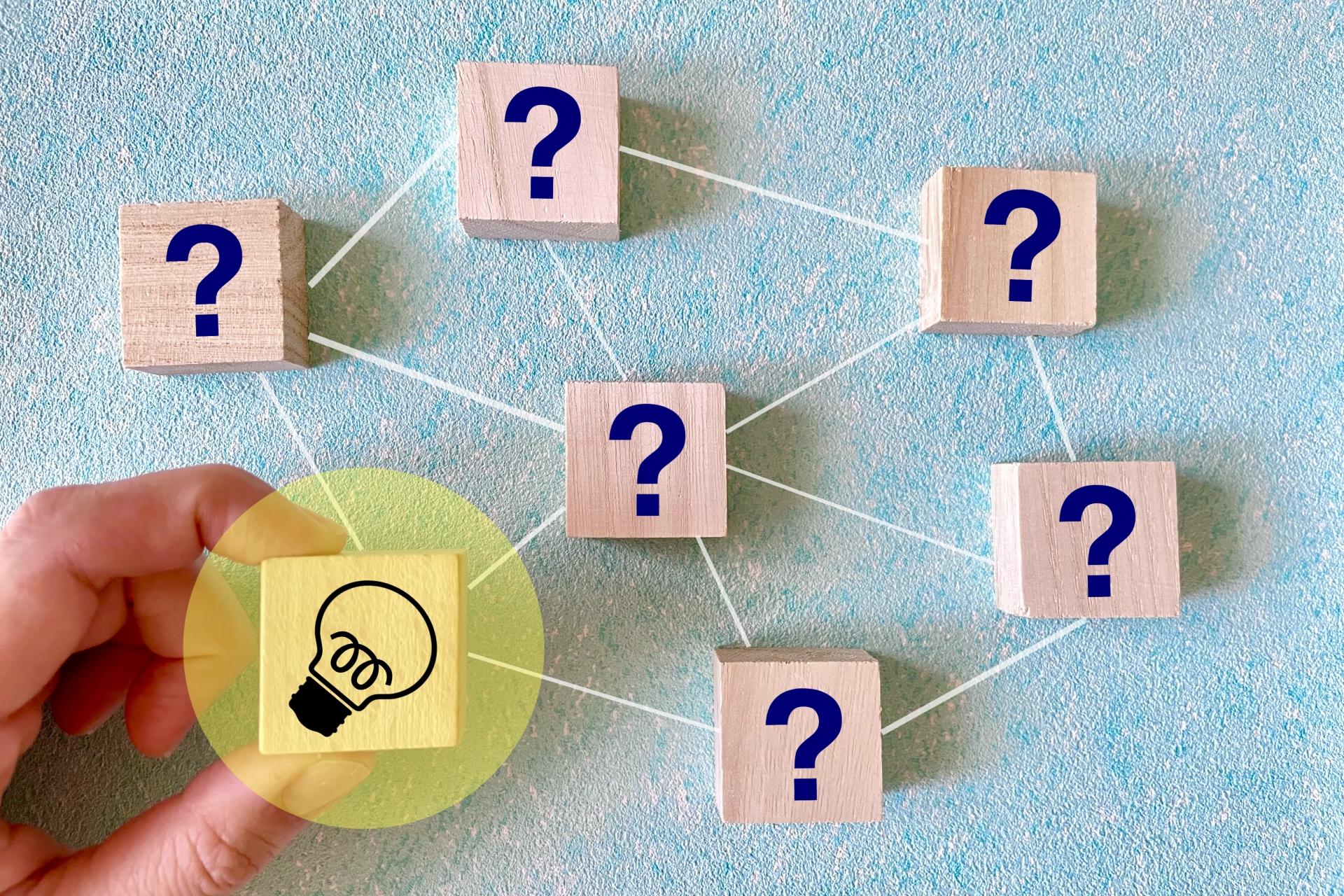
Webサイトの使いやすさを大きく左右する「アンカーリンク」について、まずは基本的な定義と役割から理解していきましょう。
アンカーリンクの定義と役割
アンカーリンクとは、Webページ内に設置されたリンクのことで、クリックすると指定した場所へ移動できる仕組みです。
具体的には、同じページ内の特定の位置に移動したり、別のページへ遷移したりする機能を持っています。
アンカー(anchor)という言葉は、英語で「いかり」を意味します。
船が海上で位置を固定するために「いかり」を下ろすように、Webページ内の特定の位置を固定して、そこへユーザーを導く役割を果たすことから、この名前が付けられました。
アンカーリンクが必要とされる理由は、ユーザーが快適に情報を得られるように工夫するためです。
初めてサイトを訪れた人は、欲しい情報を探すのに手間と時間がかかります。
特にスマートフォンでは画面が小さいため、長いページを何度もスクロールしなければならず、ストレスを感じやすくなります。
アンカーリンクを適切に設置すれば、ユーザーはワンクリックで目的の情報にたどり着けるため、サイトの利便性が大幅に向上します。
| アンカーリンクの主な役割 | 効果 |
| ページ内の特定箇所への移動 | スクロールの手間を削減し、素早く情報にアクセスできる |
| 関連ページへの誘導 | ユーザーが求める情報を的確に提供できる |
| サイト内の回遊促進 | 複数のページを見てもらうことで滞在時間が伸びる |
| ユーザー体験の向上 | ストレスなく情報を探せるため、満足度が高まる |
ハイパーリンクとの違い
アンカーリンクとよく混同されるのが「ハイパーリンク」です。
両者はクリックすると別の場所に移動するという点では共通していますが、対象範囲に明確な違いがあります。
アンカーリンクは、Webページ内に設置されたリンクのことを指します。
一方、ハイパーリンクは、Webページ以外の文書内に設置されたリンクも含む、より広い概念です。
たとえば、ExcelやWordの文書内に設置されたリンクや、メール内のリンクなども、ハイパーリンクに分類されます。
つまり、ハイパーリンクという大きなカテゴリの中に、Webページ専用のアンカーリンクが含まれているというイメージです。
実務では、Webサイトやブログの制作では「アンカーリンク」、Excelやメールでは「ハイパーリンク」という呼び方が一般的です。
| 項目 | アンカーリンク | ハイパーリンク |
| 対象 | Webページ内のリンク | Webページ、Excel、メールなど幅広い |
| 用途 | Webサイト、ブログでの使用 | あらゆるデジタル文書での使用 |
| 範囲 | 限定的 | 包括的 |
ページ内リンクとの関係
「ページ内リンク」という言葉も、アンカーリンクと関連してよく使われます。
ページ内リンクとは、同一ページ内の特定の位置に移動するリンクのことで、アンカーリンクの一種です。
アンカーリンクには、大きく分けて2つのタイプがあります。
ひとつは、同じページ内の特定箇所へ移動するタイプで、これが「ページ内リンク」と呼ばれるものです。
もうひとつは、別のページへ移動するタイプで、これは内部リンクや外部リンクとして機能します。
つまり、アンカーリンクは「ページ内リンク」と「別ページへのリンク」の両方を含む、より広い概念なのです。
| リンクの種類 | 遷移先 | 具体例 |
| ページ内リンク | 同じページ内の特定箇所 | 目次から見出しへの移動、ページトップへ戻るボタン |
| 内部リンク | 同じサイト内の別ページ | 関連記事へのリンク、カテゴリーページへのリンク |
| 外部リンク | 他のサイトのページ | 参考サイトへのリンク、引用元へのリンク |
Webサイトの使いやすさを高めるには、これらのリンクを目的に応じて使い分けることが重要です。
株式会社エッコでは、サイト全体の導線設計からアンカーリンクの最適な配置まで、ユーザー目線でのWeb制作をサポートしています。
アンカーリンクの種類と使い分け

アンカーリンクには、用途に応じていくつかの種類があり、それぞれ記述方法が異なります。
ここでは、代表的な3つの属性とその使い分けについて詳しく解説します。
href属性(別ページへのリンク)
href属性は、リンク先のURLを指定するための属性で、アンカーリンクの中でもっとも基本的なものです。
別のページに遷移させたいときに使用し、自サイト内の他のページへのリンクだけでなく、外部サイトへのリンクにも対応できます。
href属性を使った基本的な記述は、次のようになります。
<a href=”リンク先のURL”>表示するテキスト</a>
「リンク先のURL」の部分に遷移先のアドレスを入力し、「表示するテキスト」の部分にユーザーに見せたい文言を記載します。
この「表示するテキスト」は、アンカーテキストと呼ばれ、リンク先の内容を的確に表す重要な要素です。
絶対URLと相対URLの使い分け
href属性でリンクを設定する際には、絶対URLと相対URLのどちらかを選択できます。
絶対URLとは、「https://」から始まる完全なURLのことです。
たとえば、「https://example.com/blog/article01.html」のように、ドメインからファイル名まですべてを含んだ形式です。
外部サイトへリンクする場合は、必ず絶対URLを使用します。
相対URLとは、現在表示しているページを基準とした、URLの一部だけを記述する形式です。
たとえば、同じサイト内の別ページにリンクする場合、「../blog/article01.html」のように、省略した形で記述できます。
| URL形式 | 記述例 | 使用場面 |
| 絶対URL | https://example.com/blog/article01.html | 外部サイトへのリンク、確実性を重視する場合 |
| 相対URL | ../blog/article01.html | 同じサイト内の別ページへのリンク |
相対URLを使うメリットは、サイトのドメインが変わった場合でも、リンクの修正が不要になる点です。
一方、絶対URLはリンク先が明確でわかりやすいというメリットがあります。
外部リンクと内部リンク
href属性を使ったリンクは、外部リンクと内部リンクの2つに分類されます。
外部リンクとは、自社サイト以外のWebサイトへ遷移するリンクのことです。
参考資料や引用元を示す場合、関連する外部サービスを紹介する場合などに使用します。
外部リンクを設置する際には、リンク先の品質やセキュリティに注意が必要です。
内部リンクとは、同じサイト内の別ページに遷移するリンクのことです。
関連記事への誘導、カテゴリーページへのリンク、お問い合わせページへの導線などに活用されます。
内部リンクを適切に配置することで、ユーザーのサイト内回遊が促進され、SEO評価の向上にもつながります。
| リンクの種類 | 特徴 | 注意点 |
| 外部リンク | 他サイトへの遷移 | リンク先の品質を確認、必要に応じてnofollow属性を使用 |
| 内部リンク | 自サイト内の別ページへの遷移 | ユーザーの導線を意識して配置、クローラビリティを考慮 |
id属性(ページ内リンク)
id属性は、ページ内の特定の位置を識別するための属性で、同じページ内の特定箇所に移動したいときに使用します。
たとえば、記事の冒頭にある目次から、各見出しへジャンプする機能は、id属性を使って実現されています。
id属性を使ったリンクは、次のように記述します。
リンク元:<a href=”#見出し1″>見出し1へ移動</a> リンク先:<h2 id=”見出し1″>見出し1のタイトル</h2>
リンク元のhref属性には、「#」を付けたid名を記述します。
リンク先となる要素には、id属性で同じ名前を設定します。
こうすることで、リンクをクリックしたときに、該当のid属性が付いた要素の位置まで自動的にスクロールされます。
目次からの移動
id属性のもっとも代表的な使い方が、記事の冒頭に設置する目次です。
長い記事の場合、ユーザーは全体を読むのではなく、自分が知りたい部分だけを読みたいと考えることが多くあります。
そこで、記事の冒頭に目次を設置し、各見出しにid属性を付けておけば、ユーザーは興味のある項目に直接ジャンプできます。
たとえば、「アンカーリンクのメリット」という見出しに直接移動したい場合、次のように記述します。
目次部分:<a href=”#merit”>アンカーリンクのメリット</a> 見出し部分:<h2 id=”merit”>アンカーリンクのメリット</h2>
この仕組みによって、スマートフォンでの閲覧時にも、長いページをスクロールする手間が省けるため、ユーザー体験が大きく向上します。
ページトップに戻るボタン
id属性のもうひとつの定番的な使い方が、ページの最下部に設置する「トップへ戻る」ボタンです。
長いページを最後まで読んだユーザーが、再び冒頭の情報を確認したい場合、手動でスクロールするのは手間がかかります。
そこで、ページトップにid属性を設定し、最下部に「トップへ戻る」リンクを配置することで、ワンクリックでページの先頭に戻れるようになります。
記述例は次のとおりです。
ページトップ:<div id=”top”></div> ページ下部:<a href=”#top”>ページトップへ戻る</a>
このボタンは、特にスマートフォンユーザーにとって便利な機能であり、サイトの使いやすさを高める重要な要素となります。
| id属性の活用例 | 効果 |
| 目次からの移動 | 必要な情報に素早くアクセスでき、読みたい箇所を見逃さない |
| ページトップへ戻るボタン | 再読や別情報への移動がスムーズになり、回遊率が向上する |
target属性(新しいタブで開く)
target属性は、リンク先のページをどのように開くかを指定する属性です。
同じタブでページを切り替えるのか、新しいタブで開くのかを制御できます。
特に、外部サイトへのリンクや、PDFなどのファイルを開く場合に活用されます。
_blankと_selfの使い方
target属性でよく使われる値は、**「_blank」と「_self」**の2つです。
「_blank」を指定すると、リンク先のページが新しいタブで開きます。
ユーザーは元のページを閉じることなく、新しい情報を確認できるため、サイトから離脱しにくくなります。
記述例は次のとおりです。
<a href=”https://example.com” target=”_blank”>外部サイトへ</a>
「_self」を指定すると、リンク先のページが同じタブで開きます。
ただし、target属性を指定しない場合も、デフォルトで「_self」の動作となるため、わざわざ記述する必要はほとんどありません。
| target属性の値 | 動作 | 使用場面 |
| _blank | 新しいタブで開く | 外部サイト、PDFファイル、参考資料など |
| _self | 同じタブで開く | サイト内の通常のページ遷移(省略可) |
ユーザビリティへの配慮
target=”_blank”を使って新しいタブで開く設定は便利ですが、使いすぎるとユーザーを混乱させる可能性があります。
ユーザーが意図せずに大量のタブを開いてしまい、どのタブが何の情報だったのかわからなくなることがあるからです。
そのため、新しいタブで開く必要があるリンクを見極めることが重要です。
一般的には、次のような場合に「_blank」を使うとよいでしょう。
・外部サイトへのリンク(元のページに戻ってきてほしい場合) ・PDFや画像ファイルなどのダウンロードリンク ・参考資料や補足情報へのリンク
逆に、サイト内の通常のページ遷移では、同じタブで開く方が自然で、ユーザーは「戻る」ボタンで前のページに戻れるため、操作しやすくなります。
| リンクの開き方 | メリット | デメリット |
| 新しいタブで開く | 元のページを保持できる、外部サイトからの離脱を防ぐ | タブが増えすぎると混乱する |
| 同じタブで開く | シンプルで操作しやすい、ブラウザの「戻る」が使える | 元のページに戻る際に再読み込みが発生することがある |
株式会社エッコでは、ユーザーの行動を分析しながら、最適なリンク設定をご提案しています。
アンカーリンクの設定方法

アンカーリンクを実際にWebサイトに実装するには、HTMLの基礎知識が必要です。
ここでは、具体的な記述方法と、より快適なユーザー体験を提供するためのテクニックをご紹介します。
HTMLでの基本的な記述方法
アンカーリンクは、HTMLの<a>タグを使って記述します。
<a>タグは、「アンカータグ」とも呼ばれ、リンクを設定するための基本的な要素です。
もっともシンプルな記述は、次のようになります。
<a href=”リンク先のURL”>表示するテキスト</a>
この記述によって、「表示するテキスト」の部分がリンクとして機能し、クリックすると「リンク先のURL」に遷移します。
たとえば、名古屋のWebコンサル会社である株式会社エッコのサービスページにリンクを張る場合は、次のように記述します。
<a href=”https://ecco-example.com/service”>エッコのサービスはこちら</a>
この記述により、「エッコのサービスはこちら」という文字がリンクとして表示され、クリックするとサービスページに遷移します。
また、前述したtarget属性を組み合わせれば、新しいタブで開く設定も可能です。
<a href=”https://ecco-example.com/service” target=”_blank”>エッコのサービスはこちら</a>
さらに、rel属性を追加することで、セキュリティやSEOの観点からリンクの性質を明示できます。
<a href=”https://external-site.com” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>外部サイトへ</a>
「noopener」はセキュリティ対策、「noreferrer」はリンク元情報を送らない設定です。
| 属性 | 役割 |
| href | リンク先のURLを指定 |
| target | リンクの開き方を指定(_blank、_selfなど) |
| rel | リンク先との関係性を明示(noopener、nofollowなど) |
id属性を使ったページ内リンクの作り方
ページ内リンクを作成するには、リンク先となる要素にid属性を設定し、リンク元からそのidを参照するという手順を踏みます。
具体的な手順は、次のとおりです。
ステップ1:リンク先にid属性を設定する
ジャンプ先となる見出しや段落に、id属性を付けます。
<h2 id=”merit”>アンカーリンクのメリット</h2>
この例では、「merit」というid名を付けています。
id名は自由に設定できますが、ページ内で重複しないようにすることが重要です。
ステップ2:リンク元にhref属性で「#id名」を指定する
目次やリンクボタンから、先ほど設定したid名を参照します。
<a href=”#merit”>メリットを確認する</a>
href属性に「#」を付けてid名を記述することで、クリックすると該当箇所にスクロールします。
この仕組みを使えば、長いページでもユーザーが必要な情報にすぐアクセスできるため、離脱率の低下につながります。
| 手順 | 記述内容 |
| ステップ1 | リンク先の要素に id=”任意の名前” を設定 |
| ステップ2 | リンク元に href=”#任意の名前” を記述 |
スムーススクロールの実装方法
通常、id属性を使ったページ内リンクをクリックすると、瞬時に該当箇所へジャンプします。
しかし、この動きが急すぎると、ユーザーは今どこにいるのか見失いやすくなります。
そこで役立つのが、スムーススクロールという技術です。
スムーススクロールを実装すると、なめらかにスクロールしながら目的の位置に移動するため、視覚的にわかりやすく、快適なユーザー体験を提供できます。
スムーススクロールは、CSSまたはJavaScriptで実装できます。
CSSで実装する方法(もっとも簡単)
CSSに次の1行を追加するだけで、サイト全体のページ内リンクがスムーススクロールになります。
html { scroll-behavior: smooth; }
この記述をスタイルシートに追加するだけで、すべてのアンカーリンクが自動的になめらかにスクロールするようになります。
JavaScriptで実装する方法(細かい制御が可能)
より細かくスクロールの速度や動きを制御したい場合は、JavaScriptを使用します。
document.querySelectorAll(‘a[href^=”#”]’).forEach(anchor => { anchor.addEventListener(‘click’, function (e) { e.preventDefault(); document.querySelector(this.getAttribute(‘href’)).scrollIntoView({ behavior: ‘smooth’ }); }); });
このコードを追加すると、すべてのページ内リンクがスムーズにスクロールするようになります。
| 実装方法 | 難易度 | メリット |
| CSS(scroll-behavior) | 簡単 | 1行で実装でき、メンテナンスが楽 |
| JavaScript | やや複雑 | スクロール速度や動きを細かく調整できる |
スムーススクロールを導入することで、サイトの印象が洗練され、ユーザーの満足度が高まります。
アンカーリンク設置のメリット

アンカーリンクを適切に設置することで、ユーザー体験の向上だけでなく、SEO効果やビジネス成果の改善にもつながります。
ここでは、アンカーリンクがもたらす3つの主要なメリットを詳しく解説します。
ユーザビリティの向上
アンカーリンクの最大のメリットは、ユーザーが欲しい情報に素早くアクセスできるようになることです。
Webサイトを訪れるユーザーの多くは、ページ全体を隅から隅まで読むのではなく、自分が知りたい部分だけを拾い読みする傾向があります。
特にスマートフォンでは、画面が小さいため、長いページを何度もスクロールするのはストレスになります。
そこで、目次やページトップへ戻るボタンなどのアンカーリンクを設置することで、ユーザーは必要な情報にワンクリックでたどり着けるようになります。
たとえば、次のような場面でアンカーリンクが活躍します。
・記事冒頭の目次から、読みたい見出しに直接ジャンプする ・長い記事を読み終えた後、ページトップに戻って他の情報を探す ・関連記事へのリンクをクリックして、さらに詳しい情報を得る
こうした導線を整えることで、サイトの滞在時間が延び、回遊率も向上します。
結果として、ユーザーはサイトに対して「使いやすい」「情報が探しやすい」という好印象を持ち、再訪問やブックマーク登録につながる可能性が高まります。
| ユーザビリティ向上の具体例 | 効果 |
| 目次からの直接ジャンプ | スクロールの手間が省け、読みたい箇所にすぐアクセスできる |
| ページトップへ戻るボタン | 再読や別情報への移動がスムーズになる |
| 関連記事への誘導 | 興味のある情報を連続して読んでもらえる |
SEO評価の向上
アンカーリンクは、検索エンジンからの評価を高める効果も持っています。
Googleをはじめとする検索エンジンは、ユーザーにとって価値のあるサイトを高く評価します。
そのため、アンカーリンクによってユーザビリティが向上すれば、間接的にSEO評価も上がるのです。
具体的には、次のような効果が期待できます。
・ユーザーの滞在時間が延びることで、サイトの質が高いと判断される ・直帰率が下がり、エンゲージメント率が向上する ・内部リンクが適切に配置されることで、サイト全体の構造が整理される
さらに、アンカーテキスト(リンクに表示されるテキスト)に適切なキーワードを含めることで、検索エンジンがリンク先のページ内容を正確に理解しやすくなります。
内部リンク構造の強化
内部リンクとは、同じサイト内の別ページへのリンクのことです。
アンカーリンクを活用して関連ページ同士を結びつけることで、サイト全体のリンク構造が強化されます。
Googleのクローラー(検索エンジンがサイトを巡回するプログラム)は、リンクをたどってサイト内を移動しながら、各ページの内容を評価します。
内部リンクが適切に配置されていれば、クローラーがすべてのページを効率よく巡回できるため、新しいページも早くインデックス(検索結果に登録されること)されます。
また、重要なページに多くの内部リンクを集めることで、そのページの重要性を検索エンジンに伝えられます。
たとえば、サービス紹介ページやお問い合わせページなど、コンバージョンに直結する重要なページには、複数のページからリンクを張ることで、SEO評価を高められます。
クローラビリティの改善
クローラビリティとは、検索エンジンのクローラーがサイト内を巡回しやすいかどうかを示す指標です。
アンカーリンクを適切に設置することで、クローラーはサイトの構造を理解しやすくなり、すべてのページを漏れなく評価できるようになります。
特に、次のような場合にクローラビリティが向上します。
・トップページから各カテゴリーページへのリンクが整備されている ・記事内に関連記事へのリンクが適切に配置されている ・パンくずリストやサイトマップが設置されている
クローラビリティが高いサイトは、検索エンジンに正しく評価されやすく、検索順位の向上につながります。
| SEO効果 | 具体的な影響 |
| 内部リンク構造の強化 | クローラーがサイト全体を効率よく巡回でき、評価が向上する |
| クローラビリティの改善 | 新しいページが早くインデックスされ、検索結果に表示されやすくなる |
| ユーザーエンゲージメントの向上 | 滞在時間や回遊率が上がり、サイトの質が高いと判断される |
コンバージョン率の向上
アンカーリンクは、コンバージョン率(CVR:訪問者が購入や問い合わせなどの行動を起こす割合)の向上にも貢献します。
ユーザーがサイト内で迷うことなく、スムーズに目的のページにたどり着ければ、購入や問い合わせといったアクションを起こしやすくなるからです。
たとえば、次のような導線設計が効果的です。
・商品紹介記事の中に、「今すぐ購入する」ボタンを設置し、購入ページへ直接リンクする ・サービスの詳細を説明した後、「お問い合わせはこちら」というリンクを目立つように配置する ・ブログ記事の最後に、関連するサービスページへのリンクを設置して、自然に誘導する
これらのアンカーリンクは、ユーザーが「次に何をすればいいか」を明確に示す役割を果たします。
また、アンカーテキストに具体的な行動を促す言葉(CTAテキスト)を使うことで、クリック率を高める効果もあります。
たとえば、「詳しくはこちら」ではなく、「無料相談を申し込む」「資料をダウンロードする」といった具体的な表現にすることで、ユーザーは次のアクションをイメージしやすくなります。
株式会社エッコでは、コンバージョン率の改善を目的としたサイト分析と改善提案を行っており、アンカーリンクの最適な配置についてもアドバイスしています。
| コンバージョン向上の施策 | 効果 |
| 重要なページへの明確な導線 | ユーザーが迷わず目的のアクションを起こせる |
| 具体的なCTAテキストの使用 | クリック率が上がり、問い合わせや購入が増える |
| 関連サービスへの自然な誘導 | ユーザーの興味を引きながら、ビジネス成果につなげる |
アンカーリンク設置時の注意点

アンカーリンクは便利な機能ですが、設置方法を誤ると、逆にユーザーの混乱を招いたり、SEO評価を下げたりする可能性があります。
ここでは、アンカーリンクを効果的に活用するための注意点を解説します。
リンクだとわかるデザインにする
アンカーリンクを設置しても、ユーザーがそれをリンクだと認識できなければ意味がありません。
Webサイトでは、一般的に次のようなデザインがリンクの目印とされています。
・テキストの色を青系統にする(通常のテキストと区別できる色) ・テキストに下線を引く ・マウスを乗せたときに色が変わる(ホバーエフェクト) ・ボタン形式にして、クリックできることを明示する
特に重要なのは、通常のテキストとリンクテキストの見た目を明確に区別することです。
たとえば、本文が黒色で書かれている場合、リンクは明るめの青色にし、下線を引くことで、ユーザーは一目でリンクだと気づけます。
また、ボタン形式にする場合は、影を付けたり、角を丸くしたりすることで、クリックできる要素だと直感的に伝えることができます。
スマートフォンでは、マウスオーバーという概念がないため、見た目だけでリンクだとわかるデザインにすることが特に重要です。
| デザインの工夫 | 効果 |
| 青系統の文字色と下線 | リンクだと一目でわかり、クリック率が上がる |
| ホバーエフェクト(色の変化) | PCユーザーにリンクであることを明確に伝える |
| ボタン形式のデザイン | 重要なリンクを目立たせ、クリックを促しやすい |
わかりやすいアンカーテキストを使う
アンカーテキストとは、リンクとして表示されるテキストのことです。
このテキストは、ユーザーと検索エンジンの両方にとって、リンク先の内容を理解するための重要な手がかりとなります。
わかりやすいアンカーテキストの条件は、次のとおりです。
・リンク先のページ内容を的確に表している ・具体的で、ユーザーが次に何が見られるかイメージできる ・簡潔で、長すぎない(1行程度に収める)
よくある失敗例として、「こちら」「詳しくはこちら」「クリック」といった曖昧な表現があります。
これらの表現では、リンク先にどんな情報があるのかがわからず、ユーザーはクリックをためらってしまいます。
また、検索エンジンもリンク先の内容を正しく理解できないため、SEO効果が薄れてしまいます。
改善例としては、次のようなテキストが効果的です。
| 悪い例 | 良い例 |
| 詳しくはこちら | アンカーリンクの設定方法を見る |
| クリックしてください | 無料相談を申し込む |
| こちらのページ | 名古屋のWebコンサル会社エッコのサービス紹介 |
具体的なアンカーテキストを使うことで、クリック率が向上し、SEO効果も高まります。
リンク先の品質を確認する
アンカーリンクを設置する際には、リンク先のページが適切に表示されるか、内容が信頼できるかを事前に確認することが重要です。
リンク切れ(リンク先のページが存在しない状態)が発生していると、ユーザーはエラーページを見ることになり、サイトへの信頼を失ってしまいます。
また、検索エンジンもリンク切れを発見すると、サイトの管理状態が悪いと判断し、SEO評価を下げる可能性があります。
定期的にサイト内のリンクをチェックし、リンク切れがあれば修正することが大切です。
さらに、外部サイトへリンクする場合は、リンク先のサイトの品質やセキュリティにも注意が必要です。
たとえば、次のようなサイトへのリンクは避けるべきです。
・スパムサイトや詐欺サイト ・コンテンツの質が著しく低いサイト ・大量の広告や不正なポップアップが表示されるサイト
こうしたサイトにリンクを張ると、自社サイトの評価も下がってしまう可能性があります。
どうしてもリンクを張る必要がある場合は、rel=”nofollow”属性を使って、検索エンジンにリンク先を評価しないよう指示することができます。
| 確認項目 | 対策 |
| リンク切れの有無 | 定期的にチェックし、リンク先が正しく表示されるか確認する |
| 外部リンク先の品質 | 信頼できるサイトかどうかを確認し、必要に応じてnofollow属性を使用 |
| URLの記入ミス | 設置後にリンクをクリックして、正しく遷移するかテストする |
位置のズレを解決する方法
アンカーリンクを設置したとき、リンク先の位置がヘッダーに隠れてしまうという問題が発生することがあります。
これは、サイトのヘッダーを「position: fixed;」で固定している場合によく起こります。
ヘッダーが画面上部に固定されていると、ページ内リンクでジャンプした際に、見出しがヘッダーの裏に隠れてしまい、ユーザーは目的の情報を見逃してしまいます。
この問題を解決するには、CSSで位置を調整する方法が一般的です。
具体的には、次のようなコードを追加します。
#見出し { padding-top: 100px; margin-top: -100px; }
この記述では、padding-top でヘッダーの高さ分(たとえば100px)のスペースを確保し、margin-top でそのスペースを相殺することで、表示位置を適切に調整できます。
また、CSSの「scroll-margin-top」プロパティを使う方法もあります。
#見出し { scroll-margin-top: 100px; }
この記述により、ページ内リンクでジャンプした際に、自動的にヘッダーの高さ分だけ余白を取って表示されるようになります。
| 問題 | 解決方法 |
| ヘッダーに見出しが隠れる | padding-top と margin-top で位置を調整 |
| スクロール位置のズレ | scroll-margin-top プロパティで余白を設定 |
これらの調整を行うことで、ユーザーは常に正しい位置に誘導され、ストレスなく情報を閲覧できます。
株式会社エッコでは、こうした細かな実装の調整も含めて、Webサイト全体の使いやすさを高めるサポートを提供しています。
まとめ

アンカーリンクは、ユーザーが欲しい情報に素早くアクセスできるようにするための重要な技術です。
適切に設置することで、サイトの使いやすさが大幅に向上し、ユーザーの満足度が高まります。
本記事では、アンカーリンクの基本的な定義から、href属性、id属性、target属性といった種類と使い分け、具体的な設定方法、そしてSEO効果やコンバージョン率向上のメリットまで、幅広く解説しました。
特に重要なポイントをまとめると、次のようになります。
・アンカーリンクは、ユーザビリティ向上の基本であり、ページ内リンクや別ページへのリンクを効果的に活用することが大切 ・内部リンク構造を強化することで、SEO評価が向上し、検索順位の改善につながる ・わかりやすいアンカーテキストとリンクだとわかるデザインを心がけることで、クリック率が上がり、コンバージョンにつながる ・リンク先の品質確認や位置のズレ調整といった細かな配慮が、ユーザー体験を大きく左右する
アンカーリンクは、HTMLの基礎知識があれば誰でも設置できる技術ですが、ユーザー目線での導線設計やSEOを意識した実装が求められます。
もし、自社サイトのアンカーリンク設定やサイト全体の改善にお悩みであれば、名古屋のWebコンサル会社・株式会社エッコにお気軽にご相談ください。
私たちは、ユーザビリティとSEOの両面から、あなたのWebサイトをより効果的なものへと改善するお手伝いをいたします。
この記事が、あなたのWebサイト運営に少しでもお役に立てれば幸いです。



